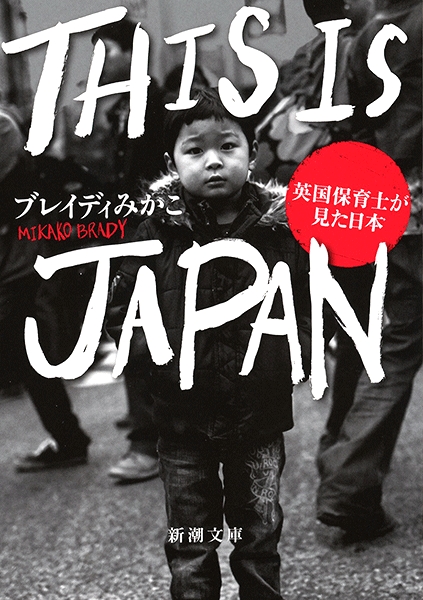本作品の全部または一部を、無断で複製(コピー)、転載、改ざん、公衆送信(ホームページなどに掲載することを含む)することを禁じます。
〔 page 1/4 〕
はじめに
2015年の夏、日本に帰省したおりに東京で数人の人々と食事をしていたのだが、そのとき、「ブロークン・ブリテン」という言葉が話題になった。
「ブロークン・ブリテン」というのは「壊れた英国」という意味で、元英国首相のデイヴィッド・キャメロンが労働党から政権を奪ったときに多用した言葉だ。彼は2000年代の英国におけるアンダークラスの台頭や下層社会でのモラルの低下を「ブロークン・ブリテン」と呼び、荒れた社会の修復を約束して政権に就いたのだったが、以降この言葉は格差が固定し、社会流動性がなくなり殺伐とした英国社会を指す言葉として定着していく。
「英国の人たちからすれば『ブロークン・ブリテン』なんていい言葉じゃないんだろうけど、響きが何か格好いいよね」
と言われたので、わたしはとっさにBBCニュースのサイトで読んだ記事のことを思い出し、
「ああ、そういえば、こないだBBCの記事で『ブロークン・ジャパン』っていう言葉も使われてたよ」
と言った。
するとなぜか、それまでにこやかに笑っていた人々が急に顔にパンチを食らったような表情になり、しんとなった。
「もうそんなことを……言われているのかあ……」
がっくり肩を落としてつぶやいた人もいた。
ふだん日本はもうダメだとか、終わっているとか、日本の政治や社会について大胆に批判している人々が、なぜ今さら「ブロークン・ジャパン」という言葉を聞いてこんなに落ち込んでいるのだろうとわたしは不思議に思った。
「ブロークン・ジャパン」という言葉が使われたBBCニュースの記事は、「女性がブロークン・ジャパンの修復に一役買えるのか」という題名で、アベノミクスが明らかに機能していない日本はまだ「終わっている」わけではないが、少子高齢化で人口が減少している国が成長するのは困難だ。その解決法の一つは女性の力をうまく活用することだろう、という主旨のものだった。
もちろん、これは英国のBBCの記事だから、「ブロークン・ブリテン」という言葉をもじって「ブロークン・ジャパン」と呼んだのであり、日本の下層社会が英国ばりに荒廃しているとかそういう意味で使われたわけではない。
しかし、女性を活用するといっても、日本には女性をめぐる古い価値観があり、東京のトップ大学の女学生が就職の面接で「子供を産むつもりですか?」と質問されたとBBCの記者に語った話や、フルタイムの仕事と家庭生活の両立がいまだに困難な日本のワーク・カルチャーについて書かれてあり、女性の力の活用は日本では実現しないだろうと結論されていて、明るい未来を感じさせる終わり方にはなっていなかった。
また、同じ年、英国の政治雑誌『ニュー・ステイツマン』にも日本に関する印象的な記事が出ていた。それは、日本の地方のさびれた村に行き、老いた家主が亡くなったあと、そのまま放置されている家屋を見てきた英国人ライターが、そのうら寂しい様子を「ゴースト・ホーム」と呼んで詳細に記述し、少子高齢化の最先端を行く日本社会の現状について書いたものだった。読んでみれば英国の下層の街とはまた違った意味で日本の空き家も荒れ放題だし、こうした家屋がゴロゴロ出てくるようになっているとすれば、日本もまた日本なりのブロークンな状況になっているのではないかと思った。
英国でもこんな記事が目に付くようになってきたのだから、当の日本の人々はもっとこうした感慨を持っているはずだとわたしは思っていた。日本には毎年帰省していたが、海外に住む多くの人々が知っているように、帰省というのは空港から実家へ、そしてまた空港に戻って在住国に帰るというパターンで終わる。子供を持つと特にそうなりがちだ。だからほぼ10年ぶりに東京へ行っていろいろな人に会って話をするのは刺激的だったが、なかでもとりわけ印象的だったのは「ブロークン・ジャパン」という言葉を聞いたときのその場にいた人たちの表情だった。
そこにあるものをあんまり見ていないようなところは昔から日本の人々にはあった。目をそらす、というほど意志的なものでもなく、もう本当にはなから目の前に明確にあるものが目に入っていないような感じである。
例えば、わたしはバブル世代と呼ばれる年代の人間だが、わたしが育った時代の日本はいわゆるイケイケの好景気の時代だった。「一億総中流」という言葉が完全に現実になったと思われていた時代である。
そんな時代に高校生になったわたしは、バスの定期代を稼ぐために学校帰りにスーパーでアルバイトしていたのだが、それが学校にバレて担任に呼び出されたことがあった。どうしてアルバイトなんかしているんだと聞かれたので、定期代を払うためだと答えると、担任はこう言った。
「嘘をつくな。いまどきそんな高校生がいるわけがない」
え? と思って担任の顔を見ると、彼の目は正義感にギラギラ燃えていた。
「俺の存在を頭から否定してくれ」と歌っていたのは、当時INUというパンクバンドに在籍し、現在は小説家の町田康だが、別にそんなことをこちらからお願いしなくとも、わたしの存在は頭から否定されていた。どんな世の中にも貧乏な家庭はあるはずなのに、あのころの日本の人たちは「そんなものはあるわけがない。自分たちはみな同じなのだ」という共同幻想を抱きすぎていて、目の前に貧民がいてもそれが全然目に入らなかったのである。
だが、わたしが過去20年間住んでいる英国という国はまったく違う。この国には階級というものが確固として存在しているからだ。別にカースト制度のようなものがあるわけではないが、それは人々の心のなかにあり、だからこそ余計に始末が悪いというか、一種の呪いと言ってもいいぐらい英国人はその意識から抜け出せない。息子の友人の父親であるカナダ人の大学の先生が、
「この国の人々は階級意識にとりつかれている」
と言っていたが、それはびっしりと英国人のサイケにこびりついていて、例えば先般おこなわれて世界の人々に衝撃を与えた英国のEU離脱投票なんてのも、一部メディアには「労働者階級の反乱」と表現された。生活苦と明日への不安で不満をためた労働者階級の人々の怒りが、彼らをアンチ政権、アンチ・エスタブリッシュメント感情に駆り立て、EU離脱などという暴挙に向かわせたというのである。
こう書いてくると英国の労働者階級というのは分別も品もない困った人々のように思われるかもしれないが、実はわたしは英国に来て、この階級に飛び込んで生活するようになって、とても気が楽になった。彼らはわたしと同じ階級の人々だったからである。だが、日本と違っていたのは、この人たちは「自分にはお金がない」と高らかに言うことができ、貧乏人はここに確かに存在するんだとやかましいぐらい主張して、それがあまりに堂々としているものだから「ワーキングクラス・ヒーロー」などと呼ばれてクールな存在とさえ見なされていた。彼らは、貧乏なのは自分のせいだと自らを責めるのではなく、「貴様らがしっかりやってくれないから、末端は苦しいのだ」と政府に拳を上げ、相手が無視を続けると暴動や反乱すら起こすのである。
確かにいまは英国でもこの層の人々はダサい社会悪の根源と見なされ、昔のように「ワーキングクラス・ヒーロー」ともてはやされることはない。が、彼らはけっしてひるまない。ブロークン・ブリテン上等、と言わんばかりのやけくそのパワーで突き進むので、この先どんなに大変なことになっても、とりあえずこの人たちは死なないだろうと思わされてしまう。
翻ってわが祖国である。
そこで暮らしている庶民には、ブロークン・ジャパン上等の気構えはあるだろうか。それどころか、ひょっとするとまだ沈んでいる自覚さえないのではないだろうか。
わたしはそうした疑念を抱いた。
そしてそのことが20年ぶりに1カ月という長期に渡って日本に滞在し、様々な人々に会って本書を書くうえでの下敷きになった。
もとよりわたしは地べたの保育士であり、無学な人間なので、何らかの日本の問題点を探り出し、突破口を見つけるなどという大それたことは最初から想定していない。
ただ日本でわたしが出会った人々や、彼らがわたしに見せてくれたことを記録しておきたいと思った。
1902年にロンドンのイーストエンドの貧民街に潜入して取材記を書いたジャック・ロンドンは、その著書『どん底の人びと ロンドン1902』を「心と涙」で書いたルポルタージュと呼んだ。2016年2月の東京の取材記である本書はそこまで激烈なルポではないが、「実際に自分の目で目撃したものだけを信用するのだ」という彼の書き手としての姿勢だけはわたしも常に持っておきたいと思う。
(本書は取材に基づいて書かれていますが、プライバシーに配慮し、一部詳細を変更しています。)