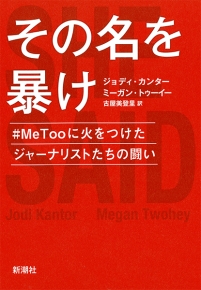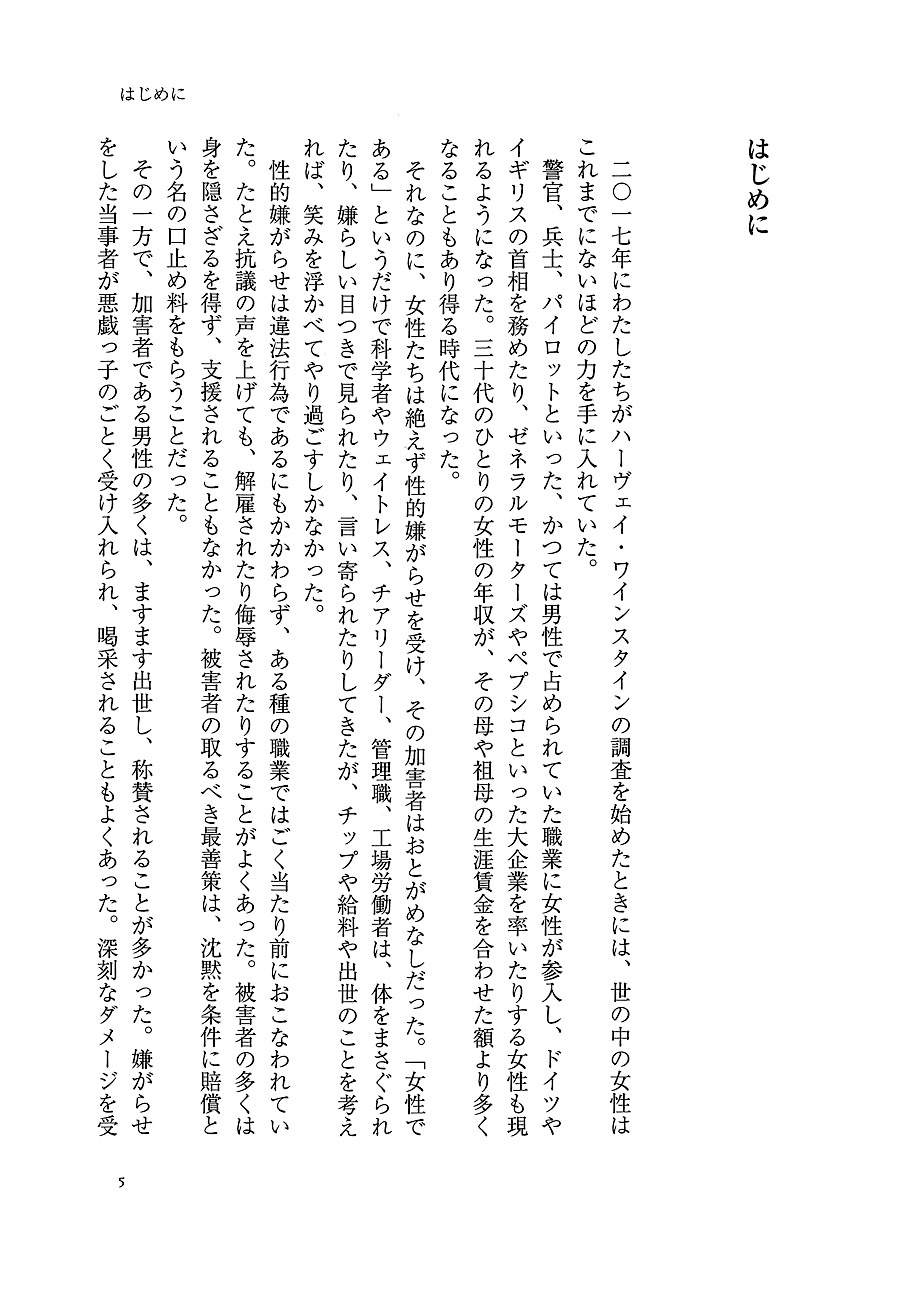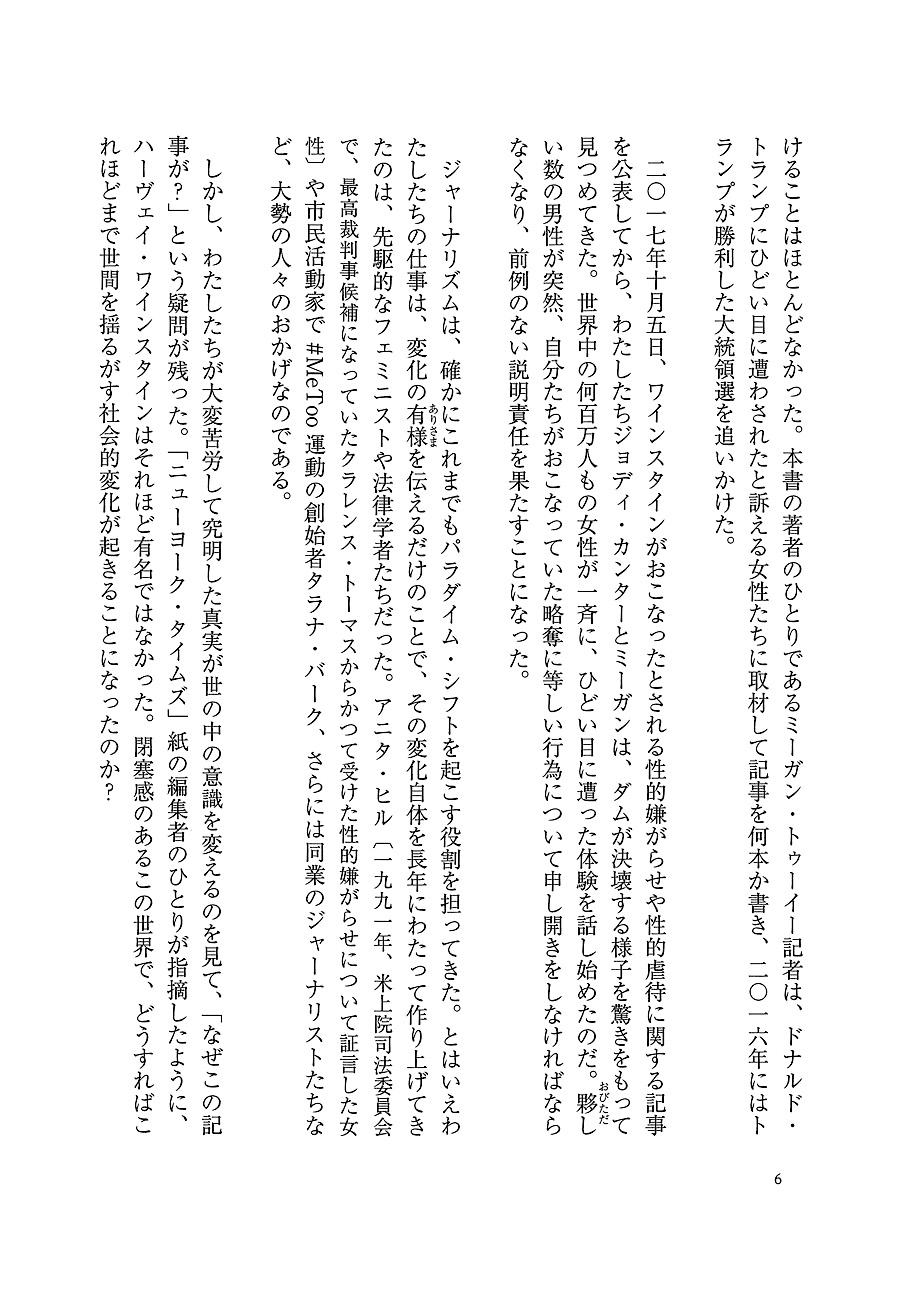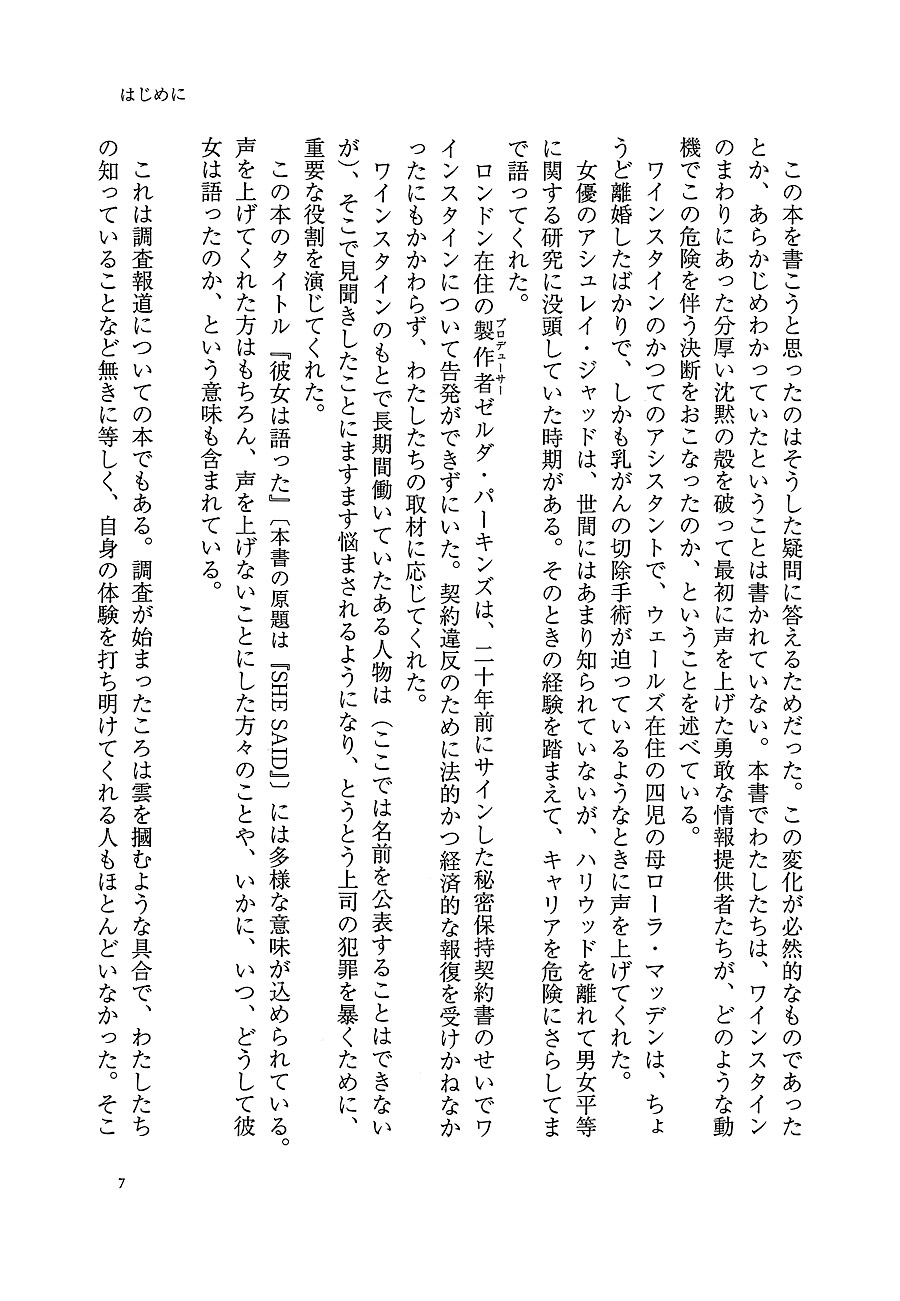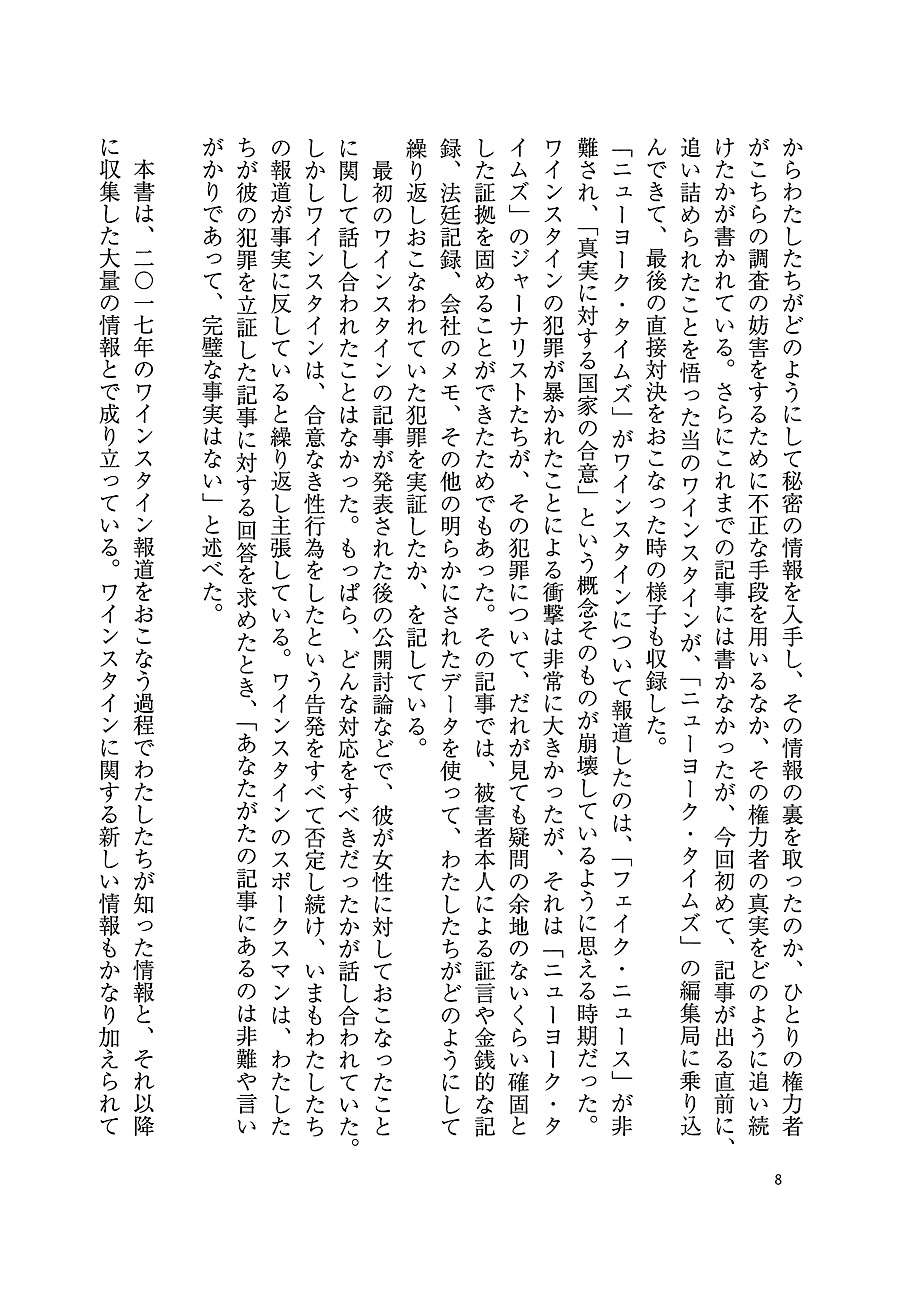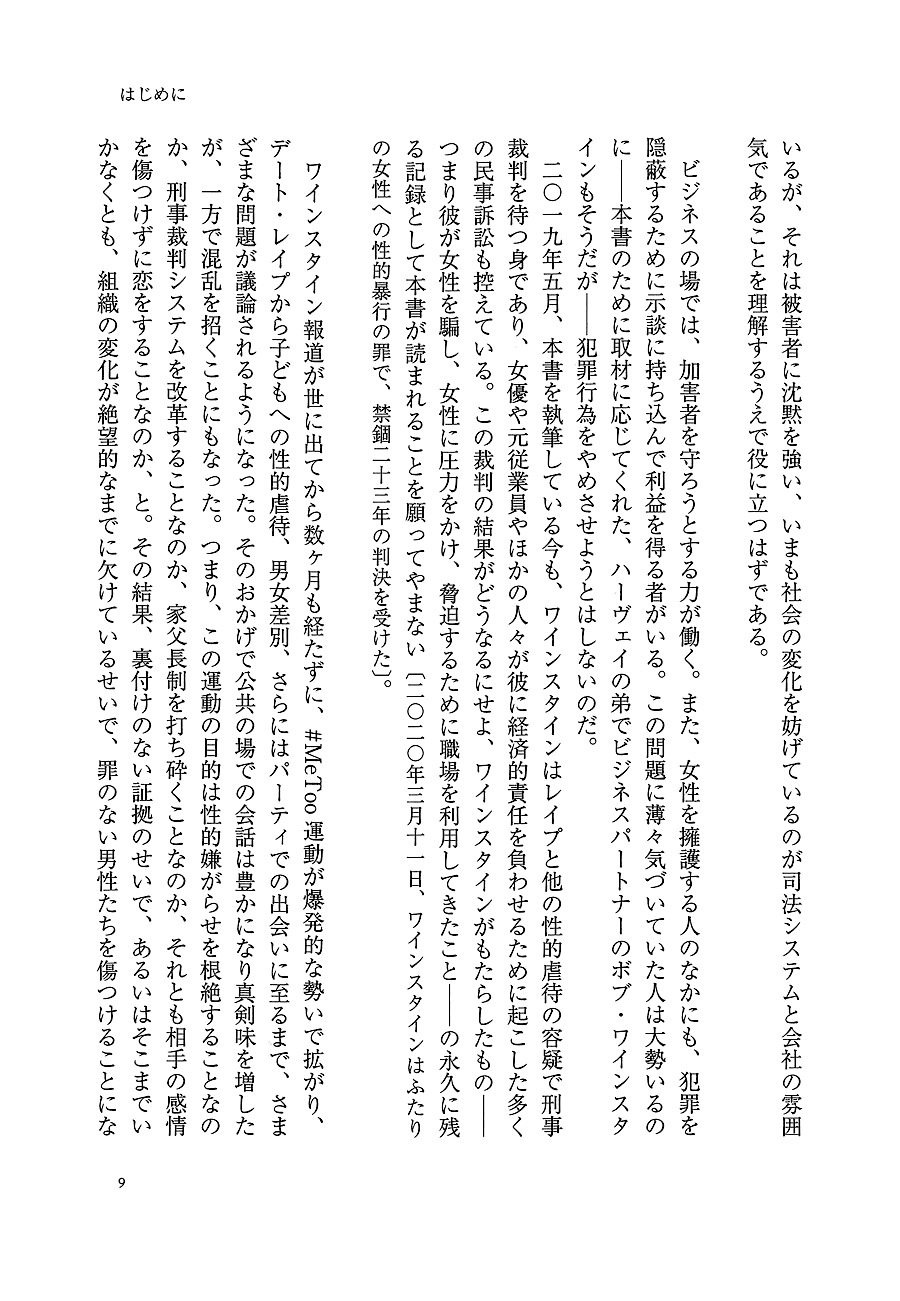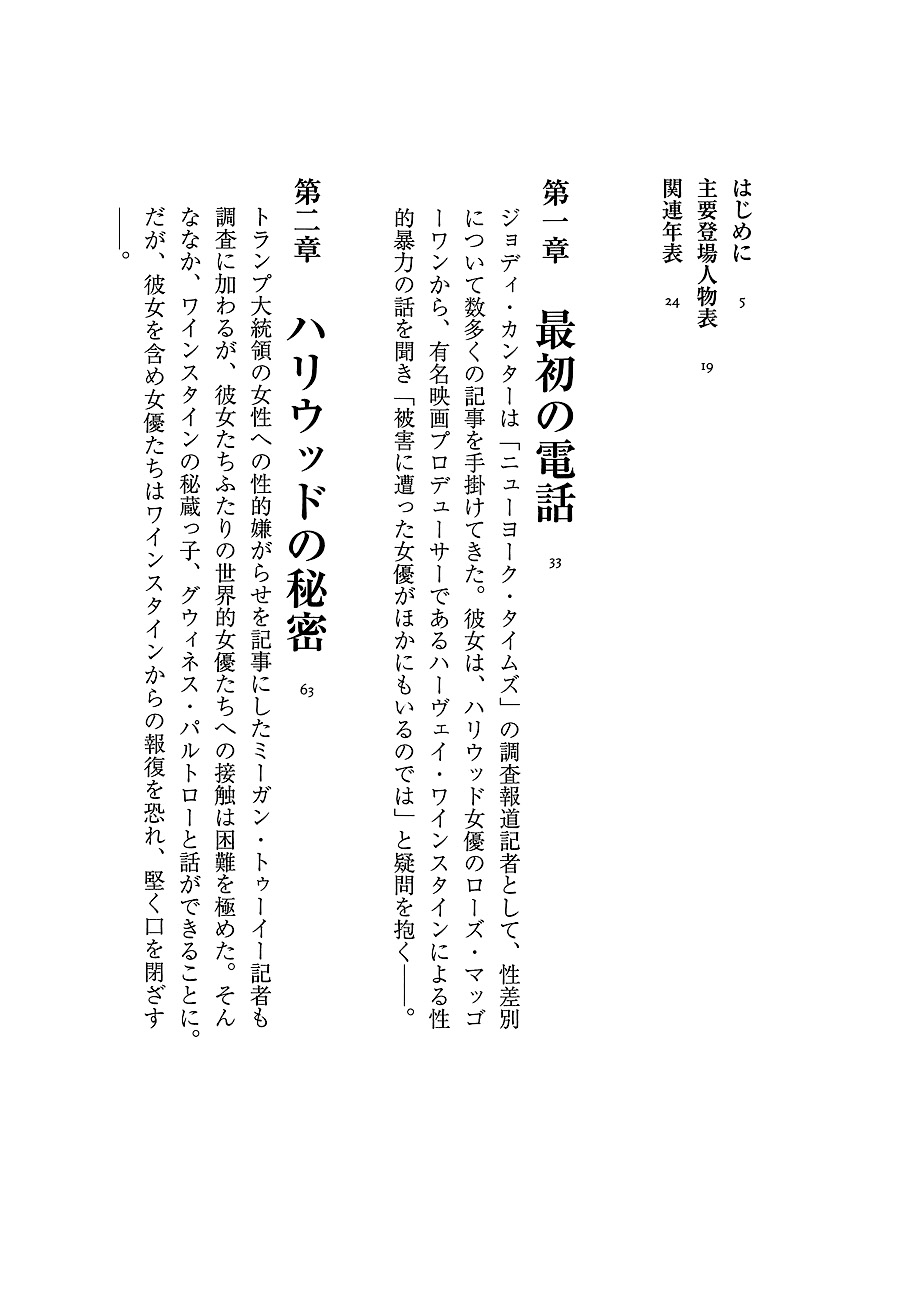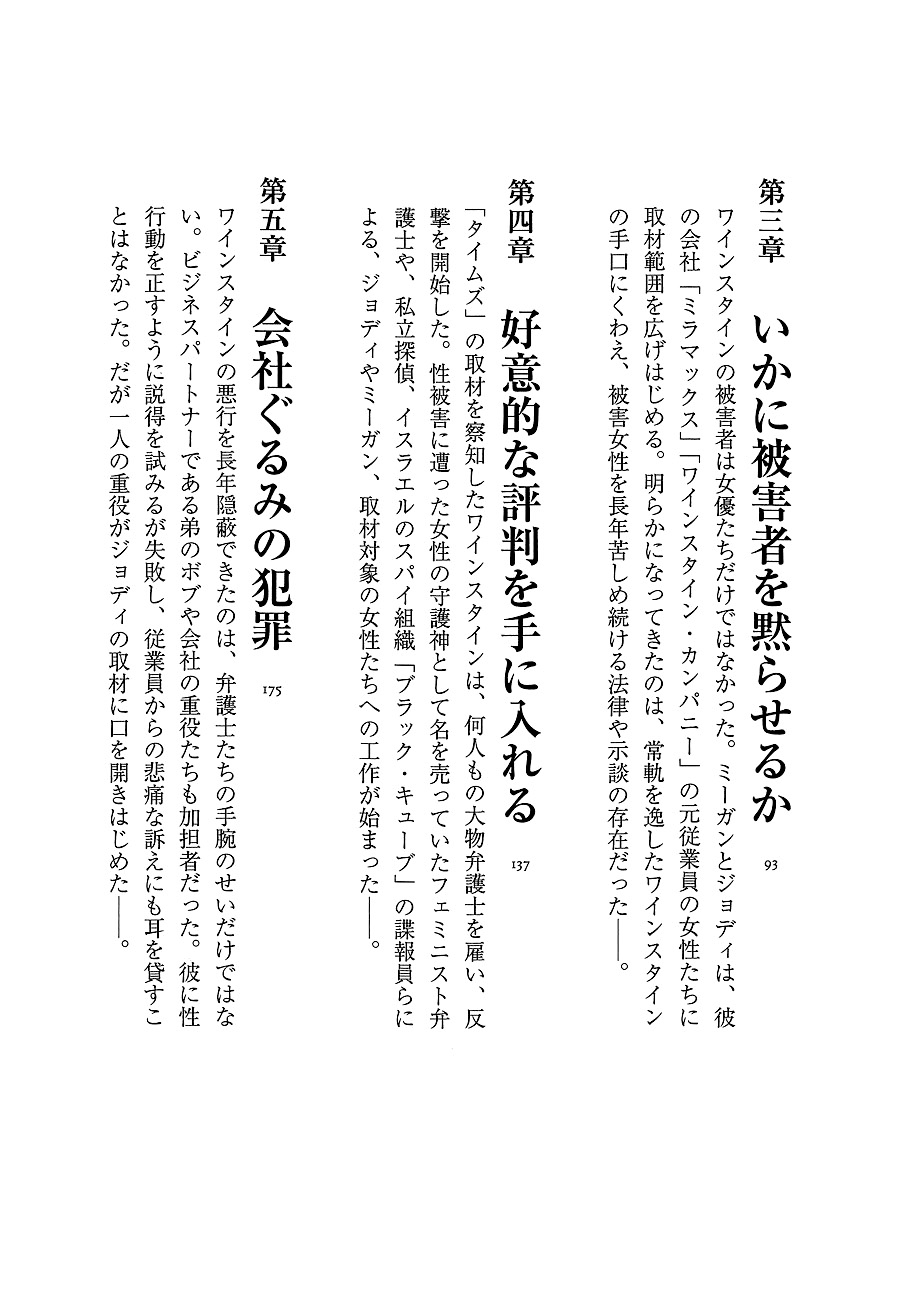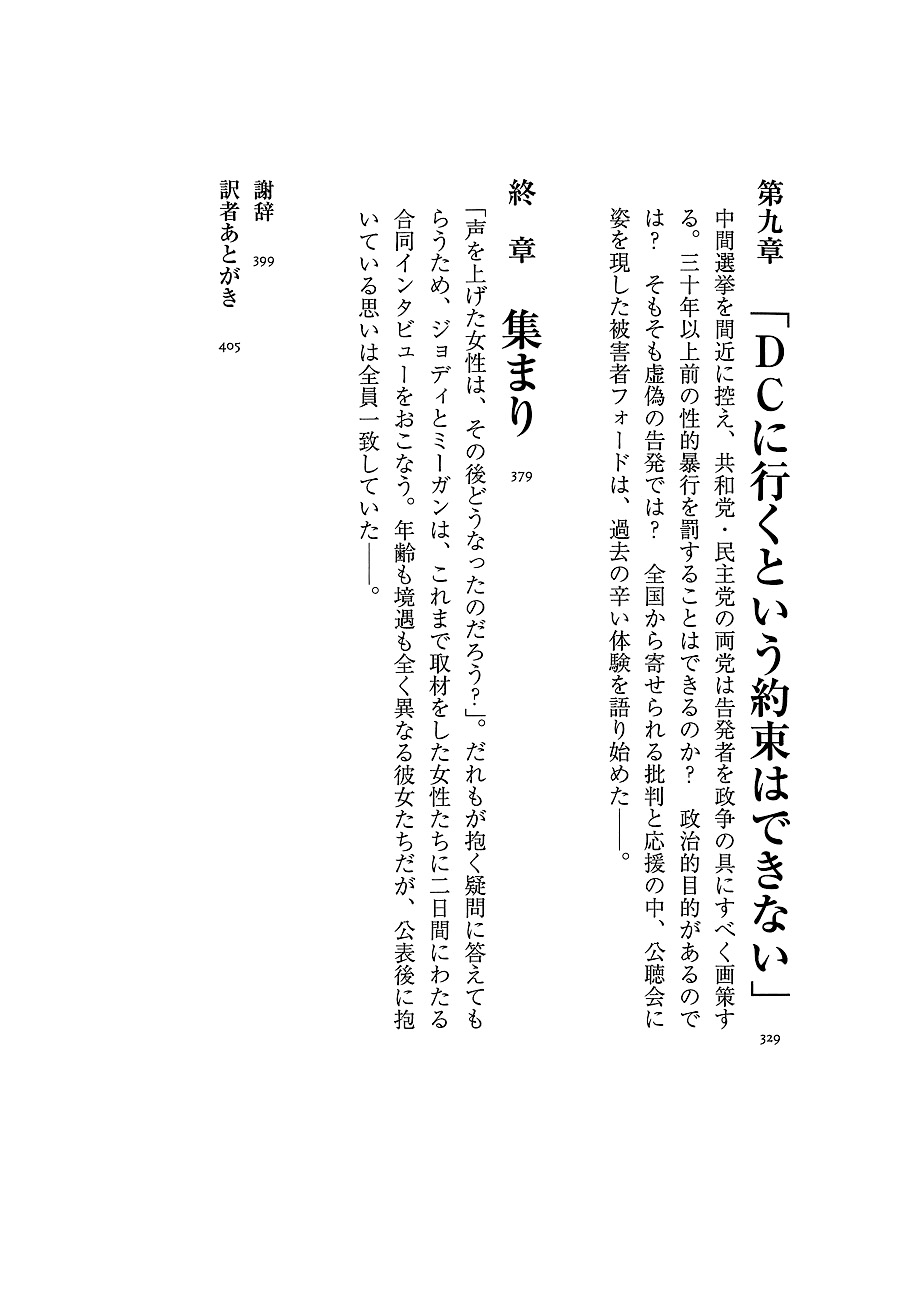はじめに
二〇一七年にわたしたちがハーヴェイ・ワインスタインの調査を始めたときには、世の中の女性はこれまでにないほどの力を手に入れていた。
警官、兵士、パイロットといった、かつては男性で占められていた職業に女性が参入し、ドイツやイギリスの首相を務めたり、ゼネラルモーターズやペプシコといった大企業を率いたりする女性も現れるようになった。三十代のひとりの女性の年収が、その母や祖母の生涯賃金を合わせた額より多くなることもあり得る時代になった。
それなのに、女性たちは絶えず性的嫌がらせを受け、その加害者はおとがめなしだった。「女性である」というだけで科学者やウェイトレス、チアリーダー、管理職、工場労働者は、体をまさぐられたり、嫌らしい目つきで見られたり、言い寄られたりしてきたが、チップや給料や出世のことを考えれば、笑みを浮かべてやり過ごすしかなかった。
性的嫌がらせは違法行為であるにもかかわらず、ある種の職業ではごく当たり前におこなわれていた。たとえ抗議の声を上げても、解雇されたり侮辱されたりすることがよくあった。被害者の多くは身を隠さざるを得ず、支援されることもなかった。被害者の取るべき最善策は、沈黙を条件に賠償という名の口止め料をもらうことだった。
その一方で、加害者である男性の多くは、ますます出世し、称賛されることが多かった。嫌がらせをした当事者が悪戯っ子のごとく受け入れられ、喝采されることもよくあった。深刻なダメージを受けることはほとんどなかった。本書の著者のひとりであるミーガン・トゥーイー記者は、ドナルド・トランプにひどい目に遭わされたと訴える女性たちに取材して記事を何本か書き、二〇一六年にはトランプが勝利した大統領選を追いかけた。
二〇一七年十月五日、ワインスタインがおこなったとされる性的嫌がらせや性的虐待に関する記事を公表してから、わたしたちジョディ・カンターとミーガンは、ダムが決壊する様子を驚きをもって見つめてきた。世界中の何百万人もの女性が一斉に、ひどい目に遭った体験を話し始めたのだ。
ジャーナリズムは、確かにこれまでもパラダイム・シフトを起こす役割を担ってきた。とはいえわたしたちの仕事は、変化の
しかし、わたしたちが大変苦労して究明した真実が世の中の意識を変えるのを見て、「なぜこの記事が?」という疑問が残った。「ニューヨーク・タイムズ」紙の編集者のひとりが指摘したように、ハーヴェイ・ワインスタインはそれほど有名ではなかった。閉塞感のあるこの世界で、どうすればこれほどまで世間を揺るがす社会的変化が起きることになったのか?
この本を書こうと思ったのはそうした疑問に答えるためだった。この変化が必然的なものであったとか、あらかじめわかっていたということは書かれていない。本書でわたしたちは、ワインスタインのまわりにあった分厚い沈黙の殻を破って最初に声を上げた勇敢な情報提供者たちが、どのような動機でこの危険を伴う決断をおこなったのか、ということを述べている。
ワインスタインのかつてのアシスタントで、ウェールズ在住の四児の母ローラ・マッデンは、ちょうど離婚したばかりで、しかも乳がんの切除手術が迫っているようなときに声を上げてくれた。
女優のアシュレイ・ジャッドは、世間にはあまり知られていないが、ハリウッドを離れて男女平等に関する研究に没頭していた時期がある。そのときの経験を踏まえて、キャリアを危険にさらしてまで語ってくれた。
ロンドン在住の
ワインスタインのもとで長期間働いていたある人物は(ここでは名前を公表することはできないが)、そこで見聞きしたことにますます悩まされるようになり、とうとう上司の犯罪を暴くために、重要な役割を演じてくれた。
この本のタイトル『彼女は語った』〔本書の原題は『SHE SAID』〕には多様な意味が込められている。声を上げてくれた方はもちろん、声を上げないことにした方々のことや、いかに、いつ、どうして彼女は語ったのか、という意味も含まれている。
これは調査報道についての本でもある。調査が始まったころは雲を掴むような具合で、わたしたちの知っていることなど無きに等しく、自身の体験を打ち明けてくれる人もほとんどいなかった。そこからわたしたちがどのようにして秘密の情報を入手し、その情報の裏を取ったのか、ひとりの権力者がこちらの調査の妨害をするために不正な手段を用いるなか、その権力者の真実をどのように追い続けたかが書かれている。さらにこれまでの記事には書かなかったが、今回初めて、記事が出る直前に、追い詰められたことを悟った当のワインスタインが、「ニューヨーク・タイムズ」の編集局に乗り込んできて、最後の直接対決をおこなった時の様子も収録した。
「ニューヨーク・タイムズ」がワインスタインについて報道したのは、「フェイク・ニュース」が非難され、「真実に対する国家の合意」という概念そのものが崩壊しているように思える時期だった。ワインスタインの犯罪が暴かれたことによる衝撃は非常に大きかったが、それは「ニューヨーク・タイムズ」のジャーナリストたちが、その犯罪について、だれが見ても疑問の余地のないくらい確固とした証拠を固めることができたためでもあった。その記事では、被害者本人による証言や金銭的な記録、法廷記録、会社のメモ、その他の明らかにされたデータを使って、わたしたちがどのようにして繰り返しおこなわれていた犯罪を実証したか、を記している。
最初のワインスタインの記事が発表された後の公開討論などで、彼が女性に対しておこなったことに関して話し合われたことはなかった。もっぱら、どんな対応をすべきだったかが話し合われていた。しかしワインスタインは、合意なき性行為をしたという告発をすべて否定し続け、いまもわたしたちの報道が事実に反していると繰り返し主張している。ワインスタインのスポークスマンは、わたしたちが彼の犯罪を立証した記事に対する回答を求めたとき、「あなたがたの記事にあるのは非難や言いがかりであって、完璧な事実はない」と述べた。
本書は、二〇一七年のワインスタイン報道をおこなう過程でわたしたちが知った情報と、それ以降に収集した大量の情報とで成り立っている。ワインスタインに関する新しい情報もかなり加えられているが、それは被害者に沈黙を強い、いまも社会の変化を妨げているのが司法システムと会社の雰囲気であることを理解するうえで役に立つはずである。
ビジネスの場では、加害者を守ろうとする力が働く。また、女性を擁護する人のなかにも、犯罪を隠蔽するために示談に持ち込んで利益を得る者がいる。この問題に薄々気づいていた人は大勢いるのに――本書のために取材に応じてくれた、ハーヴェイの弟でビジネスパートナーのボブ・ワインスタインもそうだが――犯罪行為をやめさせようとはしないのだ。
二〇一九年五月、本書を執筆している今も、ワインスタインはレイプと他の性的虐待の容疑で刑事裁判を待つ身であり、女優や元従業員やほかの人々が彼に経済的責任を負わせるために起こした多くの民事訴訟も控えている。この裁判の結果がどうなるにせよ、ワインスタインがもたらしたもの――つまり彼が女性を騙し、女性に圧力をかけ、脅迫するために職場を利用してきたこと――の永久に残る記録として本書が読まれることを願ってやまない〔二〇二〇年三月十一日、ワインスタインはふたりの女性への性的暴行の罪で、禁錮二十三年の判決を受けた〕。
ワインスタイン報道が世に出てから数ヶ月も経たずに、#MeToo運動が爆発的な勢いで拡がり、デート・レイプから子どもへの性的虐待、男女差別、さらにはパーティでの出会いに至るまで、さまざまな問題が議論されるようになった。そのおかげで公共の場での会話は豊かになり真剣味を増したが、一方で混乱を招くことにもなった。つまり、この運動の目的は性的嫌がらせを根絶することなのか、刑事裁判システムを改革することなのか、家父長制を打ち砕くことなのか、それとも相手の感情を傷つけずに恋をすることなのか、と。その結果、裏付けのない証拠のせいで、あるいはそこまでいかなくとも、組織の変化が絶望的なまでに欠けているせいで、罪のない男性たちを傷つけることになってしまったのではないか。
わたしたちがワインスタインの事件を報道してから一年近く経ったとき、カリフォルニアの大学の心理学教授クリスティン・ブレイジー・フォード博士が、アメリカ合衆国上院の司法委員会の公聴会に出席し、当時最高裁判事に指名されていたブレット・カバノーを、高校時代に酔っ払って彼女に性的暴行をしたと訴えた。カバノーは激怒してその容疑を否認した。フォード博士を#MeToo運動の最高のヒーローだと見なす人がいたが、その他の人々は、彼女をペテン師――増える一方のバックラッシュに対する弁護者――と見なした〔バックラッシュとは、ある動きが高まりを見せる時に生じる
わたしたちはフォード博士を、「彼女が語った」話のなかでも、もっとも複雑で人柄がにじみ出る話の主人公だと見ていた。大勢の人々に囲まれた上院の司法委員会で証言するに至るまでの彼女の道のりについて、世間が何も理解していないことがわかったときから、とりわけそう考えていた。ジョディは公聴会の現場で彼女の様子を観察し、フォードの弁護団の働きぶりを注意深く見つめ、その翌日フォードに面会した。十二月には、カリフォルニア州パロアルト市で朝食をとりながら、ミーガンがフォードの公聴会後初のインタビューをおこなった。それからミーガンは数ヶ月をかけて追加取材し、フォードがなぜ進んで声を上げることにしたのか、その結果どうなったのかについて話を聞いた。実際に彼女の経験を目撃したりした人たちにも取材した。そして、司法委員会で証言するまでの経緯や、さまざまな意見や慣習、政治的勢力、恐怖心などがいかに彼女を追いつめていったかについても本書にまとめている。
証言の後、彼女はどうしているか、多くの人が案じている。本書の「終章」には、非常に貴重な集団インタビューが収められている。フォードをはじめ、取材に応じてくれた女性たち(それぞれが異なる記事に登場している)に集まってもらった。フォードの旅路にも、見過ごすことのできない大きな問題があった。それは、なにが進歩を妨げたり促したりするのか、という終わりのない問いだ。#MeToo運動はこの時代に社会が大きく動いた格好の例だが、それは同時に試金石でもある。このばらばらになった状況で、男女双方にとって公平な規則と保護という新しい組み合わせを作り出すことができるのだろうか。
本書は、アメリカの女性たちのあいだで起きた二年間の驚くべき記録である。この記録はあの二年間を生きたすべての人のものだ。秘密を隠蔽する政府や、企業の秘密を扱う調査報道とは違い、わたしたちの調査は、多くの女性が生活の場や職場、家庭、学校で体験したことをもとにしている。とはいえ、わたしたちがこの本を書いたのは、みなさんをできる限り#MeToo運動の発端へと引き戻したかったからだ。
あの出来事をできるだけ直接かつ忠実に再現するために、本書ではインタビューや電子メール、その他のさまざまな文章を引用した。ワインスタインの件で映画スターたちと初めて話し合ったときのメモ、弟のボブ・ワインスタインが兄に送った手紙、フォード博士のメールの抜粋のほか、直接入手した資料も入っている。もともとはオフレコ〔報道を前提としていない発言〕であったが、追加取材をして関係者に再度話を聞くうちに掲載が叶った発言もある。わたしたちが立ち会うことのなかった対話や出来事を描くことができたのは、さまざまな記録やインタビュー記事のおかげである。本書のなかの発言はみな、ロンドンやパロアルトまで出向いていき、三年間にわたって何百回もおこなったインタビューに基づいている。
最後になるが、この本は、一連の出来事を取材しているあいだにふたりで育んだ協力関係の記録である。混乱を避けるために、章のなかではわたしたちを示す人称は三人称とした(一人称で書くと、共同作業としてはそれでいいのだが、双方の手がかりを追いかけるときなどには、「わたし」がジョディなのかミーガンなのかを確認するのに手間取ることが多かった)。その三人称が始まる前に、いわばわたしたちふたりの声で「はじめに」を書きたかった。本書を執筆するにあたって協力してくださったみなさん、出来事や手がかりを真剣に検証し、わたしたちが目にしたり耳にしたりしたことを確認してくださったみなさんに心からお礼を申し上げる。ありがとうございました。
その名を暴け・目次
主要登場人物表
関連年表
訳者あとがき

第一章 最初の電話
「ニューヨーク・タイムズ」紙〔以下「タイムズ」と略〕がハーヴェイ・ワインスタインの調査を始めたとき、もっとも有力な情報提供者からは電話での取材すら拒否された。
「つまり、わたしはこれまでずっとそちらの新聞からはずいぶんひどい扱いを受けてきました。その根っこにあるのは性差別ですね」。これが、ジョディからの取材依頼のメールに対して、女優のローズ・マッゴーワンが二〇一七年五月十一日木曜日に返してきた文章だった。マッゴーワンは自分を批判した記事の一覧を作っていて、この非難は「タイムズ」が政治集会の夕食会でおこなった彼女のスピーチを、ニュース欄ではなくファッション欄で取り上げたことがあったからだ。ワインスタインのことで「タイムズ」の記者とマッゴーワンが交わした取材当初の会話は気分のよいものではなかった。
「『タイムズ』はこれを女性差別問題として捉えなければおかしい」とマッゴーワンは書いていた。「そうでなければ、手を貸す気にはとてもなれません」
その数ヶ月前にマッゴーワンは、あるプロデューサーにレイプされたと訴えていた。噂ではワインスタインのことだと言われていた。「ハリウッドやマスコミのあいだでそのことは公然の秘密で、関係者はわたしを侮辱する一方で、レイプした相手には媚びへつらっていた」と、彼女は#WhyWomenDontReport〔どうして女性たちは声を上げないのか〕というハッシュタグを付けてツイッターに投稿した。いまは、エンターテインメント業界が女性におこなった差別を明らかにするために回想録を執筆しているという〔二〇一八年に『Brave』というタイトルで出版〕。
大半のハリウッド関係者とは異なり、マッゴーワンはこれまでも自身のキャリアを危険に晒して女性差別を訴えてきた。一度など、アダム・サンドラー〔アメリカで人気のコメディ俳優、映画プロデューサー〕の配役メモに書いてあった「胸の谷間が見えるようなタンクトップ(ブラジャーを押し上げるように促す)」という衣装への要求には我慢できなかった、とツイッターに書き込んだ。ソーシャルメディアでの彼女の口調は概して激しく、攻撃的だった。一ヶ月前には「怒ったっていいの。怒るのを恐れないで」とツイートし、さらに、「システムを解体せよ」と付け加えていた。女優であり活動家でもあるマッゴーワンが
ハーヴェイ・ワインスタインは、もはやそれほど重要な人物ではなかった。最近では彼の映画製作における魔力はすっかり衰えていた。とはいえ、その名前は“権力”と同義語だった。
彼には人を出世させてキャリアを積ませる力があった。まず初めに、彼はプロデューサーとしての自分を作り上げた。ニューヨーク州クイーンズの質素な家に育ち、コンサート・プロモーションから映画の配給、製作へと進んだ。映画やパーティ、なによりも人々など、まわりにあるものすべてをさらなる成功へと導く方法を知っているかのようだった。若い俳優を何度も何度もスターダムに押し上げてきた。そのなかに、グウィネス・パルトロー、マット・デイモン、マイケル・ウィリアムズ、ジェニファー・ローレンスがいる。さらに、『セックスと嘘とビデオテープ』(一九八九)〔『オーシャンズ11』(二〇〇一)などを手がけたスティーブン・ソダーバーグの監督デビュー作〕や『クライング・ゲーム』〔一九九二年製作の映画で、第六十五回アカデミー賞脚本賞を受賞〕といった小さな
二〇一七年の時点では、彼の製作する映画は以前ほどの成功を収めていなかったが、その名声は相変わらず桁外れだった。
ワインスタインの女性への扱い方がひどい、という噂は以前から囁かれていた。人々はそれにまつわる冗談を公の場で口に出したりもした。二〇一三年のアカデミー賞助演女優賞候補者発表のときにコメディアンのセス・マクファーレンは、「おめでとうございます、みなさん。あなたがた五人はもう、ハーヴェイ・ワインスタインの魅力にまいっているという振りをしなくてもいいんですよ」と述べた。しかし多くの人々はワインスタインのひどい態度を恋の戯れとして見逃してきたし、それについて公に報道されたことは一度もなかった。過去に記事を書こうとしたジャーナリストもいたが、みな失敗した。二〇一五年、ニューヨーク市警察(NYPD)がワインスタインに体をまさぐられたとする訴えをあるモデルから受けて調査をおこなったが、結局なんの容疑もかけられずに終わった。
当時、ジャーナリストのジェニファー・シニアはツイッターで次のような言葉を投稿している。「ハーヴェイ・ワインスタインを告発するのを恐れている女性たちは、いずれ、手を携えて立ち上がるだろう」
それから二年が過ぎた。なにも起こらなかった。ジョディは、ふたりの記者(ひとりは「ニューヨーク・マガジン」のライターで、もうひとりはテレビ局NBCのローナン・ファロー)がワインスタインの性暴力を記事にしようとしているという噂を耳にしたが、そうした記事が掲載されることはなかった。
では、ワインスタインの女性へのひどい扱いにまつわる噂は間違っていたのか? マッゴーワンがツイッターでほのめかしていた相手は別人だったのか? ワインスタインは人前では、フェミニストの信任を得ていると自慢していた。グロリア・スタイネム〔アメリカの女性解放運動家、作家〕の名を冠した講座を大学に作るために、かなりの金額を寄付したばかりだった。彼の会社は、大学構内での性的虐待事件についてのドキュメンタリー映画であり、構内での性的暴行反対のスローガンにもなった『ハンティング・グラウンド』(二〇一五)を配給した。二〇一七年一月、大統領に就任したトランプの女性蔑視・差別に抗議し、各地でおこなわれた歴史的なウィメンズ・マーチに参加もした。同年のサンダンス映画祭〔アメリカの独立系映画を対象とした大規模の映画祭〕で、ユタ州のパークシティに集まったピンク色の猫帽子を被った女性たちのデモ行進に加わったのである。
「タイムズ」の調査報道部は、編集局の他部署の騒音が聞こえないところにある。調査報道部の目的は、これまで報道されていない出来事を掘り起こし、人々や組織が故意に隠してきた犯罪を明らかにすることである。まずは充分に気をつけて取材対象者と接触するところから始まる。マッゴーワンにどのように返信すれば、電話取材を受ける気になってくれるだろう。
彼女のメールはチャンスだった。マッゴーワンがメールに返信してきたのだ。そんなことをする人はめったにいない。彼女は自分の考えをメールに書き、批判する際には充分に気を遣っていた。もしかしたらジョディを試していたのかもしれない。「タイムズ」をちょっとけなしてみて、新聞を弁護するかどうか確かめたかったのかもしれない。
とはいっても、ジョディは十四年間在籍している職場のことで言い争うつもりはなかった。また、マッゴーワンに「あなたのツイートはとても勇敢だと思う」などというお世辞を言いたくもなかった。そんなことを言えば、やりとりをするうえでジョディが持ち合わせている、わずかな権威も消え失せてしまうだろう。それに、マッゴーワンに協力してもらいたいと思っている調査については、知らせることがまだなにひとつ手許にないのだ。マッゴーワンから、何人の女性に取材したのかと訊かれたら、ひとりもしていない、と答えることしかできない。
メールには、ワインスタインの名前を出さずに、そのことを伝えなければならない。マッゴーワンは、アダム・サンドラーの配役メモを投稿したように、ツイッターに個人的な活動の様子を投稿していた。彼女は不正を暴きたがるタイプだが、そうした行為はこの状況では逆効果を生みかねない(「ねえ、みなさん、この『タイムズ』の記者からのメール、よく見て」などと投稿される可能性もある)。この問題に限っては、非常に慎重な対応を取らなければならない。マッゴーワンはかつて、自分はレイプの被害者だと言ったことがある。彼女に無理強いすることだけはしてはならないのだ。
ジョディが企業やほかの組織で女性の身に起きた出来事について調査を始めたのは、二〇一三年のことだ。アメリカ合衆国における性差別の議論は、意見欄や回想録、ソーシャルメディア上での怒りの表現や女性同士の繋がりなどという形でおこなわれ、すでに充分に感情的になっている状態だった。隠されている差別、とりわけ職場での性差別をもっと明るみに出すことが求められていた。
超エリートから下働きにいたるまで、従業員というのは雇用者側に質問する際に
ジョディはそうした自分の経験に触れながら、ローズ・マッゴーワンに返事を書いた。
「こうした問題に関するわたしの実績は次のとおりです。アマゾン、スターバックス、ハーバード・ビジネス・スクールは、わたしが明らかにした女性差別問題に対応すべく、方針をすっかり転換しました。ホワイト・カラーの女性たちは仕事中に搾乳できますが、低賃金で働く女性たちにはそれができません。この母乳育児に階級差があることを記事にしたときには、読者たちが史上初の可動式授乳部屋を作り、いまでは全米で二百室以上が設置されています。
どうしてもお話ししていただけないというのなら、それでかまいません。ご著書の出版がうまくいくことを祈っています。さようなら、ジョディ」
数時間以内にマッゴーワンから返信が来た。水曜日の前ならいつでも電話で話せる、とのことだった。
この電話取材はなかなかに大変そうだった。丸刈り頭のマッゴーワンは、たちまち戦闘態勢に入りかねず、ツイッターに情報を投稿する一筋縄ではいかない女性のように見えたからだ。ところが受話器からは心に響く元気な声が聞こえてきた。話したいことがあり、その正しい伝え方を手探りしているようだった。彼女がレイプについてツイートした内容はほんのわずかだったので、詳しいことはわからなかった。
特別な取り決めがない限り、交わされた会話は記録され、そこで得た情報は公開される、というのが取材における一般的なルールだ。しかし、ワインスタインに暴行されたと主張する女性は、だれであっても、初めは話すことすら気が重いに違いない。それでジョディは、公開への合意が取れないうちは
一九九七年、マッゴーワンはサンダンス映画祭へ意気揚々と向かっている若手の新人女優だった。映画祭ではプレミアとパーティを行き来し、テレビ・カメラに追いかけられた。それまでに彼女は、『スクリーム』(一九九六)といった若者向けホラー映画に四、五本出演しただけだったが、この映画祭で上映される夥しい数の新作映画のなかで、注目すべき新人女優のひとりになっていた。「わたしはサンダンスの花だった」と彼女は語っている。
マッゴーワンの話では、それが何年のことだったかはっきり覚えていないという。過去を思い出して語るとき、多くの女優は何年何月という日付ではなく、自身の出演した映画が撮影されたり公開されたりした時期を基準にする。マッゴーワンは、ワインスタインの右に座って映画を観ていたことを覚えていた。それが『インディアナポリスの夏 青春の傷跡』〔原題の『Going All the Way』は「セックスまでする」という意もあり〕というタイトルなの、と彼女は苦々しい笑い声を立てた。
その後で、ワインスタインが話し合いをしようと言ったのは無理もなかった。一流の映画プロデューサーが将来性のあるスターと会いたがっているのだ。
彼女はパークシティのホテル「ステイン・エリクセン・ロッジ・ディアバレー」まで行き、ワインスタインの部屋で会った。映画と配役にまつわるありふれた話をした以外、変わったことは何もなかった、とマッゴーワンは言っている。
だが、マッゴーワンによれば、部屋を出ようとするとワインスタインが彼女をお湯を張った浴槽のある部屋へ引きずり込み、浴槽の縁のところで彼女を裸にし、彼女の股のあいだに自分の顔を強引に押しつけた。自分の魂が体から離れていって、天井あたりに浮かんで、そこから見下ろしているような感じだった、という。「ものすごいショックを受けたの。なんとかこの場から生き延びて帰ろうという心理状態になってた」。そこから逃れるために、オーガスムに達したふりをし、頭のなかで体に向かってひとつひとつ命令を下した、と彼女は語っている。「ドアの取っ手を回せ」、「この場から出ろ」と。
数日後、ロサンジェルスの彼女の自宅の電話にワインスタインから伝言が入った。身の毛がよだつような内容だった。「ほかの大女優たちはぼくの“特別な友だち”で、その仲間にきみも入れるよ」。衝撃を受け動揺した彼女は、マネージャーに事情を打ち明け、弁護士を雇い、ワインスタインから十万ドルの示談金をもらい、一件落着になった。しかしその示談金の授受は、ワインスタインの悪行について不問に付して公言しない、ということが条件だった。マッゴーワンはその金をレイプ・クライシス・センターに寄付したと述べている。
その示談の書類は彼女の手許にあるのか? 「向こうが一枚のコピーもよこさなかった」とマッゴーワンは言った。
問題はワインスタインだけが最低ではないってこと、と彼女は言った。ハリウッドは女性への虐待を組織的におこなっている。名声を餌にして女性たちをおびき寄せ、高額の利益を生みだす商品に変え、その体を所有物のように扱い、完璧な姿に見えるよう命じ、それから放り出す。この電話取材で、彼女は次から次へ、ひっきりなしに非難した。
「ワインスタインだけじゃない。ひとつの大きなシステムになっていて、次々と供給されてくる」
「監視されていないから、恐れてもいない」
「どのスタジオも被害者を侮辱してはお金を払っている」
「大半の者がNDA〔秘密保持契約書〕を交わしている」
「白人男性の遊び場があるとしたら、ハリウッドはまさにそれよ」
「ここでは、悪いのは女のほうなわけ」
「列から離れちゃだめ。すぐに代わりの女が来る」
マッゴーワンの言葉には注目せざるをえなかった。ハリウッドが女性たちを利用し、無理矢理従わせ、女性が歳を取ったり反抗的になったりすると追放するようなところだという発言は、別段目新しいものではない。だが、有名女優の口から直接、ひどい扱われ方をしたことの詳細や、ハリウッドでもっとも有名なプロデューサーに利用されたということを聞くのは、それとはまったく違うことだった。切実で、より具体的で、吐き気を催すことだった。
すぐにまた話し合う約束をして、この電話取材は終わった。マッゴーワンは
新聞の義務は公平であることだ。とりわけ容疑の重大さを考えれば、公平な上にも公平を期さなければならない。
二〇一四年に、「ローリング・ストーン」誌が、十全な証拠を入手しないまま、ヴァージニア州立大学における「キャンパス内のレイプ事件」という記事を掲載した。後に続く議論は多くの訴訟へと発展し、雑誌の評判を落とし、レイプの話は女性たちのでっちあげだと主張する者たちに有利な情報を提供し、大学構内のレイプ根絶運動の足を引っ張る羽目になった。「ワシントン・ポスト」紙は、警察がこの事件を「完全なでたらめだ」と言ったと報じ、「コロンビア・ジャーナリズム・レヴュー」誌は「へま」と報じ、この記事は「エラー・オブ・ザ・イヤー」賞を獲得した。
一見したところ、マッゴーワンの発言はワインスタインから抗議されたら持ちこたえられそうになかった。ワインスタインにしてみれば、「自分が覚えているのはそれとはまったく違った内容だ、彼女は楽しんでいるみたいだった」と容易に主張できそうだった。彼には完璧な証拠があった。彼女がオーガスムに達したふりをしたという部分だ。当時の留守番電話に残されていたメッセージでもあれば重要な証拠になるので、ワインスタインがプロデューサーの権限を利用して性的行為を強要したことを証明できる。しかし、そのメッセージを記録した当時のテープがなければ、記憶に頼るだけになり、マッゴーワンの証言は簡単に否定されてしまう。
記憶に頼った体験談しかないのならば、「言った、言わない」の水掛け論になる可能性が高い。マッゴーワンが恐ろしい体験談を話す。ワインスタインがそれを否定する。目撃者がいないので、人々はどちらかの側につき、結局、マッゴーワン・チーム対ワインスタイン・チームで闘うことになる。
しかしマッゴーワンは、示談になったと言った。その記録を見つけ出すことは難しいだろうが、弁護士がいて、署名された示談書、支払われた金、レイプ・クライシス・センターへの寄付金がある。示談書はどこかに記録されているはずだ。ホテルの部屋で起きたことを証明できなくとも、係争になったときには、ワインスタインが相当な額をマッゴーワンに支払った証拠があれば、なんらかの助けにはなる。
ジョディは入手した情報をすべて携えて、「タイムズ」の先輩で、込み入った事件の調査が得意な編集者、レベッカ・コルベットのところへ相談にいった。ふたりはマッゴーワンの主張に裏付けが取れるかどうかについて話し合い、重要な疑問を抱いた。ほかの女性もあの男に同じ目に遭わされているのではないか、と。
それを突き止めるのは大仕事になりそうだった。ワインスタインはこの何十年ものあいだに何百という映画作品を手がけてきた。彼の弟ボブは、ワインスタインのふたつの会社、ミラマックス社と、ミラマックスを手放した後で、目下力を入れているワインスタイン・カンパニー(TWC)の共同所有者兼共同経営者だ。つまりそれは、ワインスタインについての情報源がたくさんあるということで、少人数だけで決定的な情報を保持している状況よりはるかにましだった。とはいえ、連絡を取るべき相手が数え切れないほどいた。女優や元従業員は世界中に散っていて、その多くが話すことを
六月半ば、コルベットはジョディに、同僚のミーガン・トゥーイー記者に連絡を取るよう助言した。ミーガンが「タイムズ」に入ってきたのは、比較的最近のことだ。「ミーガンはいまは出産休暇を取っているけれど、性差別の問題に関してはだれよりも詳しい」とコルベットは語った。ジョディはミーガンがどのような協力をしてくれるかわからなかったが、ともかくメールを送った。
ジョディからメールが届いたとき、ミーガンは生まれたばかりの赤ん坊の世話をしていて、これまでの経歴のなかでもっとも心に傷を残した出来事から回復しつつあった。
ミーガンが二〇一六年二月にニューヨーク・タイムズ社に入ってすぐに命じられたのは、大統領候補について調べて政治記事を書くことだった。彼女は躊躇いながらもその仕事を引き受けた。実は政治は彼女の得意分野ではなく、興味もなかった。
ところが入社して何週間も経たないうちに、「タイムズ」の編集長ディーン・バケットがミーガンに依頼したのは、彼女の専門知識を必要とする一連の特別調査だった。それは、「ドナルド・トランプの女性への態度は、法的または倫理的な一線を越えているのではないか」という問題だった。
ミーガンは、十年以上、性犯罪と性的違法行為を暴く記事を書いてきた。シカゴでは、その地区の警官と検察官がレイプ・キット〔レイプ被害者の体に付着した犯人の体液や毛髪など、逮捕の手がかりとなる残留物を採取保存する器具、それによって採取した証拠物件〕を握りつぶしたり、公正な裁判を受ける被害者の権利を奪ったりしていることや、性的暴行をおこなった医師がいまだ診察を続けていることなどを暴いた。その後も、養子縁組みをした児童を売買する闇市場の記事を書き、性的搾取者に子どもたちが売られていることを明らかにした。
トランプは長いあいだ自分をプレイボーイに仕立ててきた。あるいは、少なくともプレイボーイの劣化版を演じてきた。彼はその頃、三人目の妻と共に大統領選に出馬していた。しかし、人気パーソナリティのハワード・スターンのラジオ番組で自身の“性的偉業”を
バケット編集長は、トランプの虚勢の下に危険なものが隠れている、と見抜いていた。
もしトランプが見境なく女性と関係を持つような男というだけなら、なんの記事にもならない。「タイムズ」は人の性生活を覗くことはしないし、ましてや相手が大統領候補なら、よほどの理由がない限り記事にはしない。だが、トランプの発言のなかには、職場で発せられたものがあった。それは性的嫌がらせをおこなっていた証かもしれない。自身でプロデュースして出演もしている番組「セレブリティ・アプレンティス」で、トランプはある参加者に「両膝をついたら、いい映像になるだろうな」と述べた。何十年も前に、トランプの最初の妻イヴァナ・トランプは、夫婦間レイプをされたと告発したと報じられたが、やがてその訴えを引っ込めた。バケットは、トランプの女性の扱い方を調査するためにもうひとりの記者マイケル・バルバロの協力をあおいだ。彼がバルバロとミーガンに調べてほしかったのは、トランプの女性に対する態度が無礼なだけか、それとももっと深刻なものか、という点だった。
初めの頃、この調査は遅々として進まなかった。トランプの会社の元従業員の大半は秘密保持契約で縛られていて、それに逆らった者がトランプにひどい目に遭わされたことがあり、それでいまも彼らは怯えていた。また、トランプに対しては何年にもわたって
とはいえ、二〇一六年五月には、ミーガンとバルバロは記事を書く準備ができた。何百もの記録を調べ、トランプの下で働いていた人物や彼とデートした人物、社会的に交流があった人物など五十人以上を取材した。トランプは精力的な人物で、これまで女性に対して矛盾する態度を取ってきた。いっしょに働く女性たちに優しく親身に対応し、会社の重役にまで出世させた女性が何人もいた。しかし同時に、女性の身体のことでひっきりなしに意見を述べたり、職場での仕事を混乱させたりする傾向があった。
この記事は、ミーガンがイヴァナのレイプ告発のほかにも、複数の女性からの性的暴力の訴えを取材しまとめたという点で、とても重要なものだった。
元ミス・ユタ州の女性は、一九九七年にトランプが彼女に二度強引にキスした、と訴えていた。一度目はミスUSAコンテストの後の祭典で、二度目は彼のオフィスで今後のモデルの仕事について話し合いをした後で。また、トランプの美人コンテストの元共同主催者は、ずいぶん前にふたつの訴訟で彼を告発していた。プラザ・ホテルで仕事がらみの夕食会をしたとき、トランプがテーブルの下から彼女の体を撫で回し、さらには別の仕事の会合のときには彼女を部屋に連れこんで無理矢理「キスし、愛撫し」、彼女が部屋から「出られないようにした」という。
用心に用心を重ねなければならなかった。もし記事のなかにたったひとつでも怪しいものがあれば、記事全体の質が疑われてしまう。
ある美人コンテストの出場者がミーガンに訴えたのは、トランプのパーム・ビーチの別荘で、彼に体をまさぐられたので慌てて自分の部屋に戻り、
大勢の女性たちが自らの言葉で語った体験で構成されたこの記事は、二〇一六年五月十四日土曜日の夜明け(東部標準時)に発表されたとたん、たちまち爆発的に読まれ、結果的に一年間でいちばん読まれた「タイムズ」の政治記事になった。自分に批判的な記事には残忍なまでに攻撃をしかけることで有名なトランプが、その週末になんの発言もしなかったので、それが記事に書かれた内容の正しさを証明しているように思えた。記事を発表する前、ミーガンとバルバロはトランプに長いインタビューをおこない、「性的不適切な行為などしていない、いつも女性には敬意を持って接している」と主張する彼の言葉も記事のなかに加えた。
月曜日の朝、ミーガンとバルバロは「CBSディス・モーニング」というニュース番組の控え室で、今回の記事についてインタビューされる準備をしていた。そのとき、CBSの名物ジャーナリストのガイル・キングが部屋に入ってきてテレビを指さした。「ねえ、見た? ローワンヌ・ブルーワー・レーンがさっき『FOX・アンド・フレンズ』〔FOXニュースの朝の情報番組〕に出演して、あなたたちの記事をこき下ろしてた」
ブルーワー・レーンは「タイムズ」の記事のなかでいちばん初めに登場する人物だった。取材によれば、モデルだった彼女は一九九〇年にマー・ア・ラゴ〔トランプの所有するパーム・ビーチの別荘で歴史的価値のある建物〕で開かれたパーティでトランプと出会った。記事のなかで彼女は、トランプに一室に案内され、ビキニを着るように強要され、それを着た後でゲストたちの前に連れていかれた、と述べた。ブルーワー・レーンが異を唱えているのは、ふたりの交流を説明する彼女自身の発言についてではなかった。彼女が賛同できなかったのは、「タイムズ」が「トランプがよく知りもしない若い女性と品のない出会い方をした」という風に記述したことだった。
彼女についての記述は、五千語から成る記事の中のほんのいくつかの段落分しかない。その中のひとつの段落でブルーワー・レーンがトランプとデートしたことを指摘したに過ぎなかった。しかし彼女がテレビで「タイムズ」の記事を批判したおかげで、トランプは記事全体を攻撃する足がかりをかろうじて得ることができた。彼はすぐさまブルーワー・レーンのコメントに飛びつき、ツイッターで次々に批判を繰り出した。
「『タイムズ』はいい加減だ。昨日公表された私に関する記事は、ローワンヌ・ブルーワーに蹴散らされた。彼女はその記事はウソだと言った」
「私を攻撃するのに失敗した『タイムズ』の記事で重要人物だった女性が今日証言したので、あの記事がインチキであることがわかった」
間もなくトランプの支持者たちもこの記事を非難し始め、ソーシャルメディアやメールや電話で、ミーガンとバルバロを名指しで攻撃するようになった。しかし、その記事自体はトランプが性的不適切行為をおこなったとする訴えを注意深く立証したものなのだ。非難がまったく的外れだったので、ミーガンとバルバロは真剣に反撃しなかった。
右翼のニュース番組で暴露的な発言をするビル・オライリー〔FOXニュースの人気司会者。「オライリー・ファクター」という冠番組を担当していた〕のスタッフが何度もミーガンに電話をかけてきては、「あなたはフェミニストか?」と、まるでそのことが彼女の信用を損なっているかのように問いただした。番組の方針に疑いを抱いたミーガンは、インタビューの申し込みを断った。するとビル・オライリーは何百万人もの視聴者に向かって、ミーガンの仕事は信頼できないと訴え、「問題は、ミーガン・トゥーイーがフェミニストであることだ。あるいはそのように見えることだ」と言い放った。オライリーの議論はばかばかしいものだった――「ワシントン・ポスト」紙は、では男性優位主義者があの記事を書いたら文句はなかったのか? と問うた――が、彼は自分の影響力を最大限に生かし、記事が伝える事実の衝撃を和らげて、ミーガンの信用を失墜させようとした。
ミーガンは、このように世間から非難された経験がなかった。そのため、記事が出た翌月の二〇一六年六月に予定通り結婚式を挙げ、編集局から一時離れられたことをありがたく思ったほどだ。
でも、ほかの女性たちも無理矢理キスされたり体をまさぐられたり、もっと酷い目に遭ったりしたと申し立てをおこなっているのではないか? ミーガンは新婚旅行から戻ると、トランプに関する調査を続けた。
その数ヶ月後の十月七日金曜日、ミーガンが情報提供者と電話をしていると、同僚の記者たちがみな席から立ち上がり、テレビの前に群がった。「ワシントン・ポスト」紙が、二〇〇五年の「アクセス・ハリウッド」〔NBCのエンターテインメント系情報番組〕から録音テープの一部を手に入れたのだ。そのテープでトランプは、女性たちへ攻撃的な態度を取る自分のことを得意げに話していた。
「おれは美人を見ると反射的に攻めてしまうんだ――まずはキスすることから始める……待ってなんかいられない。こっちがスターなら、みんなやらしてくれる。なんだってやれる。……あそこをつかむことだってな。なんだってできるんだ」
彼のこの発言は、大統領候補たる者がこれまでに公共の電波に乗せたことのないものだった。それは、ミーガンが何ヶ月もかけて明らかにしようとしてきた彼の悪行を裏付けているように思えた。
トランプは自分の発言を謝罪し、またもや「そんなことはやっていない」と否定を重ねた。「アクセス・ハリウッド」のテープに収録されている発言は、
それから一週間も経たずに、ミーガンとバルバロは新しい記事を書き終えるところまできていた。その記事では、ふたりの女性が「録音テープのトランプの発言は、自分たちがされたことと一致している」と訴えていた。
証言者のひとり、ジェシカ・リーズは七十四歳の元株式仲買人で、ひ孫にも恵まれ、マンハッタンのアッパー・イースト・サイドの整然とした1DKの部屋で暮らしている。もうひとりの証言者、レイチェル・クルークスはオハイオ州グリーン・スプリングズ出身の三十三歳で、高等教育行政学の博士号取得候補になっていた。このふたりが「タイムズ」にメールをよこし、告発の内容を教えてくれた。
リーズは、一九八〇年代初頭に新聞印刷会社の営業員として出張中に、運よくダラスからニューヨークに向かう飛行機のファーストクラス席が取れた。その横に座っていたのがドナルド・トランプだった。金髪で長身で話し好きだった。リーズによれば、離陸から四十五分後に彼は身を寄せてくると、彼女の乳房をつかみ、スカートのなかに手を入れようとした。
「彼はわたしにのしかかってきて、体のいたるところを触ったのです」とリーズはメールに書いている。そして、エコノミークラス席に逃げていった
一方、クルークスの母親は看護師で、父親は自動車の修理工だった。ともに家で政治の話はしなかったが、共和党を支持していた。高校時代に彼女はバスケットボールと陸上とバレーボールの州代表になり、「もっとも成功に近い人」という評判を得ていた。二〇〇五年にニューヨークがどんなところか知りたくなり、ボーイフレンドと共にブルックリンの外れに安アパートメントを借りた。お金を貯めてベッドが買えるようになるまでエア・マットレスで眠った。家賃を稼ぐために、トランプ・タワーの二十四階にある不動産開発会社で秘書のような仕事をした。その会社はトランプ・オーガニゼーションと取引があった。その前年に放映が始まった「アプレンティス」〔トランプがホストを務めたリアリティ・ショー。一般人がトランプの会社の見習い社員となって課題に挑む〕は、そのシーズンでもっとも人気の高い新番組だった。
その冬のある日クルークスは、ドナルド・トランプがオフィスの外でエレベーターを待っているのを見てデスクから立ち上がり、自己紹介し、事務的な握手をかわした。「彼はわたしの手を放そうとしなかったの」と彼女は言った。そして彼は彼女の頬にキスをした。それから彼女の唇にキスをし、しかも強く押しつけた。すべてはほんの一瞬のことだった。そのとき彼女は二十二歳だった。それまでに彼女にキスをした男性は、同棲しているボーイフレンドだけだった。
「トランプさんがわたしを取るに足らない者だと見ていたから、あんなふうに勝手なことができたわけで、そのことに腹が立って仕方がなかった」と彼女のメールに書いてあった。
クルークスが説明した強引なキスは、ミーガンが以前取材した元ミス・ユタ州にされたキスと同じ
利害関係に充分に注意を払いながら、ミーガンとバルバロは彼女たちが秘密を打ち明けた友人や身内の人々に再三確認をおこなった。ふたりの経歴や身元を調べ、ヒラリー・クリントンの選挙運動とはかかわりのないことを確認した。ミーガンはクルークスに、トランプ・タワーで働いていた証拠として、オフィスのデスクにいる当時の彼女の写真を送ってほしいと頼むことさえした。厳しくおこなわれた確認作業は、女性たちを侮辱するような格好になった。しかし、それはふたりを守るためであり、ひいては「タイムズ」を守るためだった。
最終段階は、トランプ側の回答を取ることだった。日が沈むと、ミーガンは食卓を前にし、トランプの広報担当から記事内容を否定するおざなりのメールが来るのをじっと待っていた。そのとき携帯電話が鳴った。
トランプ本人からだった。
ミーガンが満足に質問できないうちに、トランプは激しい口調で非難を浴びせかけた。「ジェシカ・リーズとレイチェル・クルークスは嘘をついている。ふたりが何者なのか知らない。おれがふたりにそんなことをしたのなら、どうしてふたりは警察に訴えなかったんだ」
ミーガンは、ふたりの女性は彼の知り合いだと主張しているのではなく、彼とたまたま出くわしたと言っているだけだ、と説明した。そして、元ミス・ユタ州と、かつてのミスコンの共同主催者の申し立てについて触れた。
いきり立ったトランプは話題を変えた。「ニューヨーク・タイムズ」がふたりの女性の話をでっち上げている、と言った。「もしその記事を公表したら、告訴する」と。
ミーガンはトランプに話を続けさせたくて、さらに踏み込んだ。「『アクセス・ハリウッド』の漏洩した録音テープについてのご見解は?」 さらに彼にもう一度、「録音テープで自慢していたようなことを実際にしていたことがあるんですか」と尋ねた。
「そんなことはしない」とトランプは言い張った。声がうわずった。「そんなことはしない。あれは
トランプはミーガンに向かって言葉を
電話が切られて、ミーガンはほっとした。とても粗野な会話ではあったが、ミーガンはふたりの女性の申し立てについて彼に回答させるよい機会を与えたことになった。トランプのコメントが入った完璧な記事を公表することで前に進むことができる。
その数分後、トランプは大統領選の集会のためにフロリダの演台に立つと、群衆の
「アメリカ国民のみなさん、腐敗したメディアが力を合わせてみなさんに立ち向かっている。私がみなさんに何を言おうと、メディアは中傷し、名誉を毀損し、不快にさせ、不公平に扱う。しかし、われわれがそのシステムを打ち壊すんだ」
これが、大統領選挙の投票日が四週間後に迫っているときのことだった。共和党下院議長は、「『アクセス・ハリウッド』の録音テープにはうんざりしている」と言った。ジョン・マケイン上院議員はトランプへの支持を取り消した。副大統領に立候補したマイク・ペンス・インディアナ州知事は、トランプの家族のために祈っていると述べた。共和党議員のなかには、大統領選から身を引くべきだと言う人たちもいた。
トランプに非難を浴びせるほかの女性たちも現れた。ひとりは、ナイトクラブで友だちと会話している最中に、トランプにスカートの中に手を突っ込まれたという女性。もうひとりは「アプレンティス」の元参加者。三人目は、三番目の妻メラニアとトランプの初めての結婚記念日に、称賛の記事を書くと約束していた記者だった。三人の話はどれも、ミーガンが記事にした内容と基本的には同じだった。トランプは女性の体をつかみ、撫で回し、揉み、壁に押しやって自分の腰や性器を強く押しつけた。この繰り返される最低の行為を、無視したり忘れ去ったりできる人がいるものだろうか。
しかしジャーナリストたちには、すべての訴えを詳細に調べることができなかった。ある緊迫した民事裁判では、約二十年前にジェフリー・エプスタインという有名な資本家が主催したパーティで、トランプが十三歳の少女をレイプした点を争っていた。エプスタインは後に、未成年女性の性的人身売買の組織を運営し、未成年者を売春に勧誘していた罪で有罪になった〔エプスタインは、二〇一九年八月、勾留中に死亡〕。しかし、トランプの相手をさせられたとされる少女は、ジェーン・ドゥ〔氏名不明のときに用いられる女性の仮名〕という名で呼ばれ、どのような人物か公にされることはなく、取材内容は秘匿するという条件で会いたいという記者たちの要請に応じることはなかった。ジェーン・ドゥが存在しているかどうかすら確認がとれず、その話が真実かどうかの調査もされなかったため、ミーガンはこの事件を書くことをやめ、同僚たちにも触れないよう伝えた。
注目するような犯罪もあったが、ニュースに値するようには思われなかった。ミーガンは、ひとりの女性がテレビ中継されている記者会見で、タクシーを待っているあいだにトランプが不意に彼女の胸を触り、その指で髪を梳いた、と涙ながらに語っている姿を眺めていた。
細心の注意を払って調査し報道したクルークスとリーズの訴えが、ほかの女性たちの訴えと合わさって渦を巻いているうちに、トランプの態度は頑なな否定から大々的な攻撃へと移っていった。告発者は嘘つきだ。有名になりたくてやっている。ヒラリー・クリントンの味方をしている。あまりにも醜くて魅力がないから、おれの興味を引いたりできない。みんな告訴してやる。
彼の支持者たちはそれを合図に再度行動に打って出た。FOXビジネスの司会者ルー・ドブスは百万人近いフォロワーのいるツイッターで、ジェシカ・リーズの電話番号と住所を載せた保守系ニュース・サイトへのリンクを投稿し、さらに、「ジェシカはクリントン基金のために働いている」という嘘までついた。
リーズは簡単には怯まなかった。しかしレイチェル・クルークスはひどく慌てた。オハイオの自宅の庭に記者たちが群れているために外出できなくなった。トランプの支持者が「おまえは醜い、おまえはクビになる、だれかがおまえの頭に拳銃を突きつけたら、この国のためになるな」といったひどいメッセージを次々に書き込んでくるせいで、ネットを利用できなくなった。まったく見も知らぬ人物が、彼女の友人を装ってフェイスブックで、「クルークスがトランプについて嘘を言っているのは確かなことだ」などと主張した。クルークスの名前を検索にかけるとその主張が真っ先に現れるようになった。会ったことも話したこともない男性が、クルークスが在籍したこともない会社で、盗みを働いたと非難していた。
ふたりの女性が攻撃されるのを見るたびにミーガンの胸は痛んだ。大統領候補についての極めて重要な情報だから報道するのが公共のためだと言って、リーズとクルークスの発言を公開するよう説得したのはミーガンだった。巨大な壁に、国中の人が読めるくらい大きな文字で、ふたりの大切な情報を
ミーガンも攻撃された。トランプの支持者からの脅迫が、電話でもインターネットでも届いた。正体のわからない男から、おまえをレイプして殺し、ハドソン川に沈めてやるという脅迫が届くたびに、「タイムズ」の保安部に通報した。彼女は妊娠中で、
トランプ自身も裁判を起こすと脅しをかけてきた。彼の弁護士がバケット編集長に送りつけてきた手紙は、リーズとクルークスの発言を引っ込めるように指示していた。その手紙をトランプの弁護士チームが公開した。「不履行となれば、依頼人はできうる限りの訴訟と救済策を実行に移すしか他に方法がないでしょう」と書いてあった。
「タイムズ」の副法務責任者のデイヴィッド・マクロー弁護士は、ものに動じず、ジャーナリストを守る姿勢を貫き、編集局の全員に慕われていた。その彼が同じくらい強い語調で返事を送った。
「ふたりの声を封じることは、われわれの読者に対してだけでなく、民主主義それ自体に害をなすことになるでしょう」
マクローは、あえてトランプに「タイムズ」を訴えさせようとした。「彼がもし、アメリカ市民には、この女性たちが話すべきことに耳を傾ける権利などないと信じているのであれば、そしてこの国の法律が、わが社や彼をあえて批判した人々に黙ることを強いたり、罰を与えたりすべきだと信じているのであれば、わが社は裁判所が彼を正すことの出来るこの機会を歓迎いたします」
胸に響く弁護だった。ジャーナリズムだけでなく、権力者に立ち向かって告発をおこなった女性たちの権利を守る弁護だった。「タイムズ」がこの文書をウェブサイトに載せると、たちまち注目された。
マクローは、トランプが大統領に選ばれなければ告訴することはないと思っていたが、ミーガンはトランプが自分やバルバロや新聞社を告訴するだろうと思った。裁判になったらトランプは必ず負けるが、それまでにとてつもなく長い時間がかかる。ミーガンは将来裁判になる場合に備えて、メモ類やメールなどをすべて保存することにした。
三週間半後の十一月七日、ミーガンはアメリカ初の女性大統領が誕生する瞬間を、多くの人が待ち望んでいる場所で取材するため、イリノイ州に飛んだ。編集者から、ヒラリー・クリントンの生まれ故郷であるイリノイ州シカゴの郊外にある、パークリッジの投票所は象徴の場になるから、そこでヒラリーが大統領になる瞬間を迎えてほしいと頼まれたからだ。
ミーガンはクリントンもほかの候補者も支持していなかった。記者は支持してはならないのだ。数週間前に、民主党候補の支持者から非難の砲火を浴びた記事が「タイムズ」に掲載された。その記事でミーガンは、ビル・クリントンから性的に不適切な行為やもっとひどい行為をされたと訴えた女性たちと争う際に、ヒラリー・クリントンが果たした役割にスポットライトを当てて書いた。ヒラリーの支持者たちは、彼女の役割は小さかったと述べていたが、夫を告発した女性たちの名誉を汚すような弱点を探そうとして、ヒラリーが私立探偵を雇うための書類にサインしていたことをミーガンは突きとめたのだ。
ミーガンは投票者たちに取材をするうちに、彼らがトランプの性的嫌がらせに対する非難だけではなく、ほかにも多くの判断材料を基にしてヒラリーとトランプのどちらを支持するか決めようとしていることがわかった。実は彼女は、女性問題に対する関心が高いのではないかと予想していた。大統領選のかなり前から、ミーガンが#WhyWomenDontReportというハッシュタグを付けてツイートしたところ、女性たちが一斉に、自分たちにひどいことをした男たちのことをネットに投稿するようになった。あるプロデューサーにひどい暴力をふるわれたとツイートしたローズ・マッゴーワンもそのひとりだった。
しかし投票所でいくら取材しても、郊外に住む白人女性たちのなかに、トランプの女性への犯罪行為や「アクセス・ハリウッド」の録音テープの内容を気にしている人はいなかった。その夜ミーガンは、テレビで選挙結果を見る必要がないくらいだった。すでにトランプが勝利することがわかっていたのである。
選挙後の二〇一七年四月、ミーガンとジョディがそれぞれ驚きをもって見つめていたのは、ワインスタインの調査開始へとやがて繋がっていくことになる一連の出来事だった。権力の全盛期にあり、ミーガンを自身の番組やツイッターで批判し続けた、あの右翼のテレビ司会者ビル・オライリーが、FOXニュース・ネットワークでの地位を失ったのだ。それは、「タイムズ」が彼とその会社が性的嫌がらせで繰り返し訴えられていると報じてからのことだった。
エミリー・スティール記者とマイケル・シュミット記者が書いたその記事は、調査に八ヶ月を費やしたもので、オライリーが少なくとも五人の女性に大金を払って示談に持ち込んでいたことを明らかにした。女性たちは言葉による暴力、猥褻な発言、不愉快な口説きをおこなった罪で彼を告発した。オライリーとFOXニュースは、女性たちを黙らせるために合計千三百万ドルの口止め料を払った。アメリカでフェミニズムにもっとも批判的な会社のひとつが、こっそりと莫大な示談金を女性たちに支払っていたのである。
この記事では、ひとりの独身女性だけが報道することを条件に、自ら告発の内容を語ってくれた。その女性、ウェンディ・ウォルシュはオライリーの番組の元ゲストで、ホテルのスイートルームに行くことを断ったとたんに、番組の解説者になるという実入りのよい仕事の話を失った。この記事に登場する女性の大半は、オライリーやFOXニュースと示談になったので、本人の口から何があったのかを話すことができなかった。女性たちは多額の金を受け取る代わりに、起きたことを絶対に口外しないという条件に同意していた。
しかしスティールとシュミットのふたりの記者には、肝心なことがわかっていた。複雑な示談の手続きで秘密が漏洩しないわけがない、ということが。示談には、弁護士や交渉人がかかわり、金額も提示されるので、ほかの人々――同僚、代理人、家族、友人――に知られるのは避けられない。示談金が払われれば、それとともに法的かつ財務的な痕跡が残り、それがオライリーに対して告発があったことを物語る。つまり、示談になったところで、告発があった事実を隠蔽することはできない。示談そのものが告発があったことの証であり、それによって事件が隠蔽されたという事実は、不適切な行為があったことをいっそう際立たせる結果になる。これが性的嫌がらせを報道する新しいやり方になった。
それから何日も経たないうちに、メルセデス・ベンツやアメリカの大手保険会社、オールステート保険がオライリーの番組へのスポンサー契約を打ち切った。もっとも重要なのは、FOXのほかの女性たちがオライリーの態度について社内で不満を申し立てたことだ。「タイムズ」の記事が出てから三週間も経たない四月十九日に、オライリーは解雇された。そのオライリーと、共和党員で絶大な権力を握り、FOXの創設者だったロジャー・エイルズが職を失ったのは、女性を虐待したという訴えのせいではなく――FOXはそうした訴えがあることはよく知っていた――その訴えの存在を世間に知られたせいだった。女性たちが訴える出来事が二度も公になったことで、びっくり仰天の展開になったのだ。力学における一瞬の逆転のような展開だった。
「タイムズ」の記者たちはこの話がどれくらい重要かを検討した。世の中の女性たちはますます、女性への性暴力がはびこる現状にうんざりしているようだった。トランプの「あそこをつかむ」発言以来そうだったが、オライリーの告発記事に女性たちは触発され、自分の抱える苛立ちを記事へのコメントとしてぶつけた。通常、こうした出来事について
オライリー事件が戦略を教えてくれた。性的嫌がらせや性暴力の問題で、自ら進んで声を上げる人はひとりもいないと言っていい。でも、もし女性に対するひどい行為とはなにかを明らかにできれば、そうした体験を話しやすくなるかもしれない。
編集者たちは記者を集めてチームを作り、さまざまな業界を調べることにした。
シリコン・バレーやIT産業は、昔ながらの規則に縛られていない、理想的な仕事場のように見えるが、女性を閉め出していた。
学術の世界もまた調査するのにふさわしい領域に思われた。というのも、大学教授には同じ分野での研究を目指す院生を支配する力があったからだ。
低賃金で働かされている労働者たちにも目を配ることにした。彼らは人目を引かず、経済的圧力に屈し、しかも上位の所得階層に属する女性たちに比べて頼れる先がなかった。
オライリーが解雇されてから数日後、「タイムズ」の編集者、レベッカ・コルベットはジョディに、ふたつの問題の答えを探してほしいと言った。ひとつは、アメリカには女性たちに虐待に近い行為をおこなっている権力者がほかにもいるのではないか、という問題だ。ジョディはすでに、フェミニストの活動家シャウナ・トーマスに内々に助言を求めて電話をかけていた。それで彼女はハリウッドのこと、ローズ・マッゴーワンが出版する本のこと、ハーヴェイ・ワインスタインのことを教えてくれたのだ。コルベットはそれについて、ジョディに次の課題を出した。個々の犯罪者にとどまらず、性的嫌がらせをのさばらせ、だれからも言及されない特定のグループや組織を突きとめろ、と。そしてふたつ目は、どの事件でも必ず突然現れてくる示談とは、どれほど一般的なものなのか、それによって性的嫌がらせがどう隠蔽されているのか、という問題だ。
ジョディが助言を求めて電話をかけてきたとき、ミーガンは産休明けの予定が決まっていなかった。それでふたりは、トランプから不適切な性的行為をされたと証言したジェシカ・リーズとレイチェル・クルークスのような意欲的な女性に、進んで声を上げてもらうにはどうしたらいいかということをまず話し合った。そして、オライリーの記事は「タイムズ」がこうしたデリケートな問題をみごとに報道できることを示す格好の証拠になったことについても語り合った。
さらに、性的被害者だと推定される見知らぬ取材対象者に初めて電話をするときになんと言えばいいかということも話した。ミーガンはシカゴでレイプ被害者と話し合ったときに使った方法など、新しい取り組み方をいくつか提案した。ミーガンは被害者たちに、「過去にあなたに起きたことを変えることはわたしにはできない。でもね、わたしたちが力を合わせれば、あなたの体験をほかの人を守るために使うことができるかもしれない」と語ったのだ。
これはほかの言い方では得られない効果をあげた。この言葉は、取材対象者に過度のことを約束するものでも、おもねるものでもなかった。苦痛に満ちた辛い問題について語り合うための説得力のある理由になった。ジョディが女優のローズ・マッゴーワンに送った最初のメールで伝えたかったのはそのことだった。わたしたちは本気なのだ、と。
重要なのはほかの女性たちを救うことだ。これこそが、記者に話を打ち明ける理由として心にもっとも響き、「わたしは注目されたくない」、「辛い思いをしたくない」と主張する相手に返せる唯一の言葉だった。
ミーガンと電話した後、ジョディはコルベットに訊いた。「ミーガンの産休明けはいつですか」と。