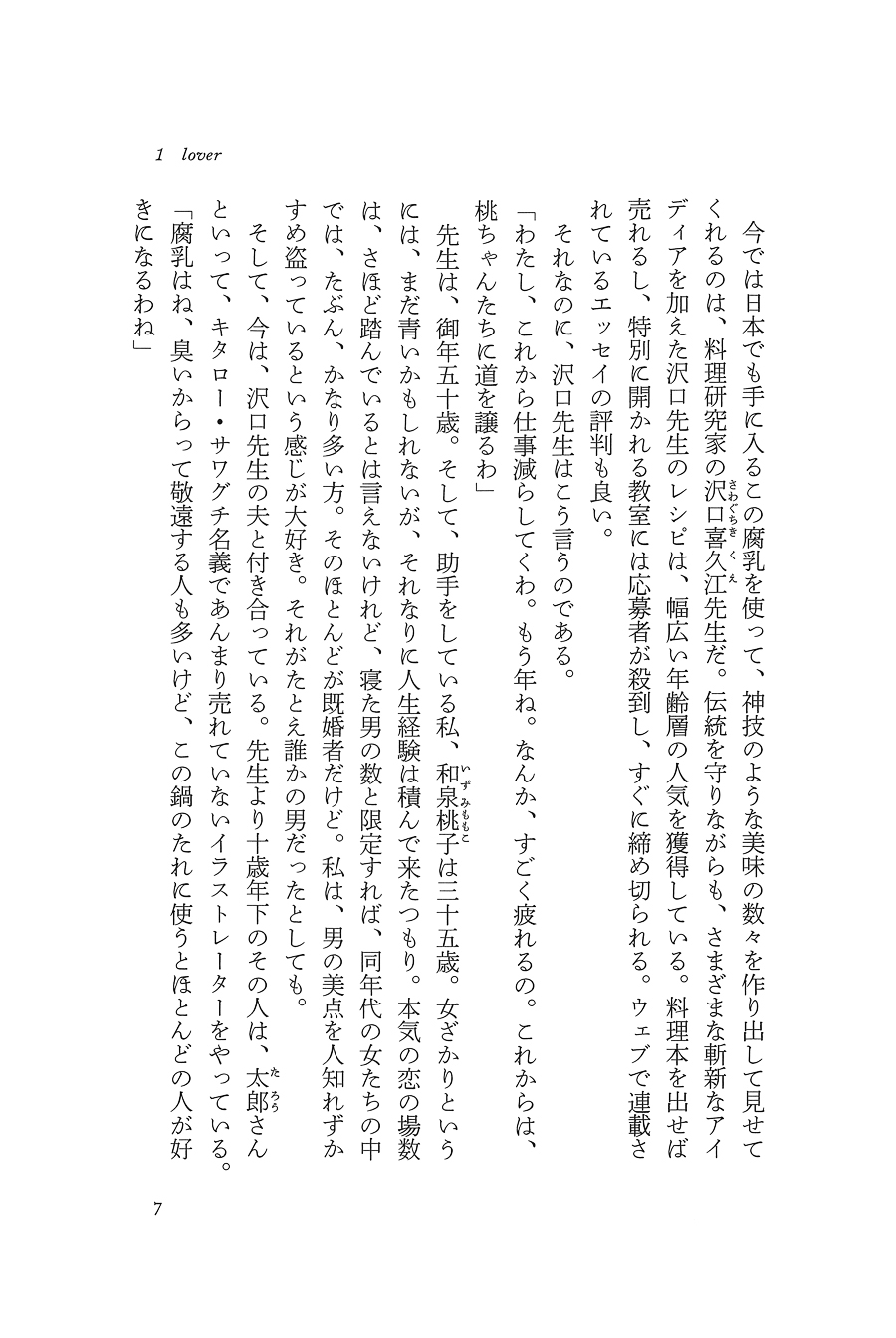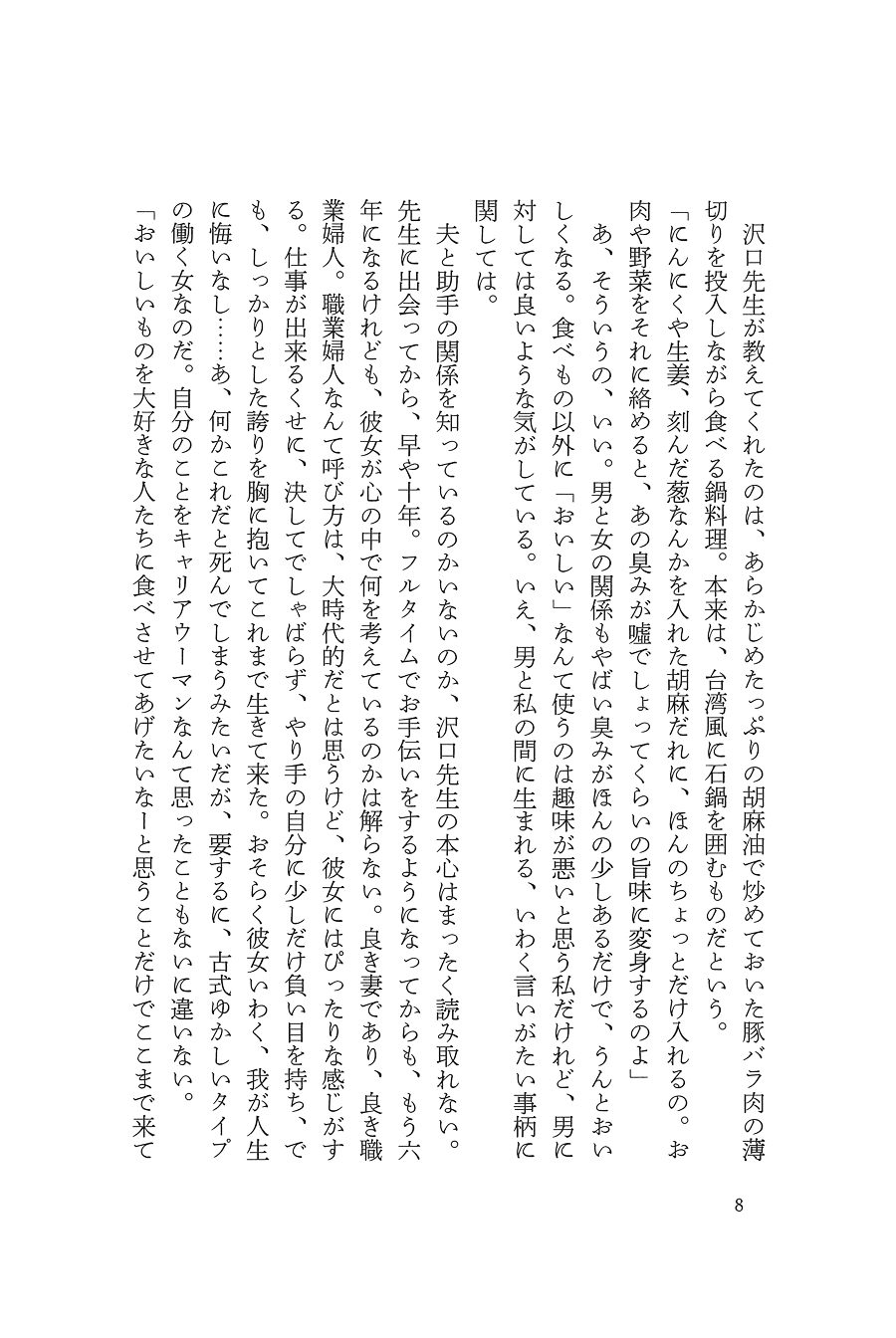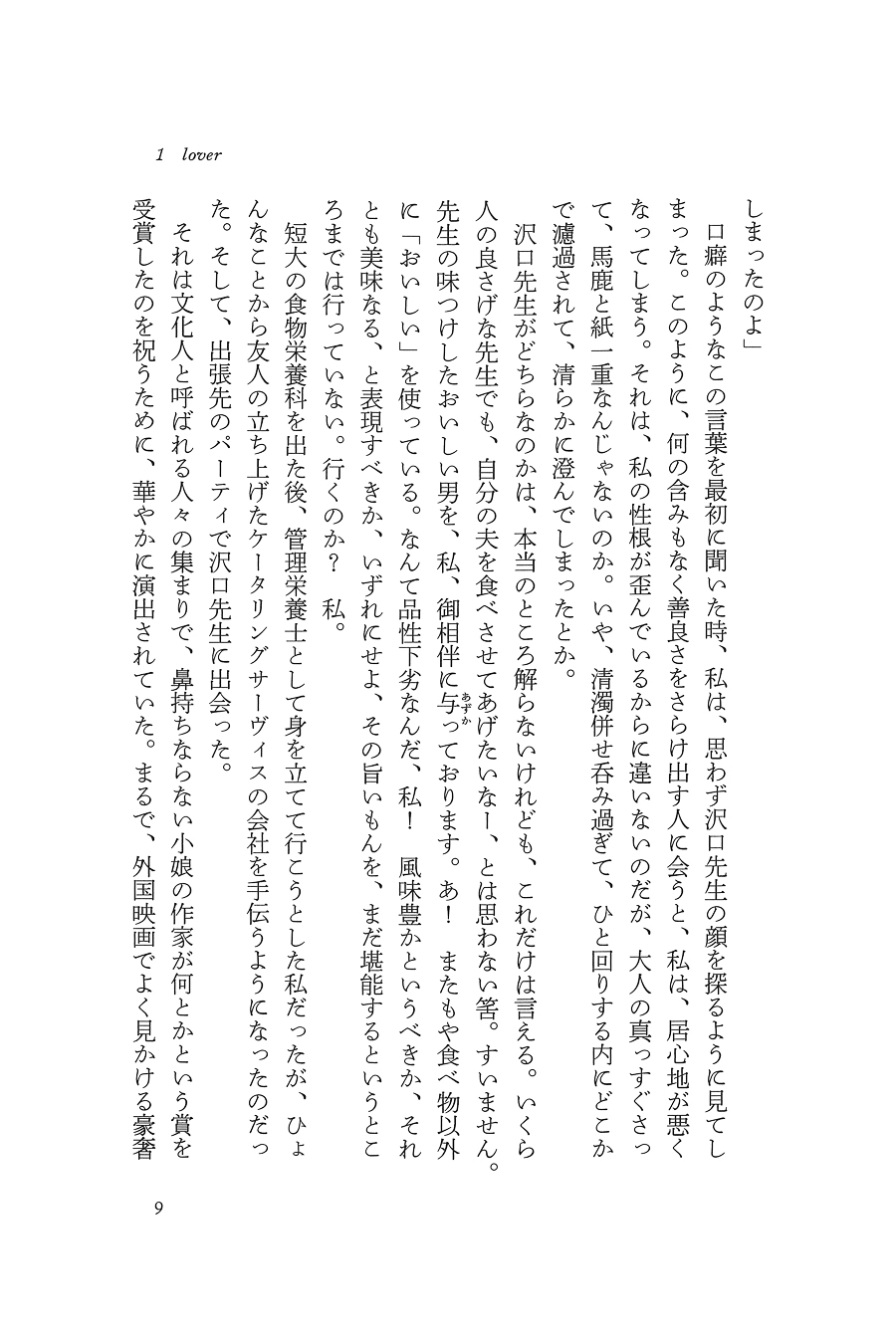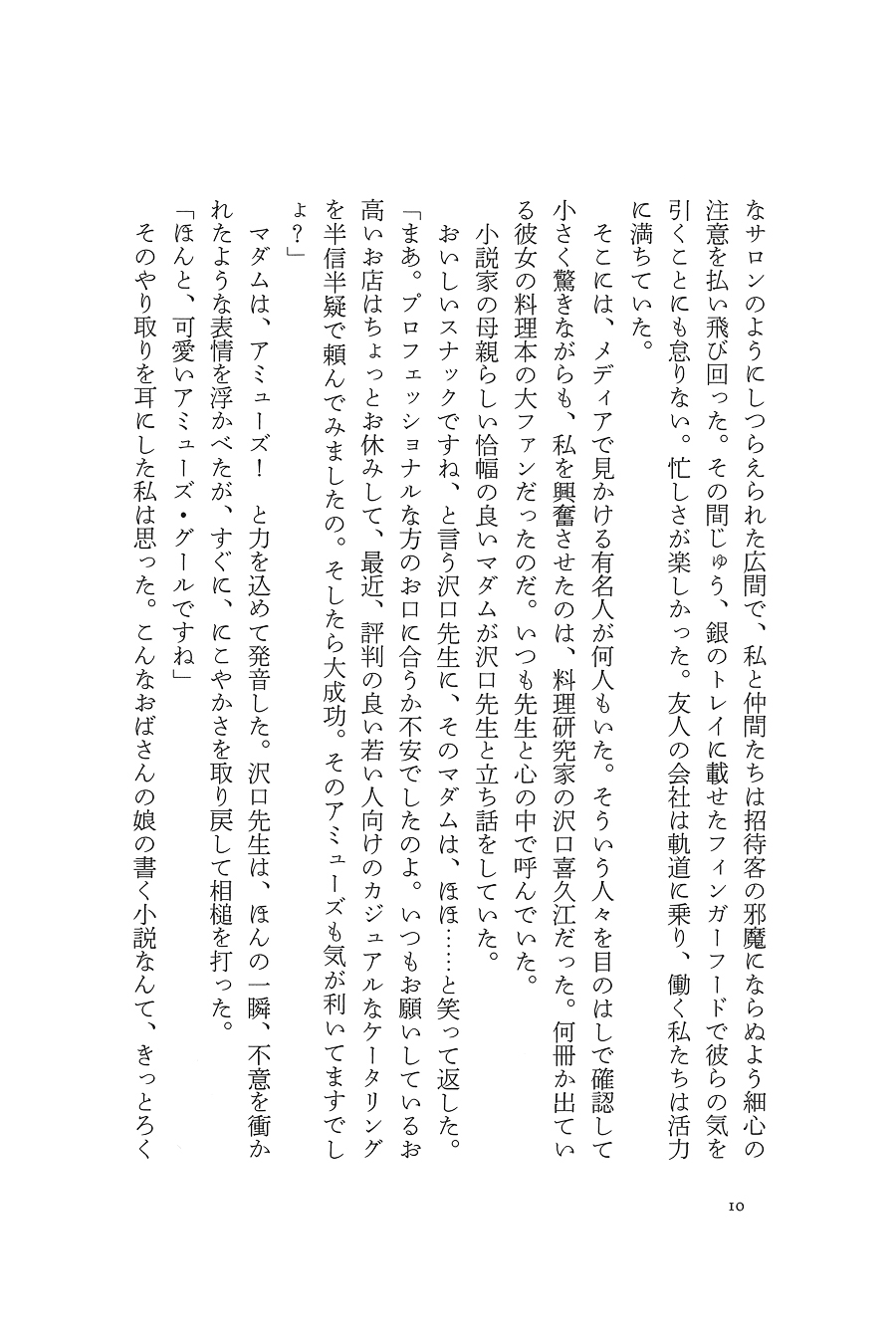私の趣味は人の夫を寝盗ることです。などと、世界の真ん中で叫んでみたいものだ。たぶん四方八方から石が飛んで来るだろうけど。そして、この性悪女! なあんて、ののしられたりする。不倫の発覚時には、何故かこういう古めかしい罵倒語が復活するから驚きだ。あばずれとか女狐とか泥棒猫とか。狐と猫、かわいそう。
不倫を辞書で引いてみたら、こうあった。
「道徳に反すること。特に、男女の関係が人の道にはずれること。また、そのさま」
で、ついでに、類語も調べてみた訳よ。そしたら、姦淫、姦通、腐れ合う、私通、出来合う、内通、密事、密通……とまあ、出て来る出て来る……しかし、腐れ合うって、……好みだ! 何でも、泉鏡花の「婦系図」とやらに登場する言葉らしいが、倫理にあらずなんて意味のものより、ずっとそそられるではないか。腐る寸前がおいしい食べ物のような男女、ってな感じのニュアンスが滲む。
腐っておいしい、と言えば、腐乳という食品が中国にあって、これは豆腐に麹を付けて発酵させたもの。かなり強いにおいで、人によっては
今では日本でも手に入るこの腐乳を使って、神技のような美味の数々を作り出して見せてくれるのは、料理研究家の
それなのに、沢口先生はこう言うのである。
「わたし、これから仕事減らしてくわ。もう年ね。なんか、すごく疲れるの。これからは、桃ちゃんたちに道を譲るわ」
先生は、御年五十歳。そして、助手をしている私、

そして、今は、沢口先生の夫と付き合っている。先生より十歳年下のその人は、
「腐乳はね、臭いからって敬遠する人も多いけど、この鍋のたれに使うとほとんどの人が好きになるわね」
沢口先生が教えてくれたのは、あらかじめたっぷりの胡麻油で炒めておいた豚バラ肉の薄切りを投入しながら食べる鍋料理。本来は、台湾風に石鍋を囲むものだという。
「にんにくや生姜、刻んだ葱なんかを入れた胡麻だれに、ほんのちょっとだけ入れるの。お肉や野菜をそれに絡めると、あの臭みが嘘でしょってくらいの旨味に変身するのよ」
あ、そういうの、いい。男と女の関係もやばい臭みがほんの少しあるだけで、うんとおいしくなる。食べもの以外に「おいしい」なんて使うのは趣味が悪いと思う私だけれど、男に対しては良いような気がしている。いえ、男と私の間に生まれる、いわく言いがたい事柄に関しては。
夫と助手の関係を知っているのかいないのか、沢口先生の本心はまったく読み取れない。先生に出会ってから、早や十年。フルタイムでお手伝いをするようになってからも、もう六年になるけれども、彼女が心の中で何を考えているのかは解らない。良き妻であり、良き職業婦人。職業婦人なんて呼び方は、大時代的だとは思うけど、彼女にはぴったりな感じがする。仕事が出来るくせに、決してでしゃばらず、やり手の自分に少しだけ負い目を持ち、でも、しっかりとした誇りを胸に抱いてこれまで生きて来た。おそらく彼女いわく、我が人生に悔いなし……あ、何かこれだと死んでしまうみたいだが、要するに、古式ゆかしいタイプの働く女なのだ。自分のことをキャリアウーマンなんて思ったこともないに違いない。
「おいしいものを大好きな人たちに食べさせてあげたいなーと思うことだけでここまで来てしまったのよ」
口癖のようなこの言葉を最初に聞いた時、私は、思わず沢口先生の顔を探るように見てしまった。このように、何の含みもなく善良さをさらけ出す人に会うと、私は、居心地が悪くなってしまう。それは、私の性根が歪んでいるからに違いないのだが、大人の真っすぐさって、馬鹿と紙一重なんじゃないのか。いや、清濁併せ呑み過ぎて、ひと回りする内にどこかで濾過されて、清らかに澄んでしまったとか。
沢口先生がどちらなのかは、本当のところ解らないけれども、これだけは言える。いくら人の良さげな先生でも、自分の夫を食べさせてあげたいなー、とは思わない筈。すいません。先生の味つけしたおいしい男を、私、御相伴に
短大の食物栄養科を出た後、管理栄養士として身を立てて行こうとした私だったが、ひょんなことから友人の立ち上げたケータリングサーヴィスの会社を手伝うようになったのだった。そして、出張先のパーティで沢口先生に出会った。
それは文化人と呼ばれる人々の集まりで、鼻持ちならない小娘の作家が何とかという賞を受賞したのを祝うために、華やかに演出されていた。まるで、外国映画でよく見かける豪奢なサロンのようにしつらえられた広間で、私と仲間たちは招待客の邪魔にならぬよう細心の注意を払い飛び回った。その間じゅう、銀のトレイに載せたフィンガーフードで彼らの気を引くことにも怠りない。忙しさが楽しかった。友人の会社は軌道に乗り、働く私たちは活力に満ちていた。
そこには、メディアで見かける有名人が何人もいた。そういう人々を目のはしで確認して小さく驚きながらも、私を興奮させたのは、料理研究家の沢口喜久江だった。何冊か出ている彼女の料理本の大ファンだったのだ。いつも先生と心の中で呼んでいた。
小説家の母親らしい恰幅の良いマダムが沢口先生と立ち話をしていた。
おいしいスナックですね、と言う沢口先生に、そのマダムは、ほほ……と笑って返した。
「まあ。プロフェッショナルな方のお口に合うか不安でしたのよ。いつもお願いしているお高いお店はちょっとお休みして、最近、評判の良い若い人向けのカジュアルなケータリングを半信半疑で頼んでみましたの。そしたら大成功。そのアミューズも気が利いてますでしょ?」
マダムは、アミューズ! と力を込めて発音した。沢口先生は、ほんの一瞬、不意を衝かれたような表情を浮かべたが、すぐに、にこやかさを取り戻して相槌を打った。
「ほんと、可愛いアミューズ・グールですね」
そのやり取りを耳にした私は思った。こんなおばさんの娘の書く小説なんて、きっとろくなもんじゃないだろうな、と。どうせ鼻持ちならないおフランス風味がぷんぷんしているんだろう。
ちなみに、二人のカンヴァセーション・ピースになったスナックは、小海老を香菜なんかと一緒に小さな春巻の皮でくるんで揚げたもの。スウィートチリソースがかけてある。私たちの間では、エビチビロールと命名されていて、完全なスナック扱い。ビールを召し上がるお客に勧めることが多い。別にアミューズ扱いされても、まったくかまわないし、格上げされたみたいで光栄であったりもする訳だが、あの種のマダムの意味のない気取りと威圧感って、私のもっとも苦手とするものだ。いや、私だけでなく、少なからぬ人々が敬遠したくなる雰囲気を撒き散らしているのだが、本人は全然気が付かない。何故なら、類は類を持って集まっているからだ。品のまったくない、お上品な人たち。

金満家のおばさんたちには、毎回、いらっとさせられるが、
などと思いながら、テーブルの上を片付けていたら、なんと沢口先生その人が話しかけて来たのである。
「おつまみ、どれもおいしいわよ。御馳走さま」
「こ、光栄です! 社長に伝えます」
「いつも、このくらいの規模のパーティにお料理を提供しているの?」
「あ、いえ、こんなに盛大なのは滅多にないんで、二日前くらいからてんてこ舞いで……」
「……てんてこ舞い……その言葉、久し振りに聞いたわ。大変なのね。皆、バイトさん?」
「何人かはそうです」
「あなたも?」
「そんなもんです。実は、社長が友達なもんで、応援している内に手伝う破目になって……」
「そうなの」
沢口先生は、しばらくの間、逡巡しているような素振りで、テーブルの上の料理をながめた後、尋ねた。
「ね、あそこにあるハワイのポキみたいな味付けの
顔が熱くなった。これは、いったいどういう種類の質問なのか。
「それと、あっちのレモンピールが散らしてあるカラマリのマリネは? WASARAのコンポート皿にちっちゃく盛り付けてある……」
WASARAは、和紙のような手触りと陶器を思わせる質感を兼ね備えた紙皿で、そのデザイン性と意外な丈夫さで重宝しているのだった。環境への負荷も減らしているとか。
「フェンネルの葉とピンクペッパーの色が、すごく綺麗ねえ……オイルは何を使ったの?」
「……ヘーゼルナッツです」
「ああ、どうりで」
感嘆したように頷き、頬を染める沢口先生を目の当たりにして、私は、幸福のあまり口を滑らせた。
「あの、ふたつ共、私が考えたんです!」
いや、口を滑らせたと言っても、それは事実ではあるのだ。ただし、お客様と料理に関する個人的な話はしないように、と社長に言われているのだった。
「あなたはプロなの?」
「……いえ、一応調理師免許は持ってますけど……」
消え入りそうな気持だった。社会に出て、もうずい分経つというのに、自分はまだ何者でもないのだ、と心許なくなったのだ。
あの日の出会いを思い出して、沢口先生は、今も懐しむかのように笑う。あれから、何度かの偶然が重なり、私たちは近しい間柄になった。そして、先生の許で働かないかと提案されたのだ。
もちろん、私に異存はなかった。料理に携わる者なら、一度は、沢口喜久江の側で働いてみたいと思うだろう。しかし。
「そっかなー。私、あの人の料理って、あんまり好きじゃないなー」
そう言ったのは、私の友人で先生との出会いのきっかけを作ってくれた、ケータリングサーヴィス会社社長の
「なんか、沢口喜久江の作るもんって、私、性に合わないんだなあ」
感じ悪いなあ、と思ったものの、緑の言いたいことは解る。料理を作る人は、皆誰かしら自分の気に入りの料理研究家がいるものだが、その選び方は理屈ではないのだ。自分のテイストに合うか合わないか、それだけ。食べ物を味わうのと同じなのだ。最初に感じた好き嫌いが変わることはない。食わず嫌いを返上することはあるけれども。
「あの人の料理本とか見てると、母性とか愛情とかが、もわっと漂ってくるんだよねえ」
「何が悪いの? それ、料理の基本じゃん」
「うーん。私の場合は、愛を料理に託して届けるとか、なるべく避けたいからねー。そういう重いもんから逃れたい、でも、旨いもんは食べたいって人たち向け?」
確かに沢口先生の料理本には愛という概念が詰まっている。寒い日の夕暮れ時、道端にどこからか流れて来る、温かい湯気に象徴されるようなものが。
「でも、桃子が沢口さんと働いてみたいなら、無理に引き留める気はないよ。ちょうど、大ちゃんとがっつり組んでやってく決心を固めたとこだしね」
大ちゃんというのは、
「正直、桃ちゃんと初めて会った時の料理、おいしいより先に、ずい分、風変わりだなって印象が来たの。近頃の若い料理人って奇をてらってばかりって。ヘーゼルナッツのオイルなんて、普通、
なんて、何年も前の料理をいつも唐突に思い出して語り始めたりするのだ、沢口先生という人は。
「でもね、あれは、小さな小さな一話完結のひと皿だったのね」
「は?」
「わたしだったら、もっと食べたいと思わせるために作ると思うの。全然、違うんだなあ、この若い人は、と目から鱗が落ちたみたいになって、それが始まりで、桃ちゃんにうちに来てもらいたいと考えるようになったのよ」
ありがたいことだ、と心から感じた。それを伝えたくて、私なりに誠実に仕えて来た。ますます沢口先生はすごい、と尊敬するようになった。そして、それと並行して、彼女への無条件の好意のようなものは減って行った。尊敬は屈託のない好きという気持を削ってしまうように、いつも私は思う。
じゃれ付く子供のように必死に先生の後を追いかけていた私は、次第に息を整え、冷静な気持で彼女を見詰めるようになった。すると、充実した仕事が私を待ち受けていて、沢口喜久江に必要とされているありがたみが押し寄せた。
出来なかったことが少しずつ出来るようになって行く。一人前らしきものに近付いて行く。私自身による私自身のための進化論は、着実な日々の積み重ねによるものなのだ。その胸震わせる実感を、ごく当り前に受け止めるようになった時には、沢口先生との出会いから十年が過ぎていた。
今では、先生からも、仕事スタッフからも信頼されている重要人物の筈。まあ、自惚れかもしれないけどさ、良いのだ。気は心。まずはそう思うところから始めてみる。すると、つじつまを合わせなくては、と普通よりギアを上げるから、仕事の出来も上々になる。そして、気が付いたら実力派……が目標。
「うちはねえ、家内制手工業みたいなもんだから、信頼の置ける少人数だけで良いの。仕事の量を増やして自分を追い込んでも誰も誉めてくれないし、わたしたちも楽しくない。のんびりとあえて余裕をもってやってます。心からの笑顔が作れなくなったら、御料理を皆さんに提供する資格なんかないですもの」
とは、某女性誌の、働く女性特集インタヴューで沢口先生が言ったこと。素晴しい御言葉で、彼女がそう心掛けているのは本当で、だからこその沢口喜久江なのだが、正直、いつもそのサイクルが上手く回っているとは限らない。
「誰か悪いわねえ! 太郎さんに、この夕ごはん届けてくれる!?」
そんなふうに、忙しい
どうする? という目で、私とほぼ同時期に働き始めた
仕方ないなあ、と私がその役目を引き受けた日があった。
「がんばれ! 弁当運搬係!」
と田辺智子ちゃんに茶化されながら思ったものだ。ばっかみたい、と。いい大人の男が奥さんの手作り弁当を待ってるなんて。そして、それを赤の他人に運ばせて平気でいる妻なんて。行って来ます、と言ってキッチンスタジオの外に出た瞬間、舌打ちをしてしまったほどだ。沢口喜久江ともあろう人が公私混同かあ……と。でも、そうなんだ、それがあの人の人気の秘密でもあるんだ。わたくし事を飾らずに見せてこそ、ファンは神が自分の位置にわざわざ降りて来てくれたような気分で、カジュアルに崇めることが出来るというもの。しかし、これは何か間違っているよなー。
などと、小さく舌打ちしたのは、今から一年前のことだ。あれから私の心境は一変した。すいません、私が間違っていました。もう不平なんぞ
嫌々ながら夕食のための料理を届けた先で、私は初めて先生の夫の沢口太郎と向かい合ったのだった。
それまでも、何度か見かけたことはあった。沢口先生のキッチンスタジオは自宅の敷地内にあり、プライヴェートエリアとは中庭の渡り廊下でつながっていた。大きな窓から見える、用もないのにそこを歩く太郎の姿は、時々私たちの目に入り、そのたびに長峰さんが、またふらふらしてる、と呟いた。
「なんか身軽そうな人ですね」
「地に足が着いていないのよ」
そんなやり取りを聞くともなく聞きながら、私は思った。地に足が着いた妻と、そうでない夫の組み合わせか、ふうーん、おもしろそう、と。
「ごめんね、わざわざ、おれの仕事場まで来させちゃって。夕めしとかいいからって、いつ
「いえ、これも仕事の内と思ってますし。では、私は、これで、スタジオの方に戻ります」
そお? と言う太郎に御辞儀をして立ち去ろうとすると引き止められた。
「ねえ、良かったら一緒に食べない?」
振り返って、その顔をまじまじと見た。その瞬間に、解った。あ、この顔、私の好きなやつ。そして、この人も私の顔を好きと感じている! 何故、解ったかって? ふし穴じゃない目を持っている大人には、そんなことはお見通しさ!
私たちは、太郎の仕事場の隅に置かれた小さなテーブルの上に料理を並べて、はしから平らげて行った。弁当とはいえ、あまりにも手がこんでいて豪華だった。料理のプロを妻に持つ男の幸運について、私は考える。
「料理本の編集やってる人に聞いたんですけど、プロって、案外、家庭で料理したりしないんですって。私の知ってるレストランのシェフも言ってたけど、下手でも奥さんの作る家の味が一番だって。おもしろいですね」
ふうん、と上の空な感じの相槌を打ちながら、太郎は、具沢山のかやくごはんを詰めた稲荷寿司を口に押し込んだ。
「それなのに、沢口先生はすごいですよね。だんなさんのためにも、おいしいものをいっぱい作るじゃないですか。看板に偽りなしってやつですよね」
太郎が突然、ぐぐっと喉から妙な音を出して胸を叩き始めたので、私は、慌てて空のグラスに水出しのお茶を注いで差し出した。すると、彼は、引ったくるようにして、ひと息に飲み干す。
「あんまりおいしいからって、がっついてはいけません。ゆっくり、味わって召し上がって下さい。先生の愛情がこもってるんですから」
お茶にむせながら、太郎は笑った。
「あんた、それ、真面目に言ってんの?」
「はあ、大真面目ですが、何か」
「喜久江の信奉者なんだ?」
「はい、その通りです」
その先の太郎の言葉を待ったが、会話は途絶えてしまい、私たちは再び食べることに専念した。そうして、あらかた片付けてしまうと、二人の間には、飽食した後のだるい空気が漂った。
「あのおいなりさんて、ひじきやら蒟蒻やらが、あんなに細かくなって、ぎっしりと詰まってるんだから、すごいですよね。五目どころか十目ぐらい? 先生のスペシャリテですよね」
私は、キッチンを借りていれ直した熱い焙じ茶を太郎の湯呑みに注いだ。

「おれ、あんなごちゃごちゃしてんのより、
「はい?」
「知らない? 駅構内とかにある稲荷寿司屋。このあたりだと三鷹駅の隅っこに小さい店がある」
「稲荷寿司にはうるさい?」
「おれは、どんなものにもうるさくないよ」
「じゃ、どんなにまずいものでも食べられるってこと?」
「それは、無理。喜久江のせいで、すっかり舌が肥えちゃってるからさあ」
何の屈託もなさげにそう言う目の前の男を、私は、図々しいと思った。
「喜久江のせい、なんて言い方はするべきではないのでは? 先生のおかげでしょ? お、か、げ。おいしいものを食べさせてもらえる恩恵に与っている訳じゃないですか」
少し気色ばんでしまったのを、たちまち後悔した。仮にも尊敬する沢口先生の配偶者ではないか。ならば、こちらにもそれ相応のリスペクトを……と思ったのだが、まるでそんな気にならないのである。
後に、この時のことを話題にするたびに、太郎は言った。ずい分、ずけずけとものを言う女だなあと呆れた、と。
「だいたい喜久江に憧れてる女って、おれに対して三種類の態度を取るの。優等生的気づかいを発揮して、先生に良い印象を伝えてもらおうと画策する奴。次は、万が一、先生が嫉妬したり、疑いを持ったりすることがないよう徹底して、よそよそしい態度を取る奴。最後は、先生の好きなものすべてを共有したいとばかりに、好意を全開にしてせまって来るやつ」
何だか、可哀相な奴だな、と感じた。敬愛されているのは妻であって自分では決してない、という経験をこの人はどれだけして来たのだろう。
「でも、桃子は、そのどれとも違ってた」
そう言って、息のかかるところで私を見詰める男は、初めて稲荷寿司を一緒に食べたその日からずっと、私に心奪われている。それが解る。私自身も、さまざまな方法を駆使して、今一番大事なものは、このひとときなのだと伝えようとする。
そこには、沢口先生はいない。この世から消えている。そもそも、太郎と二人、互いを好ましく感じていると認識し合ってから、先生は蚊帳の外の人になってしまったのだ。けれども、そんなのは気の毒なので、一応、話題にはのぼらせる。
既婚者の男との恋愛においては、妻の話は時候の挨拶のようなもの。今日の空模様はいかがですか、と尋ねるのと同じ。雨あられに見舞われそうなら、本日の逢瀬はまたの機会にしておきますか、と提案したりもする。
そういう時、妻は男の配偶者であって、男の女ではない。敬意はないが憎しみもない。私の心は、妻の存在でざわついたりしない。だって、彼は私のものだと知っているから。彼の一番おいしい(また言っちゃった)部分は、私が味わっていると解るから。
考えてみると、妻、可哀相。私のために、夫を下ごしらえして差し出し(というか、彼が勝手にやって来るのだが)、散々、あらかた食い尽くされた残り物を受け取るのだ。
レフトオーヴァーという英語がある。料理の残り物のことだ。でも残飯ではなく、取っておいて、また後で食べるために保存するもの。女を経由して自分の許に戻って来た夫は、すべてレフトオーヴァーであると、妻は知るべきだろう。
そんなふうに思っていると、男が妻の待つ家に帰って行くのも気にならない。痩せ我慢なんかじゃない。変な時刻に急遽、帰り支度をする彼の姿を見ても、大変だな、と思いこそすれ、腹を立てたりはしない。
だから、そういう時、なんかあっちに悪くてさあ、なんて言わないで欲しいのである。空模様なんだからさ! 天気に悪いと何故思う!!
そこで、こちらが不貞腐れると、ひとり残される寂しさ故と勘違いされるので、ぐっとこらえる。本当は、声を大にして言いたい。二人の間に不純物を入れるな! 私は、後ろめたさや惨めさを、ほんの欠片であっても、この関係にはさみ込みたくないのだ。
昔、不倫している女が、奥様に申し訳なくて……よよっ(泣き崩れるさま)なんてなっている場面をドラマで観たことがあるが、そして、いまだにそういう女が罪悪感を告白したりするのを雑誌コラムなどで見かけたりするが、額面通りには受け取らないよ。気持良さげなプレイと私には映る。背徳は、ある種の人々の媚薬ではあるけれども、私には効かない。奥さんに悪くて……なんて啜り泣く女に縛られて悦に入っている男は馬鹿だと思う。立場が逆だったら、と想像してごらんよ。彼女のだんなに悪くって……と男が泣くか?
私と太郎は、恋に対しては似た者同士みたいである。だから、寝るだけの相手にはならなかった。言ってみれば三角関係に進んでしまった間柄なのだが、関係のもう一角をになう妻は、決して目の上のたんこぶにはならない。後ろ暗い快楽の御膳立てをする存在にも、だ。
私たちは、平然と沢口先生の持たせた料理を食べる。それが、本物のベントーボックスであればシェアする。勝手に、先生からの私専用の「おもたせ」と受け留めた特別料理は、私が味わい尽くす。先生の、そのスペシャリテ、汝の名は夫なり。
たまに、沢口先生の不注意について考える。レシピを考案する際には、あれほど細心の注意を払って、調味料の量を決めるのに、夫の食事を私のような女に届けさせるといううっかりミスを犯すなんて。そういや、慣れたら、自分の目分量で味を作っても良いのよ、なんて料理講座で言ってたっけ。それ、駄目。先生の作る味は、0.01グラムまで厳密に守らせなきゃ。そのあたり、ずい分と甘かった。だから、私に介入させてしまった。
「で、例によって、自分を人でなしとは思ってない訳ね」
そう言うのは、親友の
「大丈夫だよ、あんたの男と深い関係になんかなる訳ないじゃん!」
「深くなくても、つまみ食いでも嫌なの!」
ああ、そうですか。コンパルは、今、会社の同僚と付き合い始めたばかり。ゲイ専用のマッチングアプリで知り合って、同じ社屋に身を置く者同士だと解った時には真底驚いたと言う。
「あの大きなビルの片隅で、ぼくを待っていてくれたなんて、運命よね!? 運命!」
「はー、そうだね、大運命だね」
「大運命! 桃子もさあ、大運命の相手を見つけなさいよ。そんな、師匠のだんなに手を付けるなんて、血も涙もないことやってないでさ」
あるよ。
この間、生理中なのに、どうしても我慢出来ずにセックスしていたら(
そして、その後、空腹を訴える太郎にカレーライスを作ってやろうと玉葱を刻んでいたら、涙がぽろぽろとこぼれ落ちた。泣いてるの? と太郎が優しく背後から抱き締めた時、私は思っていたの。ほら、血も涙もある。