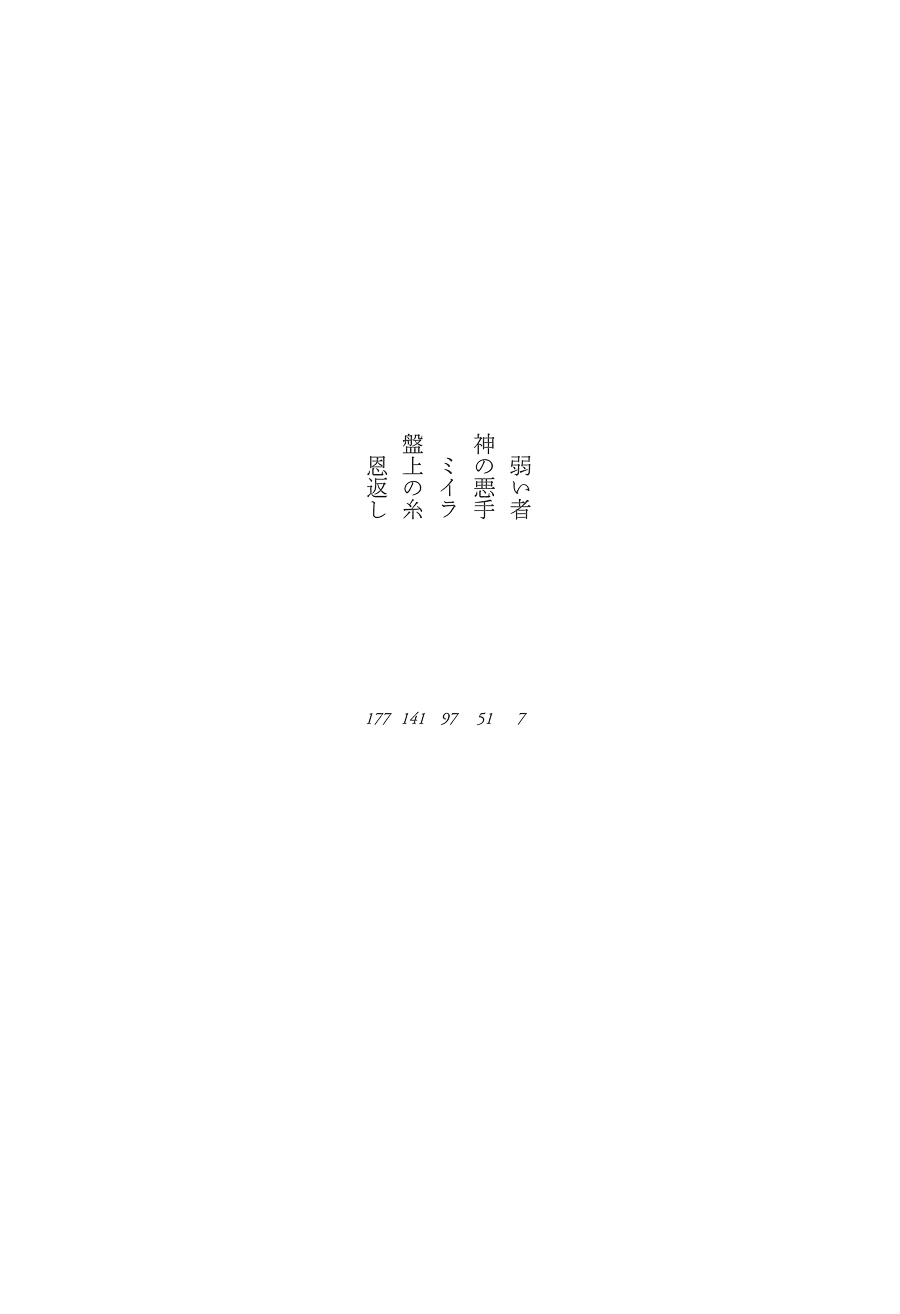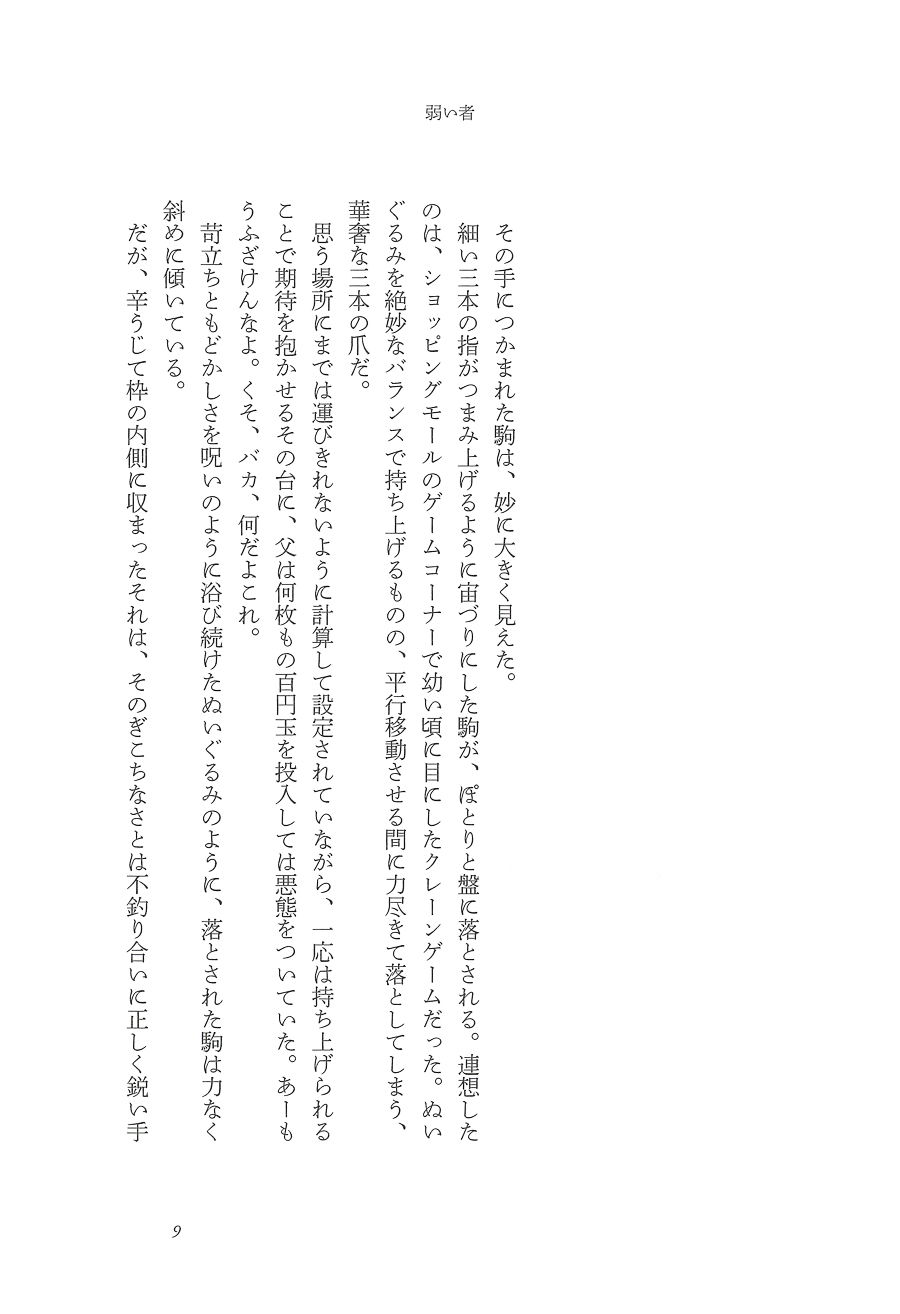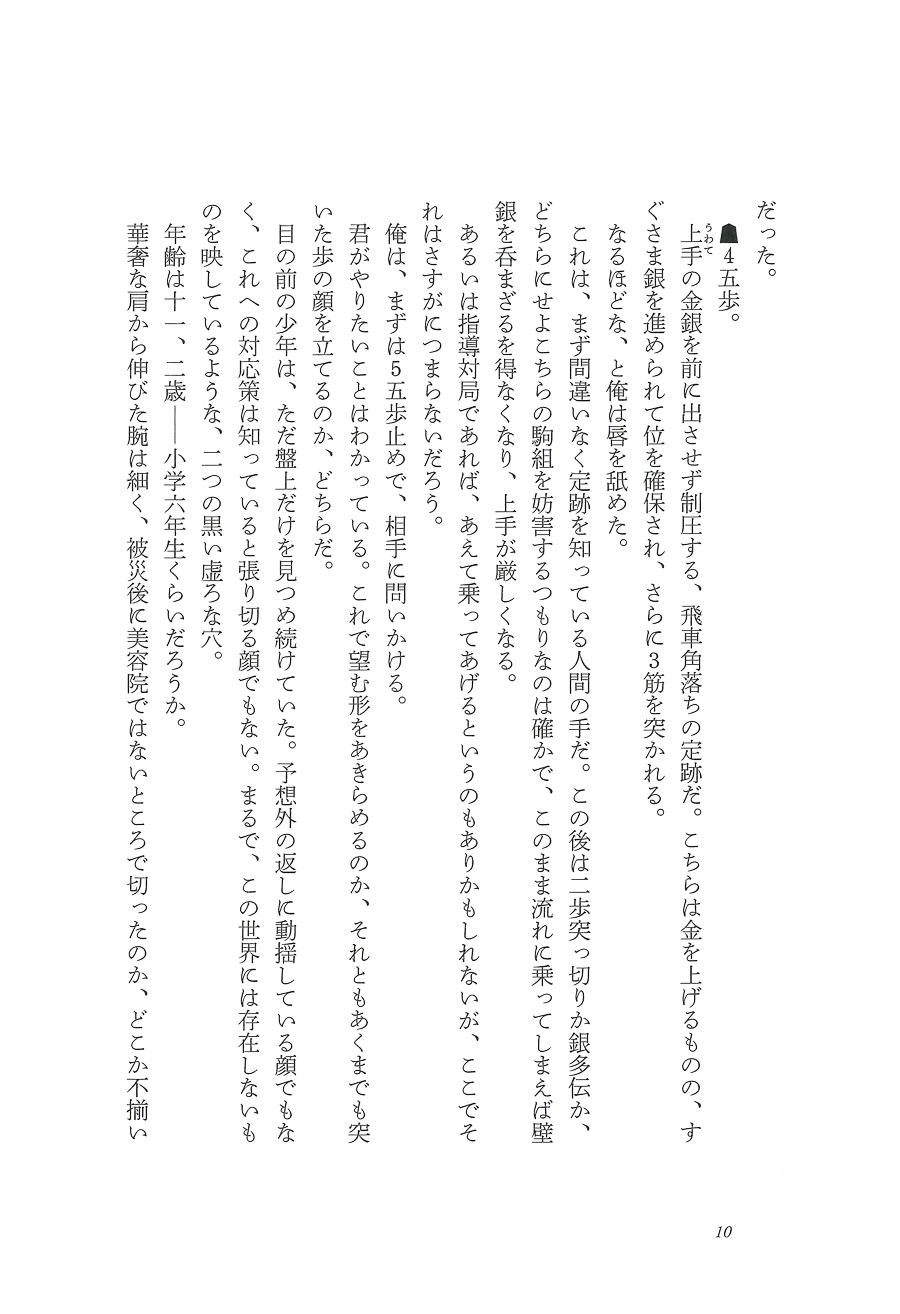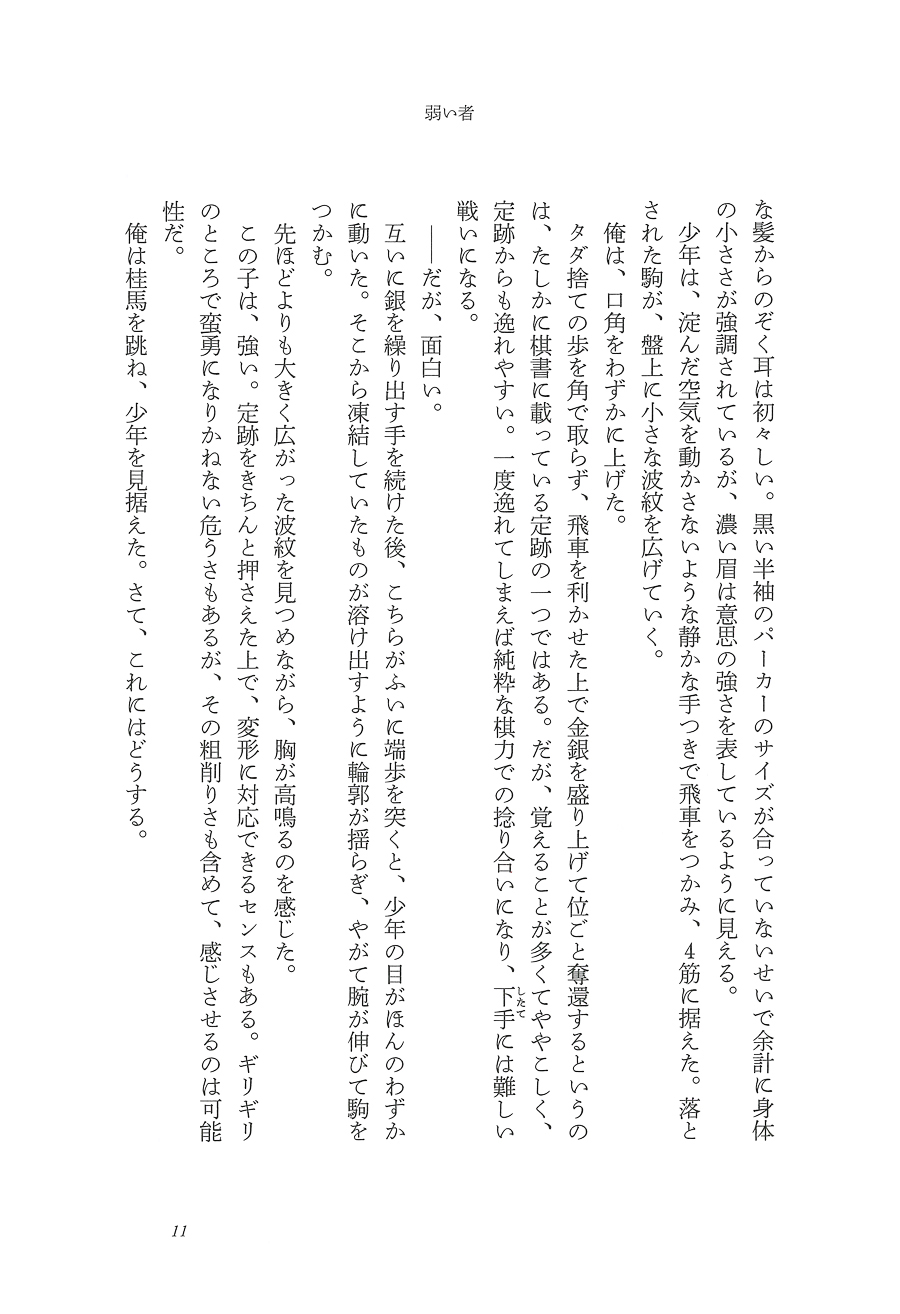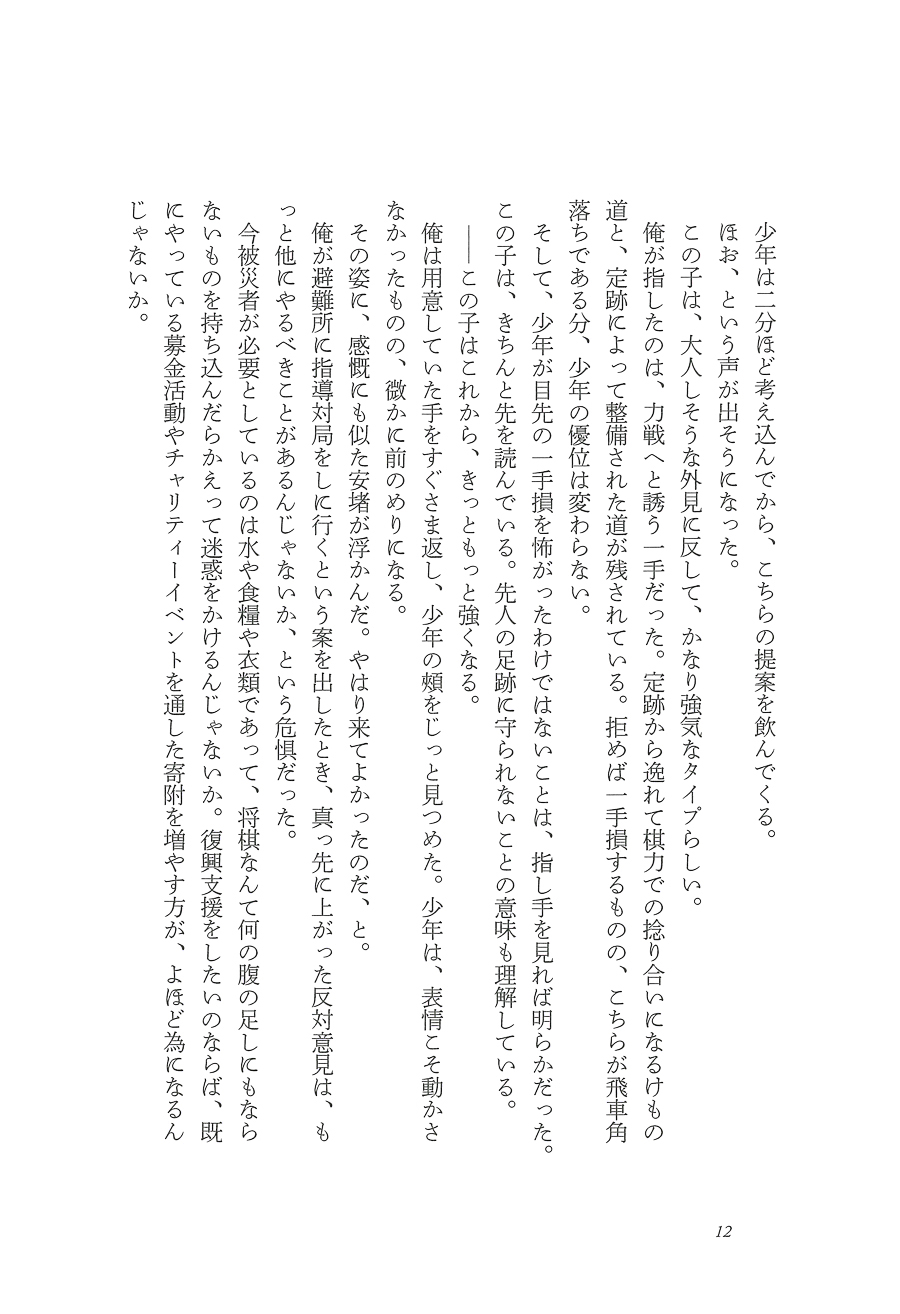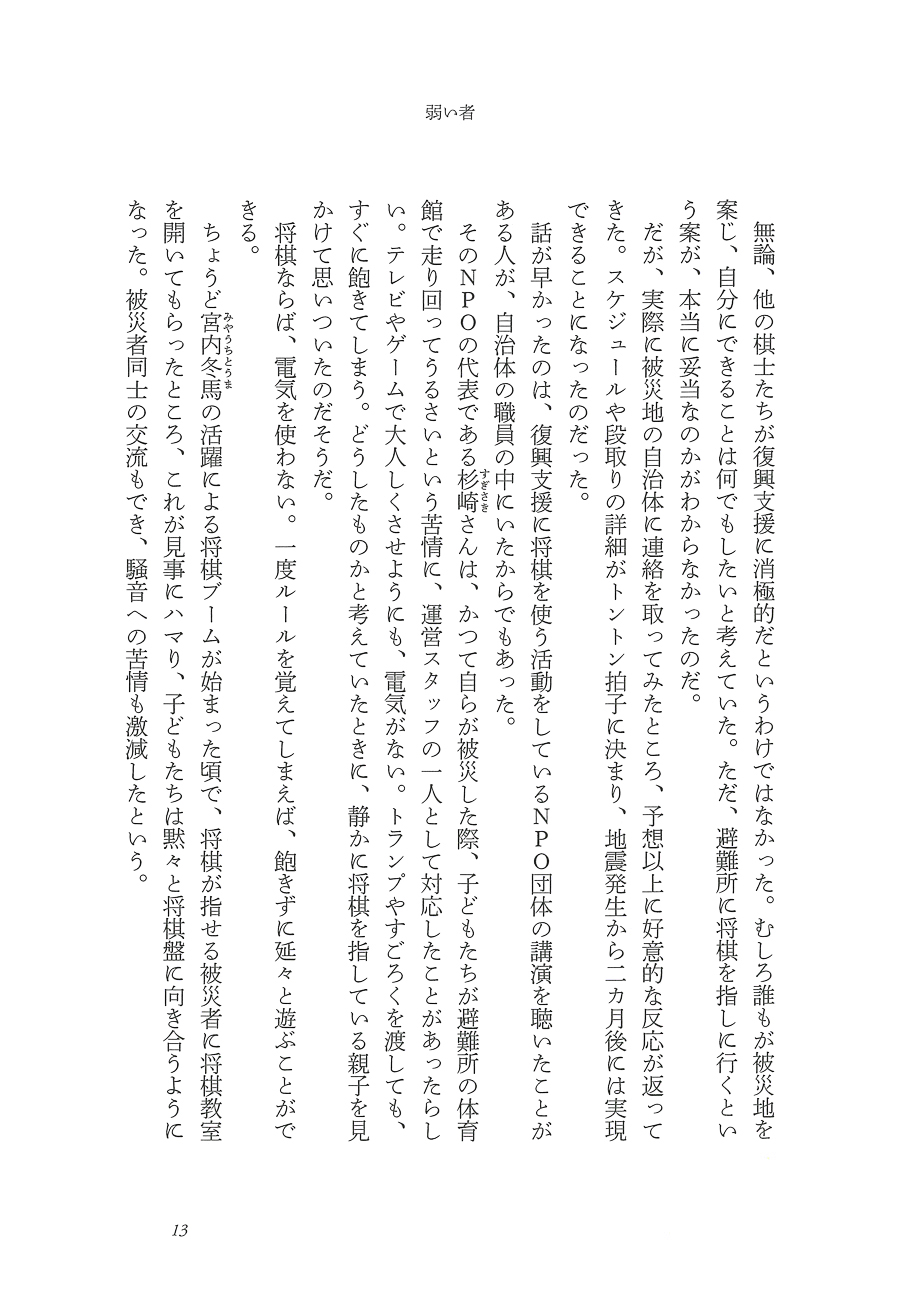弱い者――――2011
その手につかまれた駒は、妙に大きく見えた。
細い三本の指がつまみ上げるように宙づりにした駒が、ぽとりと盤に落とされる。連想したのは、ショッピングモールのゲームコーナーで幼い頃に目にしたクレーンゲームだった。ぬいぐるみを絶妙なバランスで持ち上げるものの、平行移動させる間に力尽きて落としてしまう、華奢な三本の爪だ。
思う場所にまでは運びきれないように計算して設定されていながら、一応は持ち上げられることで期待を抱かせるその台に、父は何枚もの百円玉を投入しては悪態をついていた。あーもうふざけんなよ。くそ、バカ、何だよこれ。
苛立ちともどかしさを呪いのように浴び続けたぬいぐるみのように、落とされた駒は力なく斜めに傾いている。
だが、辛うじて枠の内側に収まったそれは、そのぎこちなさとは不釣り合いに正しく鋭い手だった。
![]() 4五歩。
4五歩。
なるほどな、と俺は唇を舐めた。
これは、まず間違いなく定跡を知っている人間の手だ。この後は二歩突っ切りか銀多伝か、どちらにせよこちらの駒組を妨害するつもりなのは確かで、このまま流れに乗ってしまえば壁銀を呑まざるを得なくなり、上手が厳しくなる。
あるいは指導対局であれば、あえて乗ってあげるというのもありかもしれないが、ここでそれはさすがにつまらないだろう。
俺は、まずは5五歩止めで、相手に問いかける。
君がやりたいことはわかっている。これで望む形をあきらめるのか、それともあくまでも突いた歩の顔を立てるのか、どちらだ。
目の前の少年は、ただ盤上だけを見つめ続けていた。予想外の返しに動揺している顔でもなく、これへの対応策は知っていると張り切る顔でもない。まるで、この世界には存在しないものを映しているような、二つの黒い虚ろな穴。
年齢は十一、二歳――小学六年生くらいだろうか。
華奢な肩から伸びた腕は細く、被災後に美容院ではないところで切ったのか、どこか不揃いな髪からのぞく耳は初々しい。黒い半袖のパーカーのサイズが合っていないせいで余計に身体の小ささが強調されているが、濃い眉は意思の強さを表しているように見える。
少年は、淀んだ空気を動かさないような静かな手つきで飛車をつかみ、4筋に据えた。落とされた駒が、盤上に小さな波紋を広げていく。
俺は、口角をわずかに上げた。
タダ捨ての歩を角で取らず、飛車を利かせた上で金銀を盛り上げて位ごと奪還するというのは、たしかに棋書に載っている定跡の一つではある。だが、覚えることが多くてややこしく、定跡からも逸れやすい。一度逸れてしまえば純粋な棋力での捻り合いになり、
――だが、面白い。
互いに銀を繰り出す手を続けた後、こちらがふいに端歩を突くと、少年の目がほんのわずかに動いた。そこから凍結していたものが溶け出すように輪郭が揺らぎ、やがて腕が伸びて駒をつかむ。
先ほどよりも大きく広がった波紋を見つめながら、胸が高鳴るのを感じた。
この子は、強い。定跡をきちんと押さえた上で、変形に対応できるセンスもある。ギリギリのところで蛮勇になりかねない危うさもあるが、その粗削りさも含めて、感じさせるのは可能性だ。
俺は桂馬を跳ね、少年を見据えた。さて、これにはどうする。
少年は二分ほど考え込んでから、こちらの提案を飲んでくる。
ほお、という声が出そうになった。
この子は、大人しそうな外見に反して、かなり強気なタイプらしい。
俺が指したのは、力戦へと誘う一手だった。定跡から逸れて棋力での捻り合いになるけもの道と、定跡によって整備された道が残されている。拒めば一手損するものの、こちらが飛車角落ちである分、少年の優位は変わらない。
そして、少年が目先の一手損を怖がったわけではないことは、指し手を見れば明らかだった。この子は、きちんと先を読んでいる。先人の足跡に守られないことの意味も理解している。
――この子はこれから、きっともっと強くなる。
俺は用意していた手をすぐさま返し、少年の頬をじっと見つめた。少年は、表情こそ動かさなかったものの、微かに前のめりになる。
その姿に、感慨にも似た安堵が浮かんだ。やはり来てよかったのだ、と。
俺が避難所に指導対局をしに行くという案を出したとき、真っ先に上がった反対意見は、もっと他にやるべきことがあるんじゃないか、という危惧だった。
今被災者が必要としているのは水や食糧や衣類であって、将棋なんて何の腹の足しにもならないものを持ち込んだらかえって迷惑をかけるんじゃないか。復興支援をしたいのならば、既にやっている募金活動やチャリティーイベントを通した寄附を増やす方が、よほど為になるんじゃないか。
無論、他の棋士たちが復興支援に消極的だというわけではなかった。むしろ誰もが被災地を案じ、自分にできることは何でもしたいと考えていた。ただ、避難所に将棋を指しに行くという案が、本当に妥当なのかがわからなかったのだ。
だが、実際に被災地の自治体に連絡を取ってみたところ、予想以上に好意的な反応が返ってきた。スケジュールや段取りの詳細がトントン拍子に決まり、地震発生から二カ月後には実現できることになったのだった。
話が早かったのは、復興支援に将棋を使う活動をしているNPO団体の講演を聴いたことがある人が、自治体の職員の中にいたからでもあった。
そのNPOの代表である
将棋ならば、電気を使わない。一度ルールを覚えてしまえば、飽きずに延々と遊ぶことができる。
ちょうど
そうした経験から、杉崎さんは将棋盤と駒を持って避難所へ行くという活動を始めたそうで、その流れで我々棋士による復興支援イベントも杉崎さんのNPOと連携して行うことになったのだった。
まず杉崎さんたちが先に行って将棋教室を行い、将棋のルールを教えておく。そして次に我々が行って多面指しによる指導対局と将棋大会を開催する。
参加者たちのトーナメント戦の傍らで自分と
石埜は今年二十二歳、つい先日女流棋将戦と清玲戦を制したばかりの期待の女流棋士だ。面倒見の良さから後輩たちに慕われ、礼儀正しさと人懐こさから棋士たちにもかわいがられている。
見た目が愛らしく、解説の聞き手としても気が利いているということで以前からファンも多かったが、ここ一年でタイトル戦を二つ制したこともあって、盤上でも注目度を上げた女流棋士の一人だった。
ただし、女流棋士と棋士とでは、レベルが格段に違う。女流棋士のトップでも奨励会に入れば三段まで上がるのがやっとで、いまだ女性で棋士になった人間はいないのだ。
今の奨励会がどうだかは知らないが、俺がいた頃は「女に負けたら坊主」という罰ゲームがあった。
女流棋士という「受け皿」がある女と、棋士になれなければプロへの道が断たれる男とでは、切実さがまったく違う。そもそも女は、自分で稼げるようになる必要もない。脳の構造だって男と女では違うというではないか。女に負けるなんて坊主になるより恥ずかしい。女なんかに貴重な昇段の枠を奪われてたまるか――口から唾を飛ばして吐き捨てる人間は何人かいたが、俺自身は別に目くじらを立てるようなことでもないだろうと思っていた。
奨励会に女がいれば、それだけこちらは勝ち星を稼ぎやすくなるのだから。
石埜は現在、奨励会三段リーグに在籍している。ここで上位二名に入れば初の女性棋士だと騒ぐ声も聞こえるが、現実から考えてそれはないだろう。
一期目は大きく負け越し、二期目も昇段ラインにかすることさえなかった。三期目となる今期は来月から始まるが、その直前の時期を将棋の研究ではなくイベントの準備に使っている。
とはいえ、石埜が参加表明をしてくれたことは、このイベントにとってはありがたいことだった。俺だけが動いていたときは、まあ、
北上八段が言うならそうなんだろう。北上八段ならば受け入れられるかもしれない。そうした言葉を何度かけられたかわからない。
それは、俺がかつての「被災者」だったからだ。
俺が被災したのは、今から二十七年前、十歳になったばかりの秋のことだった。
地震による津波で両親を失った俺は、避難所ではひたすら将棋を指していた。
将棋を指していれば、黙って座っていることをそういうものとして許された。
盤の前では、笑わなくても、泣かなくても、しゃべらなくてもよかった。
次にどんな手を指すか、相手はどんな手で来るかだけを考えていれば、時間が過ぎていった。
俺は、起きている時間のほとんどすべて――時に夢の中でも将棋と向き合い続けた。相手がいれば対局し、いなければ他人の対局をじっと見つめ、他の時間には譲り受けた名局集の棋譜を延々と並べた。食事中や寝る前には必ず頭の中で詰将棋を解いていた。
それは、後に叔父の家に引き取られることになってからもだ。
あの日々がなければ、自分は棋士になることはなかったと断言できる。――棋士になれたのが幸せなことかはわからないが。
少年が、銀をつかんだ。
先ほどと同じ手つきで落とされた場所を確認すると、自然と口元が緩む。
今度はそうきたか。
「強いね」
俺は思わず話しかけていた。
少年が顔を上げ、微かに目を瞠る。周囲からは、おお、というどよめきが上がった。今回のイベントの参加者たちだ。
三十八人のうち、半数が年配の男性で、残り半分は数人を除けば子どもばかりだった。
おそらく、若い男性や女性は避難所の運営や瓦礫の片付け、食事の支度などの役割から抜けにくいというのもあるのだろう。その辺りの事情は、俺にもよくわかる。
指導対局をしたときの感触では、参加者のほとんどが将棋を覚えたばかりのようだった。定跡はおろか、銀を横に動かしてしまったり、王手放置をしてしまったりする人も少なくなく、指摘して手を戻してあげると、じゃっ、ほんとだ、と目を丸くしたり、ありゃ、なんたらや、と自ら苦笑したり、と忙しかった。この手はいいですね、と褒めると、こちらが驚くほどに喜び、あと三手で詰みますから、ちょっと考えてみましょう、と声をかけると、身を乗り出してうんうん唸った。
基本的には最後に詰ませてあげて、負けました、とこちらが頭を下げるようにした。パアア、という音が聞こえそうなほど顔を輝かせ、ありがとうございます、と言われると、将棋の楽しさを少しでも伝えられただろうかと、微笑ましい気持ちになる。どの人も本当に楽しそうで、石埜も、こんなに喜んでもらえるなんて、と嬉しそうにしていた。
ほとんどが指導対局というよりも将棋教室という方が近い形だったが、中にはかなり指し慣れている人もいた。平手を希望して最近流行している戦術で挑んでくる人もいたし、アマの大会でそれなりの成績を収めたという人もいたはずだ。
少年はこの中で勝ち上がって優勝したのだ、と思うと、何だか少し胸が
この駒の扱い方からして、おそらくみんな最初は
おそらく、この少年はきちんとした将棋教室には通わずに将棋を覚えたのだろう。駒の持ち方も教わらずに定跡を覚え、対局を重ねてきた。だから駒の扱い方と実力にこれほどの開きがあるのだ。
そういえば、対局開始時の挨拶でも、少年は「よろしくお願いします」とは口にせず、お辞儀をしただけだった。将棋教室では、必ず教えて守らせる礼儀だ。
「よろしくお願いします」と「負けました」は、絶対にきちんと口にしなければならない。特に負けたときにそれを自ら認める言葉を口にするのは、悔しく屈辱的だからこそ、欠かしてはならない儀式なのだった。
どの大会でも子どもが活躍すれば盛り上がるものだが、ここでも同様にギャラリーは沸き立っている。少年が考え込むたびに、けっぱれ、という声援が飛び、少年が好手を指すたびに、おお、と感嘆の声が上がった。
少女のように華奢で愛らしい顔をした少年は、スター性もたっぷりのようだった。宮内冬馬も、強さだけでなく容姿でも注目されているが、この子はその再来となるかもしれない。
俺の「強いね」という言葉にも浮き立ったのはギャラリーの方で、当の少年は応えることはせずに小さく黙礼した。
今いくつなの、と尋ねようとして思いとどまる。
いくら復興支援イベントとしての記念対局とはいえ、勝負の場だ。年配の棋士の中には指しながらしゃべる人もいるが、俺も対局中に相手に声を出されるのは得意ではない。
静かに歩を打ちながら、読みを進めた。
ここまでの手はある程度想定の範囲内だが、この先はあまり予想がつかない。定跡はまったく存在しない流れだし、俺自身見たことがない局面だ。
もはや、これまでの指導対局のように意図的に勝たせてあげる気はなかった。そんなことをしなくても、もうこの少年は将棋の面白さを知っている。ここまで指せる相手に、そんな手加減をしようものならかえって失礼だ。
たとえここで負けたとしても、この子がそれで折れてしまうことはないだろう。むしろ、奮起するきっかけになるかもしれない。
自分が、プロに対してどの程度通用するのか。自分には何が足りないのか。この子ならば、勝っても負けても、この対局から何かを学んでくれるはずだ。
少年は、首を捻って時計を見た。
今回の対局では、帰りの飛行機の都合上、持ち時間各一時間と定めている。少年は既に四十分以上使っていたが、俺はまだ五分ほどしか使っていなかった。
少年が会釈をして席を立ち、トイレへ向かう。ギャラリーは恭しく道を開け、少年の背中を見送った。
暗黙の了解のように誰もが声をかけずにいる中で、一人の男が少年に歩み寄り、肩を抱く。
「なあ、いつまでやってんだよ」
その親しげながら苛立ちが混じった声に少年は答えず、歩を速めた。
――あれは誰だろう。
俺は男を見つめる。
歳の頃は俺と同じくらいのようだから、三十代半ばだろうか。友達にしては歳が離れすぎているように思える。将棋仲間だとすれば不思議ではないが、あの男は今回のイベントには参加していなかったはずだ。
男はトイレの前まで少年についていったものの、ギャラリーの視線に居心地の悪さを感じたのか、そそくさと立ち去った。
――父親だろうか。
考えてみれば、俺の中学の同級生の中にも、もう父親になっている人間は何人もいる。若くして結婚していれば、あのくらいの歳の子どもがいてもおかしくはないのだ。
戻ってきた少年は、対局前に戻ったような暗い目をしていた。周囲をすべてシャットアウトするような透明な膜が、全身を覆っている。
――この子は、何を失ったのだろう。
ふいに、そんな疑問が浮かんだ。
肉親か、家か、友人か、そのすべてか――だが、その問いに意味などないことはわかりきっていた。ここにいる人間で、何も失っていない者などいない。そしてその傷の大きさなど、本人以外には――いや、本人にも推し量れないからだ。
唐突に大切なものを奪われる。その衝撃を真正面から受け止めることを本能が拒絶する。目を向けてしまえば飲み込まれる。振り落とされてしまう。それを望む一方で、完全に押し潰されるまでの苦痛と、途中で踏みとどまってしまうかもしれない恐怖に身が
しがみつくことができるのは時間だけで、それにさえも
死んでいると騒がれて避難所から運び出されていった
俺自身、今でも時折、引きずられることがある。
どれだけ時間が経ち、他の地域でもたくさんの災害が起こり、周囲から忘れ去られようとも、ふいに蘇る記憶はあまりにも鮮明で、自分はどこにも進んでいないのだと思い知らされる。長く長く歩き続け、遠くまで来たつもりでも、結局のところ抜け出せてなどいなかったのだと。
それは時間が経つほどに大きく、強く自分を打ちのめす。
少年は盤の前に座り、唇を引き締めた。
そして再び、盤上に沈み始める。
これで終わりだ、という局面が来たのは、対局開始から一時間ほど経った、午後四時過ぎのことだった。
少年が攻方での七手詰めがある。![]() 2四桂打、
2四桂打、![]() 同龍、
同龍、![]() 3四角打、
3四角打、![]() 同龍、
同龍、![]() 2二金、
2二金、![]() 1三玉、
1三玉、![]() 2三金で決まりだ。
2三金で決まりだ。
特に手を抜いたつもりはなかった。棋戦での対局のように、持ち時間を目一杯使って丹念に読み進めるということはしなかったものの、一手一手、きちんと妥当だと思われる手を指し、少年が
その中でここまで来たのだから、これは少年の実力だ。
この歳でプロに指導対局ではなく二枚落ちの真剣勝負で勝ったというのは、充分に誇っていいことだろう。これからも将棋を続けていく上で励みになるはずだ。
俺は棋譜を思い出しながら、全身が温かいもので満たされるような満足感を覚えていた。
これは、いい将棋だったと言えるのではないか。レベルという意味でもそうだし、面白さという意味でも、見所の多いスリリングな戦いだった。
詰みに気づいている人間はギャラリーの中には数人しかいないようだが、あと数手進めば、気づく者も増えていくだろう。
棋士同士の対局であれば、既に投了している局面だった。
俺は棋士の中でも往生際悪く粘る方だが、それでもここまで来ればさすがに投了せざるを得ない。
だが、投了せずに少年の手を待った。
復興支援イベントとしてこの場にいて、将棋を覚えたてのギャラリーが周囲にいるからだ。最後の最後、詰んだところまで指して投了というのが、初心者にも一番わかりやすい。
少年は、一心に盤上を見つめている。
おそらく読みに漏れがないか確かめているんだろう、と思うと、好ましく感じた。気を抜かず、調子に乗らず、最後まで集中力を保って向き合い続ける。このくらいの年頃では珍しいほどの胆力だ。
実際のところ、最後の最後でミスを犯してしまう人は少なくない。詰んでいないのに詰んでいると勘違いして思わぬ反撃に遭うとか、詰みがあるのに気づかずに別の手を指して形勢を逆転されてしまうとか、そうしたミスはプロでも秒読みの中ではまま起こることなのだ。
それに、この詰みは連続して駒を捨てなければならない怖い手でもある。もし詰めきれなければ巻き返せないほどの大損をしてしまう以上、慎重にならざるを得ないのは当然と言えば当然だ。
少年の目が、駒をなぞるように動き、さらに盤上の端から端までをさらうように動いた。
そして、一通りの確認を終えると、ゆっくりと腕を持ち上げる。
俺は居住まいを正し、応える準備をした。![]() 2四桂打、
2四桂打、![]() 同龍――展開を頭の中で浮かべる。
同龍――展開を頭の中で浮かべる。
だが、少年の手は、駒台ではなく、盤上へ伸びた。桂馬で龍を取り、腕を太腿の上へ戻す。
え、という声が喉の奥に吸い込まれた。
――まさか、詰みに気づかなかったんだろうか。
たしかに、一見龍を桂馬で取って大きく駒得したくなるような局面ではあるが、それではせっかくある詰みが消えてしまう。
周囲からどよめきが聞こえた。
思わず顔を上げると、意味がわからないのか目をしばたたかせている者もいるが、実力がある人間は一様に頭を抱えている。
俺も、頭を抱えたくなった。
少年の顔が見られない。きっと今頃、自分が詰みを見逃したことに気づいてショックを受けているだろうと思うと、いたたまれなくなった。
――これだけの棋力があって、こんなにも簡単な詰みを見逃すなんて。
信じられない思いだったが、それは誰よりも少年自身が痛感していることのはずだ。
自分は今、何をしてしまったのか。
たとえ指した瞬間には気づけなかったとしても、これだけギャラリーがわかりやすい反応をしているのだから、気づかないはずがない。
俺は、少年をかばうためというよりも、動揺している自分自身を
いわゆる、思考のエアポケットというやつだ。
プロだって、読んで、読んで、読んだ挙げ句にうっかり二歩をして反則負けをしてしまったりする。不用意なのではなく、あまりに用意周到に考えすぎるからこそ、通常ではありえないようなとんでもないミスを犯してしまうのだ。
ああ、という嘆息が周囲から響き、え、何、なしてさ、と尋ねる声が続く。いやね、今詰みがしてしまったのさ。ひそめられた声は、けれど俺の耳にも届いた。つまり、少年にも聞こえていないわけがない。
このままの盤面を晒し続けているのが忍びなくて、俺は次の手を指した。盤上の景色ががらりと変わる。
――これで、また形勢はわからなくなった。
少年は、盤を見つめたまま固まっている。
そこには、わかりやすいショックや落胆は表れていなかった。だが、ショックを受けていないはずがない。この局面でこんなミスをしてしまえば、命取りになりかねないのだ。
やがて、少年は持ち時間に促されるようにして、次の手を指した。失態を何とかカバーするための一手だ。
すぐさま脳裏に返しが浮かんだものの、わずかに
――ここでこの手を指せば、形勢は完全に逆転してしまう。
この少年相手に手を抜くようなことはすまい、と思ってきた。けれど、これで少年が負けた場合、それはこのイベントにとってどういうものになるのか。
純粋に実力で負けるのならば、まだあきらめもつくし、発奮する材料にもなるだろう。だが、こんな負け方では、後悔しか残らない。
被災し、大切なものを失い、深く打ちのめされているだろう少年に、そんなことをしていいのだろうか。
しかし、ここで手を緩めれば、少年が気づく。
とんでもないミスをして、それで手加減されて、お情けのような勝利をもらったとして、それでこの少年は喜ぶことができるのか。
俺は悩んだ末に、結局第一感として浮かんだ手を指した。
どうか、と祈るような気持ちが浮かぶ。どうか、何とか挽回してくれ。
少年は、五分ほど考え込んだ後、俺が少年でもそう指すだろうという手を返してきた。周囲で安堵と感嘆のどよめきが上がる。
俺も、その二つの感情を抱いていた。
怖いのは、ミスそのものよりも、ミスをしてしまったことに動揺してさらに悪手を重ねてしまうことだ。そうした意味で、この手ひどいミスから五分で立ち直ってみせた少年は立派だ。
少年は、辛抱強かった。既に持ち時間を使い切ってしまっているにもかかわらず、勝負を投げ出すでも、集中を途切れさせるでもなく、考慮時間をギリギリまで使って好手を積み重ねてくる。
俺も手を抜くことはなかった。心持ち、一手に時間を長めにかけるようにはしたものの、少年に勝ちを譲るために手を変えることはせずに進めていく。
おそらく、この場にいる誰もが祈るような気持ちでいるはずだ。このまま、少年に勝ってほしい。それが無理でも、せめて、先ほどのミスとは関係がないような局面まで進んでから勝敗が決してほしい、と。
それから、どのくらい手が進んだだろうか。
泥仕合のような様相を呈してきた局面の中で、ふいに少年が妙手を指した。
どよめきと同時に拍手が上がり、俺も小さく息を漏らす。
――この子は本物だ。
高揚が、じんわりと身体の内側に戻ってくる。
時計を見ると、午後四時半を回っていた。予定よりも長引いてしまったものの、ちょうどいい頃合いだ。これで少年が詰んで勝ち、表彰式をして、帰る。
むしろ、先ほどの詰みで勝敗が決していたよりも、よほど感動的な展開になったとも言える気がした。
すべてを投げ出したくなるような局面でも、辛抱強く、前に進めば、やがて道が開ける。
まるで、この場におあつらえ向きの展開ではないか。
俺は、深く息を吸って肺を膨らませながら、避難所を見渡した。
体育館一杯に敷き詰められた青いビニールシートと布団、ぎゅうぎゅうに押し込められた大量の人と荷物――その上に、二十七年前の光景が重なる。
ずっと、なぜ自分が生き残ったのだろう、と考えてきた。
自分以外の誰もが、少なくとも自分よりは生き残る価値があったように思えてならなかった。
神なんていないのだ、と思った。もしいたとしても、そこには意思はない。生死を分けたのは冷酷な無作為で、あの日自分が助かったのは何らかの選択の結果ではなく、ただの運でしかなかった。
だから将棋だったのかもしれないですね、とカウンセラーから言われたことがある。
将棋には、運が割り込む余地がない。相手の駒がどこにあるのかも持ち駒が何なのかも見えていて、手を読むのに必要な情報はすべて与えられている。常に秩序があって、予想できないような酷いことは起こらないから安心できたのではないでしょうか、と。
叔父と叔母は納得したようだったが、俺自身は、この人は何を言っているんだろう、と思っていた。
将棋は、秩序を壊すゲームだ。
収まるべきところに収まって安定した駒たちを、一手一手、混沌へ向けて動かさなければならない。
一ターンに動かせるのは一つのみ。それを攻めに出るために使うのか、守りを固めるために使うのか、常に選択を迫られる。速度のバランスをわずかでも見誤れば、機を逃す。隙を咎められる。
そして、まったくミスをしなかったと思えるような対局など、一度もしたことがないのだ。
盤上では、予想できなかった酷いことが起こり続けていた。必死に積み上げてきたものが一瞬で崩され、すべておまえのせいだと突きつけてきた。おまえが弱いから負ける。おまえは何も守れない。
だから俺は、強くなりたかった。とにかく勝ちたかった。みっともないと笑われようと、相手が間違える可能性がゼロにならない限り粘り続け、美学など
勝ってさえいれば、存在が許される。
向けられる視線が、自分の輪郭を作ってくれる。
だが、それでも俺は、一度もタイトル戦に出場したことはない。四段になったのが二十三歳のとき、それからの十四年間、チャンスを逃し続けてきた。
最も上まで行ったのは、二十九歳の頃だ。挑戦者決定戦に臨み、あと一勝でタイトル戦の舞台に進めるところまで行っておきながら、当時既に別のタイトルを三つ持っていた
そのときは、次がある、と思った。ここまで来られたのだから、もっと努力すれば次は手が届くはずだ、と。
けれど、翌年は挑戦者決定リーグに入れることさえなく終わり、その後も、大事な一戦に限って落とした。
足踏みを続けているうちに、自分よりも若くキャリアも浅い後輩たちに追い抜かれ、彼らが着々と実績を積み上げていく傍らで、特に歴史に名を刻むこともなく、ただピラミッドの土台に飲み込まれてきた。
いつか見返してやるという思いは、年々
あのときが唯一のチャンスだったのではないか。結局、俺はここまでの人間だったんじゃないか――
そう疑い始めると、もうダメだった。
ここ一、二年は、以前ほど努力することさえできず、ついに今期はB級2組から降級した。
自分は、この世界に何も残せないのかもしれない、という諦念が泥のように全身に絡みついていた。このまま、生き延びた意味も刻めずに、余生のような日々を潰していくしかないのだ、と。
――だが。
俺は、目の前の少年を見つめた。腹の底から、熱いものが込み上げてくる。
このためだったのではないか。
こうしてこの少年と出会い、将棋を指すために、俺は生き延びたのではないか。
少年は、おそらく現時点でアマ四段ほどの実力があるだろう。奨励会の入会試験は合格できるだろうし、その先できちんと鍛錬を続ければ棋士になることも夢ではない。
まだ大きな大会への出場経験がないのなら、俺が推薦人になってもいいし、本人が望むなら師匠として面倒をみてもいい。
将棋によって生かされた自分が、避難所で出会った将棋少年の師匠になり、棋士を生み出す。
まるで、定められていた運命のようではないか。
次の手を指して顔を上げると、ギャラリーの中にいた石埜と目が合った。石埜も頬を紅潮させてうなずいている。
あとは、少年が飛車を成るだけだ。
そうすれば、この先の詰み手順は、今度こそ間違えようがないほど単純なものになる。
秒読みの中で少年が腕を持ち上げ、飛車をつかんだ。俺はその
「え」
今度こそ、声が出ていた。
盤上では、飛車が、不成で転がっている。
――何を。
少年の顔を見ると、少年は無表情のままでいた。感情が大きく動きすぎて表情が追いつかないのか、それとも頭が真っ白になってしまっているのか、顔を上げることすらせず、盤上に目を向け続けている。
もはや、うっかりだとも思えなかった。先ほどよりもわかりやすい形だし、何より、もう二度と先ほどのようなミスは犯すまいと心に誓っているはずだからだ。
いくら持ち時間が切れているとはいえ、そもそもこの局面で飛車を三段目まで上げておきながら成らない理由はどこにもない。
――それとも、駒の扱いに慣れていないせいで手が滑ってしまったのだろうか。
指導対局ならば、待ったをありにして、指し直させてあげたいほどのミスだった。
だが、この場ではそんなわけにもいかない。
どうすればいいかわからずにギャラリーを見ると、何人もが顔を手で覆っていた。
俺は、第一感として浮かんだ手を読み進め、その後、別の手も考えていく。普通の自分ならばこう指す、という手は既に決まっていた。それでも、なかなか腕が伸びない。
自分は、何のためにここに来たのか。
それを問われているような気がした。
ここでこの少年がこんな負け方をすることは、少年のみならず、今回のイベントに参加してくれた人全員の心を挫くだろう。
ただ勝負の場にふさわしい手を指したいというだけで、少年を最悪の負け方に追い込むのは、結局のところ自分のエゴでしかないのではないか。
気づけば、持ち時間を十五分も使っていた。
ボランティアが帰る気配を感じて、焦りが浮かぶ。
早く指さなければならない。とにかく早く終わらせなければならない。
もはやこのまま投了してしまいたいほどだった。しかし、さすがにここで投了したのでは収まりが悪すぎる。
俺は結局、単に逃げるだけの手を指した。
本来ならば絶対に指さないだろう悪手だ。
考えに考えて指したはずなのに、駒から指が離れた途端に後悔が襲ってくる。本当にこれでいいのか。これは、少年を裏切る手ではないか。
だが、その一方で、これでもどうせ詰まされないかもしれない、という気もしていた。絶対に勝ってやるという思いでいるのなら、一度目はともかく、二度目のミスはあり得ないはずだからだ。
少年が、ちらりと体育館の出入り口を見た。盤面に顔を戻し、小さく息を吐く。
その手が駒台へと伸び、置かれた。
ゆっくりと、少年が頭を下げる。
「え?」
何をされたのかわからなかった。
周囲でも、一気にざわめきが広がる。
この子は、その動きの意味をわかっているんだろうか。駒台に手を置いて頭を下げることは――
「投了?」
ギャラリーから戸惑い混じりの声が聞こえる。
少年は太腿の上で自らの手を繋ぎ合わせたまま、目を伏せていた。周囲の声は聞こえているだろうに、否定もしない。
その取り澄ました表情に、カッと頭に血が上った。
――どうしてだ。
かなり厳しい形勢とはいえ、まだ挽回する方法がないわけではなかった。そうした道を残すために、自分はたった今、悪手を選んだのだから。
なのに、なぜ――
期待したからこそ、失望が大きかった。
この子はもっと胆力があるのだと思っていた。一度目のミスからは見事に挽回してみせたのだ。今度だってあきらめさえしなければ、勝つことだってできたはずなのに。
ここが避難所での将棋大会でなければ、叱りつけたいくらいだった。
最後まで全力を尽くせ、君に負けた他の参加者に対しても失礼だろう、と。
「いやあ、惜しがったなあ」
ギャラリーの一人が、沈んだ空気を払おうとするように言った。
「だげんと、大したもんだよ。プロ相手にここまでやれだんだから」
「すげがったよなあ。久しぶりに興奮した」
俺は目をつむって苛立ちを抑え、意識的に口角を上げる。
「今いくつなの?」
できるだけ柔らかな声になるように気をつけたつもりだった。けれど、少年は身体を強張らせ、深くうつむく。
「将棋はいつからやってるの?」
戸惑いながらも問いを重ねたが、これにも少年は答えないままだった。
俺は、少年の顔に深い影を作っている長い前髪を見つめる。
――まさか、口がきけないのだろうか。
そういえば、一度も少年の声を聞いていなかった。初めの挨拶でも、少年はお辞儀をしただけだったし、こちらの問いかけにも、途中でトイレに立った際に声をかけられたときも、返事をしていなかった。
挨拶を口にしなかったのは、きちんと教わっていないからなのだろうと思っていた。問いに答えなかったのも、対局に集中しているからなのだろうと。
しかし、もしかしてそうではなかったのだろうか。
強い精神的なショックを受けることによって声が出せなくなることがある、というのは聞いたことがあった。――被災したというのは、それに当てはまりすぎるほどの出来事だ。
俺が口を
「北上先生、お疲れ様でした」
深く頭を下げて
「すみません、時間が押してしまって」
「なんもなんも、こっちはいいんですよ。でも、帰りのお時間は大丈夫でしたか?」
スタッフは心配そうに眉尻を下げた。
俺は腕時計を見下ろし、「はい」とうなずく。
「今出れば、何とか」
本当はきちんとした表彰式でも、と思っていたけれど仕方ない。ここで帰れなくなってしまったら、結局のところ迷惑をかけてしまう。
「石埜さん」
俺が呼びかけると、石埜はそれを予想していたようにすばやく飛んできた。
「賞品は準備できています」
「じゃあ、あの子に渡してすぐ失礼しようか」
石埜に差し出された賞状と将棋盤と駒を受け取り、少年の元へ向かう。賞状に書き込まれた
少年が振り返る。
「これ、本当はきちんとした表彰式をしたかったんだけど」
少年は開きかけた口を閉じ、首を振った。
賞状と賞品を受け取り、深く腰を折るようにしてお辞儀をする。そのまま立ち去ってしまいそうな雰囲気を感じ、あ、と思った瞬間には、「奨励会に入らないか」と口にしていた。
少年と石埜が同時に振り向く。
二つの驚いた表情に、俺自身も驚いた。
俺は、何を言っているんだろう。
たしかに対局中は、この子の師匠になってもいいと考えた。だが、突然お粗末な投了をされて、腹を立てていたはずなのに。
耳の裏が微かに熱くなるのを感じながら、いや、と目を伏せる。
「いきなりこんなことを言われても困るよな。すぐには判断なんかできないだろうし、もちろん今すぐ決めてくれっていう話でもないんだけど、とにかく君みたいな強い子が埋もれてしまうのはもったいないと思って」
自然、口調が速くなる。
「えっと、知っているかもしれないけど、奨励会というのは棋士の養成所みたいなところなんだ。入会して例会で勝ち進めば級位が上がって、四段に昇段すればプロになれる」
少年が、戸惑ったように視線をさまよわせた。
「入会試験を受けるには棋士の推薦が必要だけど、もし他に当てがないようならば俺が引き受ける。例会は東京と大阪の将棋会館でやるから、地方出身者のほとんどは近くで一人暮らしをするか下宿をする。中には地元に住んだまま例会のたびに遠征してくる子もいるけれど、どちらにしても金銭的な負担があるから、まずは君さえよかったら一度親御さんに話させてもらえないかな」
頬までもが熱くなっていく。
こんなことを言ってどうする気だ。この子にそんな気があるのか? 俺は、本当にこの子の面倒を見るつもりなのか?
「あなたはどうしたい?」
石埜が少年に視線を合わせて尋ねた。
「とりあえずお金のこととかは置いておいて、将棋のプロになりたいっていう気持ちはある?」
少年は怯えるような顔をしたものの、俺と石埜を交互に見てから、一度うつむき、数秒して顔を上げる。
こくり、と真っ直ぐにうなずいた。
その、今日目にした中で一番強い力を持った瞳に、ぐるぐると回り続けていた思考がすっと落ち着く。
――ああ、そうだ。
俺は、もったいないと思ったのだ。
終盤を鍛えれば、この子はもっと強くなれるのに、と。
あきらめないことの大切さを教えたかった。投了した場面からでも、本当は挽回する道があったのだと指摘したかった。可能性にしがみつくのは恥ずかしいことではないのだと――
「お父さんと話すことはできるかな?」
石埜の言葉に、対局中、トイレに向かう少年に話しかけていた男の姿が脳裏に浮かんだ。
『なあ、いつまでやってんだよ』
苛立ちをぶつけるように、どこか甘えるように、少年の肩に腕をかけていた男。
あの男がこの子の父親なのだとしたら、これからこの子が将棋に専念できる環境が整えられることはないだろう。
あの男は将棋には理解も興味もなさそうだったし、わからなくても応援しようという気持ちも感じられなかった。
あるいは、状況が落ち着けばありえるかもしれないが――だが、それはいつのことになるのか。
見たところ、少年は小学六年生くらい――華奢な中学生だと言われればうなずけるくらいの歳に見える。奨励会には年齢制限がある以上、入会するのは早いほどいいというのに。
顔を上げると、視界にプライバシーなど存在しない空間が飛び込んできた。段ボールの衝立は腰を上げれば顔が出てしまうほどに低く、気休め程度にしかならない。
今日のイベントによって、この避難所にいる将棋好きの人間と面識ができたかもしれないが、この子にとっては実力が下の相手ばかりだ。
――このままでは、この子の成長はここで止まってしまう。
腕時計を見下ろすと、飛行機の時間が迫っていた。
父親に対してするべき話の段取りを考えながら、焦燥を感じる。
順を追って話さなければ、下手をすると詐欺だとさえ思われかねない。しかし、今はそんな時間がない。
――今日のところはこのまま帰って、落ち着いて情報を集めてから出直すべきかもしれない。
俺も、今は舞い上がってしまっている可能性が高い。一呼吸おいて、冷静になって考えた方がいいのではないか。この子にもゆっくり考える時間が必要だろう。
少年と、目が合った。
その途端、再び心がぐらりと揺れる。
俺は、このままこの子を放って東京へ帰って、後悔しないと言えるだろうか。
次にいつ、ここに来られるかもわからない。父親を説得するには、将棋大会で優勝した直後というこのタイミングを逃す手はないのに。
何より、遅くなればなるだけ、棋士になれる可能性は低くなるのだ。
本当にこの子を育て上げるつもりなら、何よりもまず、落ち着いて将棋に専念できる場所を作ることが肝要だ。避難所を出て、奨励会の例会に通いやすい場所へ――ふいに、内弟子、という案が浮かんだ。
俺が内弟子として引き取って、面倒をみる。
それなら毎日好きなだけ将棋に打ち込めるようになるし、この子の親に金銭的な負担をかける選択を迫らずに済む。
今時、内弟子を取っている棋士などいないし、自分にきちんと面倒がみきれるかと問われれば、正直自信はない。だが――
「内弟子にならないか」
少年が目を見開いた。
石埜の方からも、息を呑む音が響いてくる。
「これは、もし君が望んで、親御さんも承諾してくれたらの話だが、俺としては君を東京の家で引き取って面倒をみてもいいと思っている」
自分の言葉に、気持ちが固められていくのがわかった。
「引き取ると言っても、もちろん養子にするとか、そういう話じゃない。最近は聞かないけど、昔はよくある話だったんだ。棋士の家に何人もの内弟子が住み込んで、家の手伝いをしながら将棋を教わる。棋士になれるまでの期間限定のことで、プロとして自分で稼げるようになったら、うちを出て一人暮らしをすればいい」
少年は、言葉の意味を受け止めきれないというように目を泳がせる。その様子に、もちろんこれも今すぐに決めろという話じゃないよ、と続けようとしたときだった。
少年が、かさついた唇を小さく開く。
「それなら、すぐにここから出られますか」
一瞬、誰が口にしたのかわからなかった。
一拍遅れて、目の前の子どもが発した言葉だと気づく。
この少年――いや、この子は少女だ。
後頭部を強く殴られたような衝撃に、言葉が出てこなくなる。
女の子――
塩原涼、と書かれていた名前が蘇る。
たしかに、男の子でも女の子でもあり得る名前だった。それに――俺はこの子の容姿を見て、少女のようだと思った。
だが、それでも、女の子かもしれないなんて考えもしなかったのだ。
「いや、あの……君は、女の子だよね?」
「女だとダメですか?」
少女が、強い口調で尋ね返してくる。
「ダメっていうか……」
俺は口ごもった。背中を嫌な汗が伝い、落ち着かなくなる。
「さすがに女の子を内弟子にするわけにもいかないし……」
少女の目が、汚れた布で拭ったかのように曇った。
先ほどまで消えていたはずの膜が、再び少女の全身を覆う。
俺は慌てて口を開いた。だが、何を言えばいいかわからない。
少女は身体を揺らすようにして会釈をし、立ち去っていった。
あ、という声が喉の奥に吸い込まれる。
少女の姿が見えなくなるまで、俺は立ち尽くすことしかできなかった。
避難所を出ると、辺りはもう暮れかけていた。
借りた自転車で石埜と併走していく。
ため息を吐き、代わりに息を吸い込むと、津波の臭いがした。蒸発した海水と、魚の死骸、船や車や家から流れた油の臭いが入り混じった、重く、胸が悪くなる臭い。俺は、これを知っている、と思う。
――俺は結局、何をしに来たのだろう。
先ほども浮かべた思いが、また別の形で浮かんだ。
被災者の気晴らしになるどころか、あの子を不用意に傷つけた。こんなことなら、来ない方がよかった――
北上八段、と石埜が呼びかけてきたのは、自転車を降りたときだった。ここから先は迎えに来てもらう車で空港へ向かうことになっている。
辺りを見回したところ、連絡が上手く届かなかったのか、まだ車の姿はなかった。
「あの子のことなんですけど」
躊躇いがちな石埜の声に、口の中が苦くなる。
「あの子には変に期待を抱かせてしまって悪いことをしたと思ってるよ。でも、女の子を内弟子に取るわけにはいかないだろう」
「それは、そうですけど」
石埜がうつむいた。
その何か言いたげな表情から視線を外し、足元へ落とす。
「……たしかに、内弟子の線は無理だとしても、せめて親に話すくらいはしてみてもよかったかもしれないな。対局中に話しかけてきていたあの男が父親なのだとしたら、説得するのは難しいだろうが」
「いえ……それなんですけど」
石埜は、少し言い淀むようにしてから、音を立てて息を吸った。
「私、北上八段が対局している間に聞いたんですけど、あの人、彼女の父親なんかじゃないらしいんです」
「え?」
俺は顔を上げる。
「じゃあ、あの男は……」
「東京から来たボランティアらしいです。本当の父親は、日中は瓦礫の片付けのために避難所の外で働いているそうで」
ボランティア――その言葉が、あの姿と上手く繋がらない。
「いや、でも、あんな昔からの知り合いみたいに……」
「あの子、実は別の避難所から移ってきたらしいんです。前の避難所で、知らない男の人が夜中に布団の中に入ってきたことがあったみたいで……それで、男の子みたいな格好をして声を出さないようにしているんだって、スタッフの人が言っていました」
「布団に入ってきたって……それは犯罪じゃないか」
「警察が機能していないんですよ。周りも自分のことで精一杯だし、本人もプライバシーとか、これからも同じ空間で生活し続けなきゃいけないことを考えると訴えにくいって……私も、今日ここに来る前に気をつけろって言われて調べたんですけど」
でも、と返す声が微かにかすれた。
「父親がいるなら、あのボランティアの男のことも父親に相談すれば……」
「言いづらいんじゃないでしょうか。前の避難所のときみたいに決定的な出来事があったならともかく、怖いことが起こりそうだから不安だという話をしたって、それでまた避難所を移れるかどうかはわかりません。もし移れることになったとしても、知り合いが多い避難所から出てきて苦労している父親に、さらに負担をかけることにもなります。もう迷惑はかけられない、自分さえ我慢すればって、そんなふうに考える気持ちは……わかる気がします」
あの男は、父親なんかではなかった。あの子は、男につきまとわれて困っていた。
脳裏に、美容院ではないどこかで切ったのかと感じた不揃いな髪が蘇る。
――あの髪は、女の子であることを隠すために切られたものだったのではないか。
頬がカッと熱くなった。
どうして気づかなかったんだろう。
あの場にいて、現場を目にしていたのに。
違和感は、何度も覚えていたはずなのに。
「だけど、だったらどうしてあの男はあの子が女の子だって……」
「着替えとかトイレとか、覗こうと思えばいくらでも方法があるみたいです」
石埜が、顔を歪めて言う。
俺は、今来た道を呆然と振り返った。
あの子は、そんな中であの対局に臨んでいたのか。
そう考えた瞬間、電流のようなものが全身を駆け抜ける。
――だからだったのではないか。
ずっと、あの子がどうして二度も詰みを逃したりしたのかわからなかった。
だが、今の話を聞いて、彼女が突然投了したのがボランティアが帰ってすぐだったことを考えれば、自ずと答えは見えてくる。
――彼女は、自分の身を守るために、対局を続けていたのだ。
勝ち進んでさえいれば、イベントに参加し続けることができる。
いくら他の人が見て見ぬふりをしたとしても、対局相手だけは、対局のために、自分を守ってくれる。
だから、詰みを逃してでも対局を引き延ばした。
――あのボランティアの男が帰るまで。
詰みに気づいていながら、あえてそれを外して不本意な手を指すなんて、悔しくなかったわけがない。
負けたくない、強くなりたいと鍛錬を続けてきた人間でなければ、あれほどの力はついていないというのに。
それでも、あの子はそんな将棋指しとして当然の思いを曲げてまで手を変えた。
――それは、どれほどの恐怖なのか。
俺はここに来て、自分もこれを知っている、と何度も思った。
同じ経験をした自分にはわかるのだと。
だが、俺は、何をわかっていたというのか。
「こういうときは、弱い者にストレスのはけ口が向かうんだそうです」
「そんな、弱い者って……」
反射的に返しかけた言葉の先が、喉の奥を塞ぐように詰まる。
俺は、気づいてしまう。
自分が、あの子の容姿を少女のようだと思いながら、それでも少年だとしか考えなかったこと。
そこには、強いのだから男の子に違いないという先入観がありはしなかったか。
そして、男の子であってほしい、という願望が。
男の子ならば、一緒に棋士を目指せる。これからいくらでも伸びるし、もっともっと強くなる。
内弟子の話を引っ込めたのも、独身男性である自分が引き取るわけにはいかないというだけではなかった。
たしかに自分は――そのことに思い至るよりも前に、落胆していた。
なんだ、女か、と。
「北上八段」
石埜が、意を決したように口を開いた。
「やっぱり私、もう一度避難所に戻ってもいいですか」
俺は、声を出せないまま、石埜を見る。
「私、避難所での性被害を防ぐために活動している団体のホームページを見てきたんです。まずは、あの子のお父さんと避難所の運営スタッフの方に相談してきたいと思います」
石埜は硬い声音で言いながら、自転車の向きを変えた。ぐんぐんと力強く離れていく石埜の背中を、身動きもできずに眺める。
俺は、自らの手を見下ろした。
先ほどまで駒をつかんでいた指。その上に重なるように、あの子が飛車を不成のまま落とした瞬間のぎこちない指の形が浮かぶ。
――結局、あの対局は何だったのだろう。
身体から力が抜けていくのを感じた。代わりに、重い疲労感が押し寄せてくる。
あれは、将棋大会の優勝者との記念対局なんかではなかった。
自分と少女は、同じ将棋盤を挟みながら、まったく別のゲームをしていたのだ。
俺は、普通の将棋を――そして彼女は、ボランティアの男が帰るまでの時間、対局を終わらせない、という戦いを。
そう、考えた瞬間だった。
小さく呑んだ息が、肺に取り込まれて背筋を伸ばす。
顔が、来た道を振り返っていた。不本意な手を指して負けた彼女を不憫に思う気持ちが、繋がりや名前や意味を失ってなおそこにある瓦礫を前に霧散する。
――あの子は、負けていなかった。
将棋では、たしかに俺が勝った。
けれど、あの子はあの子で、彼女自身の戦いの中で勝利していたのだ。
背後から、車のタイヤが立てる悲鳴のような音が聞こえてくる。
振り向くと、灰色の車が瓦礫の奥から回り込んでくるのが見えた。
反射的に逃げ出したくなって、そんな自分に驚く。
この車は、俺を迎えに来た。俺は、帰らなければならない。だが――
ぞろりと、腹の底で何かが
ああ、そうだ。ただ、それだけなのだ。
――俺は、あの子と将棋が指してみたい。
あの子が別の戦いを強いられることがなければ、どんな手を指すのかが、見てみたい。
車が停まり、運転席のドアが開いた。
「先生、すみません遅くなって――」
駆け寄ってくる足音を聞きながら、俺は伏せていた顔をさらに下げる。
迎えに来た男に対して謝る言葉を口にするために、唇を開いた。