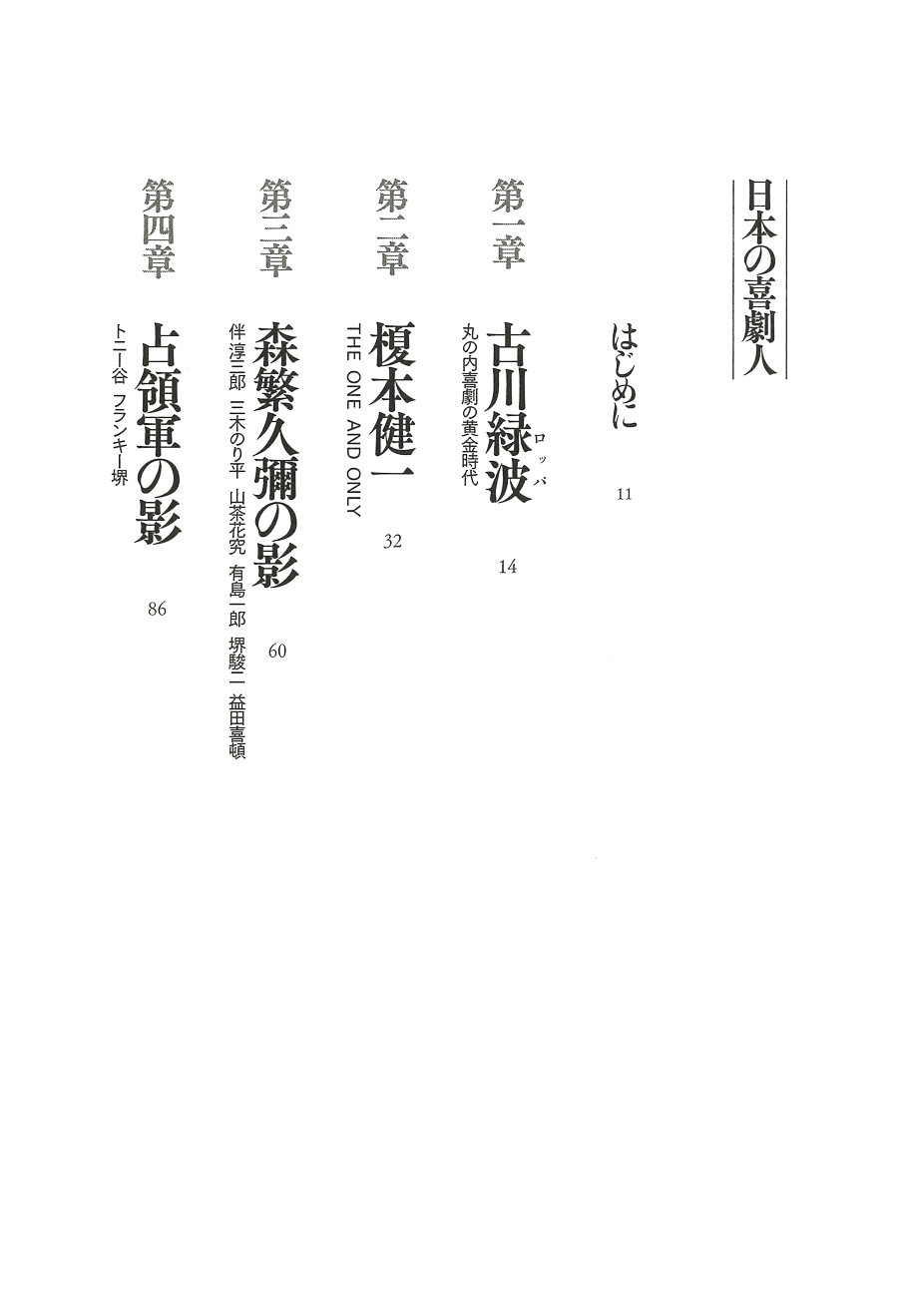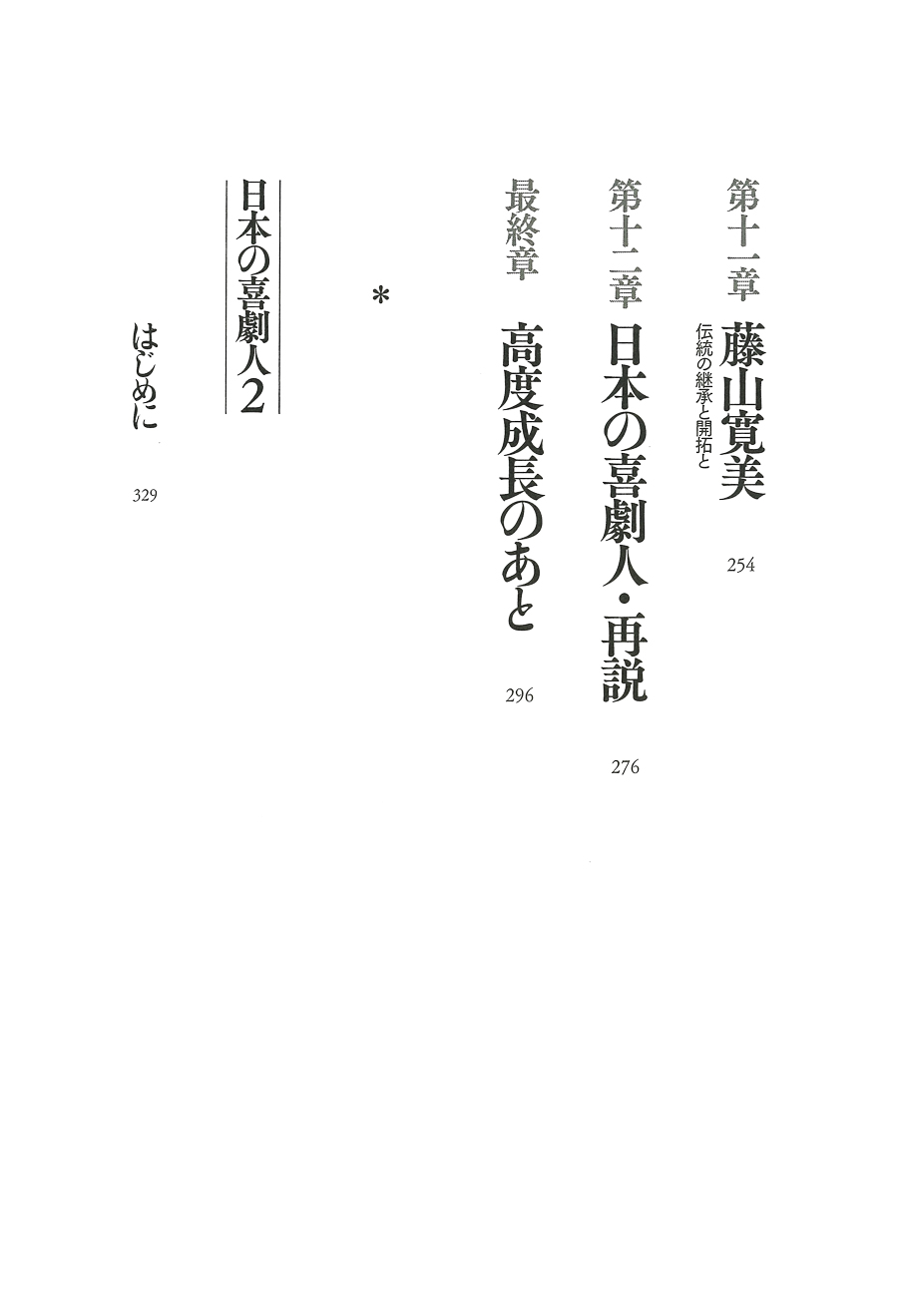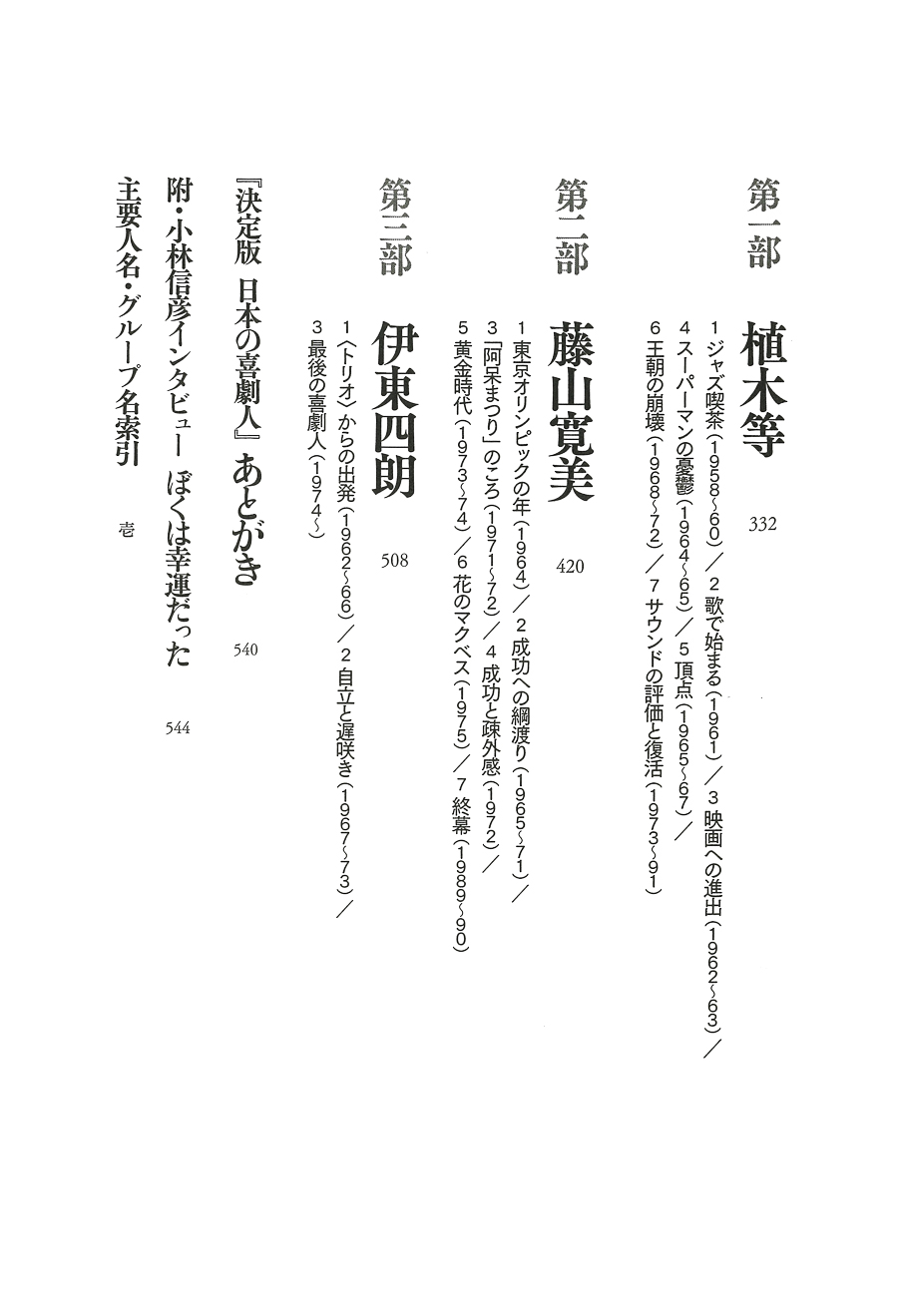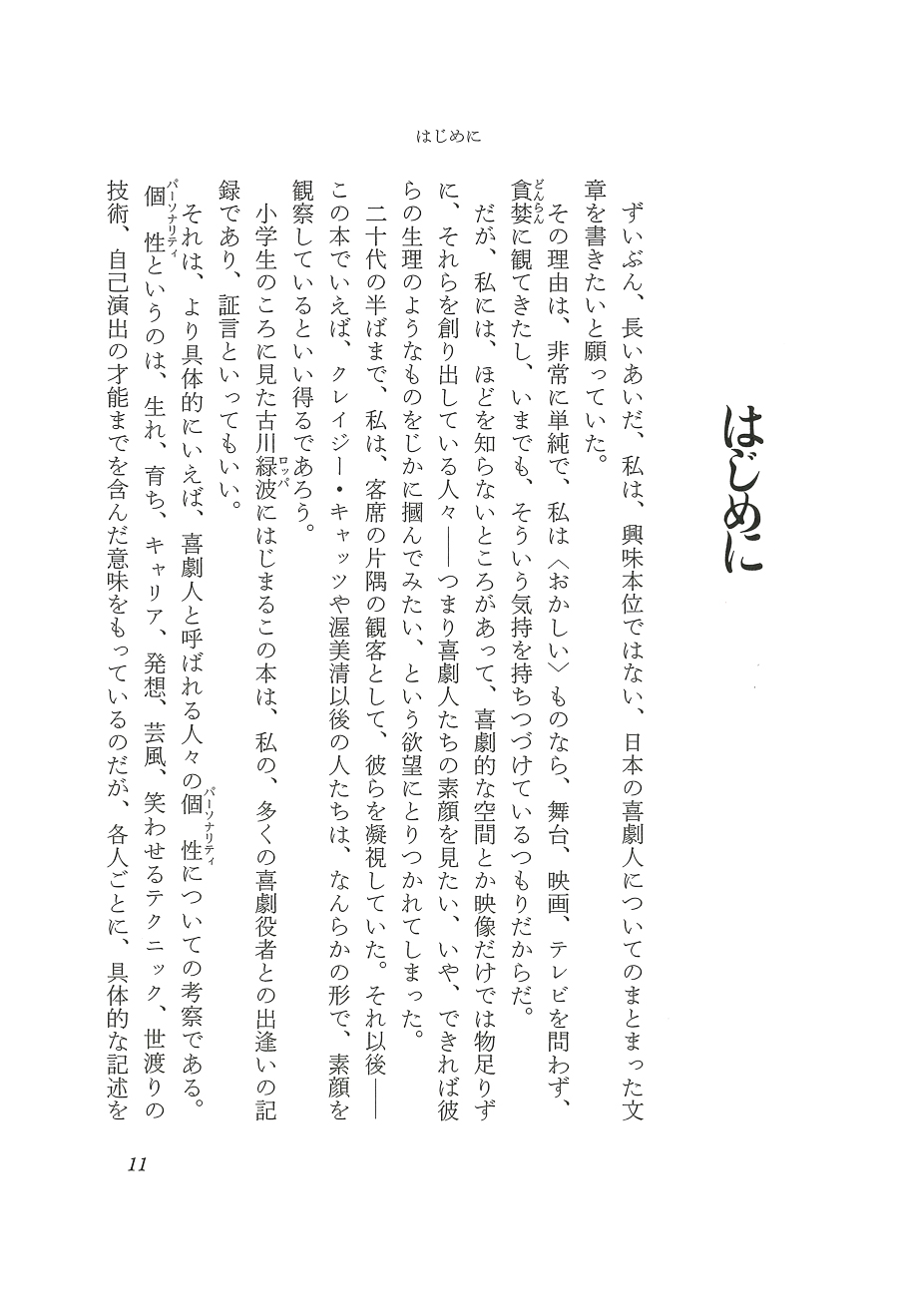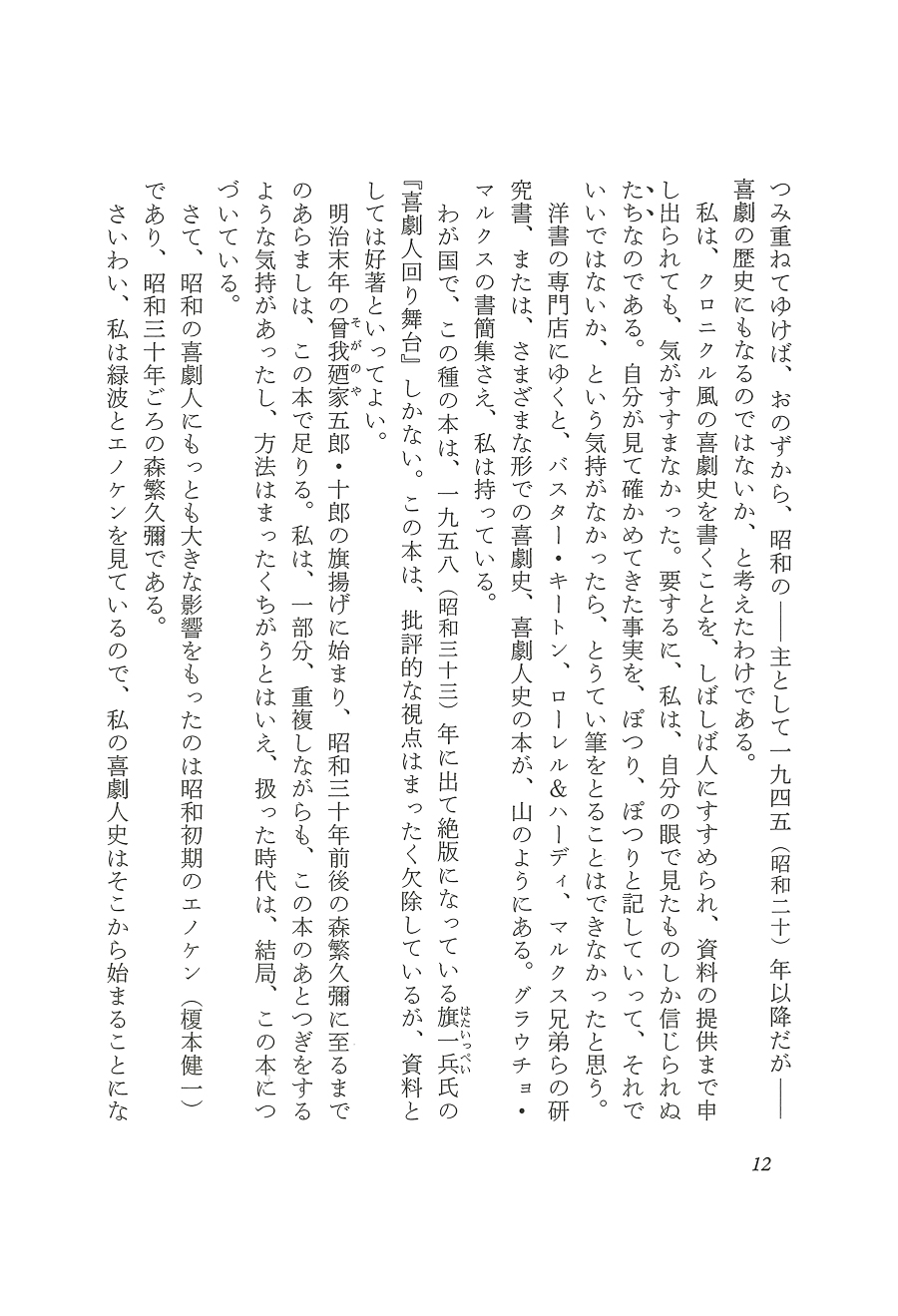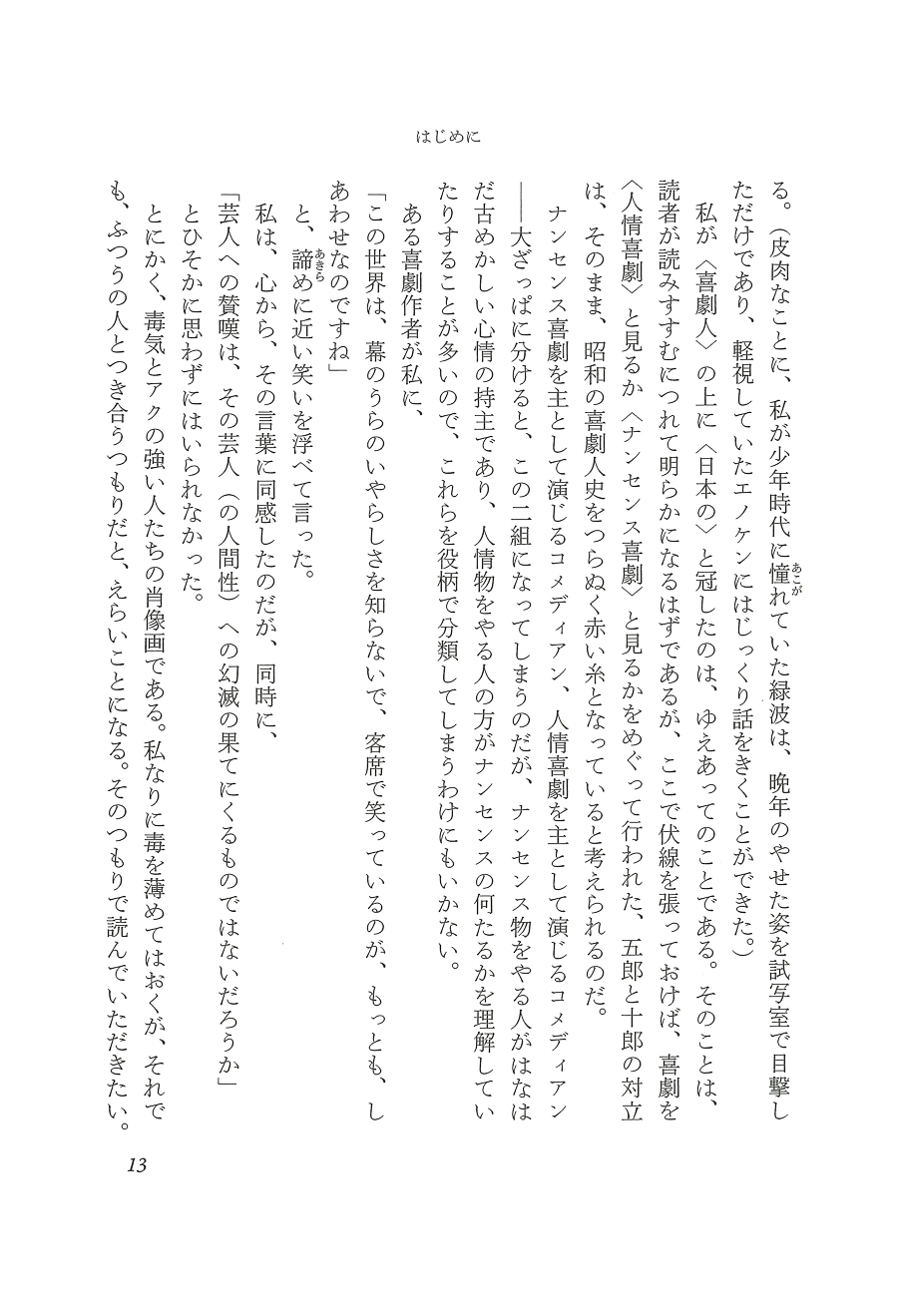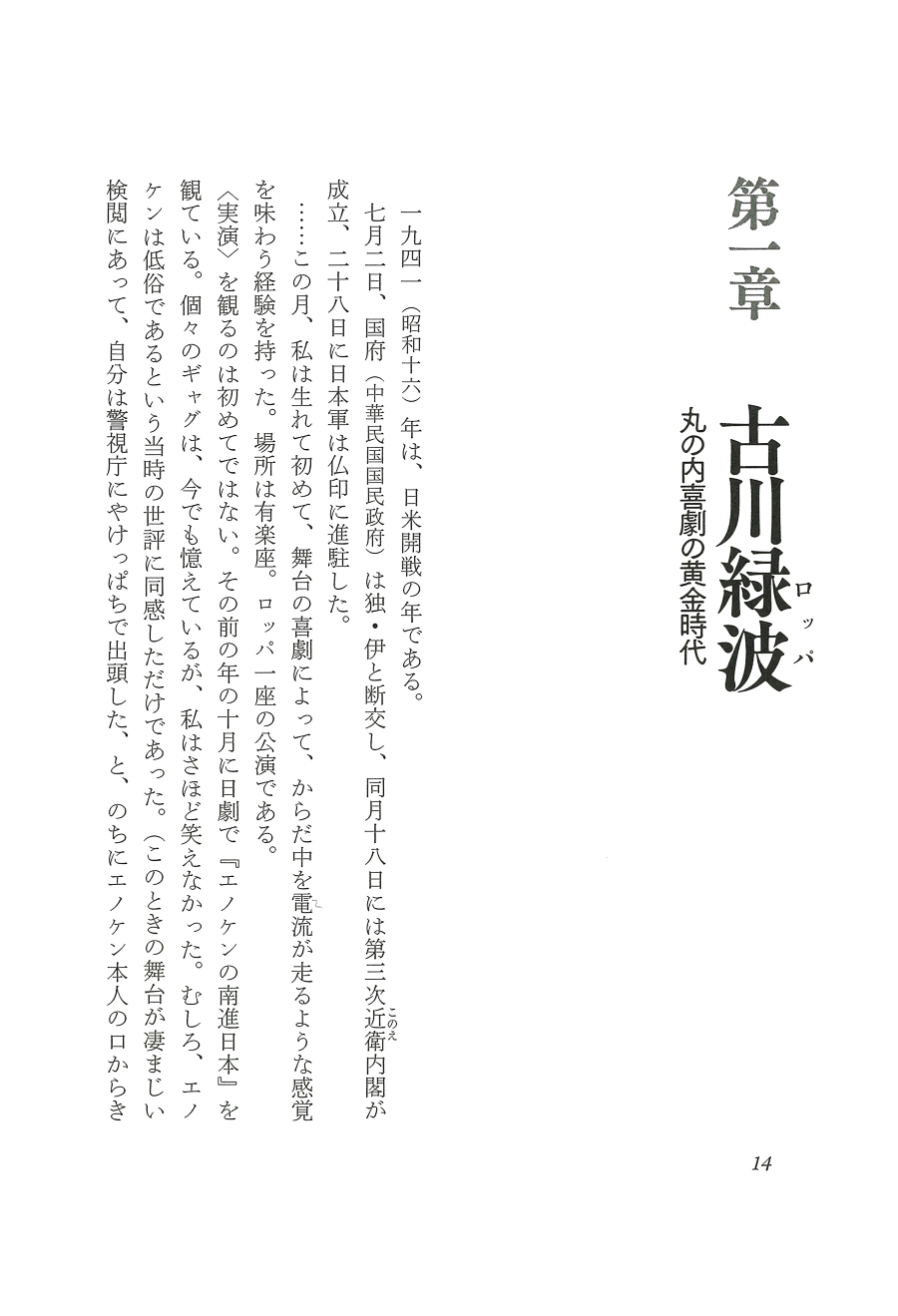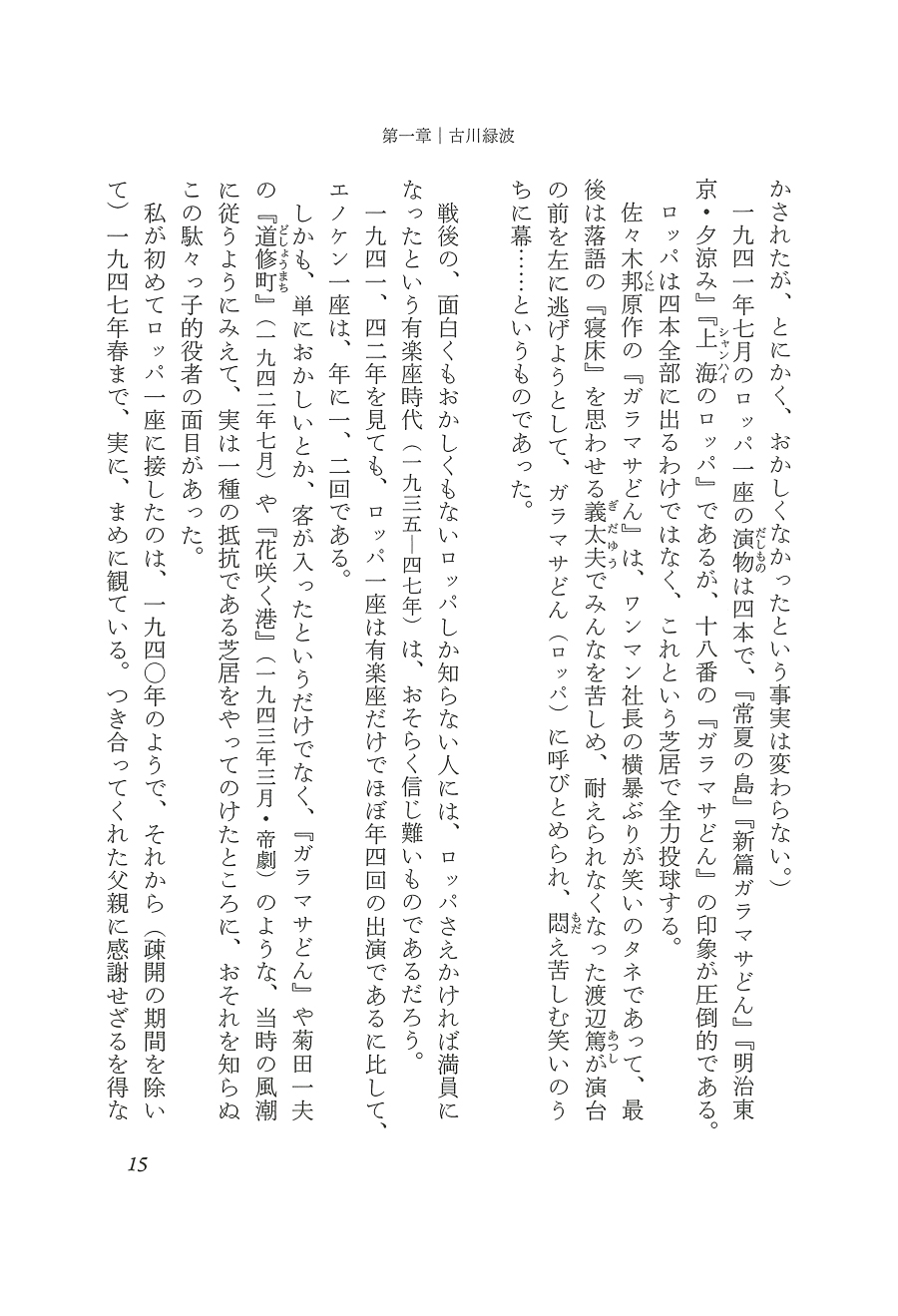はじめに
ずいぶん、長いあいだ、私は、興味本位ではない、日本の喜劇人についてのまとまった文章を書きたいと願っていた。
その理由は、非常に単純で、私は〈おかしい〉ものなら、舞台、映画、テレビを問わず、貪婪に観てきたし、いまでも、そういう気持を持ちつづけているつもりだからだ。
だが、私には、ほどを知らないところがあって、喜劇的な空間とか映像だけでは物足りずに、それらを創り出している人々――つまり喜劇人たちの素顔を見たい、いや、できれば彼らの生理のようなものをじかに掴んでみたい、という欲望にとりつかれてしまった。
二十代の半ばまで、私は、客席の片隅の観客として、彼らを凝視していた。それ以後――この本でいえば、クレイジー・キャッツや渥美清以後の人たちは、なんらかの形で、素顔を観察しているといい得るであろう。
小学生のころに見た古川緑波にはじまるこの本は、私の、多くの喜劇役者との出逢いの記録であり、証言といってもいい。
それは、より具体的にいえば、喜劇人と呼ばれる人々の個性についての考察である。個性というのは、生れ、育ち、キャリア、発想、芸風、笑わせるテクニック、世渡りの技術、自己演出の才能までを含んだ意味をもっているのだが、各人ごとに、具体的な記述をつみ重ねてゆけば、おのずから、昭和の――主として一九四五(昭和二十)年以降だが――喜劇の歴史にもなるのではないか、と考えたわけである。
私は、クロニクル風の喜劇史を書くことを、しばしば人にすすめられ、資料の提供まで申し出られても、気がすすまなかった。要するに、私は、自分の眼で見たものしか信じられぬたちなのである。自分が見て確かめてきた事実を、ぽつり、ぽつりと記していって、それでいいではないか、という気持がなかったら、とうてい筆をとることはできなかったと思う。
洋書の専門店にゆくと、バスター・キートン、ローレル&ハーディ、マルクス兄弟らの研究書、または、さまざまな形での喜劇史、喜劇人史の本が、山のようにある。グラウチョ・マルクスの書簡集さえ、私は持っている。
わが国で、この種の本は、一九五八(昭和三十三)年に出て絶版になっている旗一兵氏の『喜劇人回り舞台』しかない。この本は、批評的な視点はまったく欠除しているが、資料としては好著といってよい。
明治末年の曾我廼家五郎・十郎の旗揚げに始まり、昭和三十年前後の森繁久彌に至るまでのあらましは、この本で足りる。私は、一部分、重複しながらも、この本のあとつぎをするような気持があったし、方法はまったくちがうとはいえ、扱った時代は、結局、この本につづいている。
さて、昭和の喜劇人にもっとも大きな影響をもったのは昭和初期のエノケン(榎本健一)であり、昭和三十年ごろの森繁久彌である。
さいわい、私は緑波とエノケンを見ているので、私の喜劇人史はそこから始まることになる。(皮肉なことに、私が少年時代に憧れていた緑波は、晩年のやせた姿を試写室で目撃しただけであり、軽視していたエノケンにはじっくり話をきくことができた。)
私が〈喜劇人〉の上に〈日本の〉と冠したのは、ゆえあってのことである。そのことは、読者が読みすすむにつれて明らかになるはずであるが、ここで伏線を張っておけば、喜劇を〈人情喜劇〉と見るか〈ナンセンス喜劇〉と見るかをめぐって行われた、五郎と十郎の対立は、そのまま、昭和の喜劇人史をつらぬく赤い糸となっていると考えられるのだ。
ナンセンス喜劇を主として演じるコメディアン、人情喜劇を主として演じるコメディアン――大ざっぱに分けると、この二組になってしまうのだが、ナンセンス物をやる人がはなはだ古めかしい心情の持主であり、人情物をやる人の方がナンセンスの何たるかを理解していたりすることが多いので、これらを役柄で分類してしまうわけにもいかない。
ある喜劇作者が私に、
「この世界は、幕のうらのいやらしさを知らないで、客席で笑っているのが、もっとも、しあわせなのですね」
と、諦めに近い笑いを浮べて言った。
私は、心から、その言葉に同感したのだが、同時に、
「芸人への賛嘆は、その芸人(の人間性)への幻滅の果てにくるものではないだろうか」
とひそかに思わずにはいられなかった。
とにかく、毒気とアクの強い人たちの肖像画である。私なりに毒を薄めてはおくが、それでも、ふつうの人とつき合うつもりだと、えらいことになる。そのつもりで読んでいただきたい。
第一章 古川緑波
丸の内喜劇の黄金時代
一九四一(昭和十六)年は、日米開戦の年である。
七月二日、国府(中華民国国民政府)は独・伊と断交し、同月十八日には第三次近衛内閣が成立、二十八日に日本軍は仏印に進駐した。
……この月、私は生れて初めて、舞台の喜劇によって、からだ中を電流が走るような感覚を味わう経験を持った。場所は有楽座。ロッパ一座の公演である。
〈実演〉を観るのは初めてではない。その前の年の十月に日劇で『エノケンの南進日本』を観ている。個々のギャグは、今でも憶えているが、私はさほど笑えなかった。むしろ、エノケンは低俗であるという当時の世評に同感しただけであった。(このときの舞台が凄まじい検閲にあって、自分は警視庁にやけっぱちで出頭した、と、のちにエノケン本人の口からきかされたが、とにかく、おかしくなかったという事実は変わらない。)
一九四一年七月のロッパ一座の演物は四本で、『常夏の島』『新篇ガラマサどん』『明治東京・夕涼み』『上海のロッパ』であるが、十八番の『ガラマサどん』の印象が圧倒的である。
ロッパは四本全部に出るわけではなく、これという芝居で全力投球する。
佐々木邦原作の『ガラマサどん』は、ワンマン社長の横暴ぶりが笑いのタネであって、最後は落語の『寝床』を思わせる義太夫でみんなを苦しめ、耐えられなくなった渡辺篤が演台の前を左に逃げようとして、ガラマサどん(ロッパ)に呼びとめられ、悶え苦しむ笑いのうちに幕……というものであった。
戦後の、面白くもおかしくもないロッパしか知らない人には、ロッパさえかければ満員になったという有楽座時代(一九三五―四七年)は、おそらく信じ難いものであるだろう。
一九四一、四二年を見ても、ロッパ一座は有楽座だけでほぼ年四回の出演であるに比して、エノケン一座は、年に一、二回である。
しかも、単におかしいとか、客が入ったというだけでなく、『ガラマサどん』や菊田一夫の『道修町』(一九四二年七月)や『花咲く港』(一九四三年三月・帝劇)のような、当時の風潮に従うようにみえて、実は一種の抵抗である芝居をやってのけたところに、おそれを知らぬこの駄々っ子的役者の面目があった。
私が初めてロッパ一座に接したのは、一九四〇年のようで、それから(疎開の期間を除いて)一九四七年春まで、実に、まめに観ている。つき合ってくれた父親に感謝せざるを得ない。
この肥って、身動きの不自由な人物のどこが面白かったのか、いま説明するのは至難のわざである。(ロッパに限らず、舞台のおかしさは、すべて、そうなのだが……。)
とにかく、天性の芸人といっていいエノケンと互角で張り合ったばかりか、舞台ではそれを抜いたフシギな人物については、やはり、その経歴をみる必要がある。
彼は一九〇三(明治三十六)年に、加藤照麿男爵の六男として生れ、長男以外は養子にやるという父の方針に従って、古川家に入籍した。四男にあたる兄は、戦前では珍しい本格探偵小説『殺人鬼』の作者として知られた浜尾四郎である。
十六歳のときから「キネマ旬報」に投稿していて、十八歳(早稲田第一高等学院)で「キネマ旬報」編集同人になったというのは、早熟の才であろう。
翌年、『愛の導き』という映画に、のちの監督山本嘉次郎といっしょに出演している。
それからもずっと映画評を書き、文藝春秋社の「映画時代」の編集に当る(一九二六年)かたわら、徳川夢声らの「ナヤマシ会」の第一回で〈声帯模写〉(ただの声色ではないぞというロッパの造語)を公衆に披露している。
一九三〇(昭和五)年、ロッパは「映画時代」を独力で経営しようとして大欠損、翌年、東京日日新聞の嘱託になり、一年間、映画とレビュー評を書く。
このようなジャーナリストとしての経験は、ロッパにとってかなり本質的なものとなったのではないかと思われる。ロッパの成功は、そのジャーナリスティックな感覚に負うところが大であり、批評家としてのすぐれた資質は死ぬまで変らなかった。
ロッパは、一九五三年に『劇書ノート』という、演劇に関する書物の批評を集めた文集を出版しているが、たとえば、安藤鶴夫の『随筆舞台帖』を評して、
「面白く読んだ。然し、何となく総体に、一流の劇評を読んでゐるやうな気がしなかつた。……」
と鋭いところを見せている。つまり、安藤鶴夫を劇評家ではなく、エッセイストとして認めているわけである。


「ロッパぐらゐ〈口〉で芝居をしてゐる者はゐない。……ロッパは、この口千両に引き代へて、その他の手、足、身体全体は口程には彼のいひなりになつてゐず、特に下半身から足にかけては寧ろ甚だ大根役者である」
という安藤の評に対しては、
「この位ピッタリ言ひ当てられては一言も無い」
と、ロッパは記している。こうなると、どっちが批評家だか、わからない。
これは一例だが、私は、ロッパという人は大ジャーナリストの器であったと考えている。あとは余技で終るかも知れなかったのである。
だが、この批評家時代、すでに三十に近いロッパに大きな転機がきた。
菊池寛と小林一三のすすめで喜劇役者で立つ決意をしたことである。
本格的主演は宝塚中劇場のヴァラエティ『世界のメロディ』で、小林一三にギャラをきかれて、「千両役者だから千円貰う」と答えたのは本当らしい。(当時、千円というのは破格のギャラであった。)
それからオリエンタル映画『浪子』(水谷八重子主演)で邦画初のジャズソング「モン・パパ」をうたい、松竹系劇場に立てつづけに出たが、同じ松竹系のエノケン、ターキー(水の江瀧子)のほうに客をとられ、惨敗した。
松竹はエノケンの人気独走(とそれに伴う彼の発言力の増大)をおそれて、対抗劇団を傘下の常盤興行に作らせる策を立てた。夢声、ロッパ、渡辺篤、大辻司郎、山野一郎らによる〈笑の王国〉がそれであり、ロッパはこのときからエノケンの好敵手となるべく運命づけられていたといっていい。一九三三年四月が旗揚げで、八月にサトウ・ハチローと菊田一夫が文芸部に入っている。
〈笑の王国〉は成功した。が、これは、いわば、混成部隊であり、ロッパが完全に成功を手にしたのは松竹から東宝に転じ、一九三五年七月、有楽座での〈東宝ヴァラエティ〉(『ガラマサどん』『カルメン』『歌ふ弥次喜多東海道小唄道中』)においてであった。
ロッパの〈声帯模写〉がいかに達者だったかは、夢声が「いずれも絶品」と評しているのでわかろうが、一九三二年八月八日に夢声が酒と睡眠薬の飲みすぎで倒れたとき、ロッパは夢声がやるべき四十分間のNHKの放送を夢声の声色で埋めて、事故を聴取者に気づかせなかったという、信じがたい事実がある。
一九三五年には、七月、十月と有楽座に出て、十二月の公演では早くも一座を組んでいる。こんなスピード出世ぶりは空前であろう。
「……器用は器用でも雑誌記者上りであるから、いかにも危つかしい気がして、『うまく行くかしら』と心配であつた。……成功があまり容易で、花々しかつたのに私はびつくりした。あんなに早くエラくならないで、座頭になるまでにもう少し苦労をしておいた方が、却つて後年の緑波君のためになつたと思ふ」(谷崎潤一郎・一九六一年)
かつて私は、三十近くなった青島幸男がタレントとして売り出したとき、その器用さに舌を巻いたことがあり、旦那芸の魅力と不安定さからロッパを想起したことがある。スケールはちがうが、一脈通ずるものがあると思う。(やることなすこと、アタってしまう点も似ている。)
丸の内に進出したロッパ一座は、翌一九三六年十月に作者として菊田一夫を迎え、三七年には、女房役となる渡辺篤を、若手として森繁久彌、山茶花究を入れている。菊田、渡辺というのは最強力の布陣であった。


皮肉なことに、ロッパに半年遅れて、エノケンも(一九三六年二月)有楽座に進出した。だが、間もなく、もっとも信頼していた座付作者、菊谷栄の戦死(三七年十一月)によって、エノケンは大きな打撃を受ける。丸の内のエノケンは、子供心にも冴えなくみえた。
谷崎潤一郎は、こう書いている。
「『一ぺんエノケン君と一緒に出てみる気はないですか』
と、私が云ふと、
『これはどつちかゞ完全にペシャつてからでないと、絶対にそんなことはあり得ませんな』
緑波君はさう云つて、エノケン何するものぞと云ふ概を示した。当時はよほどエノケン君に敵意を燃やしてゐたらしかつた」
こういうことはオトナゲなく見えるが、役者の場合、むしろ、プラスに作用することがある。戦時中のロッパ劇のあの張りは、一つは当局の弾圧、一つはエノケンへの対抗意識からであったような気がしてならない。
山野一郎の『人情映画ばか』(一九六〇年・日本週報社)のなかには、浅草時代のロッパとエノケンの立場を示す典型的なエピソードが描かれている。
ロッパと山野一郎が常盤座に出ていたころ、めしを食いにゆくと、先客に柳田貞一(エノケンの師匠)がいて、ロッパを侮辱、ロッパは山野に解決をつけてこいと命じた。
結局、エノケンが、料亭にロッパ、山野を迎え、柳田を加えて、挨拶、酒という段どりになった。
やがて、ロッパが手洗いに立つ。戻ってくると、三人、大笑いなので、「何で笑っていたのか」とロッパがきいた。(以下、山野の文章より引用する。)
「……と、エノケンが、かたわらから、
――ロッパさん、君、そうヒガムなよ。
と、言った。
――ヒガム? ぼくは少年のように、ものを知ろうとしているんだ。
――それが、ヒガミだよ。
――もう一度言ってみろ。
――ソレガ、ヒガミだ。
二三応酬、エノケンは目をムイタ。
――わからねえ、カンプラチンキだ。
ビリビリと着ているワイシャツを破り、まえにあったコップを、ガリガリと噛んだ。
(中略)
私は夢中で意見をすると、案外、ロッパはおとなしく、
――では、おれが謝まろう。
――いや、べつに、仲直りさえしてくれたらいい。
下のエノケン(註=エノケンは階下に抱えおろされている)もほぼ同様の意見、また四人二階へ顔がそろった。
――いや、おれがあやまる。
――いや、おれがわびよう。
両方で謝罪の先陣争い、では、ふたりいっしょにあやまろう、と、向かい合ってロッパ、エノケン両手をついて、頭を下げたが、ロッパが先に顔をあげたので、エノケンの頭へ、ロッパのアゴがぶつかった。また、きたかと、エノケンはカンカン、さっと、拳闘の身構え。
――ちがう、ちがう、おれの頤だ。
これで四人は大笑い、あらためて仲直りの飲み直し。両者、晴れやかに、やっと気分が落ち着いて、芸談に花が咲いて快気炎、ロッパがエノケンに、こう言った。
――ケンちゃん、おおいにやろう。喜劇といえばエノケン、ロッパだ。いま、日本で一番エライのは、君とぼくだ。天皇陛下はべつだぜ。ネエ、おれ達二人が一番エライ人間なんだ!」
やや誇張された書き方とはいえ、二大喜劇人の軒昂たる意気がよく出ていると思う。
浅草にして、これである。丸の内でインテリ層をつかんだロッパの自信たるや思うべし。
ここでロッパ劇について、もう少しくわしくみてみる。
マック・セネット映画やチャップリンの影響で、全員がドタンバタンと動く風潮の中で、ロッパは動かないのである。また、動こうとしても、動きの基礎がないから、動けないのであろう。
「なるべくワキの腕達者に動いてもらって、こっちは座芸のクチ芸と願いたい」
と言っていたと、旗一兵の『喜劇人回り舞台』にあるが、私の観た範囲でも、スッテンコロリンを派手にやるのは、もっぱら渡辺篤であり、動きの笑いの決ったところで、ロッパはひとこと呟いて、横から笑いをとる。この〈最後に笑いをさらう〉やり方は、一座の若手だった、のちの森繁に継承されている。
ロッパの才能はむしろ企画面に発揮されていた。
たとえば、一九四二年一月の『四十七分忠臣蔵』であるが、一堺漁人(曾我廼家五郎)の原作をロッパが潤色して、『忠臣蔵』全景を四十七分でやるという、思いきったアイデアである。
花道に立った由良之助(ロッパ)が城に別れを告げる件りでは、これ以上、うしろにさがれないから、城のほうを舞台の奥へ遠ざけろ、と作者に文句をいう。これは演出もロッパで、戦時下に芝居の上演時間が短縮されたのを逆手にとったアチャラカであった。
同年七月の『ススメ・フクチャン』では、人気子役中村メイコをフクチャンに起用、同時上演の『道修町』では人気最高の轟夕起子を特出させていた。
四三年一月の『交換船』は、日米非戦闘員の交換という現実の事件を直ちにとりあげ、それでは陰気すぎるので、『ロッパの猿飛佐助』というナンセンスものをとりに据えて気分を変える。
『交換船』では、米国側に抑留された渡辺篤扮する無知な男が名演であった。日本軍によるプリンス・オブ・ウエールズとレパルスの撃沈のニュースをきかされて、
「へえ、プリンス・オブ・レパルスってのをやっつけたんですかい」
などという男で、この男は日本の船に乗りうつる直前に死んでしまう。おかしさではロッパを圧倒していた渡辺篤の味を今に伝えるのは、意外に黒澤明の映画である。『生きる』で志村喬の主人公にガンの症状を伝えるブキミな男とか、『どん底』『どですかでん』で、渡辺は往年の名演技の匂いをかすかに残している。
企画・脚色・演出のほかに、ロッパの功績は、いまでいうミュージカルを、毎月、必ず一本は入れていたことである。
一九三五年の第一回公演で、すでに徳山璉と組んで『歌ふ弥次喜多』を演じているのでわかるとおり、ロッパはこの方面に抜群の才[註1]があった。生れつき声が良かったのである。『唄えば天国』や『ちょんまげ分隊長』のテーマソングなど、私はいまだに歌えるくらいだから、〈劇場を出るとき、観客がテーマ曲を口ずさむ〉という、ミュージカル本来の在り方であったと思う。(同じ菊田一夫作とはいえ、戦後の自称・東宝ミュージカルスは、これからはるかに後退した代物で、問題にならない。)
このようにロッパという存在は、およそ規格外れであり、出来合いの物差でははかれぬところがある。
だが、役者としての評価も、どうしても出てくるわけで、これは、前記の彼の芝居のスタイルと、からんでいるわけである。
座長芝居――というコトバがあるが、ロッパのは、それどころではない。〈殿様芝居〉である。
もともと生れが良くて、順調に出世して、しかも初めから座長である。急にエラくなってイバる奴を〈出来上る〉というが、ロッパは生れながらにして〈出来上〉っていた。いわゆる三枚目特有のコンプレックスがないのである。
弱味はただ一つ、喜劇人としての〈自立性〉のなさである。
「オリジンの強いエノケンに対抗するため、自分は企画の新しさと広さと、まわりの腕達者を存分に活躍させることで客をつかんできた。いうなれば今の天外のやり方をしてきたんだ」
とロッパは、晩年、旗一兵に語ったというが、舘直志の名で台本を書き、アイデアにすぐれ、藤山寛美という才能を育てた渋谷天外はロッパに似ているところが確かにあろう。
右のようなロッパが爆発的人気を得たのは、彼の個性が時代の風に合ったからである。どんなに才能、実力があっても、この〈風に合〉わないと、どうしようもない。
「彼は非常に我がままで、一座をひきいる場合にも暴君であつた。それがまた彼の特色でもあり、味でもあつた。病気のためやせてきた時、ロッパがロッパらしくなくなり、妙におとなしくなり、人気まで下向きになつてしまつた」(徳川夢声)
波に乗っていたとき、ロッパの姿には、豪快なユーモアと、しかもふしぎなペーソスがあった。
戦争の進行によってドタバタが禁じられても、もともと動かぬ彼は困ることがなかった。エノケンにいわせると、菊田一夫の芝居は〈新劇と新派の中間の味〉だそうだが、ロッパほど、この〈味〉に合う人はいなかった。
映画においても、この堂々たるペーソスを生かして、『家光と彦左』『男の花道』(いずれも一九四一年、マキノ正博=のちの雅弘=監督)の二つの秀作を生んでいる。ロッパの代表的な仕事が、戦時中になしとげられているのは、彼の〈殿様的個性〉の強さが、外部からの強風に耐えた証拠である。(ほかの演劇人がどのような時局迎合をしていたか、興味のある方は、しらべてみるといい。)
むろん、ロッパとて、迎合はあり、弾圧も受けたろう。とにかく、彼は戦争が終ったとき、ある週刊誌で、それまでの弾圧者に対して、活字で啖呵を切った。それをしておかしくない数少ない役者の一人であった。
註1 ロッパの歌は各種出ていると思うが、「古川ロッパ傑作集」(Neach Records)は悪くない。
戦争が終ったとき、それまで左、右と慌しく動いてきた前進座はレジスタンス劇『ツーロン港』をいち早く(一九四五年十一月―十二月)上演している。
一方、インフレと人気下降で、ロッパもエノケンも一座の維持が不可能になっていた。戦時中、あれほど求められていた笑いは、いまや巷に氾濫している。わざわざ有楽座や日劇に出かける必要はない!
自由を得たとたん、ロッパもエノケンも張りを失ったのは皮肉である。
私個人を考えても、チャップリンを含むアメリカの喜劇映画を追いかけるのに忙しく、有楽座どころではなかった。
だが、切り札ともいうべき企画があった。浅草いらい十五年間、対立してきた両巨頭の共演である。
一九四七年、有楽座における四、五月の二カ月ぶっ通しの『弥次喜多道中膝栗毛』は、ロッパとエノケンの最後の輝きであった。とくに両者の演ずる劇中劇『どんどろ大師』は珍品だったが、全編を食いまくったのは、由比正雪の子孫、由比積雪に扮した渡辺篤で、カルメンの「闘牛士の唄」で名乗りをあげる場面は、抱腹絶倒ものであった。渡辺篤が浅草オペラ出身だと私が知ったのは、はるか後年である。
この『弥次喜多』は、作・演出、菊田一夫で、四月がたしか大井川までで、五月に京都入りした。いわゆる菊田アチャラカの集大成といっていい。こんなぜいたくなキャスティングの弥次喜多は、私の生涯に二度と観られるとは思えない。
この公演は大ヒット[註2]だったが、インフレのために、満員でも赤字になるらしい。数年のうちに、ロッパ、エノケンともに一座解散の羽目になった。
これ以後のロッパについて書くのは、むしろ苦痛である。
一九四七年から、映画、ラジオが生活の糧となったらしいが、帝劇オペラ『モルガンお雪』、NHK放送劇『さくらんぼ大将』(ともに一九五一年)など、もはや生活のための仕事でしかない。このころから健康も害していたらしい。
エノケン、柳家金語楼と喜劇人協会をつくったとき(一九五四年)、私はロッパは心身ともに弱っている、と思った。翌年九月の協会第二回公演をみた私は、
「ロッパは往年の活気を失っている。成功者のお道楽といった気分がつきまとうのは、そのためか?」
とノートに記している。
だが、経済的には、とても〈成功者〉などといったものではなかったらしい。それらについては厖大な日記(『古川ロッパ昭和日記』一九八七年・晶文社)が明らかにしてくれる。晩年のロッパについては、石田というCMエージェントの人が、ロッパ追悼の文集に寄せた短文が、その面影を伝えている。


「……昔、舞台でみた印象よりも大分年をとられ、瘠せてみえたけれど、お腹だけはでっぷりと出て貫禄がありました。二人の付き人がまるでお殿様に仕える小姓のように、うやうやしく世話をします。『エッヘン』というとサッとちり紙を、『チャ』というと間髪をいれず魔法ビンのお茶がさしだされるといった具合です。二十センチも厚みのある大きな紫の座ぶとんが印象的でした。
ところが、衣裳を脱いでいるロッパ氏のお腹のあたりからバサリと落ちたものがあります。よくみるとそれはお腹を太くみせるための小さな座ぶとんの腹巻でした。私はそのとたんキュッと胸に痛みがはしったのを想い出します。……」
一九五五年九月の協会第二回公演(日劇)は、三木のり平を売り出したことで記憶されるに足るが、五十歳のエノケンが『最後の伝令』で熱演したのにくらべ、一つ上のロッパは、いかにも大儀そうであった。糖尿病のせいであろう。
それが「いやいや出ているように見えることすらあった」(森岩雄)のは、こらえることを知らぬ気質のためであろうか。少なくとも、エノケンが死ぬまで持っていた芸人の根性を、ロッパは、とうに手離していたとおぼしい。
最後の舞台となった梅田コマ劇場の『お笑い忠臣蔵』(一九六〇年十二月)の舞台写真をみると、異常な瘠せ方に、ぞっとさせられる。
遺児の古川清氏の話によれば、完全に生計のための、苦痛に耐えての出演だったらしい。その顔には、死相が浮んでいるといっても、大げさではない。(ロッパの斜めうしろに、藤田まことの顔が見えるのも、時の流れを想わせる。)
ロッパの名が、死後、急速に忘れられたのは、おそらく、かつての横暴ぶりへの反動からであろう。それはそれで仕方がない。
だが、戦後の仕事の質でいえば、故エノケンも大差はない。どちらも、戦後は、名前だけである。コメディアンは人を笑わせられなくなったとき、生命を失ったに等しいといえよう。
だからといって、ロッパのかつてのすぐれた仕事の数々が忘れられていいというものではないし、少なくとも、小学三年生のひとりの少年を喜劇狂にしてしまったという事実は動かしがたい。
古川緑波(本名・郁郎)――一九六一(昭和三十六)年一月二日、順天堂病院に入院、心臓病に肺炎を併発、十六日死去。享年五十七。
註2 このヒットが、ロッパ・エノケンの初共演映画『新馬鹿時代』前後編(一九四七年十月・山本嘉次郎)を生んだ。これもヒットし、三船敏郎が闇屋の親分役でデビューしている。
写真提供:古川清、新潮社写真部