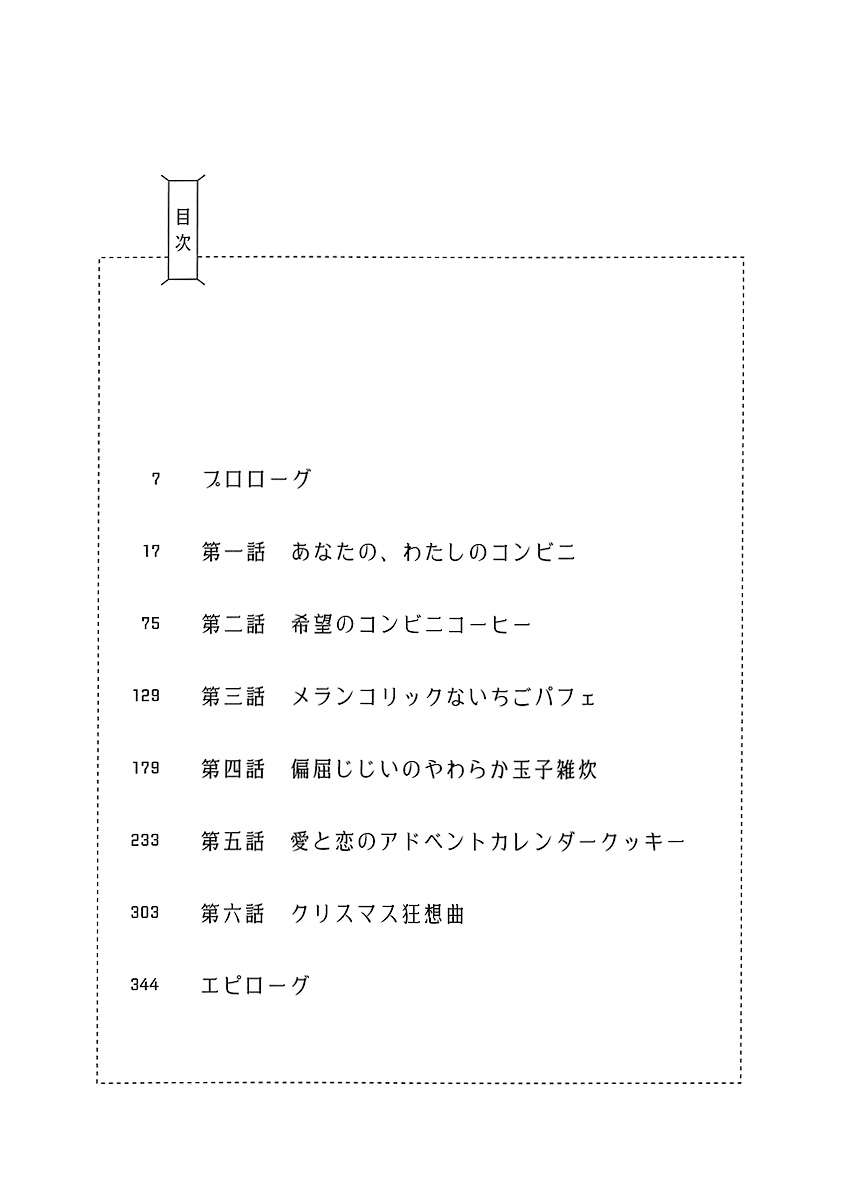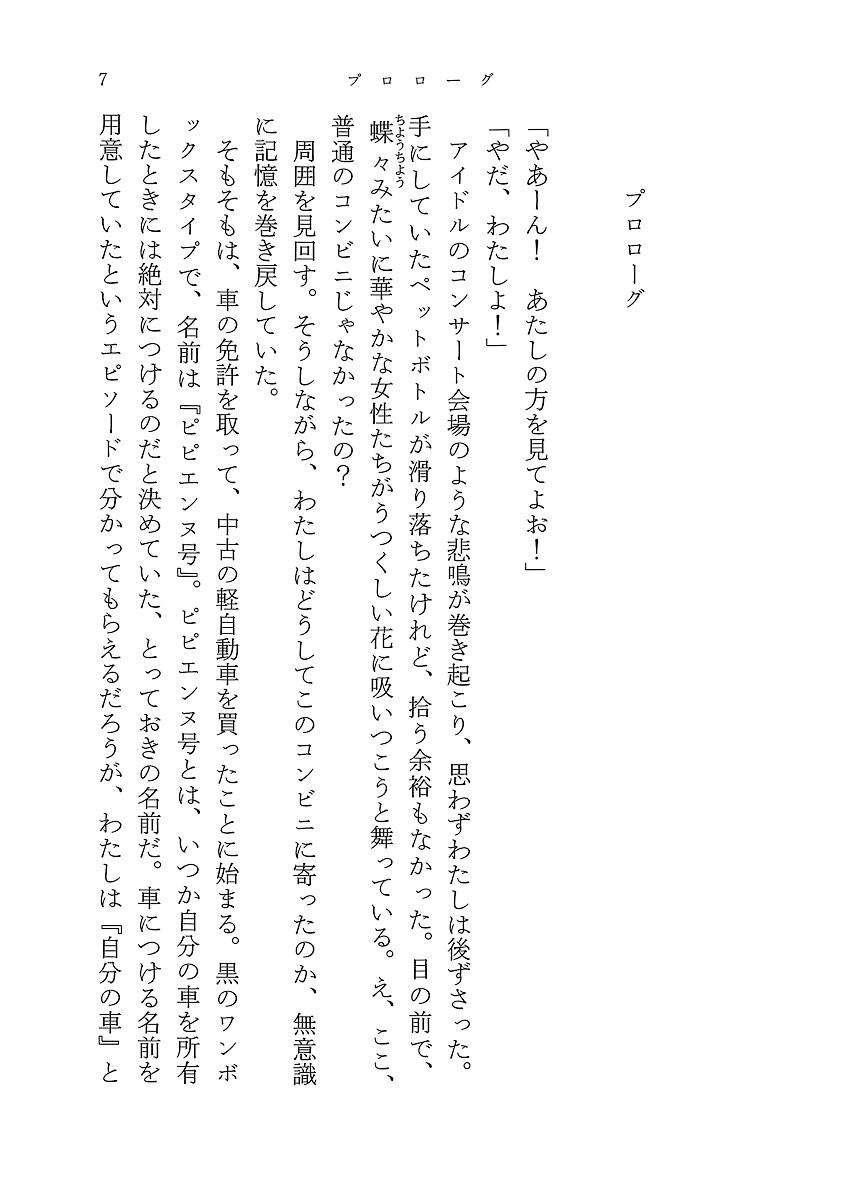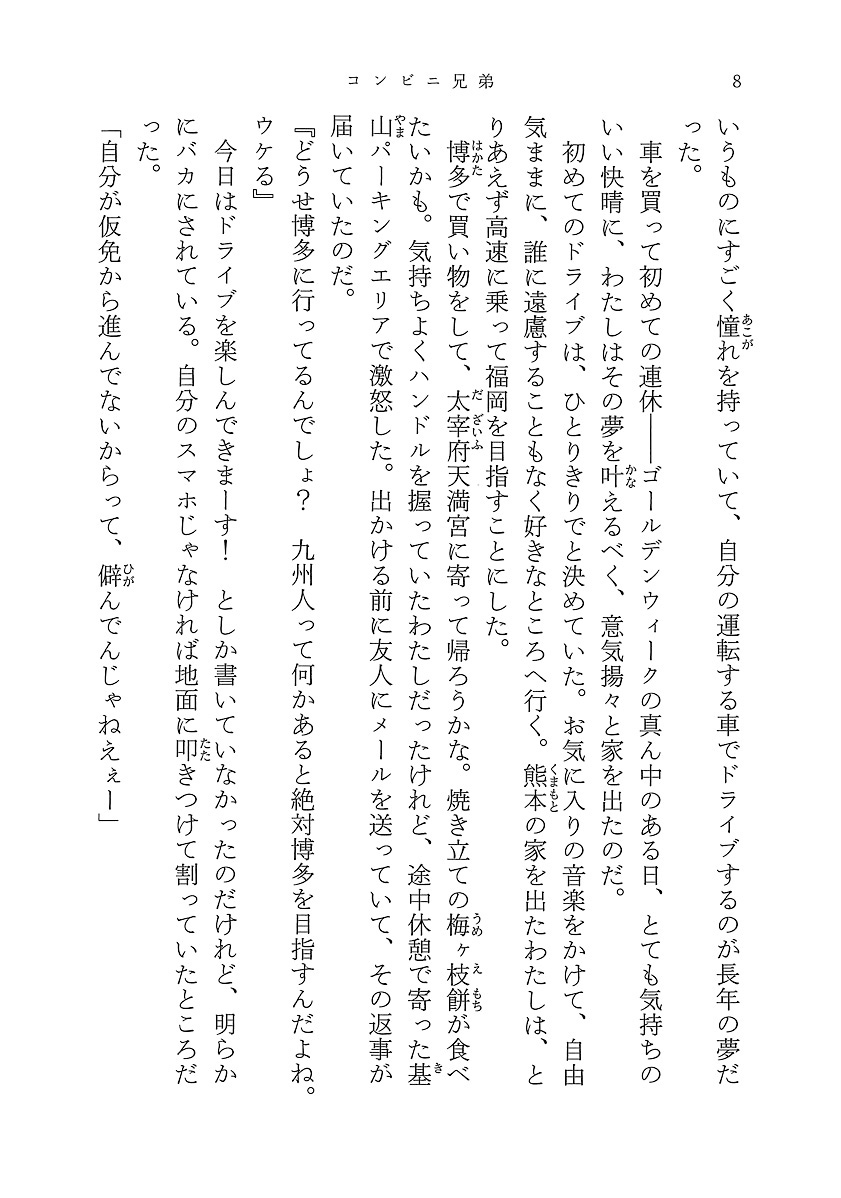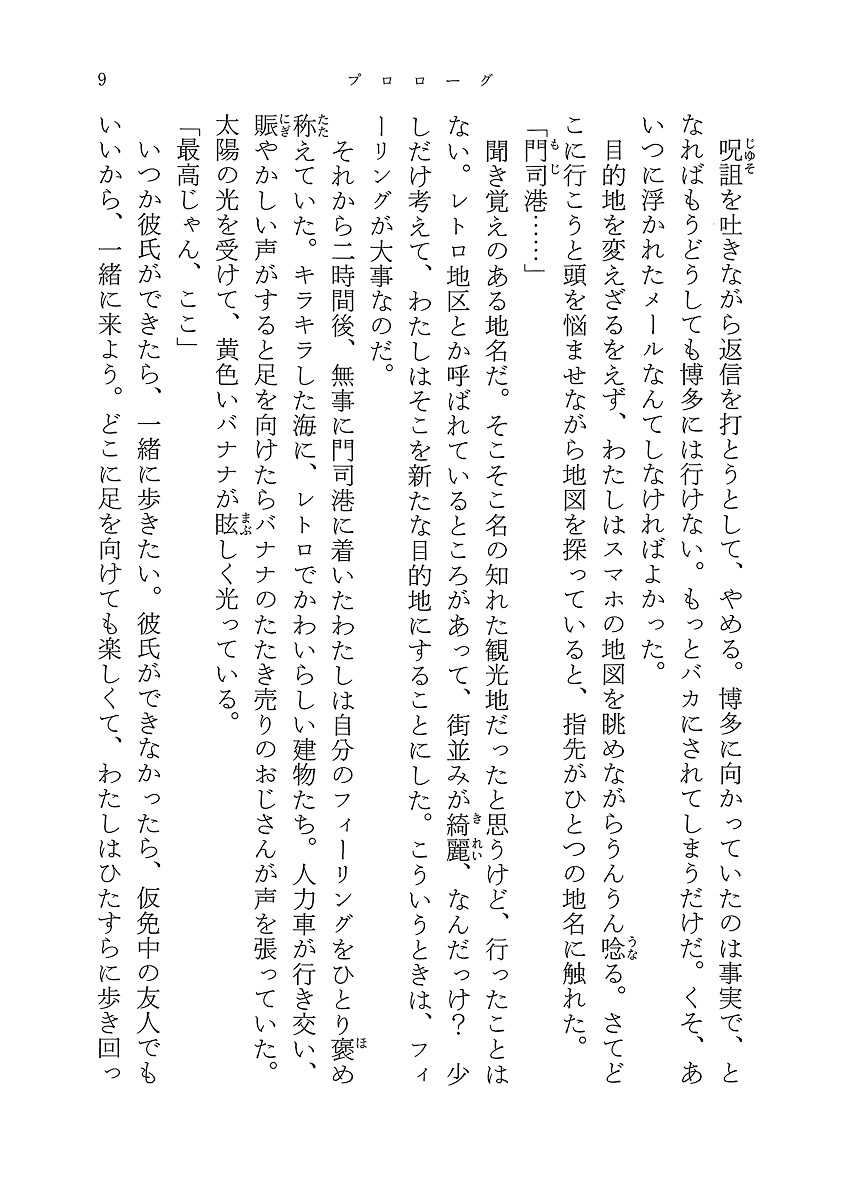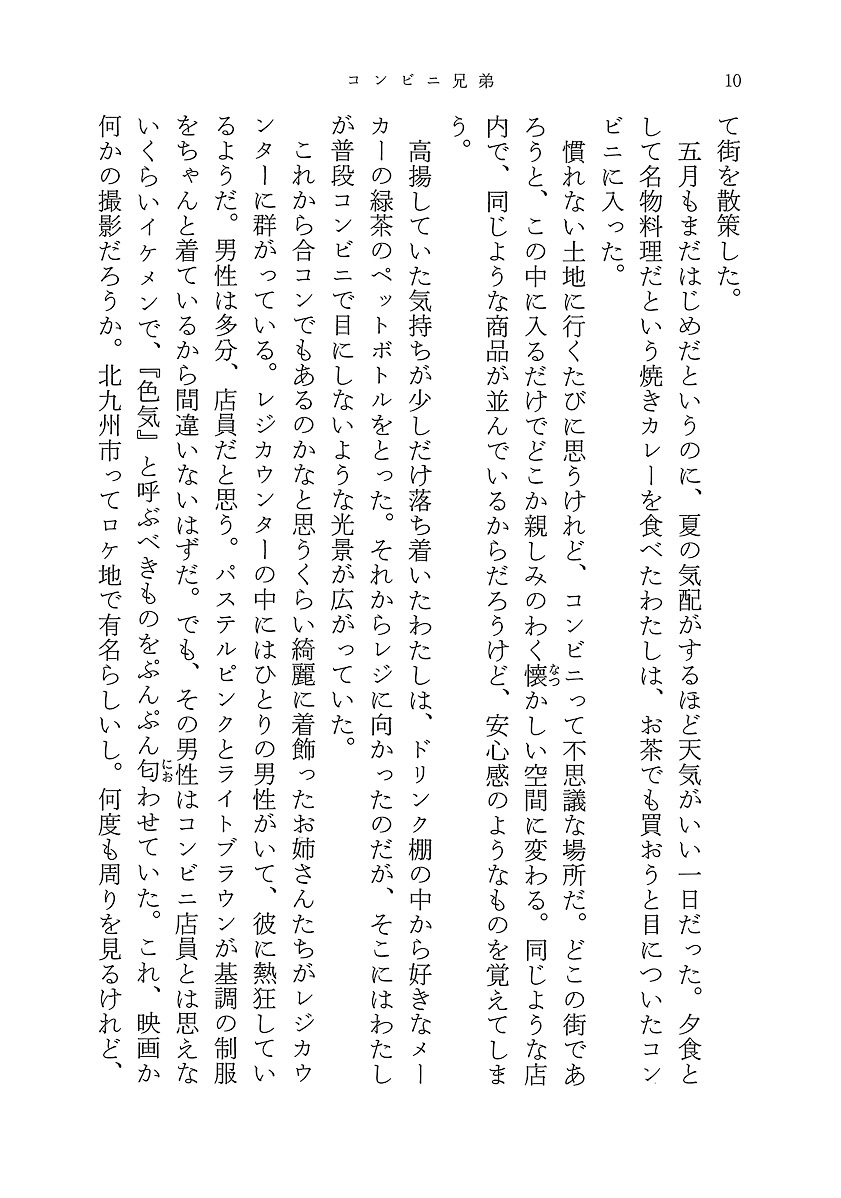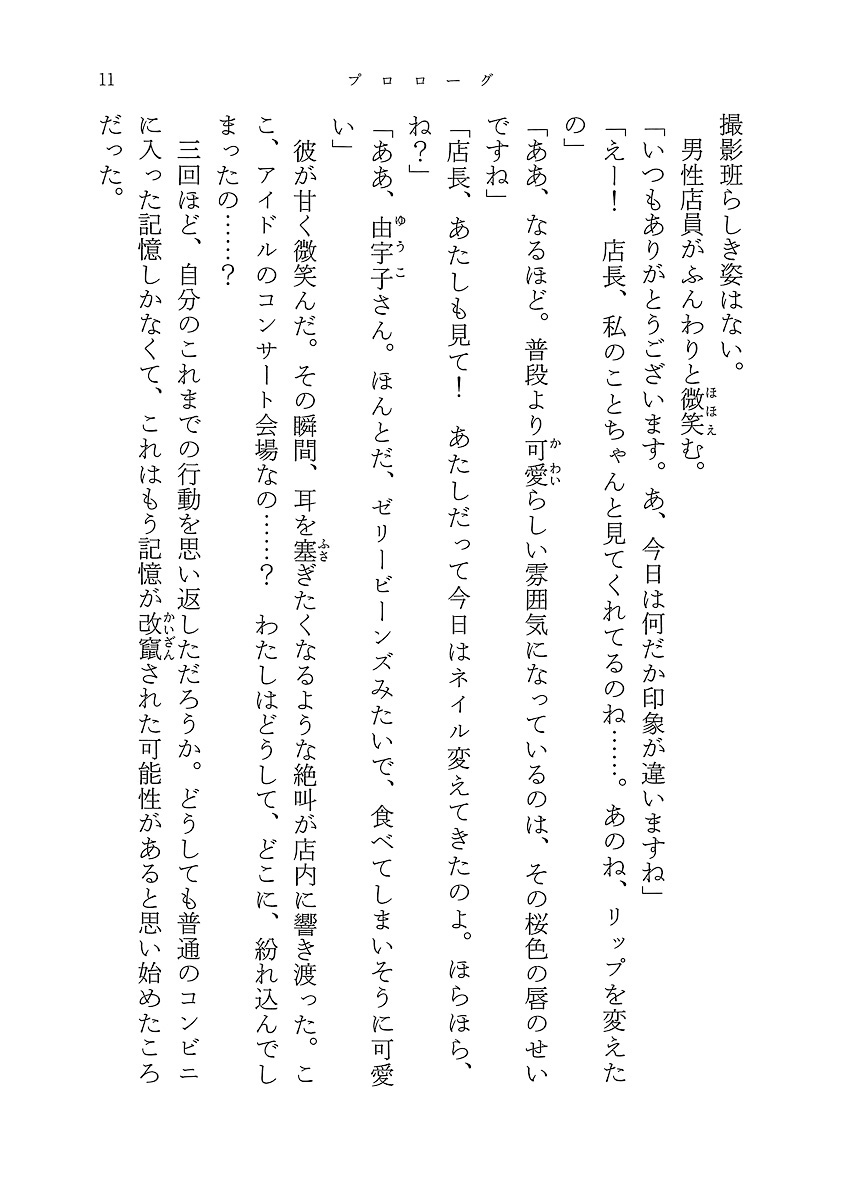プロローグ
「やあーん! あたしの方を見てよお!」
「やだ、わたしよ!」
アイドルのコンサート会場のような悲鳴が巻き起こり、思わずわたしは後ずさった。手にしていたペットボトルが滑り落ちたけれど、拾う余裕もなかった。目の前で、
周囲を見回す。そうしながら、わたしはどうしてこのコンビニに寄ったのか、無意識に記憶を巻き戻していた。
そもそもは、車の免許を取って、中古の軽自動車を買ったことに始まる。黒のワンボックスタイプで、名前は『ピピエンヌ号』。ピピエンヌ号とは、いつか自分の車を所有したときには絶対につけるのだと決めていた、とっておきの名前だ。車につける名前を用意していたというエピソードで分かってもらえるだろうが、わたしは『自分の車』というものにすごく
車を買って初めての連休――ゴールデンウィークの真ん中のある日、とても気持ちのいい快晴に、わたしはその夢を
初めてのドライブは、ひとりきりでと決めていた。お気に入りの音楽をかけて、自由気ままに、誰に遠慮することもなく好きなところへ行く。
『どうせ博多に行ってるんでしょ? 九州人って何かあると絶対博多を目指すんだよね。ウケる』
今日はドライブを楽しんできまーす! としか書いていなかったのだけれど、明らかにバカにされている。自分のスマホじゃなければ地面に
「自分が仮免から進んでないからって、
目的地を変えざるをえず、わたしはスマホの地図を眺めながらうんうん
「
聞き覚えのある地名だ。そこそこ名の知れた観光地だったと思うけど、行ったことはない。レトロ地区とか呼ばれているところがあって、街並みが
それから二時間後、無事に門司港に着いたわたしは自分のフィーリングをひとり
「最高じゃん、ここ」
いつか彼氏ができたら、一緒に歩きたい。彼氏ができなかったら、仮免中の友人でもいいから、一緒に来よう。どこに足を向けても楽しくて、わたしはひたすらに歩き回って街を散策した。
五月もまだはじめだというのに、夏の気配がするほど天気がいい一日だった。夕食として名物料理だという焼きカレーを食べたわたしは、お茶でも買おうと目についたコンビニに入った。
慣れない土地に行くたびに思うけれど、コンビニって不思議な場所だ。どこの街であろうと、この中に入るだけでどこか親しみのわく
高揚していた気持ちが少しだけ落ち着いたわたしは、ドリンク棚の中から好きなメーカーの緑茶のペットボトルをとった。それからレジに向かったのだが、そこにはわたしが普段コンビニで目にしないような光景が広がっていた。
これから合コンでもあるのかなと思うくらい綺麗に着飾ったお姉さんたちがレジカウンターに群がっている。レジカウンターの中にはひとりの男性がいて、彼に熱狂しているようだ。男性は多分、店員だと思う。パステルピンクとライトブラウンが基調の制服をちゃんと着ているから間違いないはずだ。でも、その男性はコンビニ店員とは思えないくらいイケメンで、『色気』と呼ぶべきものをぷんぷん
男性店員がふんわりと
「いつもありがとうございます。あ、今日は何だか印象が違いますね」
「えー! 店長、私のことちゃんと見てくれてるのね……。あのね、リップを変えたの」
「ああ、なるほど。普段より
「店長、あたしも見て! あたしだって今日はネイル変えてきたのよ。ほらほら、ね?」
「ああ、
彼が甘く微笑んだ。その瞬間、耳を
三回ほど、自分のこれまでの行動を思い返しただろうか。どうしても普通のコンビニに入った記憶しかなくて、これはもう記憶が
「あ、お客様、こちらのレジどうぞー」
気の抜けた声がして、はっと我に返った。宇宙人のアブダクトが終わってしまったのか。足元に転がったままだったペットボトルを拾い上げ、見ればもうひとつのレジにいた男性がわたしを見ていた。彼が、声をかけてきたのだろうか。わたしと年が変わらなそうだから、多分、大学生バイト。失礼だけど、顔は普通。ドラマで言うところのモブって感じだ。あれ、わたしは変な白昼夢でも見ていたのか。
どこか夢うつつな感じで大学生バイト――名札に
「いえ。撮影でもなんでもなくて、あれは当店の日常の光景です」
「え、日常……?」
廣瀬くんは小さく頷いて、わたしの手におつりを乗せた。わたしはテープを張ってもらったペットボトルを手に、もう一度隣の光景を見る。仲が良いと思われた女性たちが、険悪な雰囲気になっていた。ネイルが可愛いと言われた女性が、店長の口元に「食べてほしいな」と指先を持っていったのが
「ああ、
男性が困ったように言い、女性たちは笑顔を作ろうとする。相手より余裕を持って微笑もうとすればするほど、引き
もう少しここで観客として見ていたい気もするけれど、しかしそろそろ熊本に向かわなければ帰宅が真夜中になってしまう。後ろ髪を引かれる思いで廣瀬くんのいるレジカウンターを離れ、出入り口の自動ドアに向かう。
「ありがとうございました」
外に出たところで、背中に廣瀬くんのものではない声がかかって振り向く。あの男性店員が、わたしの方を見て微笑んでいた。背中の奥、皮膚と肉の内側に守られた神経を直接
「いってらっしゃいませ」
静かな、でも確かな声が離れたわたしの元まで届いたその時、わたしたちを分かつように自動ドアが閉まった。
駐車場の真ん中で、わたしは立ち尽くした。店内に戻るべきではないのか。今感じたものの正体を見極めなければいけないのではないのか。でも、入ってしまえばわたしは底なし沼に落ちてしまうような気がする。どうしたら、いいんだろう。
自動ドアが開いて、はっとする。もしかして、彼がわたしを追いかけてきたのではないだろうか。
「ほらほら、喧嘩するなら帰りなさい」
出てきたのは、筋肉マッチョなダルマみたいなおじいさんと、さっきの女性たちだった。おじいさんは白いタンクトップに真っ赤なオーバーオールという奇妙ないでたちで、異様な迫力がある。
「買うもの買ったら、帰りましょう。ね!」
大きな声でおじいさんは言い、そしてにたりと笑った。人ひとりくらい食べてしまいそうな
「か、帰ります!」
一体、このコンビニは何なんだ。イケメン店員でおびき寄せておいて、あんな
『いってらっしゃいませ』
あの笑顔にもう一度会いたい。あの笑顔の本質を知りたい。
これって恋かも。でもあのおじいさんに会うのはやだなあ……。いや、でもこれが恋なのか確認するべきでしょ。
門司港を猛然とダッシュしながら、わたしは降ってわいた恋心について、悩むのだった。
第一話 あなたの、わたしのコンビニ
とにかく、中尾光莉は充実している。
「あ、来月からラインナップが変わるんすね」
バイトの
「冷やし中華に、ざるそば。そっか、夏商品っすね」
「もうすぐ七月だからねえ。早いよね」
「オレ、テンダネスの冷やし中華がコンビニ界最強だと思ってるんすよ。バランスがめちゃくちゃいいんす。でも、量が上品すぎるんで二個は必須ですけど」
野宮は、九州共立大学の一年生だ。大学入学と同時にテンダネスでバイトを始めた。元レスリング部だという野宮の体は筋肉が膨れ上がっていて、大きめの制服を支給されているにも
九州共立大学のレスリング部は強豪だが、どうしてそこに入学しておいてレスリングを辞めたのか、本人は言わない。光莉もまた、わざわざ
「野宮くんなら、夏野菜焼肉
夏メニューの中でも、毎年若い男性に大人気の品だ。炭火で焼かれた牛肉と、色とりどりの夏野菜が目にも
「いや、それは別格っすよ。ああ、そうだ。テンダネスって飯も
「そりゃ、こだわってるからね。お弁当にスイーツ、食べ物は特に」
手元の画面の数字を迷いなくタッチしながら、光莉は答える。光莉がテンダネス
テンダネスは、九州だけで展開するコンビニチェーンだ。『ひとにやさしい、あなたにやさしい』をモットーとし、その人気は他のコンビニチェーンに劣らない。そして、北九州市門司区大坂町通りの中ほど、こがね村ビルの一階にテンダネス門司港こがね村店はある。レトロ建築で有名な門司港駅や旧門司三井
店内に、やさしいオルゴールのメロディが流れた。自動ドアが開閉する――来客の合図だ。ふたりが同時に顔を向けると、白いタンクトップに真っ赤なオーバーオールを着た老人が入って来るところだった。梅雨明け宣言までもう少しかかるはずだが、老人の格好は既に真夏である。顔の半分を
「ハローハロー。いつも
「こんにちは、
「ううーん。中国からツアーのお客さんが多いみたいだねえ。駅前を観光して、そのあとは関門連絡船で唐戸に向かうんだってさ」
「わしのことを、俳優か? だなんて
正平は自慢げに言うが、光莉はどちらかというと
「写真撮らせてくれってそりゃもう大人気で、観光マップもすっからかんさ。家に帰って、印刷せにゃならん」
げへへと悪役のように――本人は普通にしているだけなのだが――笑って、正平は「というわけで今日のパトロールはこれで終わりだ、すまん」と申し訳なさそうに言った。正平は自称門司港の観光大使で、そして地域の治安を守る自称頼れる用心棒なのだ。観光マップを配る傍らで、何度も店に立ち寄っては休憩している。
「こっちは気にしないでいいですよ、正平さん。今日は、店長お休みだし」
光莉が笑って言うと、「お、そうか」と正平は顔を明るくする。
「あいつがいないなら、この店も平和だな」
「そうそう、大丈夫です」
「なら、安心して帰る。じゃあ、またな」
正平は満足したように
「元気っすよねえ、正平さん」
しみじみと野宮が言い、光莉は頷く。どんな天気であっても一日たりとも休むことなく三輪車に乗っているせいか、正平は
またもやメロディが流れ、顔を向けると今度は
「こんにちは!
野宮が大きな声で言うと、浦田は顔を
「そうでかい声を出さんでも、聞こえとる。そんなに体力が有り余ってるなら、金稼ぎなぞせんと運動せんか」
杖先を野宮に向けての口調は厳しい。
「ほら、メシを食いに来たぞ。用意してくれ」
野宮は一瞬だけむっとしたように唇を
「はい。昼ごはん、すぐ用意しますね!」
野宮がすぐに弁当を取りにバックヤードの冷蔵庫に走り、その間に光莉は「隣で待っててください」と浦田に声をかけた。浦田は返事もせず、ドアで
レジカウンター内は、さほど広くない。弁当とお茶のペットボトルを持って戻ってきた野宮は大きな
「さて、これから忙しくなるな」
時計を見上げて、光莉は小さく
テンダネス門司港こがね村店では、『イエローフラッグランチ』というサービスを提供している。毎日テンダネスの特別日替わり弁当が食べられる定額制のもので、これが年配客を中心に好評を博している。日替わりなので飽きがこないことはもちろんなのだが、一番の大きな売りは『その日の体調を伝えられる』ことにある。
こがね村ビルの三階から最上階の八階までは、高齢者専用のマンションになっている。もとは、その住人向けのサービスだった。毎日の昼食作りの手間がなくなるし、テンダネスの横にある住民専用の談話室――いまはイートインスペースとして開放されている――で食事をすれば他の住民ともコミュニケーションが取れる。そして、弁当を受け取りに来ないことで万が一の事態を早急に察知することができる。そんな風にアピールしたのだった。じわじわと利用者が増え、いまでは浦田のように、マンション以外の近隣の方も利用してくれている。
「戻りました」
野宮が明るくない顔で戻って来た。浦田に何か言われたのだというのは想像に難くない。どうしたの、と光莉が訊く前に、「オレ、うざいっすか」とぼそりと言う。
「さっさと置いて行け。無駄な筋肉男が傍にいるとメシが
野宮は大きな体躯に反比例して、繊細で気弱な性格をしている。客の
「浦田さんは、誰にでも当たりがきついんだよ。だから、あんまり気にしないで」
「あんな言い方されて、それは難しいっすよ。だいたい、年寄りだからって、あんなに偉そうにしなくってもいいじゃないすか」
野宮がこぶしを握ると、上腕二頭筋がぐっと膨れた。
「こういう言い方好きじゃないっすけど、ああいうのを老が……」
「はいはい、ストップ」
野宮の言葉を止める。いまは幸い店内に客の姿はないけれど、安易に不満を口にする癖がついてはいけない。野宮は不服そうな顔をしたが、しかし口を閉じた。少しして、「すみません」と頭を下げる。
「言い過ぎました」
「気持ちはわかるけどね、でも、そういう言葉は飲み込んでようね」
にこりと笑うと、野宮がぎこちなく笑い返してきた。野宮のいいところは素直さだろう。
メロディが鳴り、派手な格好をした青年が入ってきた。それは徒歩五分のところにあるヘアサロンのスタッフだった。エナジードリンク二本とレタスサンドを手に取る。
青年が野宮の立っているカウンターに商品を置く。その手は遠目に見ても、痛々しくあかぎれていた。四月に入店したばかりの見習いのはずだから、いまの時期はひたすらシャンプーに取り組んでいるのだろうと光莉は思う。
「あと、唐揚げボックスひとつください」
「はい、唐揚げボックスですね」
野宮がてきぱきとレジを打つ。その隣で唐揚げボックスをフライヤー商品の棚から取り出しながら、光莉は思う。
ああー、唐揚げ、一個おまけしてあげたい!
年を取ったのか、若い子が頑張っている姿を見るとつい手を差し伸べたくなってしまうようになった。特にこの青年は顔立ちが
会計を済ませて店を出て行く薄い背中を見送っていたら、青年がぴたりと足を止めた。
「ああ、
イートインスペースの側から入ってきた男を認めて、青年がはしゃいだ声を上げる。入って来たのは、私服姿の志波
背が高く、モデルのようにすらりとした体躯。そのスタイルのせいか、白シャツとチノパン、サンダルというありがちな格好なのに、どこかお
「あれ、アユムくん。休憩かな?」
「はい! そうです!」
「志波さん、そろそろお店に来て下さいよ。あれから僕、シャンプー褒められるようになったのに全然来てくれないんだから」
「ああ、なかなか行けなくてごめんね。でも、アユムくんが頑張ってたのは、この手を見たら分かるよ」
志波がアユムの手を取った。あかぎれをやさしく指先で
「もうすっかり美容師の手だね。近々行くよ」
「はい。僕、楽しみにしてます。ずっと、待ってます」
熱っぽい目で、アユムが志波を見つめる。志波はその視線を当たり前のように受け止めて、「午後もお仕事頑張って」と白い歯を
一連の流れをじっと見守っていた光莉は、何とも言えないため息を
光莉は志波のことを、フェロ店長と呼んでいる。もちろん、フェロモン店長の略だ。志波は、フェロモンを泉の
志波は、
四年前、パートの面接のために事務室で志波と向かい合った光莉は、店を間違えたのだろうかと不安になった。目の前の男がコンビニエンスストアの店長だとは、どうしても思えなかったのだ。しかし話せば普通だし、業務内容におかしなところはない。脳に入って来る情報の整理がうまくいかなくて混乱したのを、よく覚えている。
結果、志波はごく普通の雇われ店長で、それ以上でもそれ以下でもなかった。あまりの色香にオーナーとわりない仲なのかとも勘ぐったけれど、このコンビニを含んだこがね村ビルのオーナーは七十を過ぎた愛妻家の男性であるので、その線はないだろう。志波もまた、ただのチャラチャラした男かと思えば、
光莉は志波に、どうしてコンビニの雇われ店長なんてしているんですか、と訊いたことがある。志波ならばもっと他にも――人心を
「お疲れさま。野宮くん、中尾さん」
アユムを見送った志波がゆっくりと振り返って微笑む。しかし、アユムと違って光莉と野宮の表情は変わらない。お疲れ様です、と普通に返した。この店で働くための絶対条件は、志波のフェロモンを『臭い』と言い切れることだ。
「店長、お休みなのに降りて来たんですか?」
光莉が訊く。志波は、オーナーの好意で四階の一室に部屋を借りている。職場が真下というのは通勤にはいいけれど、近すぎて嫌になりそうだなと光莉はいつも思う。
「そろそろランチタイムでしょ。みんなと混じろうかと思って」
志波が隣を指差す。え! と声を上げた野宮が、「店長、プライベートがないじゃないすか」と
「普段もしょっちゅう行ってるのに、なにも休みまで」
「イエローフラッグランチは、いまのところうちしか導入していないサービスだからさ。気になるんだよね」
「ええっと、誰でしたっけ。確か、ご意見番のイタコ? サセボ? の発案なんすよね」
「ニセコ。ニセコだよ」
イエローフラッグランチの発案は、テンダネスの創業者である
お客様の声を直接承ります、という触れ込みで、事実、届いた手紙は会長が
『黄色い旗運動』とは、外から確認しやすい軒先やベランダなどに毎日朝から夕方まで黄色い旗を掲げ、独り暮らしの住人が元気であることを周辺住民に知らせるというものだ。もし掲げられていない、仕舞われていないという場合は、気付いたひとが家を訪問して安否を確認する。
『もちろん旗を掲げることもいいのですが、独居老人の住まう家だと悪意のあるひとに知られてしまうリスクもあります。弁当を日々受取りに来る、などとすればそのリスクは減りますし、人づきあいを深められるメリットもあるように思います』
会長はこの意見をいたく気に入り、その実証実験をする店舗として白羽の矢が立ったのが、門司港こがね村店だった。会長の指示を受けた志波はすぐにマンション内全戸を回り、本部から示された最低契約数を優に超した数を取って来て企画を始めた。契約数は伸びるばかりで、大きな問題もない。年末には他店舗でも導入されることになっている。
ここまで軌道に乗せたのだからお役御免だと光莉は思うのだが、志波は暇さえあれば老人たちに混じって話相手を務めている。
「そのニセコってやつがご意見番とか呼ばれて会長にちやほやされてるのってムカつきませんか。店長の方がよっぽど頑張ってんのに」
野宮が腹立たしそうに言うが、志波はにこにこと笑う。
「そんなことないよ。それに、婦人会のみんながぼくと一緒に食べるのを楽しみにしてくれているから、無下にしたくないだけだよ」
志波の人気は、絶大だ。出勤するとしないとでは、売り上げが違うほどだ。それだけならいいのだけれどデメリットもあり、例えば志波目当てに来る客同士での
それを止めるのがさきほどの正平と、こがね村ビル婦人会――別称『志波三彦ファンクラブ』の面々なのだ。
そこにタイミングよく、「みっちゃーん」という華やいだ声と共に、イートインスペース側からファンクラブのメンバーが数名、なだれ込むように入ってきた。イートインスペースの奥には上階へ繋がる出入口があり、こがね村ビルの住民はそこから出入りするのだ。
「もう来てたのね、探したのよ。わたし、一緒にお昼を食べるの楽しみにしてたの」
「わたしね、いなりずしを作って来たの。みっちゃんは、お弁当買わなくっていいわよ」
「あら、私だってお
志波を取り囲む女性たちはみな、少女のように頬を染めている。そのひとりひとりに笑みを返し、志波は「隣に行きましょうか。ここだと、他のお客さまの迷惑になりますし」と言う。女性たちは「はぁい」と可愛らしく答えた。
「中尾さん、彼女たちのお弁当をお願いしていいかな」
「ええ、もちろん」
光莉はざっと女性たちの顔を確認して、チェックシートを手に取った。チェックを入れながら、隣室に移動する婦人たちの声に耳を傾ける。そろそろ、土用の
「さすが、フェロ店長」
この調子なら、今回も売り上げは上々そうだ。くふふ、と笑うと入店のメロディが鳴る。目だけ向けると、のそりと一人の男が入ってきた。
あ、なんでも野郎。光莉は心の中で思う。男は、この店の常連のひとりだ。伸び放題の髪に、正平のように顔の下半分を覆い尽くす髭。一張羅と思われる、ライトグリーンのツナギの背には、白抜きで『なんでも野郎』の文字。駐車場には、彼の愛車の白の軽トラック。荷台のアオリ部分は『不用品回収・お困りごとはなんでも野郎にお任せ!』と書かれている。荷台には古い冷蔵庫や腕の曲がったマネキンがしょっちゅう積まれていたりするので、廃品回収業者なのだろう。お困りごと、というのは不明だ。
男はいつも、店内の滞在時間が長い。ブックコーナーからドリンク棚、日用品の棚、とにかく店内全てを見て回る。最初こそ警戒したけれど、そういうのが好きなようだ。
「また来た。なんすかね、あの客」
そっと近づいてきた野宮が声を潜めて言う。男を
「正平さんも詳しくは知らないって言うし、どうにも
「へえ、それはすごい」
独特の観光マップを作り、門司港の最新情報を求めていつも走り回っている正平は、わしこそが門司港の情報屋だと豪語する。事実、正平に訊けば大抵のことは分かる。その正平が白旗を上げたというのか。
光莉がこの店に入店したときから、男は通って来ていた。これまでに何度か話しかける機会があったのだが、男は「ああ」「はい」「まあ」、と二文字以上の返答をしてくれなかった。もう辞めてしまった先輩パートは「極度の人見知り」ではないのかと推察していたが、そんなことでは廃品回収業などできないだろう。光莉は、どこか距離を置かれていると感じている。必要以上に
「あと、これけっこうヤバいことかもしれないんですけど」
野宮が一段と声を小さくして言う。
「実はオレ、門司のジョイフルであいつが店長とふたりきりで会ってるところを見かけたんですよ」
「まじで!」
思わず大きな声が出て、
「なんか小包? みたいなものを店長が受け取ってました。あいつ、店長に
光莉の口から「ほええ」と意味のない声が漏れる。アユムの件といい、今日は驚きが多すぎる。ぽかんとしてしまっていた光莉だったが、はっと我に返った。
「いかんいかん。とりあえず、バックヤードに行って来るね。ここはよろしく」
光莉が人数分の弁当を抱えてイートインスペースに向かう途中に視線をやれば、男はカゴを片手に楽しそうに棚を眺めていて、戻ったときもまだいた。カゴの中にはウインナー盛り合わせと大盛りペペロンチーノが入っているのが見えた。男はトッピング好きで、いつも幾つかの惣菜を組み合わせたような買い方をする。そして最近はペペロンチーノがお気に入りのようだ。ペペロンチーノは光莉の息子――
あ、これは、声をかけるチャンスかもしれない。でも、訊いていいものかしら。少しだけ考えて、しかし思いついたときには光莉の心は決まっていた。
「あの」
ドリンク棚の前で飲み物を眺めている男に声をかけると、男がゆっくりと振り返った。長い前髪の下の目が光莉を捉える。一瞬どきりとした光莉は、そういえばまともに向き合ったのはこれが初めてかもしれない、と思った。
毛で覆われているせいで分からなかったが、存外若い。志波と同い年くらいではないだろうか。そして、意志の強そうな黒い目に、何か引っかかるものを感じた。「何?」と男が静かに訊いてくる。
「あの、廃品回収業をやられている、んですよね? 壊れた自転車なんかは、引き取ってもらえるのかなと思って」
先日、恒星が自転車を壊して帰って来たのだ。どんな乱暴な扱いをしたのかフレームが大きくひしゃげていて、修理もできそうになかった。捨てなくてはいけないと思うものの、裏庭に置いたままになっている。
「できるけど、どこにあります?」
二文字以上を引き出した! そのことに少しの達成感を覚えつつ、光莉は「家なんですけど」と答えた。
「家、どこです?」
「ここから徒歩で十分くらいのところです」
住所を言うと、男は頷いて、「今度、そこ回る」と言う。
「他にも捨てたいものがあったら、一緒に持って帰る。自転車は無料だけど、場合によってはリサイクル料が発生するものがあるから、その点だけ気を付けて」
「あ、はい」
男の声音や口調がやさしいことに、光莉は内心ものすごく驚いていた。いくら仕事とはいえ、つっけんどんだったり、無愛想だったりするのではないかと想像していたのだ。
「えーと、あ、あったあった」
男がツナギのポケットを探り、紙を取り出す。はいこれ、と手渡されたのは名刺で、背中と同じレタリングで『なんでも野郎』と書かれていた。小さく、携帯電話の番号も記載されている。
「何かあったら、ここに連絡してください」
「不用品回収・お困りごと……。あの、お困りごとってなんですか?」
ずっと気になっていた質問だった。名刺から男に視線を移すと、「困ってることをなんでもやる」と返って来る。
「年寄りの家とかに行くと、雑用を頼まれることが多いんだ。家具の移動とか、買い物とか。だから、いっそ書いておこうと思って」
なるほど、と光莉は思う。
「あ。これ、名前が書かれてない……」
名刺に名前がないことに気付いて呟くと、「名刺を発注するときに、入れ忘れてしまって」と男は少しだけ恥ずかしそうに
「ツギ」
「はい?」
「ツギって呼んでくれたらいいから」
ツギ。津木、都城、そんな漢字だろうか。訊こうとしたところで、客が立て続けに入店してきた。
「あ、行かなきゃ。すみません、じゃあ今度、お願いしますね」
ツギともう少し話をしてみたかった。後ろ髪を引かれるような思いで、光莉は仕事に戻ったのだった。
夫がベッドに入る二十二時から、光莉のゴールデンタイムが始まる。きれいに片づけたダイニングテーブルに、ノートパソコン、ペンタブ、読みかけの漫画にスマホ。そして
「今日はいいネタが入ったなあ」
熱いコーヒーを
「アユムくんは、金曜日の更新分に絶対入れこもう」
パソコン画面では、ピクシブの漫画ランキングが開かれている。三位につける『フェロ店長の
漫画が好きで好きで、自分でも描こうと思い至ったのは中学生のころだった。高校、大学とずっと描き続け、漫画誌に投稿もした。けれど結果はいつも最終選考手前で落選。そんなときに出会った男性に夢中になって、結婚した。すぐに子どもに恵まれて、そしたら毎日が慌ただしく過ぎていくようになった。漫画のことを思い出したのは、夫と穏やかな関係に落ち着き、ひとり息子が早々に精神的な親離れをしてしまったころ。自分のために使う時間が出来たのだ、と感じたときに真っ先に思い出したのは、やはりというべきか、漫画だった。
いまの時代はすごい、と光莉はしみじみと思う。なにしろ、ネットにアップするだけで、多くのひとの目に触れるチャンスがあるのだ。かつては友人たちと必死に同人誌を作るも売れず、在庫の山ができた。せめて誰かに読んでもらいたいよね、とみんなで悔し泣きしたものだ。それがいまでは読者数も着々と増え、「面白いです」「更新楽しみです」などという嬉しい感想を貰う。なんと素晴らしい時代だろう。
「まあ、それもこれも、フェロ店長のお
趣味を充分に楽しむには、お金が必要だ。光莉は元々ペンタブ欲しさにパートに出たのだったが、そこで志波に出会ったのは運命だと思う。
志波が本当にただの雇われ店長だと分かったあとに、光莉は感動した。なんて、なんてキャラが立ったひとなの……! テロ行為のごとく色気をまき散らすコンビニ店長だなんて、それだけでもう面白すぎる。仕事を覚えるのと並行して、志波観察を始めた。
志波は、知れば知るほど面白い男だった。コンビニには絶対不必要なオーラを発しながら、しかし丁寧に接客をする。テンダネス内で毎年行われている接客コンテストでは殿堂入りを果たしているらしい。熱狂的なファンがいる一方、女子中高生には「顔面セクハラ」と呼ばれて避けられている。臭いほどのフェロモンは、若い女の子には気味が悪いのだろう。私生活は、謎だ。休日でも店に出没することもあれば、休暇を取りますと言って数日いなくなることもある。関門海峡ミュージアムでうつくしい着物姿の女性と腕を組んで歩いているところを見かけた翌日に、野宮以上に筋肉質な男におぶわれてプレミアホテル門司港に入っていくところに遭遇した。気になりすぎて「どんなひとと付き合ってるんですか」と訊いたら、「中尾さんとぼくの『付き合う』という意味の
光莉は、気付けば色恋とは別のところで志波に夢中になっていた。このひとを漫画にしないでどうする。志波を主人公にして、舞台はもちろんコンビニ。フェロ店長と、彼をとりまく様々な人びととの日常を描こう。タイトルはそのものずばり、『フェロ店長の不埒日記』。絶対に面白いものになる、と確信を持って描いたものの、まさか数年
「店長って本当に存在してるんですか? だったら店の場所を教えてください、かぁ」
連携しているツイッターに送られてきたダイレクトメールを見て、光莉は笑う。漫画の人気がじわじわ出始めたころに、さすがに本人の了解を取っておこうと志波に告白をした。もし不快ならば
既に、フェロ店長に会いに行きたいというコメントが届き始めていたので、光莉は「もちろん、絶対に」と強く言った。そんなことをしたら騒ぎになることくらい承知している。個人のプライバシーは守ります、そう言う光莉に、志波は「じゃあオッケー」と軽く答えたのだった。
「実在していますが、場所は言えません。いろいろフェイクも入れてますが、店長の迷惑になった時点で連載を取りやめなければなりませんので、捜索は止めてくださいね、と」
何十回目となる返信を打って、コーヒーを飲む。それからコメントのチェックを済ませていると、ふらりと恒星が現れた。冷蔵庫を開け、パックの牛乳を
「またマンガかよ。いい年して、そういうオタク活動やめてくれよ」
「親の趣味に口出さないでって言ってるでしょ」
むっとして言い返す。恒星は、光莉の趣味が気に食わないのだ。小さなころは、ボクのママは絵がとっても上手なんだよ、と誇らしげに言って可愛かったのに。でもそれを言うと、もっと嫌な顔をするから口にはしない。
「見るのも嫌なら、早く部屋に戻りなさいよ」
「言われなくても戻るよ。あ、そういや廃品回収業者にチャリの回収頼んだ?」
驚いて「どうして」と言うと、「学校から帰って来たときにちょうど軽トラックが通りかかって」と牛乳をまた飲む。
「お母さんにチャリを引き取ってくれって言われたんだけど、いま持って行ってもいい? って。だからお願いしたけど」
「ひ、髭もじゃだった? 正平さんみたいな」
まさか、もう来るなんて。訊けば恒星は頷いて、「髭だけは確かに赤じいと近いか。でも、すごく若いよね」と言う。
「何がどうって訳じゃないんだけど、面白いひとだったな。あと、かっこよかった」
「かっこよかったぁ?」
また驚いてしまう。顔なんて
「あの髭の下の顔、わりとイケメンだと思うな。まあ、女には分かんねえ良さかなあ」
十六になったばかりの子どものくせに一人前なことを言い、「とにかく、チャリは渡しておいたから」と恒星は部屋に戻っていった。
「えー、早すぎる」
光莉はバッグの中から昼間に
「わたしの面白人間センサーが、鳴り響いてるんだよねえ」
ツギは、何か特別なものを持っている。そんな予感がするのだった。
*
それから数日後のことだった。その日、いつも一番乗りで弁当を食べに来る浦田が、姿を見せなかった。全員の受取りと食事が済んでも現れず、登録されていた携帯電話に光莉が電話を掛けてもでない。志波に報告し、志波が自宅アパートまで様子を見に行くことになった。店から浦田の家まで、徒歩で十分ほどだ。
「病院の診察日だったとか、寝過ごしたとかだといいんだけどね」
前にも何度か同じようなことがあったが、どれも伝達ミスだった。今回もきっとそうだろう、と光莉は気楽に「行ってらっしゃい」と見送った。しかしその十五分後に遠くから救急車の音が聞こえると、足が
「やだ、もしかして……」
浦田と救急車は関係ないかもしれない。そんな風に思おうとしたけれど、しかし志波はいつまで待っても帰って来ない。不安だけが膨らんでいった。
「わし、ちょっと行ってこよう」
イートインスペースの端で用心棒中だった正平が言い、光莉は「すみません」と頭を下げる。赤い三輪車に乗って出て行った正平はものの十分で帰って来て、その顔つきを見た光莉は自分の予感が確信に変わったことを知った。
「自宅で倒れていたらしい。みっちゃんは、ついていったそうだ」
「そう、ですか……」
「みっちゃんから、何かしら連絡が入るだろう。それを待とう」
志波から連絡があったのは、店を出て行ってから二時間が過ぎたころのことだった。疲れ切っているものの、どこかほっとした声で志波は「大丈夫だよ」と言った。
「まだ予断を許さない状態だけど、でも、助かった」
浦田は、くも膜下出血を起こして倒れていたらしい。病院に搬送されるのがもう少し遅ければ命はなかったという。
「ついさっき、山口県に住む娘さんと連絡がついたんだ。娘さんが着くまで、こっちにいるよ」
「分かりました。店長も大変でしょうけど、頑張ってくださいね」
スタッフルームで電話をしていた光莉が店内に戻ると、レジカウンターの前に複数のひとがいた。待たせていたかと慌てていくとそれは婦人会の面々と正平で、野宮を捕まえて話しこんでいる。
「浦田のじいさん、どこが悪かったのかしら」
「最近やっとお話しするようになったけど、持病があるなんて聞いてなかったわよ」
「年を取ればどこかしらガタがくるもんだけどよ、気をつけないといけないよなあ」
かしましく
「店長の発見が早かったのがよかったみたいです」
その場の全員の顔がぱっと明るくなった。
「あらやだ、そうおお」
「年を取ると嫌な話題ばかりで
「さすが、みっちゃんよね。ちゃんとお客のことを見てくれてるわあ」
話はあっという間に志波の賞賛に変わり、みんなはしばらく会話を楽しんだあと、帰っていった。
光莉が夕方から出勤のスタッフと引き継ぎを終えてスタッフルームに入ると、先に上がったはずの野宮がまだ残っていた。テーブルの上に置いた携帯電話を眺めて、どこか
「どうしたの、野宮くん」
光莉の声でのろりと顔を上げた野宮は、苦しそうに顔を
「え、具合でも悪いの?」
驚いて訊けば、首を横に振る。じゃあどうしたの、と重ねて訊くと、「浦田さん」と消え入りそうな声で言った。
「分かった、急なことだったから驚いたんだ? 無事だったんだし、よかったよね」
うちのサービスも、なかなかやるよね。そう続けようとした光莉だったが、口を
「ね、ねえ。どうしたの」
野宮の涙の理由が、見当もつかない。おずおずと訊くが、野宮は声もあげずにただ涙を流す。とりあえず落ち着くのを待とうと、野宮の前の
「オレ、いつも、ひとのヘルプを無視するんす」
光莉は「ヘルプ?」とおうむ返しに言って首を
「高校のとき、いつも一緒に練習してた
涙を堪えようとするあまりか、ぐぅっと野宮の
「だ、大学入っても……大学入っても一緒にレスリングやろうって言ってたのに、あいつ、もうできなくて。オレ、それがすげえ申し訳なくて」
そんなことがあったのか、と光莉は野宮を見る。彼はだから、レスリングを辞めたのだ。
「オレ、それがめちゃくちゃ頭にあって、もう、消えなくて。次にこんなことがあったら絶対に後悔しないようにしようって思ってたんす。でも……」
テーブルの上に置かれていた手が、ぐっとこぶしを握る。岩のように大きくごつい手は震えていた。
「この間、浦田さんにお弁当を持って行ったとき、『頭が痛い』って言われたんです」
「あたま?」
「浦田さんが、いつもより機嫌が悪い日があったじゃないすか。あの日、今日は嫌なことでもあったんですかーって言ったんです。そしたら、頭が痛くて仕方ねえんだって怒鳴られたんです。でかい声で話しかけられると、もっと痛くなるから黙ってろ! って。で、オレそれにムカついてしまって。そこで話を終わらせてしまったんです。メシが不味くなるから向こう行ってろって言われて、そのまま……」
これ、と野宮が携帯電話を差し出す。くも膜下出血について検索をしたらしい。その前兆として頭痛が起きることがある、と書かれていた。
「また、やっちゃったんすよ。オレ、あんなに考えてて、絶対にって思ってて、でも全然ダメでした。ちょっとムカついたからって……」
「え、えっと、浦田さんの機嫌が悪いのは、いつものことだよ。同じ状況だと、私も聞き流しちゃうと思う」
光莉は数日前のことを思い出す。あのとき確かに、入店して来たときから浦田の機嫌は悪かった。しかし光莉もまた、いつものことだと気に留めもしなかった。野宮が悪いというのなら、それは自分も一緒だ。しかし、野宮は「そうじゃない!」と叫んで勢いよく立ち上がった。椅子が大きな音を立てて倒れる。
「他のひとだったらどう、とかじゃない。ずっと気にかけていたのに、肝心なときにまた同じ失敗を繰り返した自分が、許せなくてどうしようもないんだ!」
あまりの剣幕に、光莉は見つめるしか出来なかった。それに気づいた野宮が顔を歪める。
「怒鳴ったって、仕方ねえっすよね。自分が嫌になる。ほんと、最低っすよ、オレ」
そう言って、野宮は逃げるように部屋を出て行った。光莉は慌てて追いかけたが、店の外に出たときにはもう野宮の姿はなかった。
「ねえ、野宮くんどっち行ったか分かる?」
店内に戻って訊くと、レジカウンターの中にいた
「野宮、どうかしたんすか? すげえ勢いで原チャリで飛び出して行きましたけど」
あれ、危ないすよ。心配そうなその口調に、光莉の不安が増す。野宮は思いつめた風だった。このまま放っておいてはいけない気がする。
「ええと、ええと」
志波に連絡をしたいが、まだ病院にいるはずだ。じゃあ、どうしたら……。必死で考えて、思い出したのは白い紙切れだった。
「名刺ぃっ!」
思わず叫んで、バッグの中に手を突っ込む。探り当てたものを見ながら、電話を掛けた。数コール目で、低い声がした。
「もしもし、あの、テンダネスの店員ですけど」
心臓が少しだけ鼓動を早める。
「あの、お困りごとで、頼みたいんですけど」
電話の主は低い声で笑って、「なんでしょう?」と訊いた。
テンダネス門司港こがね村店横のイートインスペースは充実している。外の通りを眺めることができるカウンター席が五席。四人掛けのテーブル席がふたつ。それぞれに、季節の花――いまはひまわりを生けた一輪挿しと、ティッシュボックスが置かれている。端にはお湯が満たされたポットとトースターに、ゴミ箱。こがね村ビルの住民間では、ここにテレビを置くことも検討されているという。そのイートインスペースのカウンター席の端っこに座った光莉は、そわそわと外ばかりを気にしていた。
すっかり日は暮れて、空にはクリーム色の半月がかかっている。開け放たれた扉からは、やさしい夜風が流れ込んでいた。光莉は手元のスマホで時間つぶしをしているものの、画面の内容は殆ど頭に入って来ていなかった。
「あ!」
何十回目とも知れない視線の往復を繰り返していた光莉の顔が明るくなる。見慣れた軽トラックがゆっくりと駐車場に入ってくるところだった。軽トラックの荷台には洗濯機や掃除機と共に、野宮の原付バイクが積み込まれていた。運転手の髭もじゃの男が光莉に気付き、手をあげる。その横には、
「見つけてくれたのね。ありがとう!」
外に出て、軽トラックに駆け寄る。車を降りた髭もじゃに言うと、ツギはにっと歯を見せて笑った。
「死にそうなツラはしてたけど、死にそうではなかったぞ」
人探しもできますか? そう
野宮を探して欲しい、光莉の言葉に、ツギは『ああ、バイトのマッチョくん』とすぐに分かったように言った。店員に全く興味がなさそうだったのに、まさか把握しているとは思わなかった。
『
ツギは少し考えるように沈黙したあと、『了解』と答えた。
『いまどこから電話かけてる? ああ、いつものテンダネスね。じゃあそこで待っててくれるか。なるべく早く連れて帰る』
『え、そんな、大丈夫?』
『得意って、言っただろう』
自信ありげだったけれど、まさかこんな短時間で見つけてこられるとは思わなかった。のろのろと軽トラックを降りてくる野宮に「よかった」と微笑みかける。野宮は「すみません」と消え入りそうな声で頭を下げた。
「光莉さん、こんな時間に、お家はいいんですか。あの、オレのためにそんな」
「家には
こんな時でさえ光莉を気遣う心に笑ってみせて、光莉は続ける。
「お腹
念のため報告だけしておこうと志波に連絡を取ったら、弁当を食いながら待っててと言われたのだ。誰に野宮くんの捜索頼んだの? え、なんでも野郎? まじかー。いつか声かけるんだろうなあとは思ってたけど、このタイミングか。まあ、あのひとならきっとすぐに見つけてくれるだろうから、人選は間違っていないけどさ、そうかあ……。志波の口調からは、ツギに関わって欲しくないような気配がした。
やだもう、ふたりはどんな関係なのかしら。気になる気になるぅ。踊りはじめそうな
「なんでも野郎さんも、ご一緒にどうですか?
「ツギでいいって。じゃあ俺もありがたくご相伴に
多少口調が砕けたツギだが、何の情報も得られそうにない。実は腹減ってたんだよな、とお腹を
「私が買ってくるから野宮くんはイートインスペースで待ってて。最近お気に入りだったカツ丼でいいかな?」
訊くと、野宮は首を横に振る。
「食欲なんて、ないです」
「昼食もほとんどとってなかったよね? 食べた方がいいよ」
普段は三人前でもぺろりと平らげてしまうのだ。二食も抜いたら筋肉がしわしわに
「でも、食いたくなくて」
「サンドイッチはどう? サラダパスタとか」
一口でも食べたら、呼び水になって食欲が増すものだ。思いつくままに言う光莉に、野宮は決して首を縦には振らない。
「俺、買ってきていい?」
傍でやり取りを見ていたツギがふいに言った。
「あんたは、こいつの話し相手してなよ。俺買ってくる」
「え、でも」
「いいからいいから。会計は、ミツにつけとけばいいんだろ?」
ツギはそう言って、ひょこひょこと気楽な足取りで店内へ消えて行った。
「変なひとっすよね」
ぼそりと野宮が言う。オレ、
和布刈公園は夜景の
それからイートインスペースの四人掛けテーブルに野宮と向かい合って座っていると、両手に大きなレジ袋を抱えたツギが「買ってきたぞー」と楽しそうに戻ってきた。
「めちゃくちゃ買った。いやー、ひとの金で手当たり次第買えるって最高」
どっかと野宮の横に座り、袋の中から次々と食べ物を取り出す。大盛りペペロンチーノにウインナー盛り合わせがふたつずつ。カルボナーラにカツ丼に、キムチ、レタスサンドに温泉卵。ふわとろプリンと特製どら焼きは三つずつあった。
「さあ、食え!」
好物を前にした子どものようにうきうきした口ぶりで言うツギに、光莉は思わず笑う。
「ツギさんもどうぞ。お腹空いてたんでしょう」
「あ、そう? じゃあいただきます。お前、どれから食べたい?」
ツギは野宮に訊き、野宮が首を横に振ると、カルボナーラに手を伸ばした。ウインナー盛り合わせも一緒に開封し、パスタの上に数本トッピングする。その上に温泉卵も乗せた。
「
へっへっと笑って、ツギは
「しあわせそうに食べるのねえ」
「
ぺろりとカルボナーラを食べ終え、次はペペロンチーノに手を伸ばす。ツギがあまりにも美味しそうに食べるせいだろうか、光莉は家で軽く食事をしてきたというのにお腹が空いてきた。三人分ということだろう、ふわとろプリンに手を伸ばす。
「野宮くんも、食べなよ」
野宮も食欲を刺激されているだろうに、目の前の弁当たちに依然手を伸ばそうとしなかった。
「お前が
終わらないやりとりに
「みなさんにご迷惑かけて、すみません」
「いいっていいって。私がおせっかいなもんだから、心配しすぎてるだけだもん。野宮くんはきっと、ひとりでもどうにかできたよね」
「……分かんないす。オレ、情けないっすよね。どうしてこうなんだろ」
野宮が悔しそうに唇を噛んだ。
「私は野宮くんのことやさしい子だって思うよ。気付かなかったことは、仕方ないじゃない。次に生かそうよ」
「その次を、生かせなかったんですよ。オレは」
野宮が苦しそうに言い、光莉は言葉を探す。
「そもそもオレはやさしくなんかない。自分勝手なんです。高木のときは、自分の目の前にある大会のことしか考えていなかった。浦田さんのときは、ムカつく年寄りに言い返すことばかり考えてた。あとから絶対後悔するのに」
「誰しも聖人君子でいられないよ。私だって、自分本位な考え方はする。特に今回のことは、野宮くんのせいじゃない。野宮くんが仮に気付いて病院を勧めていたって、浦田さんが聞き入れなかった可能性だってあるの。だから、そんなに気にしちゃだめだよ」
泣きながら首を横に振る野宮に、光莉の言葉は何も響いていない。どう言えば彼に伝わるのだろう。光莉が心の中でため息をついたときだった。
「こうすると、旨く食えるぞ」
いつの間にかペペロンチーノを食べ終わっていたツギが、野宮の前にカツ丼を置いた。そしてその上に、キムチをばさりと乗せた。カツの茶色と黄色い卵、青いネギが絶妙のバランスを保っているその上に真っ赤な漬物が汁ごとかかり、野宮が「うああ」と声を上げた。
「なんてことするんすか!? こんなの、食えないでしょ!」
「食える。旨いぞ」
ほれ、とツギが割り箸を野宮に差し出すが、野宮は受け取ろうとしない。少しだけ野宮を待っていたツギだったが、「食え!」と箸を押し付けた。
「早くしないと、弁当が冷めちまうだろ!」
ツギが語気を強め、野宮はその勢いに押されるように箸を受け取った。それからこわごわと、キムチと卵、玉ねぎとタレのかかった部分を
「あ、大事なモン忘れてた。これこれ」
袋の中を掻き回し、ツギが取り出したのは小分けパックのマヨネーズだった。封を切ったかと思えばキムチ乗せカツ丼にかける。野宮がまたも「うああ」と情けない声をあげた。
「だから、こんなもん食えたもんじゃねえです、って……」
野宮が黙って、口に運んだ。咀嚼して、今度は大きくひと口。その勢いは、どんどん増していった。
「な、旨いだろ?」
ツギが言うと、野宮が何度も頷く。
一旦食べ始めると、スイッチが入ってしまったらしい。野宮は普段以上の勢いでカツ丼を掻き込む。あっという間に、半分以上が消えた。しかしその途中で、野宮はぴたりと箸を止めた。ぽろぽろと涙を
「ど、どうしたの、野宮くん」
「オレ……悩んでたはずなのに、メシが旨いってがっついてやんの……」
情けねえ。野宮が声を
「旨いモンを旨いと感じるのは当たり前だろ」
いつの間にかレタスサンドに余ったウィンナーを挟んで食べていたツギは、
「親が死んだとしても、腹は減るぞ。旨さを感じられないときは、どっかおかしくなってるときだ。ていうかな、美味しく食わねえと食いモンに失礼だろう」
サンドイッチを平らげたツギは「これ、お前のノルマだからな」とペペロンチーノとウィンナー盛り合わせを野宮の前に置き「いまは無心で食え!」と強く言う。
「
野宮はカツ丼を食べ、そのままパスタに手を伸ばす。ツギがウィンナーをどさっと載せた。しばらく無言で食べていた野宮が、何か呟いた。光莉は耳を澄ませてみる。
「……旨い、です」
ツギが「だろう」と頷いた。いまはただ、メシと向き合え。
野宮は黙って食べる。光莉は野宮のその顔に生気のようなものがゆっくりと戻ってきている気がした。そして、ツギを窺った。このひとは、不思議なひとだ。
「弁当食べててとは言ったけど、まさかの量。何人前だよ」
くすくすと笑い声がして光莉が顔を向ければ、店側から志波が現れた。昼前から拘束されていたせいだろう、少しだけ疲れた顔をしている。
「遅れてごめん。浦田さんの娘さんがすごくお話好きなひとでさあ。それでちょっとお話ししてたら遅くなった」
光莉の横に腰かけた志波は、手を止めた野宮に「食べて食べて」と勧める。野宮が食べ終わるのを待って、柔和な笑みを零す。
「あのね。浦田さん、楽しみだったんだって」
え、と野宮が顔を上げる。
「浦田さんは、毎日このコンビニに通うのを楽しみにしてたんだって。娘さんには、電話で言っていたらしいよ。店員はにこやかだし、気難しい自分にもいつも笑いかけてくれる。同じような境遇のひととも知りあえたし、これからはもっと外に出て行こうと思うって。そしてね、浦田さんには高校三年生のお孫さんがいるんだ」
思い出したように、志波がくすくすと笑う。
「病院にも来てたんだけど、現役ラグビー部員で、めちゃくちゃ筋肉マン。そのお孫さんに野宮くんが似てるってずっと言ってたんだってさ」
「……オレに?」
「孫よりもいい体格をしている子が、どうしてだか部活をやめてぼんやり過ごしている。そのことがとても気になっていたそうだよ」
そういえば、と野宮が小さく呟く。
「最初のころ、部活をしているのか訊かれました。それで、元レスリング部だって答えたんです。いまはもう辞めちゃったんですけど、って。そしたらもったいないって。その体を
それは全部、オレに対する嫌味かと思ってました、と野宮が
「あのひとはね、期待をかけていたみたいだよ。言い方がきつくて、分かんなかったよね。分かるのは、難しかったと思うよ。ぼくだって、そうさ」
志波はやさしい口調で、「ひとの内面は、分かりにくいものだよねえ」と言う。
「顔つきとか言葉だけで判断してると、大きな勘違いをすることになる。じゃあどこで判断すべきかと言うと、ぼくは行動だと思ってるんだ。浦田さんは、本当にうちのコンビニに通うのが楽しみだったんだよ。だってそうだろ? 毎日誰よりも早くに来てた。野宮くんにしつこく言い続けていたのもきっと、浦田さんなりのエールだったんだよ」
野宮の顔が、奇妙に歪められる。
「それとね、これはぼくからの提案なんだけど。浦田さんは生きていらして、回復すればお話もできる。本人に会って、一度話してみたらどうかな」
ね? と志波が微笑みかけ、テーブルの上で組まれた野宮の手をそっと握った。
「後悔することがあったとしても、まだいくらだって取り返せる。大丈夫だよ」
野宮は少しだけ考えるように目を閉じたのち、小さな声で「行きたいです」と言葉を
「オレ、浦田さんのところに行きたいです。話をちゃんとしたいし、謝りたい」
志波が微笑む。
「今度、一緒に行こうか。浦田さんもきっと喜ぶと思うよ」
初めて、野宮の顔に笑みのようなものが浮かんだ。少しだけ晴れやかな顔に、光莉はほっとする。
「解決か? それならほら、どら焼き食え」
ツギがどら焼きを野宮に差し出す。野宮はそれにも笑い返し、それから志波に握られた手をぺっと振りはらった。
「店長がやると、これはれっきとしたセクハラっす」
志波が「あう」と情けない声を洩らす。それを見てげらげらと笑いだしたツギに、野宮は続けて言う。
「なんでも野郎さんは、オレの分のプリン食ったでしょう。オレ、プリン大好きなんで、買い直して来て下さい」
今度はツギが「あう」と声を上げた。
*
テンダネス門司港こがね村店は、いつでも人材不足だ。というのも、志波のフェロモンに耐えられる人間が少なすぎるのだ。レスリング部に入部した――友人から、お前だけはレスリングを続けて欲しいと言われたという――野宮が辞めたあとのシフトのしわ寄せは、
「あー、しんどい。店長、早く誰か入れて下さいよ」
「面接に来るひとは多いけど、でも働けそうなひととなると、なかなか……」
スタッフルームには、連勤続きのふたりしかいない。テーブルにうつぶせてため息をついた光莉に、志波も重ねるように息を吐く。野宮の代わりとして早期退職をしたという五十代男性を採用したはいいが、どういうわけだか彼の妻が志波に一目ぼれをしてしまい、離婚
「店長、馬のマスクかなにか
「中尾さん、そんなことすると漫画のタイトルが馬店長になるけど、いい?」
「あー、それは嫌かも……」
ふたりで何度目かのため息をついているとドアがノックされ、廣瀬が顔を覗かせる。
「店長、なんでも野郎が来て、店長を呼んでますよ。イートインスペースで待ってますけど、大丈夫ですか?」
いないって言います? と廣瀬が言うが、志波は「すぐ行くって言って」と返した。
「あ、あの!」
やれやれ、と立ち上がる志波に、私も一緒に行っていいですか? と光莉は訊く。
「いいけど……中尾さん、どうしてそんなに嬉しそうなの」
「だって、あれ以来会ってなかったし」
野宮が落ち着いたところで、せっかくの機会だしいろいろ訊くぞと思っていたのに、仕事の電話が入ってツギは去ってしまった。それからはどういうわけだかぷつりと来なくなって、どうしたのだろうと気になっていたのだ。
「私なりに彼のことを心配してたんですよ」
「へえ。中尾さんの顔に『ネタ』って書いてあるように見えるんだけどな」
「ぐ……。そんなこと、ないですよう」
バレてる、と思いながらも笑ってごまかしてみる。
「えっと、ほら、あのときのお礼も支払ってませんし」
「ああ、それはぼくがもう払ってるから大丈夫」
え、と声が出る。ということは、店外で会っていたのか。即座に想像を巡らせてしまう光莉に、志波が「潮時だろうねえ」と言う。
「中尾さんはいまじゃうちの最古参だもんな。四年か、わりと持った方かなあ」
「へ?」
「隠してたんだけどなあ」
あーあ、と志波がため息を
ツギは相変わらずのツナギだが、山の中でも
「おう。呼び出して悪いな」
「それはいいけど、何をしてたら、そんなことになるの」
「あ? ああ、ここに来る途中で山仕事を手伝ってた。礼だとかで猪肉
志波が「いらない」と言い、正平が「わし、好き」と笑う。
「そんなら半分やるよ。てか、正平さんの家で食わせてくれよ。焼肉がいいな」
「おう、いいぞ」
「え、正平さんって、ツギくんと知り合いですか」
正平はツギのことをよく知らなかったのではないのか。志波の背後にいた光莉が驚いて言うと、そこで光莉に気付いたツギが「あ、どうも」と頭を下げる。それから志波に「すまん。お前だけかと思ってた」と言う。正平もまた「おっと、すまん」と
「いやいや、いいんだ。彼女にいつまでも隠しておくのもなと思って、だからここに連れて来たんだ」
志波が光莉を振り返る。
「あのね、光莉さん。このひと、ぼくの兄なんだ」
「え」
一瞬、『あに』という単語の意味を忘れた。
「ふたつ上の兄、
志波と、ツギを交互に見る。視界の端にいる正平があくどい笑みを浮かべているのが分かる。いやそんなことより、似ていない。全く、似ていない。天然フェロモン発生装置とこのむさくるしい男が、兄弟?
「え、ツギっていうのは……」
「それ、
適当でしょう、うちの親。少し恥ずかしそうに言う志波に、光莉は混乱する。情報量が、多すぎる。
「待ってください。えっと、五人兄弟? 店長みたいのがあと何人? え、五人なら、五人目は五彦?」
「五人目は女の子で、名前は
「ごめんなさい、ちょっともう整理できそうにない」
よたよたと、ツギの前の椅子に腰かける。毛むくじゃらの奥の目が愉快そうに揺れていた。その目に、光莉は気付く。以前感じた違和感のようなものの正体。ツギは、目だけは志波によく似ているのだ。
「うっそ。まさかの共通点。目かあ……」
「驚いたろ、光莉ちゃん。わしもなあ、初めて知ったときは驚いた」
正平がげへへと笑い、枯葉のついたツギの頭をくしゃくしゃと掻きまわす。
「門司港で一番
「まっさきに気付いたくせに、よく言うな」
訊けば、正平は誰よりも早くふたりの関係に気付いたのだと言う。さすが門司港の情報屋。
「それにしても、どうして三人ともそのことを隠してたんですか」
自分の観察力のなさが情けなくて光莉が頬を膨らませると、「面倒くさいんだよ」とツギが言った。
「こいつと兄弟っていうだけで、どれだけ面倒があったか。
光莉は「うわやば……」と思わず身震いした。でも、あり得る話ではある。行き過ぎた志波ファンなど、毎日のように見ているのだ。
「ぼくのせいだけにしないでほしいな。ぼくだって、弟ってことでいろいろあったよ。ヤンキーにケンカ売られたり、記憶にない借りを返されそうになったり」
とにかく、とふたりは声を
「赤の他人ってことにしておく方が、気楽なんだ。だから、できればこのことは広めてほしくない」
「わしも、その方がいいと思う。無駄な騒ぎを産むだけだからな」
「了解。洩らしません」
確かに、こがね村ビルの住民たちにバレただけでも面倒そうだ。みっちゃんのお兄さんならお世話しなくちゃと張り切りだしそうな婦人が少なくとも三人くらいいる。
「あ、それよりミツ。これを預かって来たんだ」
ツギが紙袋から取り出したのは、大きめのタッパーだった。
「うわ、美味しそう」
思わず光莉が言うと、ツギが「妹の得意料理」とどこか自慢げに言う。
「俺は今朝まで実家にいたんだけど、妹が大の三彦好きでな。ミツにこれ持って行けって預かったんだ。早く渡さないと俺が叱られるんで、仕方ないから呼んだ」
「ぼく、妹のおはぎが大好物でね。でもこんなにたくさん作らなくてもいいのにな」
妹の樹恵琉――本当にそういう名前らしい――は十七歳になるという。年の離れた妹の手作りを前にした志波は、普段とは違う兄の顔をしていた。こんな表情を見せられたら、ファンクラブの面々は大興奮だろうなあと光莉は眺めながら思う。
「兄ちゃんは食べた? せっかくだし、一緒に食べない?」
「形の悪いやつを死ぬほど食わされた。でもまあ、貰うかな」
「中尾さんと正平さんもどう? ぼくひとりじゃ、食べきれない」
それから四人で、店で購入してきた紙皿と割り箸で、おはぎを食べた。上品な甘さのあんと、もっちりとしたもち米が美味しい。得意料理というのも充分頷ける、と光莉は遠慮なく食べた。
「そうか、あのマッチョくんはレスリング頑張ってるのか」
おはぎを死ぬほど食べ、カツ丼をがっつり食べた後だと言うのに、ツギは今日初めての食事のようなペースでおはぎを胃に収めていく。
「あの子の接客も、なかなかよかった。いい人材を失ったな」
「そうだよ。わしの門司港情報屋を引き継がせてもいいと思うくらい、いい体格しとったのに」
正平も、老体とは思えない勢いでおはぎを食べる。
「本当はここを辞めたくなかったみたいなんだけど、レスリングを真剣にやる以上、両立は難しいからねえ。仕方ないよ」
上品におはぎを口に運んでいた志波がふと箸を止め、嬉しそうに笑った。
「そうそう。彼、すごく嬉しいことを言っててさあ」
光莉が、志波の顔を見る。
「この店に来るひとはみんな、自分の一日を一所懸命生きてる。レスリングのなくなったオレなんてどうでもいい存在だと思っていたけど、みんなの一日の手助けをすることで、いてもいいのかなって思えていたって」
へえ、と光莉も目を細める。これまでレスリング一筋で、生まれて初めてのアルバイトがこの店だと言っていた。最初は慣れないことばかりで、必死で接客をしていた大きな体の男の子。気持ちいい接客だね、と客に褒められたときの輝く笑顔を、覚えている。
「昔、同じようなことを言っていた女の子がいたんだよね」
しみじみと志波が言い、「あの子か」と正平が
「あの子の言葉を聞いて、ぼくはこの仕事を精一杯頑張ろうって思ったんだ。誰かの人生の
志波の声が、光莉にやさしく響く。このひとがそんな風に思って働いていたなんて、想像もしなかった。そして、すっかり仕事に慣れきって、そつなくこなすことしか考えていなかった自分を恥じた。わたしも、意識を変えなくちゃ。
「あの言葉でいまのぼくがあるんだよ。コンビニがあって、よかった」
静かに、自身に語るように志波が言う。その顔にはいつもの胡散臭さも臭いくらいの色香もなかった。うつくしい
そして、彼は本当に、この仕事を好いているのだ、とも思った。
「えっと、私も、この仕事は好きですよ。でも、これ以上の連勤はごめんですから」
冗談めかして言ったのは、自分が露に触れていい人間ではないことを知っているからだ。これに触れられるひとは、彼にとっての特別な存在でないといけない。観察力はなかったけれど、それくらい悟れる人生経験は積んでいるのだ。
露を花びらの奥にしまいこんだ志波が「う」と胸元に手を当てて笑う。
「そんなこと言わないで。ぼくも面接頑張ってるんだから」
「ミツはマスクとか被ったほうがいいんじゃねえの。馬とか大仏とか」
「兄ちゃん、中尾さんと同じこと言わないで」
「じゃあいっそ着ぐるみでどうだ。わしの知り合いのイベント会社に訊いてやろうか」
「やめてよ、正平さんまで」
和気
ああ、私、こんなに充実していていいのかしら。おはぎをぱくりと食べ、光莉はくふくふと笑うのだった。