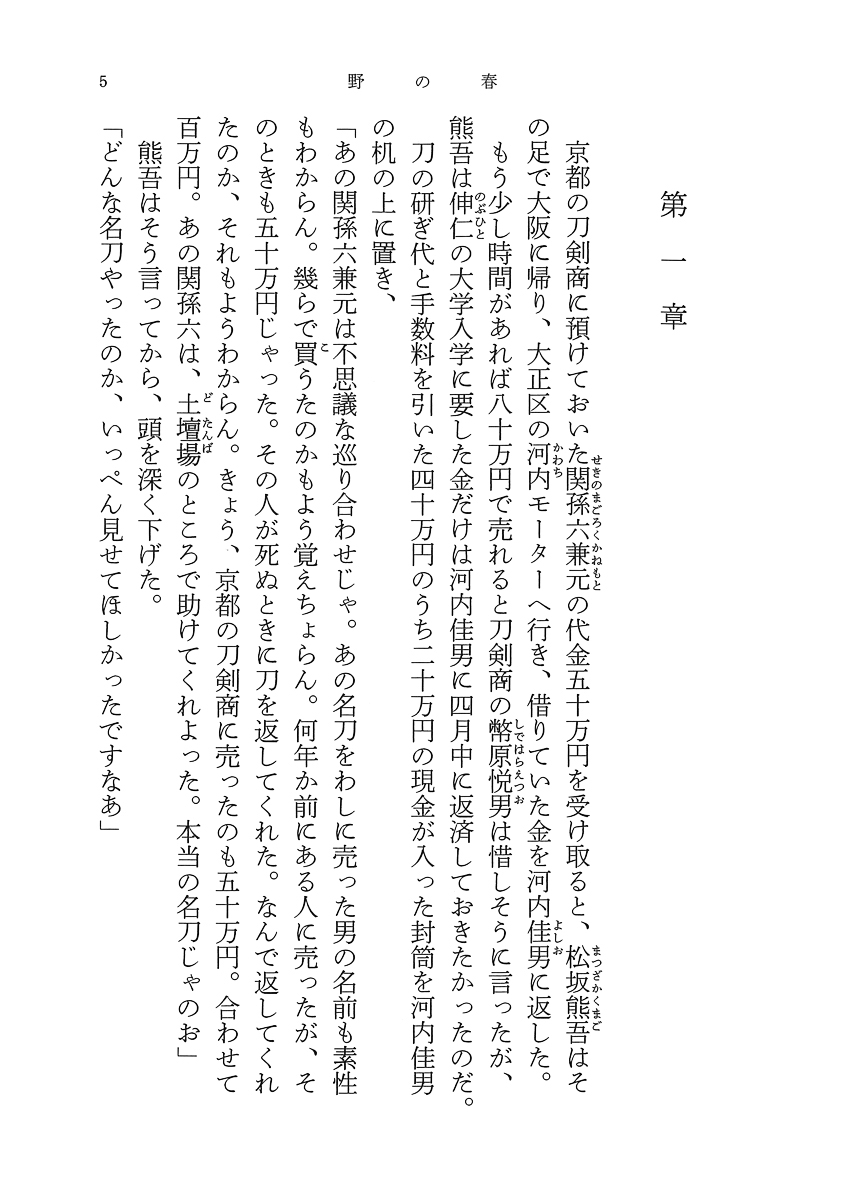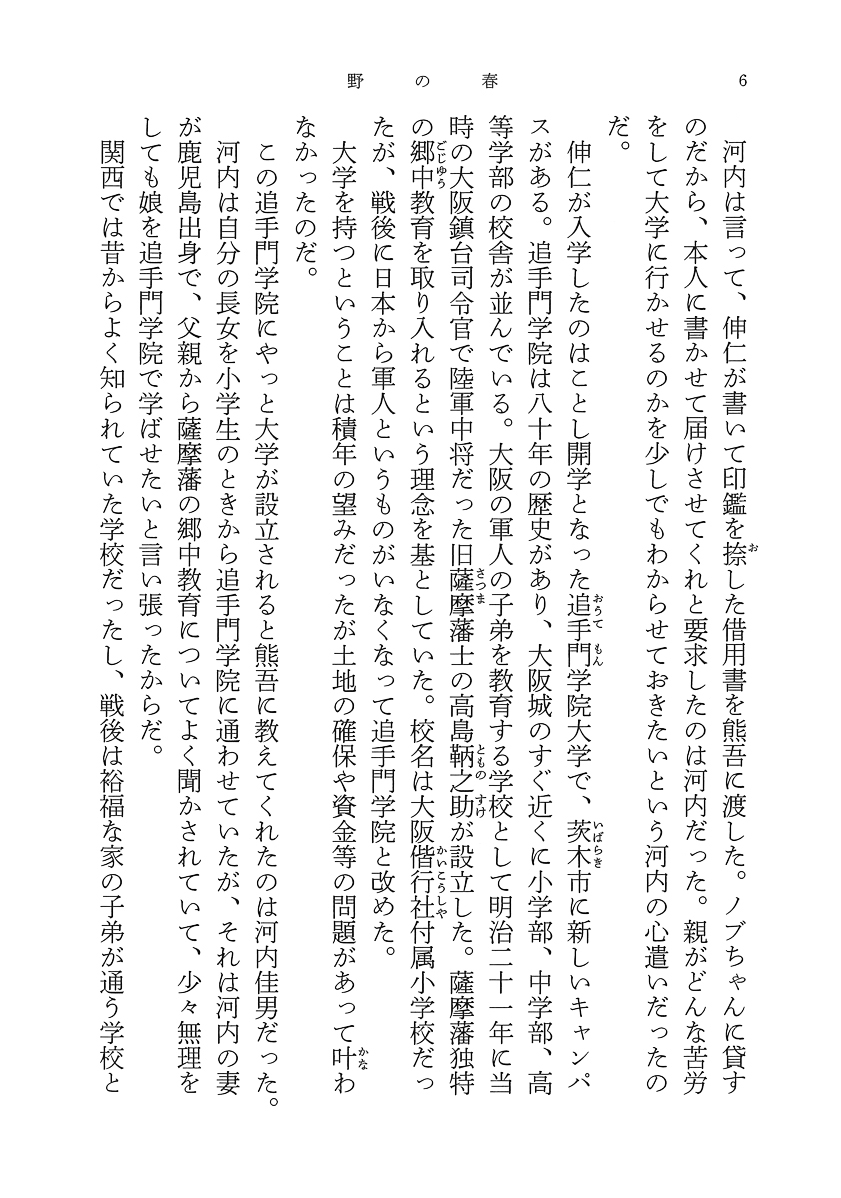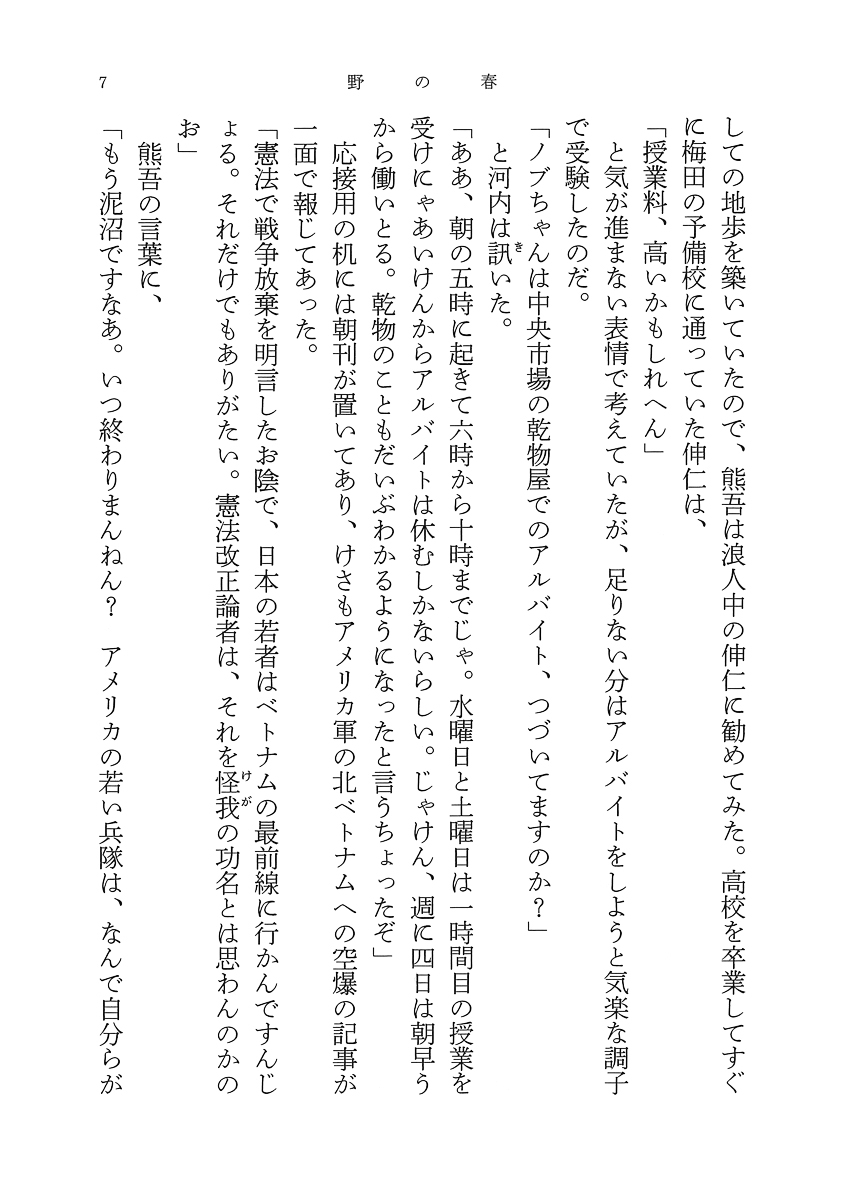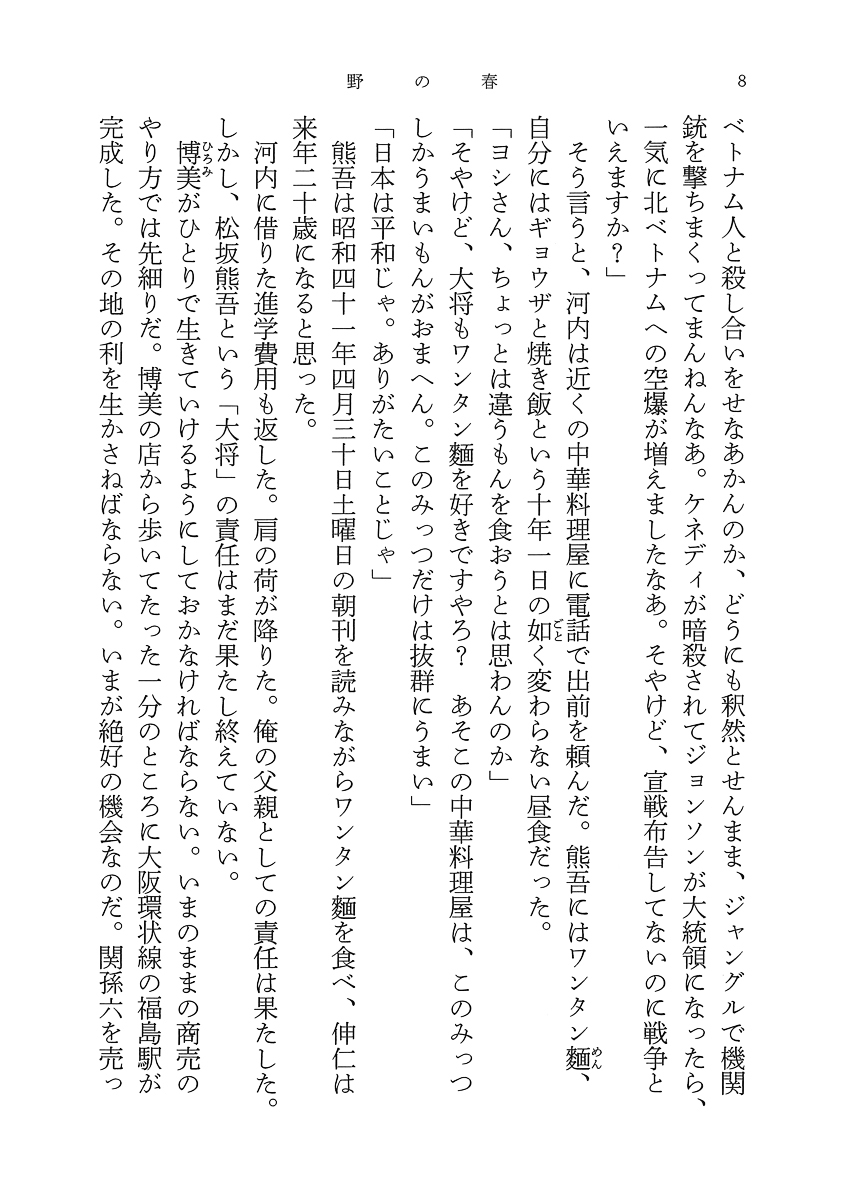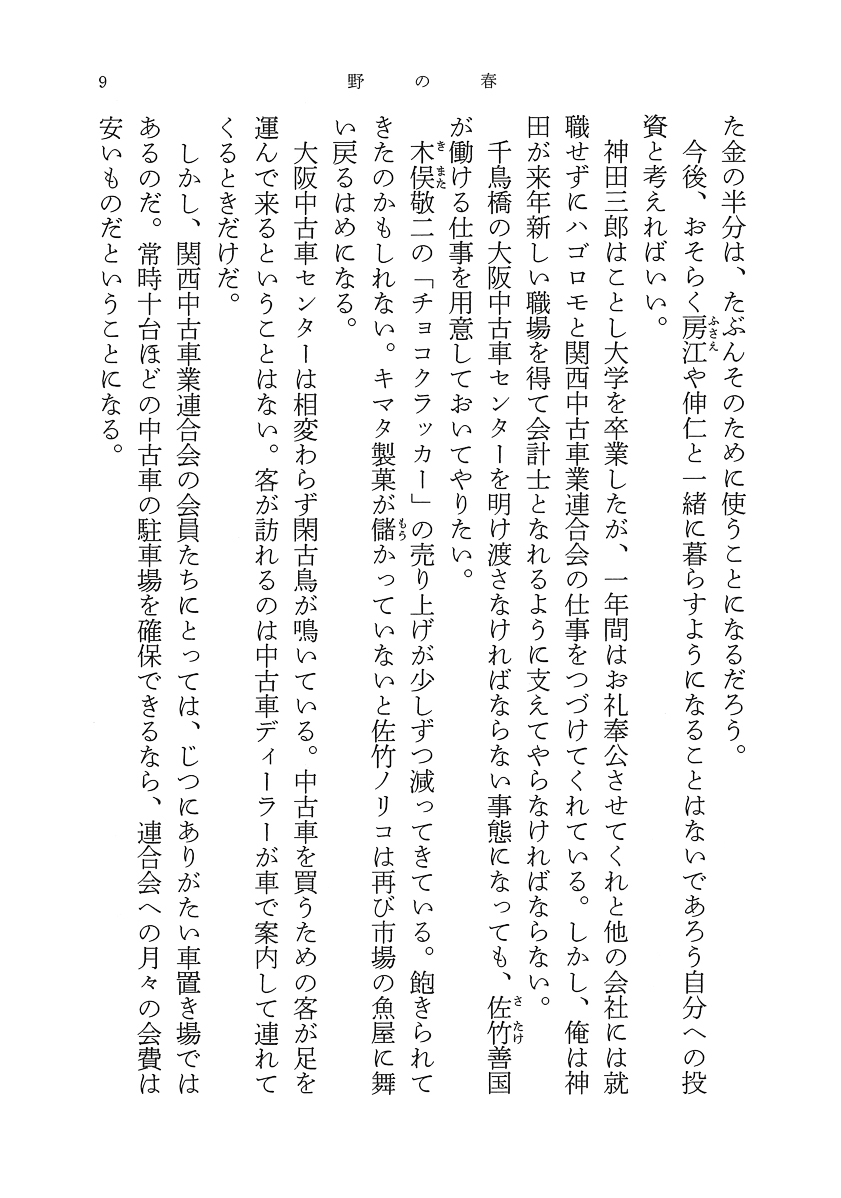解説
三十七年もの長きに渡って宮本輝氏が書き続けてきた自伝的大河小説「
私は、「流転の海」各巻を読了するたびに余韻に浸っていった。「流転の海」を手に取って、松坂家の
私の場合、「流転の海」に出会ったのは高校生の頃であった。その前に宮本氏の傑作「
真夏の気だるい日であった。
あれから時を経て、四十代になった私は一ファンであることに変わりはないが、氏に二度インタビューさせていただき、このように「流転の海」最終巻の文庫解説を書いている。こんなことが果たして人生に起こり得るのだろうか。私は今もって驚きを隠せず
そんなことは偶然でしかないと言い切る人もいるだろう。だが、私は宮本文学との初めての接触によって強烈に感応したのだ。十代の私は純粋に敏感に感応していったからこそ、宮本文学との真の出会いに成り得たのであった。
この感応力と人生の機微を解する力をさらに私の内側でじっくりと磨き上げてくれたのが、「流転の海」である。このシリーズの第一部を手に取ったのも高校生の多感な頃で、無我夢中で読み
『流転の海』第一部の舞台は大阪。敗戦から二年後の昭和二十二年、大阪駅のホームより見渡す「
「まあ見ちょれ、俺はまだひと花もふた花も咲かせてやるけん」、熊吾はそう再起を期するのであった。このあまり
「流転の海」は序盤圧倒的な強い存在感を示す熊吾が、ぐいぐい物語を引っ張ってゆく。その熊吾に青天の
早産で生まれてきたのは、七百目しかない
「流転の海」では一巻ごとに、数々の名場面がある。こんなに読者同士で語り合いたいと思える名場面を持つ小説も珍しいのではないだろうか。私は「流転の海」完結記念インタビューにて、絞りにしぼった名場面ベスト六を挙げて、宮本氏にお話をうかがったが、今回ここで取り上げるシーンは、そのインタビューと重なる部分もあれば、重ならない部分もあるだろう。ご容赦願いたい。
第一部で挙げるとすれば、「お前が
「お前に、いろんなことを教えてやる。世の中の表も裏も教えてやる。それを教えてから、わしは死ぬんじゃ。世の中にはいろんな人間がおるぞ。こっちがええときは、大将やの社長やのと言いよるが、悪うなると
それから「きれいな目をしちょる。お前は特別にきれいな目をしちょる」、「食べてしまいたいわい」という
私は「流転の海」の最新刊が出るたびに第一部から読み直していった。だから一番、一巻目を読んだ回数が多い。この解説を書くにあたっても再読していったが、今回は四十六歳になって初めての我が子を授かった境遇において、私はこの場面にあらためて触れたのであった。五十歳で子を授かった熊吾と四歳違いで、私は我が子に巡り合ったわけだが、熊吾の子を思う
伸仁の誕生をはじめ、第一部では熊吾と房江の生い立ち、二人の
「流転の海」の読者はすでにおわかりだろうが、この熊吾のセリフは物語の大きな流れの伏線となっている。だが、第一部ではほんとうに何気ない熊吾の
大阪での再起を胸に誓っていた熊吾だったが、やがて病弱に生まれてきた伸仁と同じく体調を崩しがちな房江を見て、「事業よりも、妻や子の健康のほうがはるかに大切だ」と思い至り、大阪の一等地にある松坂ビルの跡地を売り払って、郷里の南宇和に帰ることを決心するのであった。
第二部『地の星』の舞台は南宇和。昭和二十六年、熊吾が父の墓参りをしようと、四歳になった伸仁を連れて一本松村に到着する場面からはじまる。伸仁が熊吾と会話できるほど成長していることに、読者は思わず笑みが
第二部は熊吾と伊佐男との対立軸を中心にして、松坂一家の田舎暮らしの模様が語られてゆく。「
茂十は県会議員に立候補することになり、熊吾は選挙参謀を引き受けるのだった。
田舎で退屈を
第一部で熊吾を裏切った井草正之助は金沢にて結核で、和田茂十は
「俺のふるさとの使命は終わった」という熊吾のセリフが印象的である。そして「この世のありとあらゆる生き物も、事柄も、なんらかの使命によって存在しているのだと思えてきたのだった。人間だけでなく、
五十五歳の熊吾は家族を伴い、再び人間が
第三部『血脈の火』の舞台は大阪。昭和二十七年、もうすぐ小学一年生になる伸仁が、家の裏側から眺められる土佐堀川をゆくポンポン船に向かって手を振る場面からはじまる。宮本氏の出世作「泥の河」の舞台とも重なる場所である。また「きのう六歳になったばかりの、
熊吾は大阪で再び一旗揚げるべく、いくつもの商売を開始した。消防のホースを修繕する会社「テントパッチ工業株式会社」、
熊吾は、はしっこい伸仁を競馬や
一方、南宇和から熊吾の妹のタネとその子である千佐子、熊吾の母ヒサが上阪してくる。千佐子の兄の明彦は先に大阪入りして熊吾の知人宅に預けられていた。明彦は、第二部で不慮の事故で死んだ野沢政夫とタネとの子である。やがて、突然ヒサの行方がわからなくなり捜索願を出す事態になる。房江が少し眼を離した
熊吾の商売はどれもうまくいっていたが、昭和二十九年に発生した
松坂家が大阪で暮らすあいだに、
第三部の名場面は、船上生活を営む
伸仁がやくざの観音寺のケンの頼みで、ならず者たちと
「そやけど、ノブちゃんは、おとはんとおかはんに可愛がられて、しあわせや。おとはんとおかはんに可愛がられて育った子ォは、絶対に俺らみたいにはなれへんのや」――この観音寺のケンがふと漏らした「しあわせ」という言葉に、私はこの「流転の海」のテーマを鮮烈に
宮本氏に「文学のテーマとは、と問われて」というエッセイがあるが、表題のごとく問われると、〈「人間にとって、しあわせとは何か、ということではないでしょうか」〉と、氏は答えるのである。「作家として、
第四部『天の夜曲』の舞台は富山。昭和三十一年、大阪から富山へ向かう立山一号の車窓から見える猛吹雪の風景からはじまる。松坂家の三人は、大阪での暮らしに見切りをつけて、富山に新天地を求めて旅立ったのだった。大阪を離れた理由は、熊吾が経営する中華料理屋の弁当で食中毒が発生したり、きんつばが売れなくなったり、「杉松産業」の共同経営者・杉野信哉が
熊吾は、伸仁の「いつ大阪に帰るのか」という問いにこう
冒頭に自伝的大河小説と書いたが、熊吾は宮本氏の父上、房江は氏の母君、伸仁は氏ご自身というモデルを当て
やがて熊吾は高瀬の器の小ささに失望し、共同経営を
大阪で熊吾は、ヌード・ダンサーの西条あけみこと森井博美と再会。その折に博美の持っていたセルロイドのキューピー人形に
「
第四部の名場面もいろいろあるが、熊吾が一番頭を下げたくない相手でかつての部下・海老原太一に名刀・関の孫六兼元を買い取ってもらうシーンを挙げたい。海老原が大恩を忘れて、むかし人前で大恥をかかせた熊吾を散々
第五部『花の回廊』の主な舞台は兵庫県尼崎。昭和三十二年、富山の高瀬家に預けていた小学四年生の伸仁を連れ帰り、熊吾の妹タネが暮らす「貧乏の
熊吾は大阪でエアー・ブローカーを続けながら食いつなぎ、房江も家計を支えるために道頓堀川沿いにある小料理屋「お染」で働く。
伸仁は、在日朝鮮人が多く住む蘭月ビルで多様な人間と交流し、人の臨終に立ち合うという小学生にして壮絶な現場にも直面する。蘭月ビルの二階に住む、同じクラスの月村敏夫とその妹光子との出会いも、伸仁には大切であった。敏夫は給食を食べるためだけに登校し、伸仁が残したパンを敏夫が持ち帰って、光子が食べるという貧しい家庭だった。敏夫は夕刊の配達をしている。自分と妹の朝食になるたこ焼きを買うための新聞配達だった。
伸仁も敏夫と一緒に夕刊売りを体験する。房江は反対であったが、熊吾は「たったの三時間で、いろんなことを体験することじゃろう。たったの三時間で、わしら夫婦の一人息子はこの
宮本氏のエッセイ「夕刊とたこ焼き」にも、この場面が凝縮されたかたちで描かれているが、「おまえのたこ焼きと、あの子のたこ焼きとは、味が違うんやでェ」という父上の言葉が
この夕刊売りも名場面であるが、私には熊吾と伸仁が京都競馬場に行って、大穴馬券を当てるシーンが忘れられない。
「やったァ! お父ちゃん、三―四や」
「これはでかい馬券じゃぞ」
親子は手をつないで払い戻し窓口に向かい、配当の大金を受け取る。
「平然としちょれ。ぼくら親子は負けに負けて、すっからかんでございますっちゅう顔をしちょれ。スリがあちこちで目を光らせちょるけんのお」という熊吾の忠告をよそに、伸仁はどうにも嬉しさを隠し切れない表情をしてしまうのだった。
「それがお前の平然としちょるふりの顔か。目が笑うちょる。嬉しゅうてたまらんちゅう目じゃ。プロのスリには、たちどころにわかるんじゃ」と伸仁を諭す。私は、なんと「おもろい親子」なのだろうと、二人の微笑ましいやり取りに、温かい笑いが込み上げてくるのだった。競走馬の世界を舞台にした宮本氏の傑作長編『優駿』にもつながる原体験でもあろう。伸仁のモデルである宮本氏は、熊吾のモデルである父上の
第六部『慈雨の雨』、第七部『満月の道』、第八部『長流の畔』の舞台は大阪。第五部の後半から松坂一家は、柳田元雄が経営に乗り出した福島区の「シンエー・モータープール」に隣接する住居に引っ越した。「やがて巨大な城の主となるかもしれない」と熊吾が第一部で予想した通り、柳田は「シンエー・タクシー」の社長となり、熊吾の提案と助言によって大規模な駐車場経営も開始したのだった。
第六部は昭和三十四年からはじまり、伸仁は中学生になっている。伸仁は、城崎で小料理屋「ちよ熊」を営み麻衣子らと共同生活をしていた浦辺ヨネの死去を受けて、彼女の遺言であった散骨の大事な役割を
「鯉のぼり、見えたかなァ」と言う伸仁の涙声に、「見えたに決まっちょる。冬の暗がりのなかの鯉のぼりは、あいつらの心から消えんぞ。お前が振りつづけた鯉のぼりじゃ」――熊吾の言葉は、父としての限りない優しさに満ちている。人の死や動物の生や別離に真正面から向き合いながら、伸仁は人間として奥深い大事な何かを感得してゆくのであった。
余部鉄橋を歩いて散骨する際、房江は高所を恐れることなく進み思わぬ度胸を見せるが、熊吾は足がすくんでしまう。「房江、お前が先に行ってくれ。わしはお前のあとにつづくけん。これからの人生、そうしたほうがええかもしれんぞ」――
房江は「シンエー・モータープール」での新しい生活に「しあわせ」を見出しながら、どんどん輝いてゆくのである。通信教育でペン習字を習いだすこともその一つだ。学歴コンプレックスのある房江は、美しい字を書けるように学習し、知らなかった漢字も積極的に覚えてゆく。熊吾をひたすら支えてきた房江の能動的に動き出す姿は、読者にとっても胸が弾むものである。
そんな房江が熊吾に進言する。「中古車の売買を小商いから始めて少しずつ大きくしていこう」という房江の提案を熊吾が受け入れたのだった。結婚以来初めての出来事であり、二人の関係性にも変化が生じてきたようだ。
モータープールの管理人をしながら「中古車のハゴロモ」を立ち上げ再起を図る熊吾であったが、かつての部下で宿敵であった海老原太一の自殺が、また本書の生と死の陰影を深くするのである。熊吾の金を海老原が横領した証拠となる借用証書に替わる名刺を握っていた熊吾は、観音寺のケンにその名刺を手渡した。衆議院議員選挙に出馬表明していた海老原は、おそらく観音寺のケンに脅されたのだろう。熊吾は、観音寺のケンに名刺を渡すまでにも、海老原の心理を巧みに揺さぶり出方を
第七部は昭和三十六年からはじまり、高校生になった伸仁は、ついに熊吾の身長を越すまでになった。生意気な口も
これまでも熊吾は何度も社員に
会社が傾いてゆくのと同時に、第四部で男女の関係を持った森井博美と再会してしまったことも、熊吾の生命力の衰えにつながってゆく。熊吾は、博美との関係の再燃を警戒していたにもかかわらず、「お父ちゃん、私を助けて」という彼女の悲痛な訴えに耳を傾けてしまう。読者は松坂一家の不幸を招き寄せるに違いない博美の接近に、気をもむだろうが、熊吾は愛欲に嵌りこんでしまうのである。
一方、房江はペン習字の立派な修了証書をもらったり、城崎に住む麻衣子に『ちよ熊』を
麻衣子に「房江おばさんは料理の天才や」と言わしめるほど、房江の天分が花開いてゆく。房江は城崎温泉に入りながら、「半年にいちどくらいは、麻衣子の家に遊びに来て、こうやってゆっくりと露天
名場面は、熊吾と伸仁が真正面から組み合うシーンである。房江の飲酒癖に怒った熊吾を制した伸仁は、一升
熊吾は顔を
第八部は昭和三十八年からはじまり、熊吾は、新たに「大阪中古車センター」を開業させる。だが、千鳥橋のその売り場まで直接客がやって来ることは少なかった。「中古車のハゴロモ」も「松坂板金塗装」もだんだん左前になっていく。松坂板金塗装を閉めるつもりでいた熊吾であったが、「柳田元雄のゴルフ場建設のために銀行から引き抜かれた男」であった東尾修造が柳田の会社を退職後、「私に松坂板金塗装という会社を大きくするという新しい役目を与えてくれませんか」と、熊吾に話を持ち掛ける。東尾に松坂板金塗装を売った熊吾だったが、間もなく東尾の
さらに第七部で再会した森井博美との腐れ縁を断ち切れなかった熊吾は、
妻にも息子にも口をきいてもらえなくなった熊吾は自身の肉体の衰えも痛感するようになった。加齢とともに進行する糖尿病が原因で、次々に歯を抜かざるを得なくなる。熊吾の生気が衰えてゆくと同時に、事業も行き詰ってゆくのである。一方、柳田元雄はシンエー・タクシーの経営をやめて、彼の夢であるゴルフ場経営に乗り出してゆく。熊吾の衰退と柳田の躍進は非常に対比的だ。「流転の海」を企業小説としての観点から眺めていくと、熊吾の経営方針と柳田のそれとは真逆のようであり、つぶさに比較しながら読み進めてみてもおもしろいであろう。
熊吾の浮気を知ってからの房江は、酒量が増して
この自殺未遂を機に、房江の意識は転換される。「私は一生のうちで二回誕生日を持った。だから私は変わらなければならない。二度の生を授かったのだから、一度目の生と同じ生を生きてはならない」と決意する。また、「伸仁が社会へ出るまで、私が働くことだ。モータープールでの仕事を
名場面は、房江と伸仁が城崎大橋の真ん中で満月を仰ぐシーンである。生まれ変わった房江は、第七部『満月の道』で見上げた彼女とは違い、生きながらにして転生し本来の強さを
その後、房江は生まれて初めて履歴書を書いて、「多幸クラブ」というホテルの従業員食堂の仕事の面接を受け採用される。「私に運が廻ってきた」と房江は嬉しくなる。「多幸クラブ」というホテル名も、「多幸多福」につながる房江の明るい行く末を暗示するようだ。
第九部『野の春』の舞台は引き続き大阪である。昭和四十一年からはじまり、十九歳の伸仁は大学生になった。
熊吾はもうすぐ二十歳になる伸仁に対して「父親としての責任は果たした」と思う。だが、「大将」としての責任はまだあると考えた。森井博美が一人で生きていけるように、ハゴロモの社員・神田三郎が会計士になれるように、大阪中古車センターを守衛する佐竹
房江は自殺未遂以降、活力に溢れていた。多幸クラブの正社員となって、料理の才能を社員食堂でいかんなく発揮する。熊吾の妹タネを新たに社員食堂の
伸仁は大学でテニス部に入部し、そのコート作りからはじめた。夏の合宿に行っては、真っ黒に日焼けして帰ってくる。十八歳のときに隠れてアルバイトをしていた、ストリップ劇場の照明係の話を伸仁が大人びた口調で、時に熊吾に似た話しぶりで房江に
房江は、誓いを果たした熊吾にもプレゼントを用意する。それは帽子がよく似合う熊吾への上等な鳥打帽であった。
「ノブが二十歳になるまで生きてくれはったお祝い。お父ちゃん、誓いを果たしはったねえ。おめでとう」と熊吾を心からねぎらい讃えると、熊吾は「房江も伸仁も
誕生日の席では、第二部の舞台でもある南宇和での家族の思い出話にも花が咲く。伸仁が野壺に落ちたことや房江が
房江は、熊吾が「巨大な土俵」と名づけた一本松村の田園風景を思い起こす。それはれんげの花や菜の花が咲き乱れる春の野の光景であった。「お父ちゃん、私、春真っ盛りの一本松に行きたいわ。三人で一度は行っとかなあかんわ。ノブにふるさとを見せておかなあかんわ」と、熊吾に提案する。熊吾が伸仁は神戸の
この二人の会話はさりげないようでいて、重要な場面である。私は宮本氏へのインタビュー時にもお話ししたが、最終巻を読み終えたあと、第一部に帰って読みはじめると、第九部で死んだはずの熊吾が再び立ち上がってきて、颯爽と闇市を
伸仁に対して、思わぬ冷酷なことを言ってしまった熊吾は謝りたいと思っていたが、それが果たせぬままに
多幸クラブで仕事をしている房江は、愛人の森井博美に熊吾の看病を助けてもらいながら、夫が入院している病院に通った。やがて、熊吾は失語症に陥る。そんな言葉も出ない状態になった熊吾を、博美は裏切る。熊吾の隣のベッドの入院患者と関係を持ってしまうのである。それに感づいた熊吾が、不自由な口で懸命に「サンカク」「オロカ」と房江に伝える場面は、人間の宿業ともいうべき
見舞いから去った房江を恋しがって熊吾は病室で暴れ、
狭山精神病院では患者らの凄まじい光景を二人は
四月十一日、午前十時四十五分、熊吾はこの世を去った。
その後の二人の会話は熊吾が臨終を迎えたにもかかわらず、どこかユーモラスだ。この場にこの
「なんと穏やかな顔だろう。微笑んでいるようだ。私と伸仁を見て安心したのだ。いや、そのせいではない。誓いを果たして死んだからだ」と、房江は熊吾の死に顔を見つめるのであった。
熊吾は「お前が二十歳になるまでは絶対に死なん」という誓いを見事に果たして亡くなったのだ。私は思う。熊吾は伸仁を二十歳まで見守り育てるという「使命」を全うするための「宿命」のなかにいたのだと。その熊吾の宿命が死を以て閉じたのである。
春の日の、この病院の桜が満開のときに熊吾は亡くなり、房江は「桜の花が松坂熊吾を迎えにきてくれたんやなあ」と、伸仁に語りかける。私はこの時ふと、西行の一首「願はくは花のしたにて春死なむその
熊吾ならこの病院の満開の桜を眺めて、なんと言うだろうと私は思いを馳せた。この西行の花の一首を諳んじるかもしれないし、西行を尊崇して旅に出た芭蕉の一句「さまざまの事おもひ出す桜かな」を呟くかもしれないとも思った。房江と伸仁と一緒に過ごした、さまざまな人生の情景を思い出しつつ、病院の桜を静かに眺めたことであろう。
熊吾の病室の窓外には、穏やかな春の風景が広がっている。南宇和の一本松村の大きさにはかなわないが、どこか熊吾の故郷の情景が重なって見える。『野の春』というタイトルは、熊吾が息を引き取った河内の春景色であると同時に、熊吾の郷里・南宇和の「巨大な土俵」の春景色でもあるのだ。熊吾の魂は、れんげの花や菜の花や桜が咲き誇る一本松村の春へと還っていったのであろう。かつてやんちゃ
熊吾の葬儀に集まったのは、人生において彼に助けられた善意の人ばかりである。心根の清い人ばかりだ。熊吾の「きょうは、いばってはいけない日」に際して、そんな近しい人々が寄り集まってくれた。「
父である熊吾の嵐のごとき激動の人生に巻き込まれながら、母の房江と息子の伸仁はこれまで生き抜いてきた。この長大な物語は社会的事件や事象や風俗をクロニクル的に織り込みながら、戦争で傷ついた人々としのぎを削り合い、時に優しくいたわり合いつつ、戦中戦後を力いっぱい生きてきた松坂熊吾という「
「『流転の海』第二部について」という氏のエッセイのなかで、「『お父ちゃん、いつか俺が
(令和三年二月、俳人)