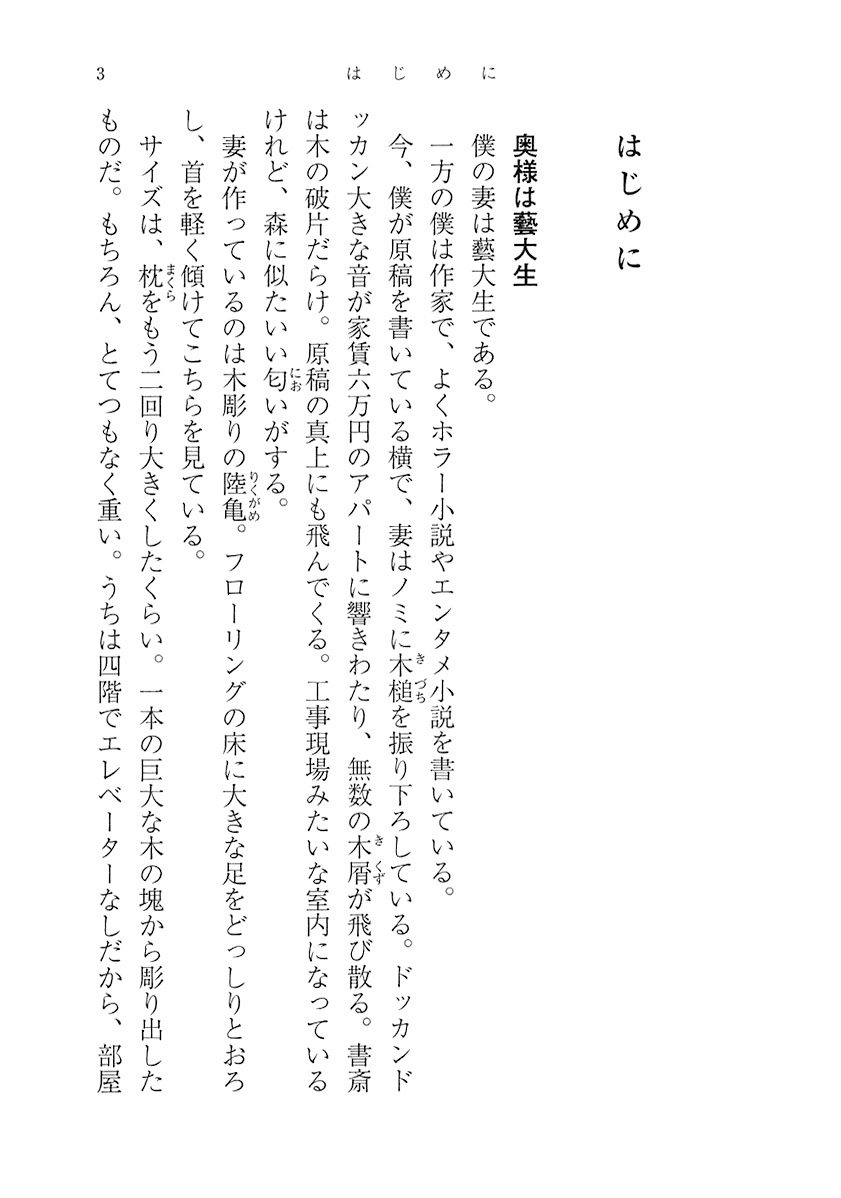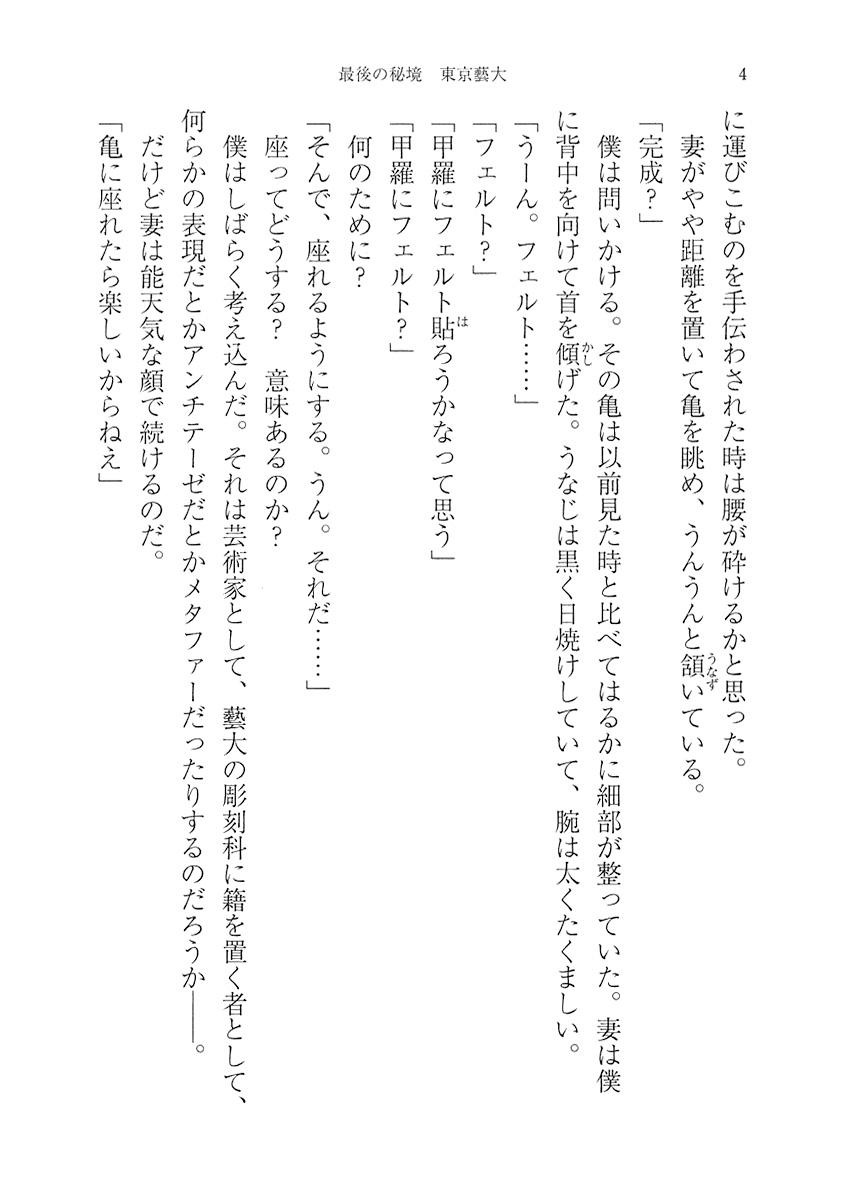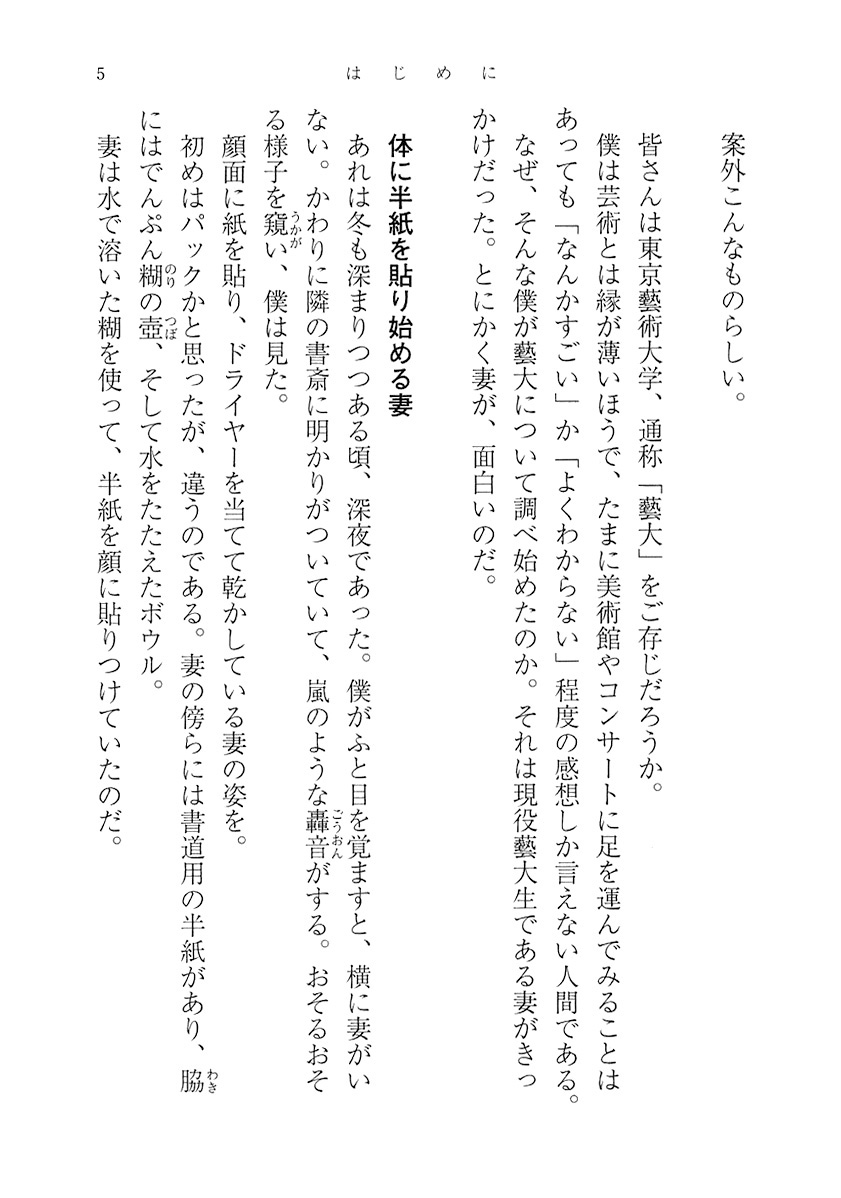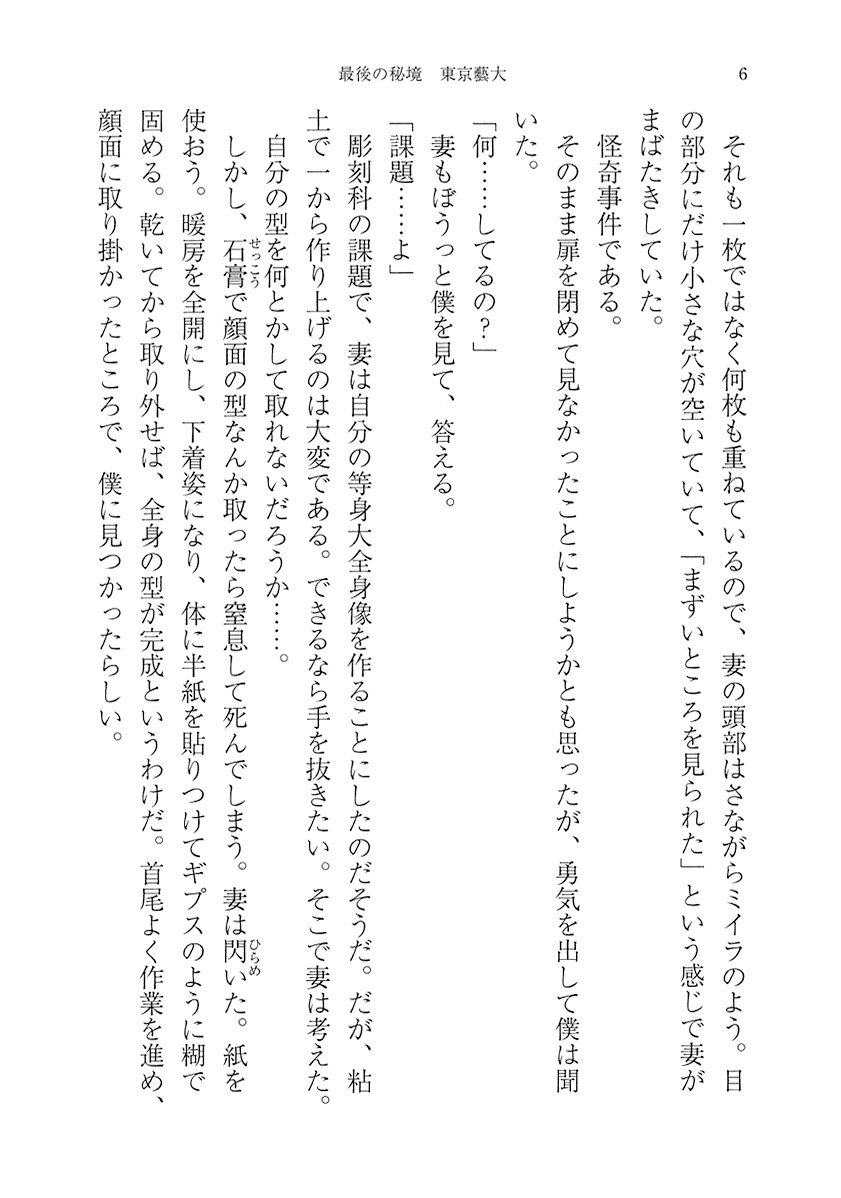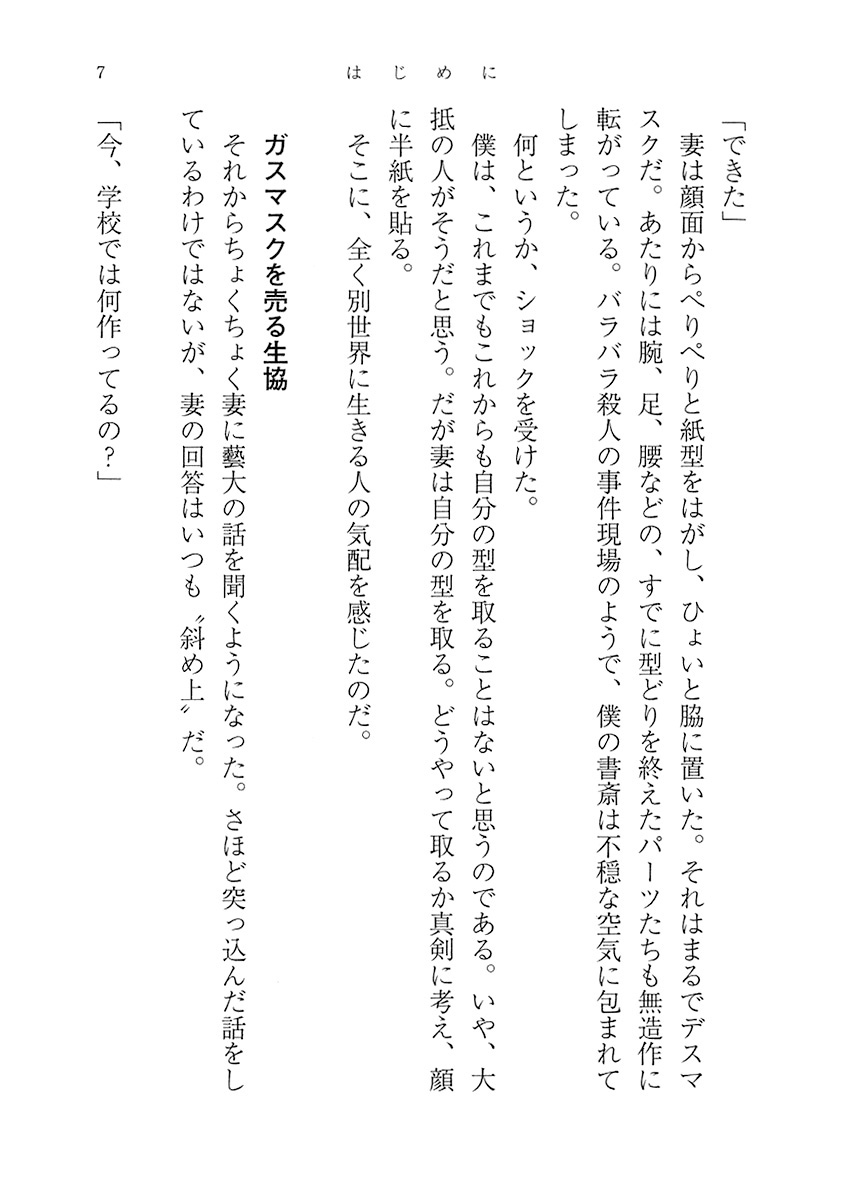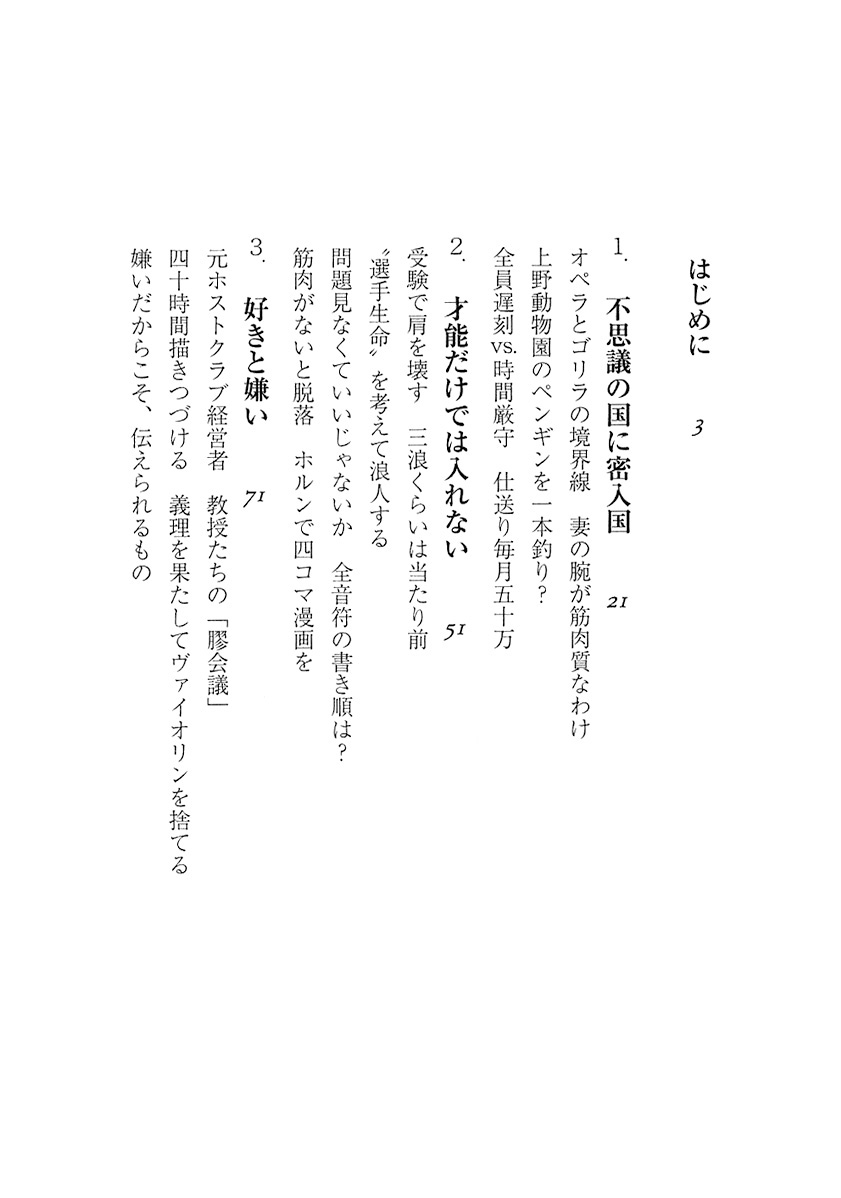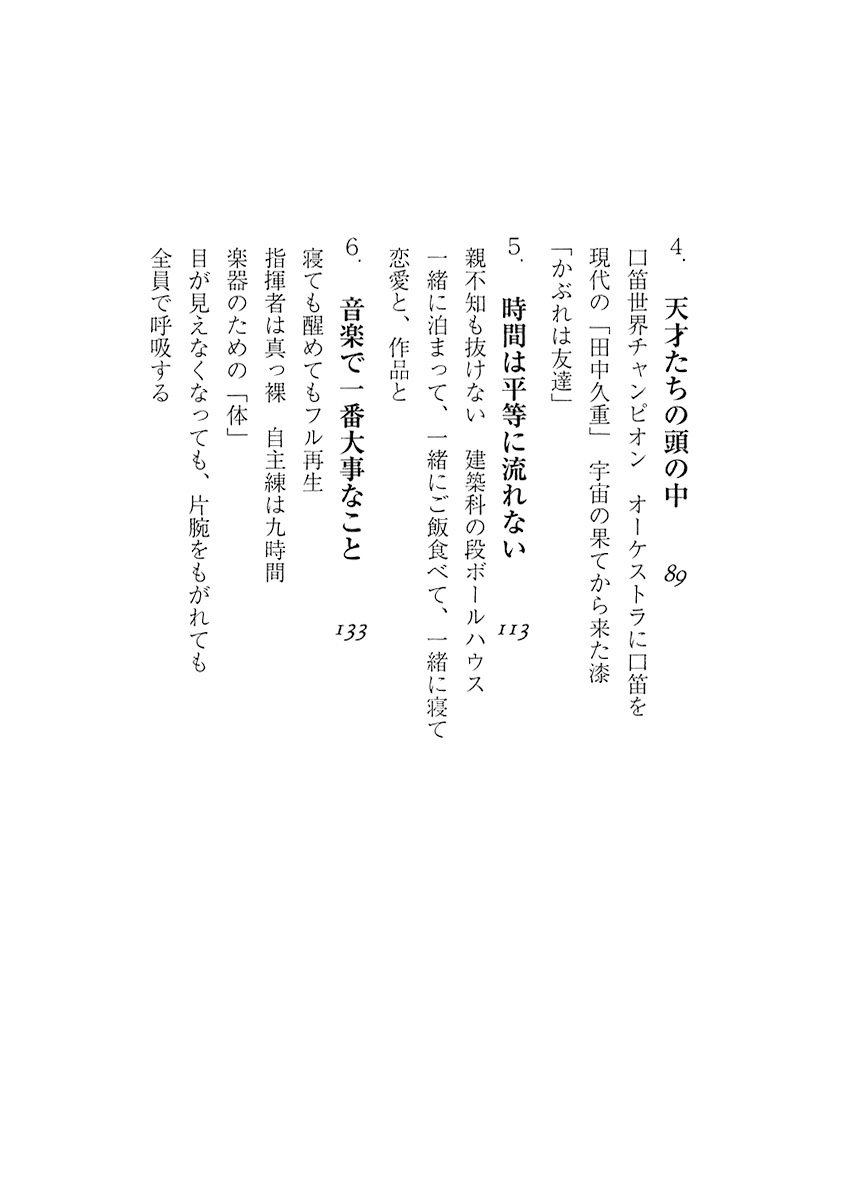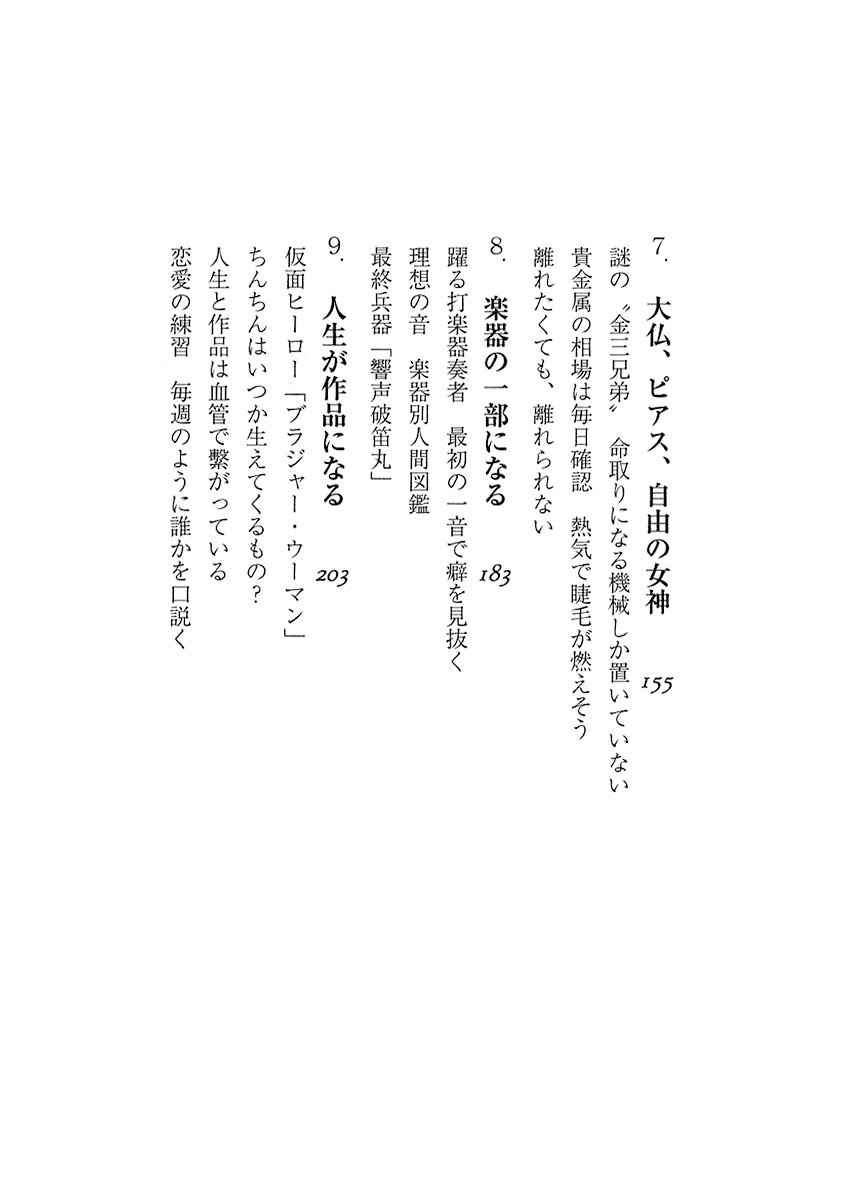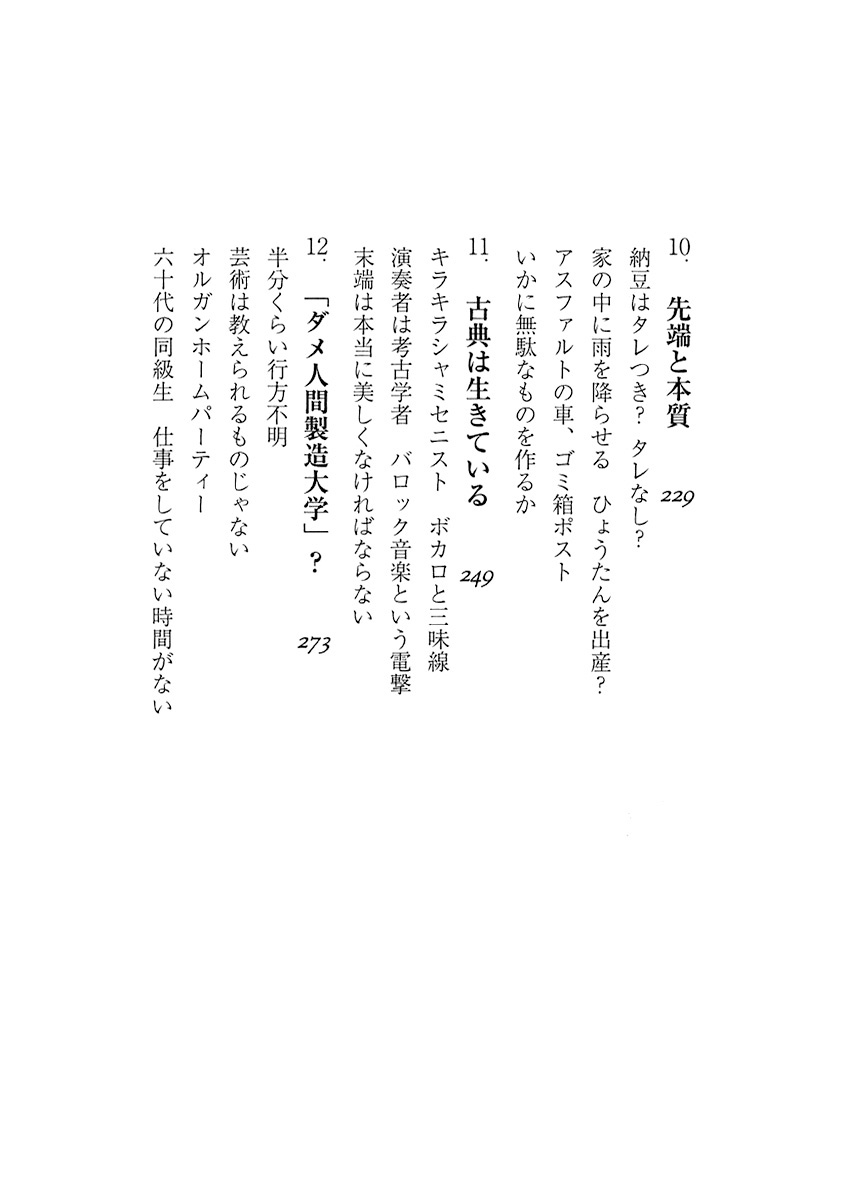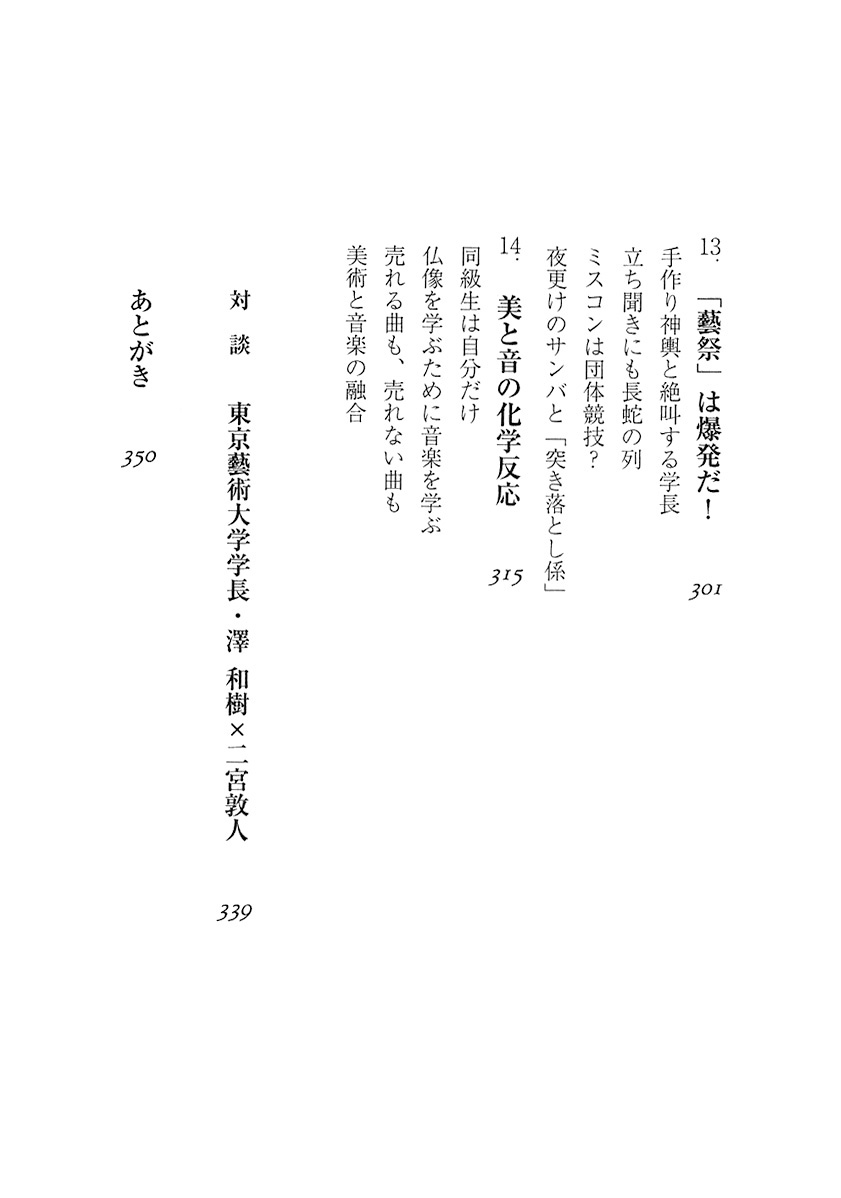はじめに
奥様は藝大生
僕の妻は藝大生である。
一方の僕は作家で、よくホラー小説やエンタメ小説を書いている。
今、僕が原稿を書いている横で、妻はノミに木槌を振り下ろしている。ドッカンドッカン大きな音が家賃六万円のアパートに響きわたり、無数の木屑が飛び散る。書斎は木の破片だらけ。原稿の真上にも飛んでくる。工事現場みたいな室内になっているけれど、森に似たいい匂いがする。
妻が作っているのは木彫りの陸亀。フローリングの床に大きな足をどっしりとおろし、首を軽く傾けてこちらを見ている。
サイズは、枕をもう二回り大きくしたくらい。一本の巨大な木の塊から彫り出したものだ。もちろん、とてつもなく重い。うちは四階でエレベーターなしだから、部屋に運びこむのを手伝わされた時は腰が砕けるかと思った。
妻がやや距離を置いて亀を眺め、うんうんと頷いている。
「完成?」
僕は問いかける。その亀は以前見た時と比べてはるかに細部が整っていた。妻は僕に背中を向けて首を傾げた。うなじは黒く日焼けしていて、腕は太くたくましい。
「うーん。フェルト……」
「フェルト?」
「甲羅にフェルト貼ろうかなって思う」
「甲羅にフェルト?」
何のために?
「そんで、座れるようにする。うん。それだ……」
座ってどうする? 意味あるのか?
僕はしばらく考え込んだ。それは芸術家として、藝大の彫刻科に籍を置く者として、何らかの表現だとかアンチテーゼだとかメタファーだったりするのだろうか――。
だけど妻は能天気な顔で続けるのだ。
「亀に座れたら楽しいからねえ」
案外こんなものらしい。
皆さんは東京藝術大学、通称「藝大」をご存じだろうか。
僕は芸術とは縁が薄いほうで、たまに美術館やコンサートに足を運んでみることはあっても「なんかすごい」か「よくわからない」程度の感想しか言えない人間である。
なぜ、そんな僕が藝大について調べ始めたのか。それは現役藝大生である妻がきっかけだった。とにかく妻が、面白いのだ。
体に半紙を貼り始める妻
あれは冬も深まりつつある頃、深夜であった。僕がふと目を覚ますと、横に妻がいない。かわりに隣の書斎に明かりがついていて、嵐のような轟音がする。おそるおそる様子を窺い、僕は見た。
顔面に紙を貼り、ドライヤーを当てて乾かしている妻の姿を。
初めはパックかと思ったが、違うのである。妻の傍らには書道用の半紙があり、脇にはでんぷん糊の壺、そして水をたたえたボウル。
妻は水で溶いた糊を使って、半紙を顔に貼りつけていたのだ。
それも一枚ではなく何枚も重ねているので、妻の頭部はさながらミイラのよう。目の部分にだけ小さな穴が空いていて、「まずいところを見られた」という感じで妻がまばたきしていた。
怪奇事件である。
そのまま扉を閉めて見なかったことにしようかとも思ったが、勇気を出して僕は聞いた。
「何……してるの?」
妻もぼうっと僕を見て、答える。
「課題……よ」
彫刻科の課題で、妻は自分の等身大全身像を作ることにしたのだそうだ。だが、粘土で一から作り上げるのは大変である。できるなら手を抜きたい。そこで妻は考えた。
自分の型を何とかして取れないだろうか……。
しかし、石膏で顔面の型なんか取ったら窒息して死んでしまう。妻は閃いた。紙を使おう。暖房を全開にし、下着姿になり、体に半紙を貼りつけてギプスのように糊で固める。乾いてから取り外せば、全身の型が完成というわけだ。首尾よく作業を進め、顔面に取り掛かったところで、僕に見つかったらしい。
「できた」
妻は顔面からぺりぺりと紙型をはがし、ひょいと脇に置いた。それはまるでデスマスクだ。あたりには腕、足、腰などの、すでに型どりを終えたパーツたちも無造作に転がっている。バラバラ殺人の事件現場のようで、僕の書斎は不穏な空気に包まれてしまった。
何というか、ショックを受けた。
僕は、これまでもこれからも自分の型を取ることはないと思うのである。いや、大抵の人がそうだと思う。だが妻は自分の型を取る。どうやって取るか真剣に考え、顔に半紙を貼る。
そこに、全く別世界に生きる人の気配を感じたのだ。
ガスマスクを売る生協
それからちょくちょく妻に藝大の話を聞くようになった。さほど突っ込んだ話をしているわけではないが、妻の回答はいつも“斜め上”だ。
「今、学校では何作ってるの?」
「ノミ」
「え? ……ノミって、虫の?」
「道具のノミ」
木や石を削るために使う、あのノミである。少なくとも彫刻を作っていると思っていたのだが……。まずは彫刻を作るための道具を作るそうだ。元となる既製品の先端を叩き、形を整え、焼きを入れるなどして、自分用のノミを作り上げる。道具はどこかで購入してきて終わり、ではないらしい。
「今日は随分早く行くんだね」
妻は玄関で靴ひもを結んでいる。
「うん。入試が近いからみんなで教室の掃除をするんだ」
入学試験が行われる教室には、制作中の彫刻や、完成したまま放置されている作品が無数に転がっているので、それらを外に出さなくてはならないという。
「それって、物凄い力仕事じゃない?」
「そうね。でも、みんなでやると早いよ」
聞けば、みな何十キロもある作品をバンバン外に運び出していくらしい。「こんなの持てなーい」などと口にする女子は皆無。なんと逞しいことか。
「大変だろうね。大きい作品もあるだろうし……」
「そういえば、先輩の作品にでっかい馬があったんだけどね、それは外に出そうとしても出せなかった。大きすぎて入口でつっかえちゃって」
「……え? それ、どうしたの」
「真っ二つに切断して出したよ」
豪快すぎる。それにしても、作る前に気づかないのだろうか。
「何か準備してるみたいだけど、旅行にでも行くの?」
妻はリュックサックにせっせと物を詰めている。
「明日からコビケンなんだ」
「コビケンって?」
「古美術研究旅行。二週間、奈良の宿舎に泊まって、京都や奈良の仏像を見学するの」
「なるほど、お勉強か。大変そうだね……」
「藝大生だと特別に、普通は入れないお寺の結界の内に入れたり、一般公開されていない仏像も見られるんだって」
「え……」
「それに教授やお寺の人の解説つきだから、旅行が終わる頃には仏像を見るだけでどの時代のどの様式かとか、パッとわかるようになってるらしいよ」
「なにそれ僕も行きたい」
研究旅行一つとっても、一味違うのである。
こんなこともあった。
ある日、僕は台所で缶詰めを見つけた。
「あれ、ツナ缶買ったの?」
パッと見はツナ缶に思えたのだが、よく見ると覚えのないパッケージである。蓋は開いていて、白い繊維質のものがぎっしりと詰まっていた。指で押してみると固い。一体なんだ、これは?
本を読んでいた妻がこちらを見て言った。
「あ、それガスマスクよ」
「ガスマスク?」
「そ」
ガスマスクを思い浮かべてほしい。口の先に丸いものがついているのがわかるだろうか。このツナ缶はあの丸い部分だそうだ。フィルターという毒を濾過するためのパーツで、一定期間で交換する。つまり僕が今、手にしているのはそのフィルターであり、中にはたっぷり濾し取られた毒が詰まっているわけだ。
これはまずい。
思わず手を離すと、ツナ缶状のフィルターは音を立てて落ち、かすかな埃が舞った。
「まだほとんど使ってないから大丈夫だよー」
妻は笑ってそれを拾い、「変な感触だよね」とフィルターを指でぷにぷに押す。やめろ。毒で死ぬぞ。そもそも台所に置かないでくれ。
「樹脂加工の授業で使うんだよ」
妻はのほほんと言ってのける。彫刻科では木や金属、粘土の他に樹脂を扱う授業がある。樹脂加工の際には有毒ガスが発生するので、学生はみなガスマスクを購入するそうだ。
「こういうの、どこで買うの? やっぱりそういう専門店があるの?」
妻は首を傾げた。
「ううん。生協」
藝大の生協にはガスマスクが売っているのだ!
聞けば他にも指揮棒などが売られているという。指揮棒が消耗品かどうかすら、気にしたことがなかった。
何もかもが僕にとっては新鮮で、いちいち驚いてしまう。しかし妻はといえば、きょとんとしている。「それって、そんなに珍しいことなの?」と言わんばかり。この人の通う大学は、思った以上に謎と秘密に溢れているようだ。
こうして僕は、秘境・藝大について調べ始めたのである。
1.不思議の国に密入国
立ち並ぶ彫刻とホームレスの皆さま
藝大のメインキャンパスは上野にある。
上野動物園。国立科学博物館。東京文化会館。国立西洋美術館。様々な文化的施設が立ち並ぶ街だ。広場では大道芸人が曲芸をしていたり、錦鯉や盆栽の展示販売会が行われていたりする。アメヤ横丁というパワフルな商店街もあれば、一日中エロ映画を流しているオークラ劇場という怪しい映画館もある。
駅から広場を抜けて歩いていくと、芝生の中に彫刻がたくさん並んでいるのに気がつく。藝大の学生や教授の作品がさりげなく飾られているのだ。もっとよく目をこらすと、その合間にホームレスが寝転んでいたり、何か食べていたりもする。
妻は言っていた。
「キャンパス内にもホームレスさんの家があるよ。取手キャンパス(茨城県取手市)には普通にあった」
僕は聞いた。
「え? それって段ボールハウスってことだよね。守衛さんに追い出されたりしないの?」
「追い出されないみたいだね」
「…………」
「たまに、お菓子を置きっ放しにしてるといくつか取られてる」
まるで野リスのような扱いである。
訪れる前から、藝大の懐の深さを感じざるを得ない。
オペラとゴリラの境界線
藝大に近づくにつれ喧騒が遠ざかり、緑が増えていく。赤レンガの塀の中、校舎が現れた。キャンパスは二つに分かれていて、道路を挟んでそれぞれの校門が向かい合っている。
上野駅を背にして左側は美術学部、“美校”と呼ばれている。絵画、彫刻、工芸、建築……いわゆる美術に関する学科が、こちらのキャンパスにある。
右側は音楽学部、“音校”だ。ヴァイオリンやピアノ、あるいは声楽など、いわゆる音楽に関する学科がこちらのキャンパス。
音楽と美術の両方を擁しているのが藝大の特徴の一つでもある。
実際にその境界線に立ってみると、不思議な感覚を覚える。
行きかう人の見た目が、左右で全然違うのだ。
音校に入っていく男性は爽やかな短髪にカジュアルなジャケット、たまにスーツ姿。女性はさらりとした黒髪をなびかせていたり、抜けるような白いワンピースにハイヒールだったりする。大きな楽器ケースを担いでいる学生もちらほら。みな姿勢が良く表情が明るいため、芸能人のごとくオーラを放っている。バッハのような髪型の中年男性も見かけた。どうやら教授のようだが……。
対して美校の学生たちは……ポニーテールの、髪留め周りだけ髪をピンクに染めている女性。真っ赤な唇、巨大な貝のイヤリング。モヒカン男。蛍光色のズボン。自己表現の意識をびりびりと感じさせる学生がいる一方で、まるで外見に気を遣っていないように見える学生も多い。ぼさぼさ頭で上下ジャージだったり、変なプリントがされたTシャツだったりが通り過ぎる。数人に一人は、眉間に皺をよせて俯き、影を背負ったような顔をしている。
数分も眺めていれば、歩いてくる学生が音校と美校のどちらに入っていくか、わかるようになってくる。
音校からはかすかに楽器の音が聞こえてくる。駅に向かう二人組の男性が、何気なくオペラの一節を歌っていた。軽く口ずさむ、という雰囲気なのだが、よく通る美声で音程も完璧。そして何気なくハモっていて、思わず聞きほれてしまう。声楽科に所属する方だろうか。
対して、美校からはゴリラのドラミングが聞こえてきた。上野動物園に所属する方だろう。
美校――ものを作る――
まず、美校を覗いてみることにした。案内役は美校の中でも特に外見に気を遣っていないだろう人物の一人、妻だ。今日の姿は上下抹茶色のジャージ。木屑があちこちにくっついているばかりか、頬には白く固まった石膏までつけている。言うまでもなく、化粧はしていない。
「どうせ汚れるしねー」
それが妻の言い分だ。
彼女は予備校時代「眉毛繋がり」で有名だったそうだ。木炭デッサンの際、集中するあまり額の汗を素手で拭う。すると手の墨が顔について、眉毛が繋がってしまう。しばしば髭が生えたりもする。もちろん、それを洗い流さずに平気で過ごしているのは妻くらいなのだが……。
美校の校門をくぐる時、鉢巻をしてツナギに身を包み、全身泥だらけのおじさん集団とすれ違った。美校では校舎の補修工事か何かをしているらしい。時間帯から言って、ちょうど昼休憩というところだろう。熟練の肉体労働者とおぼしき彼らからは、働く男の汗の匂いがした……と、その時、妻が言った。
「あれが彫刻科の教授、あれが准教授、あれが助手さんだよ」
僕は思わず二度見した。どれだけ目をこらしても、やはり工事現場の方々にしか見えない。
そう、美校では体の汚れは避けて通れない。
油絵では大きなカンバスに向き合い、筆で塗りたくる。彫刻では巨大な木や石を削る。絵の具まみれ、あるいは泥まみれになる世界なのだ。最低でもエプロン、大抵はツナギやジャージが彼らの制服。炎天下で石にノミを叩きつけていれば汗もかく。だから鉢巻やタオルを頭に巻くし、日焼けもするわけだ。
美術は肉体労働なのである。
美校の中は、いい意味で荒っぽい。
守衛所の前には巨大なトラックが止まっていた。宅配便のトラックなのだが、よく街で見かけるタイプではない。サイズはタンクローリーほどもあり、荷台が横に跳ね上がる。中には引っ越しと見まがうほどの量の荷物が詰め込まれていて、学生が駆け寄って来ては宅配便のお兄さんと一緒に運び出している。おそらく美術用の材料か、作品だろう。男子学生も女子学生も、力を合わせて大きな荷物を運んでいく。
少し歩いた先には石だの木だのが大量に転がっている。「三年 野村」などと名前だけ書かれて、野ざらしになっているのだ。材料置き場なのだろう。遠目からは粗大ゴミ置き場に見えるが……。
不思議なのは、彫像がやたらと多いことだ。茂みの中とか建物の陰とか、とにかく所狭しと林立している。
「なんかいっぱいあるけど、誰なのかよくわからないんだよね」
妻が言うように、一般的な大学と比べても明らかに多すぎるため、ありがたみがない。
他にも学生の作品なのだろう、絵や彫刻などがそのへんにぽいと置かれてあり、さながら美術館の倉庫のようだ。
中には作りかけの彫刻もある。大理石から半分だけ人間が現れていたりして、面白い。片側には躍動感が漲っているのに、反対側はまだ「ただの石」なのだ。そこでは人間の手によって今まさに芸術が生み出されつつあり、完成品とはまた別の感動があった。
教授陣が制作中の作品も、あっさりとそのへんに置かれている。こんな大きくて重いものを盗んでいく奴もいないのだろうけれど、おおらかなものだなあ。
妻の腕が筋肉質なわけ
彫刻棟の中に入ってみよう。
そこはまるで工場だった。天井からは二トンの物体を持ち上げられる強力なクレーンが吊り下げられ、巨大な加工機械が並んでいる。大きな木を切る機械、石を削る機械と、なんでもありだ。部屋は広く天井も高く、小さめの体育館ほどの空間がある。教授も、四年生も、一年生も、みんな一緒に肩を並べてここで彫刻を作るそうだ。時々、教授たちが回ってきてアドバイスをしてくれたり、あるいは自分から教授に質問しにいくこともある。
棚にはノコギリだとか、ペンキ缶だとか、いろいろな道具が並んでいる。大小様々なサイズのチェーンソーもあった。
「このチェーンソー、持ってみてもいい?」
「いいよ」
僕は一番大きい奴を持ち上げてみ……持ち上げてみ……持ち上がらない! 大の男が腰を入れても、簡単には持ち上がらない。その重量たるや、六十キロ。大人ひとりを抱えて持つようなものだ。妻の腕が筋肉質な理由がよくわかった。
「これじゃホラー映画みたいに振り回すのは無理だね」
少なくとも常人には。妻が頷く。
「実際には重みに従って下ろして、縦に切るように使うんだよ」
なるほど。なお、傍にはハンドクリーナー程度の大きさのものもあった。これなら僕でも振り回せる。ホラー小説の敵役にはこっちを持たせよう。
工場っぽい外見は、どこまでも続く。
例えば金属加工を行う部屋では、金属を裁断する機械や、金属を削る機械が置かれている。八人掛けのテーブルほどもある機械で、ばっちんばっちんと鉄板を切っていくのだ。脇では面をつけて火花を散らしながら、溶接をしている人の姿も見える。鋭い音が響き渡っている。
謎の実験装置のようなものが、何台も並んでいる。宇宙船の一部のような、金属で覆われた四角い箱型。扉は固く閉ざされていて、バルブが据え付けられている。これは陶芸で使う窯だった。点灯しているオレンジのランプは、燃焼中であることを示しているそうだ。たまに中で爆発が起きるらしい。爆発って……。
版画研究室を覗くと、部屋の中にまるで喫煙所のように区切られ、密閉されたスペースがある。銅版画のために作られた場所だ。銅板に薬品をかけ、化学反応を起こして絵を描くのである。この際に有毒ガスが発生するため、隔離されているというわけだ。これもなかなか怖い。
染織を行っている教室には、銀色の壁で覆われたシャワー室のようなものがある。これはスチームルーム。強烈な蒸気を吹きかけて、染色するための設備だ。お隣にはぼこぼこ泡立っている大釜。聞くと、水酸化ナトリウム溶液を沸騰させているらしい。とても危ない。その脇には小さ目のプールが三つ。布を抱え、大釜とプールを行ったり来たりしている女性の姿が見える。布を薬品と冷水に交互に漬けこむことによって行う染色があるそうだ。あたりには様々な色合いの布が洗濯物のようにかけられていて、棚には薬品の瓶がずらり。硫酸だとか塩酸だとか、劇薬の名前もある。
建築科には構造実験室という部屋があり、そこでは破壊実験を行っている。物体に圧力をかけたり、引っ張ったりする機械が置かれていて、これで素材の強度を計り、建築の設計に応用するそうだ。稼動中は轟音が響く。
僕はいつのまにか、美術の裏側に入り込んでいた。
確かに茶碗を作るには巨大な窯が必要だし、金属を曲げるには特別な機械がいる。日常の道具は、こうした異世界からやってきていたらしい。ものを作る、とはこういうことだったのか……。そりゃあガスマスクくらい、生協で売るはずだ。
上野動物園のペンギンを一本釣り?
ところで美校の敷地は、上野動物園とフェンス一つで接している。そのためか、動物園絡みの伝説をいくつか聞いた。
いわく「学生が絵画棟からペンギンを一本釣りした」「鹿を盗んできて焼いて食べた」「酔った勢いでペンギンをさらい、冷蔵庫で飼おうとしたが死なせてしまった」「藝大生は無料で上野動物園に入れたが、悪行のためにダメになった。上野の博物館や美術館は学生証を見せれば無料で入れるのに、動物園が例外なのはこのため」……。
真相を確認したところ、どうやらこういう顛末らしい。
ある日、上野動物園でペンギンが一頭死んでしまった。一人の学生が死体を貰い受け、一時的に染織専攻の冷蔵庫に保存した。それを知らない教授が冷蔵庫を開け、大騒ぎになった……。
当時はフェンスが低く、大らかな時代でもあったため、藝大生は境界線を乗り越えて動物園に入り、動物たちをデッサンしていたそうだ。それが現在は難しくなったことと、ペンギン冷蔵庫事件とが合わさって、伝説が形成されたと思われる。
ある美校の学生からは、こんな話も。
「動物園って『ライオン』とか『トラ』とか立札があるじゃないですか。工芸科の学生が『ホモ・サピエンス』の札をそっくりに作って、藝大との間のフェンスにかけたそうです」
もちろん上野動物園から抗議を受け、札は撤去された。
音校――舞台に立つ――
美校はどこでも入り放題で、誰でもウェルカムな空気があった。例えば金属加工を行っている部屋の前でうろうろしていると、髭を生やした准教授が話しかけてきた。怒られるのかと思いきや。
「見学かい? 今、鉄を切ってるから見てく?」
「いいんですか?」
「うん」
こんな感じなのである。機械などを見せてもらいながらしばらく雑談した。
「鉄はいいよねえ」
「鉄の何がいいんですか?」
「硬いところだね」
「硬いところ……ですかあ」
「うん、硬いところだねえ」
お願いすればどこまでも見学させてくれそうであった。
だが、音校は違った。
まず目に入るのは、入り口のセキュリティロック。学生証をカードリーダーにかざさなければ入ることすらできない。あちこちに「不審者注意」などと張り紙もされている。不審者の一人である僕は、びくびくしながら妻について歩く。
ある音校卒業生が教えてくれた。
「防犯意識は高いですよ。女の子に、ストーカーっぽいおじさんがついてきたりするんです。それから楽器には高価なものが多いですから」
「やっぱり盗難を警戒するんですね」
「そうですね。昔、ピアノをまるまる一台盗まれたことがあったそうです」
「えっ、ピアノをまるまる一台?」
「業者の振りをして泥棒が入ってきて、『運び出しますんでー』と。みんな、そういうものかと思ったらしく……」
「豪快な泥棒ですね」
「それから、これは滅多にないことですけれど。上手な女の子のヴァイオリンが、壊されるという事件があったんです。犯人はわからないままですけれど、誰かに嫉妬されたんじゃないかって。そういうことが起きてもおかしくない雰囲気というのは、あります」
校舎内で目立つのは、いくつも並んでいる小さな個室。ビジネスホテルのように、扉がずらりと廊下の両側に並んでいて、それぞれの部屋からかすかに音楽が響いてくる。
扉には覗き窓がついていて、中を見ることができた。部屋は防音壁に囲まれていて、ピアノや譜面台が置かれている。女性が一人、一心不乱にピアノを弾いていた。廊下にはベンチがあり、部屋が空くのを待つ学生がそこに座り、退屈そうに携帯を眺めていた。
なるほど、これは練習室だ。肩を並べて彫刻を作ることができる美校とは違い、音校での練習は個人単位になるわけだ。
扉の見た目に大差はないのに、その向こうには全く違う世界が広がっている。
ヴァイオリンを一人で弾く程度の六畳ほどの空間もあれば、自動販売機八つ分くらいの大きさのパイプオルガンが、デンと据えられた部屋もある。邦楽科の練習室は入ると襖があり、それを開けると畳敷き。能や日本舞踊を舞える舞台が設置されていた。
蜂の巣のような練習室がある一方で、コンサートホールも六つある。中でも最大のホールが、奏楽堂だ。この奏楽堂、座席数が千百席! 音校の生徒数は四学年を合計しても千人弱だから、全員余裕で収容できてしまう。さらにオペラ座のようなバルコニー席があり、オーケストラピットまである。楽屋なんて八室もある。楽屋が八つもあってどうするのだろうか。
奏楽堂に入ると、見上げるほど巨大な、美しい装飾の施された木枠が目に飛び込んでくる。パイプオルガンだ。
「藝大のオルガンの中でも、奏楽堂にあるものは億の値段ですね」
オルガン専攻の学生、本田ひまわりさんがそう教えてくれた。億……馴染のない金額に思わず震えがくる。
「ええと……実際に触れるんですよね?」
「はい、練習でも使ってますよ。そうそう、奏楽堂は天井が可動式なんです」
「え? 何のためにですか?」
「音の残響時間を調整するんですよ。演奏内容によって、お客さんに一番良い状態の音を届けられるように」
うーん、違いがわかる自信がない……。
練習室とは別に、門下部屋というものもある。
これは楽器の担当教授と、その門下生ごとに与えられている部屋だ。例えば器楽科ファゴット専攻であれば、ファゴットを学ぶ一年生から四年生までの全学生のたまり場となる。
ファゴットを愛するファゴット使いたちの部屋。
「部室みたいで居心地いいですよ」
安井悠陽さんは、大柄な体を揺らしてそう言った。
「どんなことをして過ごすんですか?」
「そうですねえ、みんなでファゴット吹いて遊んでますね」
「ファゴットを吹く……? 個人個人で、ですか」
「いえ。例えば一人が、ピアノ協奏曲を吹き始めるとするじゃないですか。すると別の奴が、それにハモって吹き始めます。別の奴がヴァイオリンのパートで参戦してきたり、また別の奴が入ったり……」
いつの間にか合奏になるのだという。
「たまに誰かがふざけて短調に変調して、悲しいメロディにしてみたり。あるいは倍速で吹いてみたり。一人がテンポをあげるとみんなついていこうとしますし、追い抜こうとして競争みたいになったり。楽しいですよ!」
音校は、どこもかしこも音楽で満ち溢れている。練習室、ホール、門下部屋、果ては階段の踊り場まで……。
夜になって学生がみな帰れば、音は消え、空っぽの部屋だけが残される。
全員遅刻vs.時間厳守
「音楽は一過性の芸術だからね」
音校楽理科卒業生の柳澤佐和子さんの言だ。
「つまり、その場限りの一発勝負なのよ。作品がずっと残る美校とは、ちょっと意識が違うかもしれない。あと、音楽って競争なの。演奏会に出る、イコール、順位がつけられるということ。音校は順位を競うのが当たり前というか、前提になっている世界なんだよね」
美術でもコンクールなど順位がつく場もあるとはいえ、競争意識は音校に比べてゆるいようだ。妻もこんなことを言う。
「美術って、みんな一緒に並べて展示できるからいいよねー」
美術の作品はずっと残る。だから今評価されなくても、いつか評価される可能性も、共に残り続けるのだ。
そんな美校のゆるさは、いろいろな形で表れているようだ。
「どちらかと言えば、美校の教授ってルーズというか、のんびりしていると思います」
絵画科油画専攻四年の奥山恵さん(仮名)は、そう教えてくれた。
「毎週、教授会議があるんですよ。十三時からなんですけど、私ちょっと用事があってそこに入ったことがあるんです」
「どうでした?」
「教授、一人しかいませんでした」
一人を除いて全員遅刻……。
「私が『先生、一人ですね』って言ったら、『うん……』って。ちょっと可哀想でした」
妻も以前、こんなことを言っていた。
「あ、雨だ。ちょっと待って、休講かもしれない」
そして携帯を見て、藝大のホームページを開く。
「どういうこと?」
「雨降ると休講になることがあるから」
まるでハメハメハ大王の歌じゃないか……。
一方の音校。邦楽科三年の川嶋志乃舞さんによれば、随分違うらしい。
「教授は絶対です。先生というか、師匠ですから」
「では時間厳守、ということですか」
「はい、もちろんです。邦楽科では、学生はレッスンの三十分前に来るのが基本です。その間にお部屋の準備をするんです。座布団を並べたり、楽器を用意したり。時間が余ったら譜面を読んだりしますね。もちろん、事前に予習はしてくるんですけれど。万全にしておいて、時間になったら先生がやって来て、授業が始まります」
音校の中でも邦楽科は特に厳しいようだが、全体的に美校よりも時間の意識は強い。作品が置いてあればよい展覧会と違い、演奏会は奏者が欠けたら成立しないのだ。
ほぼ全員遅刻の美校と、時間厳守の音校。美校と音校の合同教授会議では、喧嘩にならないのだろうか?
「音校に合格した学生が一番最初に何をするか知ってる? 写真を撮るの」
そう言うのは、楽理科卒業生の柳澤さん。
ドレスを着て楽器を携え、にっこりと笑う宣材写真を撮るそうだ。演奏会のチラシを作るにも、ホームページに載せるにも写真が必要になる。春になると新入生同士で「もう写真撮った?」「いい写真屋さん知ってる?」といった会話が交わされるという。
「やっぱり自分が商品だからね。舞台に立って、鑑賞してもらうわけなんで」
ピアノにしろヴァイオリンにしろ、声楽にしろ、スポットライトを浴びるのは自分だ。お客さんは演奏だけでなく、演奏者の振る舞いや指の動き、容姿や表情まで含めて楽しむ。
学生ながら、自分は「見られる側」だとすでに知っているのだ。学生たちの服装の違いも、そういったところから出てくるのかもしれない。
「美校に合格して最初にやること……? 特にないかなあ。めっちゃ寝たりとか?」
妻はそう言って首を傾げた。
美校にも、音校の宣材写真に相当するものはある。「ポートフォリオ」だ。作品の写真や、これまでの展示風景などを一冊のバインダーにまとめたもので、自己紹介代わりに見せる。しかし、こちらの場合はあくまで作品が主役。作品を見てもらえば、作者の外見なんてどうでもいいのだ。
小さじも、机も、トロフィーも作る
ところで、美校の妻と音校の柳澤さんとでは、同じ芸術を愛する者でも異なる部分がある。それはお金との関わり方だ。そもそも、妻はお金をあまり使わない。貧乏やケチとは少し違う。作れるものは何でも作ろうとするのである。
ある日砂糖壺を開けると、中に木製の小さじが入っていた。ちょうど壺に入る大きさで、よく磨かれていて、つるつるとした触り心地が楽しい。
「あれ、これいいね。買ったの?」
「作ったよー」
そういえば、数日前からベランダで何かを削っていたけれど……窓を開けてベランダを見ると、切断された木片が転がっていて、木屑がプランターの脇にたまり、ごろんとノコギリが放り出されていた。
妻と一緒にいると、これくらいは当たり前になってしまう。床の傷をパテで埋めて元に戻していたこともあるし、突然、下駄箱の上に木製の写真立てが出現したこともある。
妻の実家では、そんな習性に慣れっこの様子。先日、お義父さんがプレゼントをくれた。
「これあげるよ」
「……何ですか、これは」
目を白黒させている僕に、お義父さんが言う。
「板だよ」
板なのはわかりますが。抱えるほど大きい、立派な板ですが。
「なかなかいい板だから、テーブルでも作りな」
「わーい、お父さんありがとう」
喜ぶ妻。戸惑う僕。
現在その板は、我が家の二つ目のテーブルとして立派に働いている。
この自給自足の精神は、美校の中でたくさん見ることができる。
「鞴祭」というものがある。鞴というのは人力の送風装置で、金属加工ではとても重要な道具だ。この鞴を使う鋳物師や鍛冶屋が、神様を祭るために行う儀式が鞴祭。藝大の彫刻科や工芸科でも金属加工を行うので、十一月には学内で鞴祭が行われる。
部外者でも参加できるようなので遊びに行ってみたが、祭りはなかなか本格的なもの。
鞴が祭壇にデンと置かれ、注連縄や紅白の幔幕が張られている。教授を筆頭に関係者が集まり、袴に烏帽子をつけた神主が祝詞を唱え、巫女が玉串を配っている。大きな酒樽はたった今、割られたところらしかった。厳粛な空気が漂い、思わず襟を正す。
祝詞が終わった。やんややんやと歓声があがる。学生たちが皆におでんを振る舞いはじめた。妻に言う。
「ちゃんと神主さん呼んでやってもらうんだね」
「あれ、院生の先輩だよ」
「…………?」
「巫女さんも四年生」
「え? 自前なの?」
全て“お手製”だそうだ。祭壇、幔幕は一年生によるセッティング。注連縄は稲藁をより合わせて作る。神主や巫女は学生。おでんも裏で煮ているという。覗いてみると、焚き火の上に巨大な釜。中では大量のおでんダネがぐつぐついっている。燃料はなんと彫刻の端材となった木材。おでんをすくう巨大オタマまで手作りだ。細長い角材の先端にボウルを針金でくっつけている。火が消えかければ倉庫からガスバーナーを持ってくる。着火したら送風機で火を大きくし、端材を追加する。
キャンプ場で自炊しているみたい。
彼らの姿を見ていると、自分の頭がひどく固くなっているようでショックを受ける。何事もお金を使うという前提で考えていたことに気づくのだ。
例えば家が欲しくなれば、僕はどうしても賃貸と分譲とどっちがいいかとか、価格がこれから上がるのか下がるのかとか、考えてしまう。通帳とにらめっこする作業が、家を手に入れる作業になる。
妻はきっと、自分で建てるという発想を持てるのだ。もちろんお金を使えば時間は短縮できるが、それはあくまで選択肢の一つというわけ。
会場の裏手の棚に、トロフィーが飾られていた。「彫刻科ボウリング大会優勝」と書かれている。
「こういうトロフィーのほうが、欲しくなるねえ」
僕はしみじみと言った。妻が頷く。
「なんたって、准教授の手作りだからね」
そのトロフィーは一本の木から彫りだされたもので、ボウリングのピンの形に美しく磨き上げられていた。
仕送り毎月五十万
一方、音校卒業生の柳澤さんが教えてくれた、学生時代の話。
「私、月に仕送り五十万もらってたなあ」
「え、五十万?」
「音校は何かとお金がかかるのよ。学科にもよるけど。例えば演奏会のたびにドレスがいるでしょ。ちゃんとしたドレスなら数十万はするし、レンタルでも数万。それからパーティー、これもきちんとした格好でいかないとダメ」
音楽業界関係者のパーティーは頻繁にあるそう。そこで顔を売れば、仕事に繋がるかもしれないのだ。
「楽器も高いものが多いですからね。ヴァイオリンやピアノは、特に高いと思いますよ」
器楽科でハープを学ぶ竹内真子さん(仮名)が言う。
「ハープって、よく上流階級っぽいなんて言われますけど、まだ庶民的なほうではないかと思います。高くても一千万ですから。ちゃんとしたのを買おうとすれば、三百万くらいかな……うーん、それでも高いですかね。でもヴァイオリンは、ものによっては億いっちゃいますからね。何だか金銭感覚麻痺してきますね。ヴァイオリン専攻の友達に『ちょっとトイレ行くから楽器見てて』なんて言われると……そんな責任負えないよ、ってなります。だって手の中に家があるんですよ、家が!」
竹内さんは、わなわなと手を震わせていた。
器楽科ホルン専攻の鎌田渓志さんも、こう話す。
「いい楽器を使わないと、受験でも不利なんです。僕は浪人した時にローンを組んで、新しいホルンを買いました。定価が百三十万で、少し負けてもらいましたけど、それでも百万はしましたね」
楽器は高いけれど、自分で作るわけにはいかないし、そんな時間があれば練習をすべきなのだ。
「楽器は運ぶのも大変なんですよ」
これは、器楽科コントラバス専攻の小坪直央さんの話だ。
「新幹線では、コントラバス用の指定席も買わないといけませんから……」
高価な楽器を持ち、上等な衣装を着て演奏する。レッスンをして、演奏会に出て、パーティーに参加する。長期休暇には海外に飛び、本場の演奏を聴く。
何だか優雅な雰囲気に満ちている。
顔に半紙を貼りつけている妻とは、方向性がだいぶ違うようだ。
ある日、柳澤さんに誘われた。
「今度、同窓会をするんだけど、来ない?」
「僕が行っていいの?」
「大丈夫。みんな友達連れて来たり、ゆるい会だから」
それなら安心と、ゆるい格好で向かった僕は仰天することになった。
会場が「鳩山会館」なのである。
総理大臣にもなった鳩山一郎が建てた洋館で、ここの応接室で自由党(自民党の前身の一つ)結党に関して議論がなされたり、ソ連との国交回復に向けて準備が行われていたとされる。大正末期そのままの英国風建築、ステンドグラスからはバラが咲き誇る庭が見え、鳩山一郎の銅像が立っている。
大広間を一日借りるのにけっこうなお金がかかる鳩山会館。それも、鳩山家関係者の紹介が必須となる。そんなところで同窓会を行う人々が存在するなんて。
恐縮しているのは僕一人で、みなのびのびと談笑している。つまり、彼らにとってはこれは日常であり、取り立てて驚くべきことでもないのだ。
余興の時間になると、参加者の何人かが壇上に立つ。そして歌を歌う。ピアノを弾く。宴会の、それはあくまで余興なのだが……。
プロなのである。
オペラの一節を歌い上げれば美しい声が響き渡る。遊びとして童謡を歌っていても、それがまた聴き惚れるほどなのだ。
「私、洗い物したことないのよ」
柳澤さんが言う。
「ピアニストにとって指は商売道具だもの。傷つけて演奏ができなくなったら大変、練習できないだけでも困る。一日練習しないと、三日分ヘタになるって言うくらいだからね。重いものも持たないし、スポーツもしない。それは、プロならばより意識してるはずよ。私も高校の頃は、体育は見学してた」
試しに聞いてみた。
「じゃあ、自分で板からテーブルを作ったりなんかは……」
「ありえないわ!」
柳澤さんは、口に手を当てた。
何でも作ろうとする人と、洗い物さえしない人。何もかも自前で飲み会をする人と、鳩山会館で同窓会をする人。普通なら交わらないだろう両者が、同じ学校に通う。
それが藝大なのだ。
2.才能だけでは入れない
芸術界の東大
ところで、藝大が屈指の難関校であることをご存じだろうか。僕も初めは知らなかったのだが、学生たちに話を聞いているうち、「難関」の片鱗が感じられ、今では恐ろしさすら感じるようになった。
大学受験最難関の一つとして、東京大学の理科三類が知られている。各都道府県からトップクラスの秀才たちが集う場だ。どんな雰囲気なのか、実際に合格した人がこんな話をしてくれた。
「怖かったよ。試験中に、いきなり前の席のヤツが『ギャアーッ』って叫んでさ、鉛筆もテスト用紙も放り投げて、外に飛び出していったんだ」
「それは怖いね」
「いや、違うんだよ。本当に怖かったのはそこじゃない。そんなことが起きたのに、教室中の誰もが動じずにテスト用紙に向かってるんだ。響くのは、カリカリという鉛筆の音だけ……」
飛び出した方はそれっきり、戻ってこなかったという。
恐るべし理科三類。平成二十七年度の志願倍率が四・八倍、百の枠を約五百人が奪い合った。難関の名にふさわしい倍率と言えるだろう。
対して藝大の最難関、絵画科の同年度の志願倍率はなんと……十七・九倍。八十の枠を、約千五百人が奪い合う。藝大全体でならした倍率でも七・五倍に達する。
なお、昔は六十倍を超えたこともあったという。もはや入試ではなく顕微鏡の倍率である。
藝大は「芸術界の東大」と言われているそうだが、むしろ東大を「学問界の藝大」と呼んでもいいのかもしれない。
受験で肩を壊す
「そもそも、ある程度の資金力がないと藝大受験は難しいんだよ。もともと私は器楽科のピアノ専攻を目指してたから、大阪から東京まで、新幹線でピアノの塾に通ってた。月謝と交通費だけでも、相当のお金がかかるよ」
楽理科卒業生の柳澤さんが、受験について語ってくれた。
「地元にも、もちろんピアノの教室はあるけど。音校を受けようと思ったら、藝大の先生に習うのがほぼ必須なのよ。高校の音楽の先生や、それまで習っていたピアノ教室の先生なんかにお願いして、紹介してもらうの」
藝大で実際に教えている教授、あるいは元教授――。そういった方を師匠と仰ぎ、レッスンを受けるのが当たり前なのだ。教授のコネが必要という話ではない。試験の採点は、師匠を除いた残りの教授陣によって行われる。
藝大に合格するにはトップレベルの実力が必要で、それを身につけるにはトップレベルの指導者に習う必要があり、トップレベルの指導者は藝大の教授であることが多い。そういうことのようだ。他の受験生がそうしている以上、自分も同じようにしないと戦えない。
「じゃあ、親は大変だね」
「そうね、親が本気じゃないとダメだと思う。でも、大抵の親は本気だよ。特にピアノ専攻やヴァイオリン専攻では、二歳とか三歳から音楽やってて当たり前だから。小学校から始めたら、遅くてハンデがあるねって言われるくらい。小さいころから英才教育を叩きこまれた、その延長線上に藝大があるのよ」
柳澤さんもお母さんがピアノの先生で、子供のころからピアノを習って育ったそうだ。
「コンクールの上位常連、あるいはすでにコンサートで客が呼べる……そんな人たちが、みんな藝大を目指すわけ。だから藝大には頂点っていうか、最高峰っていうか……凄いブランドイメージがあるんだよね。本人よりも親のほうが憧れてるケースもあったりして。自分は藝大に入れなかったから、せめて娘だけは入れたいっていう」
壮絶な戦いであることが何となくわかってきた。ちなみに柳澤さんは結局、器楽科ピアノ専攻ではなく、楽理科に入っている。僕は理由を聞いてみた。
「断念したの」
「どうして?」
「練習しすぎで、肩を壊しちゃって……全力で弾けなくなっちゃったの」
まるで、プロ野球選手だ。
三浪くらいは当たり前
「うん、君には才能があると思うけど、三浪は必要だろうね」
妻が藝大彫刻科を志した時、先生にそんなことを言われたという。妻は奮起し、何とか一浪ですべり込むことができたが、美校で三回の浪人はさほど珍しいことではない。
美校の現役合格率は約二割。平均浪人年数が二・五年。
美校の場合は、藝大の教授にレッスンを受けるのが当たり前、という風潮はない。しかし独学が可能かというとそうでもなく、美大受験予備校に通うのが一般的だ。ここでデッサンなどの練習を積む。それはもう、三年ほどみっちりと積んで、ようやく合格圏が見えてくる。五浪、六浪の人も当然いて、同級生でも年齢が十歳近く離れていることもざらだという。
なお、この中には「仮面浪人」も含まれる。
例えば、私立の美大にいったん入学する。普通に授業に出ながら同時並行で受験対策も進め、藝大に合格後、私立をやめて藝大に入るというやり方だ。
「藝大って国立じゃないですか。学費が安いんです。私立に入っても二年生までに藝大に移ることができたら、金銭的にはお得なんですよ。けっこうそういう人、います」
実際に仮面浪人して、藝大の絵画科に入った奥山恵さんの言葉だ。
“選手生命”を考えて浪人する
音校では事情がちょっと違う。肩を壊してピアノを断念した柳澤さんによると、浪人する人は少ないそうだ。
「それは、金銭的な事情?」
「それももちろんあるけれど、もっと大きいのは時間の問題かな。卒業が遅くなったら、それだけ活躍する時間が限られちゃうから」
「……え? それって、“選手生命”があるってこと?」
「演奏家は体力勝負だもの。ハードなのよ、コンクールの前に掌一杯の砂糖を食べるピアニストもいるくらいだから。年とともに体力は衰えていくでしょう。入試に何年もかけたら、もったいないのよ。だったら他の大学に入って、早くプロとして活動し始めたほうがいい」
やっぱりプロ野球選手だ……。「巨人軍」にこだわるより、他球団に活躍の場を求めたほうが大成することもある。
「それから、やってるうちに先が見えてくるということもあります」
こう言ったのは、器楽科ピアノ専攻の三重野奈緒さん。
「どこまで自分が行けるのか、自分でわかっちゃうんですよ。だから明らかに失敗してしまった場合などをのぞけば、何回も浪人するということはありません」
問題見なくていいじゃないか
そんな受験生たちの前に立ちはだかる藝大の入試は、一体どういうものなのだろうか。
多くの学科では実技試験が大きなウエイトを占めている。
「一応、センター試験も必要なんだよね?」
そう聞くと妻は頷く。
「でも、あんまり重視されないよ」
「どれくらい取れればいいの」
「科にもよるけど、彫刻では七割くらいを目指すべきみたい」
「で、何点取れたの?」
少し照れる妻。
「……自己採点では三割くらい……かな」
「…………」
「へへ」
センター試験はマークシート方式なので、問題を見ずに適当に塗りつぶしたって二割前後は取れるはずなのに。妻は続ける。
「先輩で、センター一割しか取れなかった人いたらしいよ」
「問題を作っている人が聞いたら泣いちゃうね」
「でも、実技の順位が上から三番目くらいだったんだって。それで絵画科に合格」
「…………」
あくまで重要なのは実技試験なのだ。ただ、合否ラインぎりぎりで実技の得点が拮抗している場合は、センター試験の得点が高い方から合格になるようなので、ちゃんと勉強するに越したことはない。
「悩ましいんだよね。どこまでセンター対策するか。みんなと同じくらいには対策しておきたいし、でもできるだけ実技に時間を振り分けたいし。たまにセンター捨てた、って公言する人もいるけどハッタリかもしれないからね。なんだかちょっと、頭脳戦?のような……」
なお、学科によってもセンターの重要度は異なり、建築科、デザイン科、芸術学科、楽理科、音楽環境創造科などでは比重が大きくなってくるそうだ。
全音符の書き順は?
実技試験は複数の段階に分かれている学科がほとんどで、当然ながら一次試験で落ちれば二次試験には進めない。また、学科によって異なるものの、三次試験や四次試験では筆記試験が課されることが多い。
「一次試験はほんの五分くらいの演奏で、合否が決まるの。そこで落ちたら筆記試験の勉強もぜーんぶ無駄になっちゃう。一発勝負よ」
柳澤さんの眼差しは、真剣そのものだ。
「一次では半分以上、ごっそり落とされるんですよね。部屋に入るとですね、周りをずらりと教授陣が、十人くらいかな、取り囲むように座っていて、難しい顔でこっちを見ているんです。粗探しをする目ですよ。そこで『じゃ、始めて』と。緊張感ありますね」
器楽科ファゴット専攻の安井悠陽さんは、そう振り返った。
「事前に課題曲が二十一曲与えられてまして、その中から当日に四曲かな、指定されて演奏するんです。二次試験になるとピアノ伴奏つきでこれをやります」
試験を行う部屋の前では、受験生たちが順番を待っている。お互いにライバルであり、同じ楽器を愛する同志でもある。中にはコンクールで顔を合わせた人物もいるだろう。室内からは他の受験生の演奏が聞こえてくる……想像するだけで胃が痛くなってしまう。
しかし音楽家たるもの、演奏は全て一発勝負だ。一発勝負に弱くては話にならない。
「試験には新曲視唱というものがあります。初見の楽譜が渡されまして、しばらく目を通して、それからその場で歌う、という試験です。いかにリズムや音階を正確に歌えるか、がカギになりますね」
作曲科の小野龍一さんは思い返すように首をひねりながら、少しずつ続けた。
「楽譜の冒頭だけが与えられて、その続きを自分で作って書くという試験もありましたね」
いかにも作曲科らしい試験だ。
「打楽器専攻にも他とは違うテストがあります。リズム感のテストです。1、2、3、4と口で言いながら足踏みをして、裏拍で手拍子するんです。一定のテンポで十秒くらいやらされますかね、それで判断されます」
打楽器専攻の沓名大地さんは、実際に目の前でやってみせてくれた。なんてことはなさそうなのだが、自分でやってみると難しい……。
加えて多くの科では筆記試験がある。大きく分けて「和声」と「楽典」である。
「和声はね、音楽理論だよ。和音ってあるでしょう? いくつかの音をいっぺんに出すこと。この和音、どの音とどの音を組み合わせたら綺麗な音になるか、どう和音を続けたら美しい音色になるか、ちゃんと法則があるの。その法則を覚えて、応用して問題を解いていく。なんかね、数学みたいな感じ。私は苦手だったな、凄くややこしいのよ」
そう言って渋い顔をしたのは、楽理科卒業生の柳澤さん。
「楽典は音楽の文法問題ですね。楽譜を書いたり、読んだりするのに必要な知識です。そんなに難しくはありませんが、たまに凄く変な問題が出ることも……。僕が受けた年には、『全音符の書き順をこたえよ』って問題がありましたよ」
苦笑とともに話すのは、器楽科ファゴット専攻の安井さんだ。
「えっ、全音符に書き順なんてあるんですか? 全音符ってあれですよね、数字の0みたいな……」
「はい、ちょっと潰れた数字の0ですね。その時はわかんなかったんですが、ちゃんと書き順があるんです。二画です」
安井さんが手本を示す。まず上から下へ左側の半円を書き、続けて上から下へ右側の半円を書く。これで二画。
「たぶん、みんなわからなかったんじゃないかな。おかげで差がつきませんでしたけど……」
筋肉がないと脱落
五分の演奏で合否が分かれる音校。
では、美校はどうなんだろう? 僕は過去問を調べてみた。
「人を描きなさい。(時間:二日間)」
平成二十四年度の絵画科油画専攻、第二次実技試験問題である。二日間ぶっ続けではなく、昼食休憩の時間もあるため、試験時間は実質十二時間ほどだが、それでも長い。
問題は学科によって異なるが、一次試験では鉛筆素描、つまりデッサン。二次試験では学科の専門性に応じた問題が出されることが多い。絵画科油画専攻なら油絵で何か描かせる、彫刻科であれば粘土で何か作らせるという具合だ。
一次試験に一日、二次試験に二日といった具合に、試験は何日間かにわたって行われる。まるで、中国の官吏登用試験「科挙」だ。
どんな様子なのか、妻に聞いてみた。
「教室に入ると、席をくじ引きで決めるんだ。部屋にモチーフの石膏像が置かれてて、それを素描するんだけど、席によって書きやすい角度とかがあるのね。私は得意な角度の席が当たったから、ラッキーだった!」
「角度によって有利不利があるの?」
「うん。かなり違うよ。ちょっとでも見やすい角度にするために、椅子の脚に少年ジャンプ挟んで座る人もいた」
「ジャンプは持ち込み可なんだ……試験時間は長いんだよね」
「うん。そのデッサンは六時間だったかな」
「長いね!」
「でも、足りないくらいだよ」
「そんなに集中が続くものなの?」
「うーん……やっぱり辛いよね。私は途中でお腹がすいて、お腹が鳴ったよ」
「どうしたの」
「トイレに行って、ソーセージ食べてた」
「…………」
「トイレにはタバコ禁止とは書いてあったけど、おやつ禁止とは書いてなかったから……」
お肉の匂いで絶対にばれていたと思うが、藝大の試験監督はその程度なら見逃してくれるみたいだ。
「油画の入試はとにかく体力がいるんですよ!」
絵画科油画専攻の奥山恵さんは、大きな目を見開いて言う。
「そもそも、画材を持ち込みますからね」
一般の大学入試なら、持ち込む筆記用具はシャープペンシルに消しゴム程度だろう。しかし、藝大入試に必要な筆記用具は半端な量ではない。
デッサンに必要な道具がカルトン(下敷き)、木炭、練り消しゴム、消しゴム(あるいはパン)……。
油絵を描くのに必要な道具が絵の具、ペインティングオイル、ペインティングナイフ、筆数種類、紙パレット、クリーナー(筆を洗う溶液)、バケツ……。
これらのものを予備も含めて持ち運ぶには、なかなかに大きな鞄が必要となる。上京してくる人にとってはなおさらだ。しかし、ここでキャスター付きのキャリーケースなどを選ぶと大変なことになってしまう。
「入試当日は、エレベーターが使えないんです。そして困ったことに、油画の試験は絵画棟の五階とか六階で行われるんですよ」
試験会場まで階段で上らなくてはならないのだ。さらに美校の教室は大きなサイズの絵を描いたり展示したりできるように、一階分の天井高が通常のビルの二階分ほどある。試験会場が六階であれば、実質十二階分、重い画材を担いで上ることになってしまう。
「試験当日、集合場所に集まるじゃないですか。すると試験官の方が現れて、『では、ついて来てください』と言うんです。それからいきなり、軽快に階段を上り始める。いきなりみんなで耐久レースですよ。ひいひい言いながら階段を上る、上る。女の子とか途中でへたり込んでしまったり……運動不足の人は顔真っ赤にしてますね。途中で離脱してしまう人もいると思います。『ハンター試験』って呼ばれてますね」
この試練を乗り越えぬ限り、油画の試験を受けることはできない。画材を背負って階段を上り続ける。遥か下の景色が見える。上野動物園の檻も見下ろせる。酸欠になりかけながら、前の人に遅れぬよう必死でついていく。遅れる者、倒れる者、友達同士であれば励まし合い、あるいは「俺を置いて先に行け」「お前だけ置き去りにできるか」などというやり取りが……。
「受験生はみんな真剣に、当日の荷物を少しでも軽くする方法を考えますよ。あとは、試験に備えて筋トレしたり」
小柄で細身の奥山さんは、大変だったあ……と笑った。
ホルンで四コマ漫画を
藝大の過去問に目を通していると、たまに首をひねりたくなるような問題文に遭遇する。
「……の状態を、下記の条件に従い解答用紙に美しく描写せよ」
こんな表現はまだ序の口だ。
「問題一 自分の仮面をつくりなさい」
この問題には注釈がついている。
「※総合実技2日目で、各自制作した仮面を装着してもらいます」
さらに問題の続きには、
「解答用紙に、仮面を装着した時のつぶやきを100字以内で書きなさい」
とあり、その隣にまた注釈。
「※総合実技2日目で係の者が読み上げます」
これらの不思議な問題の意図は、平成二十三年度建築科の問題文にある一節を読めば理解できるかもしれない。
「……しなさい。なお、この試験はあなたの構想力、創造力、表現力を考査するものであり、正解を求めるものではありません」
何か抽象的なものを測ろうとしているようだ。
藝大のレベルは総じて高い。音校なら演奏技術、美校ならデッサン力。そういった、いわば基礎の部分にまずは高い能力が求められる。だが、それはできて当たり前。なぜなら努力で何とかなる部分だから。
藝大が求めているのは、それを踏まえたうえでの何か、才能としか表現できない何かを持った学生だ。「光るものを持っている」と審査する教授に思わせることができないと、合格点は得られないようである。
「音楽環境創造科には、『自己表現』って試験科目があるのよ」
音校卒業生の柳澤さんが、同級生の逸話を教えてくれた。
「自己表現……?」
「何でもいいから、自分をアピールするの。私の友達は、ホルンで四コマ漫画をやったわ」
「えっ、どういうこと?」
「四コマ漫画を画用紙に書いて、持ち込んだの。それで一枚ずつめくりながら、ホルンで台詞の部分を吹いたんだって。台詞っぽく聞こえるようにね」
「……その人はどうなったの?」
「合格したわ」
「…………」
「あとね、こんな課題もあったって聞いた。鉛筆、消しゴム、紙を与えられてね、好きなことをしなさいって言われるの」
「それは何となくアートっぽいね」
「うん。私の友達は、黙々と鉛筆の芯を削り出した。それからその芯を細かく砕いて、顔にくっつけていったの」
雲行きが怪しくなってきたぞ。
「最後に、紙を顔に叩きつけた。パーンって。紙に黒い跡がつくでしょ。それを自画像って主張して提出したんだって」
「……その人はどうなったの?」
「合格したわ」
たとえ思いついたとしても絶対に実行できない。
極端な例を挙げたが、個性はとても重要になる。
例えば、平成二十七年度絵画科油画専攻の問題。
「折り紙を好きな形に折って、それをモチーフにして描きなさい」
折り紙をどんな形に折るか、何をテーマにするか、どんな角度からどういった構図で描くか。人間性や価値観を浮き彫りにする、と言っても過言ではない問題である。
もちろん絶対的な正解は存在せず、採点基準はつまるところ「教授の好み」になってしまう。それでも好みが偏らないように、審査する教授は複数存在し、それぞれがいいと思った作品に票を投じる。得票数がそのまま得点となる仕組みだ。合格ラインは年によっても異なるが、五~六割程度だという。
それぞれが日本を代表するアーティストでもある藝大の教授陣、その半数の心を動かせるか否か。それが、藝大の入試なのである。
4.天才たちの頭の中
口笛世界チャンピオン
藝大生はみんな、僕には天才に見える。しかし、そんな藝大生をして「あいつは天才だ」と言わしめる藝大生も存在する。
音楽環境創造科の青柳呂武さんも、その一人だ。
「僕は、口笛をクラシック音楽に取り入れたいんです」
太い眉を柔らかく曲げて笑い、青柳さんはそう言った。
青柳さんは、二○一四年の「国際口笛大会」成人男性部門のグランドチャンピオン。名実ともに口笛界の頂点だ。そしておそらくは最初で最後の「藝大に口笛で入った男」になるだろうと言われている。
「二次試験の『自己表現』で、ヴィットーリオ・モンティ作曲の『チャルダッシュ』を口笛で吹きました。そして、口笛を他の楽器と対等に扱えるようにしたい、と言ったんです」
『チャルダッシュ』という曲は前半はゆっくりのびやかなのだが、後半には小刻みで非常に速いリズムがやってくる。この速いパート、どれくらい速いかと言うと……早口言葉の「生麦生米生卵」が人生で一番スムーズに言えた時を思い出してみてほしい。たぶん、その二倍は確実に速いと思う。早口言葉だって舌を噛むのに、口笛で吹くなんて……。
「いやあ……練習すれば、できるようになりますよ」
「どれくらい練習されてるんですか?」
「日によって違いますけど、三、四時間くらいです。でも、遊びながら練習する感じですね。お風呂で吹いたりとか。楽しんで続ければ、上達しますよ」
「口笛のうまいとかへたとかって、どういうところで決まってくるんでしょう」
「一つの基準としては、多くの奏法をマスターすることでしょうか。口笛にはいろいろな奏法があるんです。ウォーブリングとか、リッピングとか……。例えば『下唇系舌ウォーブリング』という奏法では、吹きながら舌を下唇の内側につけたり離したりすることで、息を止めずに高速で音を切り替えることができるんです」
こんな感じですね、と青柳さんはさっと口をすぼめて吹いてみせる。ピロピロピロ……僕はまばたきもせずに見つめていたのだが、何がどうなっているのかさっぱりわからなかった。
他にも上あごを使ったり、喉を使ったり、唇を使ったり、お腹を使ったり、場合によっては口を手で塞いだりなど、息の流れるあらゆる部分を操作することで、多彩な表現ができるという。複数の奏法をマスターできる人物はほんの一握りだそうだ。
「奏法を複数習得すると、ぐっと世界が広がるんですよ。ウォーブリング一つだけだと、二つの音しか出せません。でも、それに別の技を組み合わせるんです。そうすると、素早くたくさんの音に切り替えられます。音階を作れるんです」
「奥が深いんですね」
「深いですねー。まだまだ発展途上な世界ですから。これまでにない奏法を、自分でも発明していく必要があります。あるいは、組み合わせるのが不可能だと言われている二つの奏法を、何とかして組み合わせられないか考えたり。口の仕組みを勉強したり、音色を音楽的に研究したり。口笛界ではみんな、いろんな研究をしています。僕、今では口笛界の先導者みたいに扱われてるんで、どんどん新しい目標を作っていかないといけないんです……」
青柳さんは頭をかいて笑った。
「その目標の一つが、クラシック音楽に口笛を取り入れることなんですね」
「はい。びっくり芸ではなく、音楽として純粋に楽しめるようにしたいんです。オーケストラや室内楽に『口笛』というパートを作りたいんですよ」
オーケストラに口笛を
「口笛って、楽器がいらないのが大きな利点だと思うんです。いつでもどこでも吹けるし、両手もあいてますよね。何か他のことをしながら吹けます」
青柳さんの言うとおりだ。両手が空く楽器は珍しい。
「それから口笛は息を吸っても音が出せるんです。つまり、息継ぎがいらない」
「あ! それは曲の可能性が広がりますね」
「そうなんです。まだありますよ。口笛はグリッサンドができるんです。音を自由に上下できるんですよ」
グリッサンドとは、音程を区切らず、滑らかに音高を上下させる奏法。例えばピアノなら、鍵盤をざあっと手で滑らせるようにして弾くことができるが、これをグリッサンド奏法という。しかし、ピアノでは鍵盤と鍵盤の間の音は出せない。
「滑らかなグリッサンドができるのは、弦楽器的な特徴なんです。でも、口笛は弦楽器かというと違う。人間の体という管を使って、音を響かせるので管楽器的でもありますよね。もっといえば声楽にも似ています。口笛はいろんな特徴と、可能性を秘めているんです」
弦楽器、管楽器、声楽のいいとこどり。そう言われてみると、どうしてこれまで口笛がオーケストラになかったのか不思議に思えてきてしまう。
「ただ、欠点もあります。一番は音の小ささですね。他の楽器と一緒に演奏すると、聞こえなくなっちゃうんです。マイクで音を拾ったり、あとは音の響きやすい演奏場所を選ぶことで、ある程度解消できますが」
なるほど、音響技術の発展が必要だったのだ。
「それから、手で鍵盤を操作するわけではないので、音に関しては完全に自分の感覚が頼りになります。だから音感を鍛えないと。口を器用に動かす訓練も必要ですね。あと、基本的に倍音が出ません」
「倍音って何ですか?」
「ええと……音楽用語なんですが」
青柳さんはスマートフォンを取りだしながら、ゆっくりと説明を始めた。
「ピアノの『ド』を弾くと、『ド』が鳴りますよね。この時、もちろん人間の耳には『ド』が聞こえているんですが……実は一オクターブ高い『ド』も同時に鳴っているんです。これが倍音です。一オクターブ高い『ド』は周波数が二倍になっているので、そう呼びます。ある音を弾くと、その周波数の二倍の音、三倍の音、四倍の音……そんなふうにいろんな周波数の音が一緒に鳴るんですよ」
この「倍音」の現れ方は、楽器によって異なるらしい。そしてその違いこそが、楽器特有の音色を生んでいるそうだ。その倍音が出せないということは……。
「これ、機械的に作った、倍音なしの音です」
スマートフォンのアプリをいじる青柳さん。
ポー。
あ。これは聞き覚えがある。聴力検査で、ヘッドホンから聞こえてくる電子音だ。
「こういうブザーみたいな音です。凄く味気ない音なんですよね。サイン波って言うんですけど。口笛はどうしてもこういう音になっちゃうんです。単調で、高音寄りで……聞き手としては長時間聴きづらいんですよ」
「倍音が出せないのは、どれくらい大きな欠点なんですか?」
「うーん……教授には、楽器として致命傷だよ、と言われちゃいましたけど……」
青柳さんはアプリを終了させてから、僕の方を見た。
「でも、どんな楽器にも長所と短所がありますから。逆に利用してみたいですね」
「なるほど、楽しみですね」
「受話器を取った時のプーって音や、信号機の『ピヨピヨ』って音もみんな倍音のないサイン波なんですよね。口笛でそっくりな音が出せます。だから、僕はたまに信号待ちをしながら『ピヨ』を口笛で一個増やしてみたり」
青柳さんは歯を見せて笑った。
真剣だけど遊び感覚
「僕は、兄二人がヴァイオリン教室に行ってまして。一緒について行ってたんですけど、兄たちがよく曲を口笛で吹いてたんですよ。それを僕も真似するようになって、三人で口笛でハモったりしてたのが始まりですね。でも、あくまで遊びでした」
やがて青柳さんもヴァイオリン教室に通うようになった。青柳さんは他にもピアノ、ホルン、オーボエなどができるそうだ。
「中学でみんなから『口笛うまいね』って言われるようになりました。高校の頃は、僕が吹き出すとみんな吹くのをやめて、聴いてしまうんですよね。僕は一緒に吹きたかったのに……」
「その頃から藝大に入って、口笛を楽器にしようと思ってらしたんですか?」
「ええと、高校一年生くらいから世界大会を目指して本格的に練習を始めました。高校三年生になって進路に悩んでいたら、親が『口笛をもっと極めてみたら』と藝大を勧めてくれたんです。音楽環境創造科という学科なら、そういうことができそうだよと」
「え? じゃあ……」
「はい。最初から口笛で藝大を考えていたわけじゃないんです。むしろ、先生になろうと。だから私大の教育学部も受けました。藝大に落ちたら、普通の大学生でいいと思ってましたね」
青柳さんが、大柄な体を揺らして笑った。
「でも、結果として藝大に入れちゃったんで。とりあえず、ここにいる間は本気で口笛やってみようと思ってます。世界大会も優勝しちゃいましたしね。ただ、この先口笛で食べていけるか、というとやはり難しいと思うんです。積極的にチャレンジする気はないですね」
おや、と僕は思った。
青柳さん、随分ふわっとしているぞ。
「僕の兄二人も、普通の会社員として働いています。音楽は好きでしたけど『プロとしてやっていくほどの実力はない』と。僕も教職の免許を取って、ちゃんと他で仕事をして……口笛は副業にするのが現実的かなと」
意地でもプロ奏者、あるいはアーティストを目指す。そんな人が藝大には多いのに。
「僕、やっぱり今でも遊び感覚でやっている部分があるんですよ。音楽が好きなんで、楽しんでやってます。なので正直、嫌いな曲は聴きたくないし、知らないままでもいいやって思っちゃってるところがあります。こういうのは、他の音校の人が聞いたら信じられないって言われるかもしれませんが……」
口笛は遊び。
でも、口笛をクラシックに取り入れる方法を真剣に研究している。
何だか青柳さんの言葉を消化しきれなかったような感覚が、僕の中に残った。
現代の「田中久重」
「あいつは『現代の田中久重』ですよ。もう、後にも先にも、あんな奴は入って来ないと思いますよ」
工芸科鍛金専攻の山田高央さんはそう言い、
「佐野君は天才です。天才」
工芸科鋳金専攻の城山みなみさんも、そうつけ加える。
田中久重は江戸後期の発明家で、「文字書き人形」を始めとする数々の絡繰り人形を作ったことで知られている。人呼んで「東洋のエジソン」。
「どうも、初めまして。佐野です」
目の前に現れたのは、小柄で物静かな青年だった。佐野圭亮さんは右手で大切そうに工具箱を持ち、左手を茶色のコートのポケットに入れて、ぺこりと頭を下げた。
佐野さんもまた、絡繰り人形を作っているという。
「中学のころ……ですね。絡繰り人形を見て衝撃を受けたんです。電気がない時代に、この動作を実現させたのは凄いと……仕組みを考えたりしているうちに、頭の中で何となく動かせるんじゃないか、というところまで来て。それを形にしてみたくなりました。木工を学校で先生に習っていたので……『文字書き人形』の真似をして、作ってみようと」
田中久重の最高傑作のひとつとされる、「文字書き人形」。
電力や回路なしに発条と歯車だけで動き、筆を持って墨をつけ、「寿」などの文字を半紙に書く人形だ。まるで人間のようなリアルな動きが特徴で、顔を動かして視線を変えながら筆を繰り、「止め」や「払い」まで器用に再現してしまう。
「久重の『文字書き人形』は、床に座ってるんですが……僕は立たせてみたんです。でも、思ったよりも難しくて。正直、やるんじゃなかったと思いました」
「立たせると、難しくなるんですか?」
「かなり難しくなります……座っている人形であれば、お尻や腰に機構を仕込めますよね。しかし直立していると、二本の細い足に……直径六センチの円柱二本に、機構を通さなくてはなりません。バランスもとりづらくなります」
「じゃあなぜ……」
「せっかくだから、ですかね……」
佐野さんは考え考え、言葉を継ぐ。とても丁寧に説明してくれるのだが、あまり話すのは得意ではない、といった様子だ。
「絡繰り人形は、図面から作るんですか? 久重の図面を参考にしつつ」
軽く頷く佐野さん。
「そもそも百五十年前の人形ですし、図面も一般公開されていません。僕にわかるのは、動きだけです。図面を作るだけで一年以上はかかりました」
「ええと、それは真似をして作ったというよりも……ゼロから作ってますよね」
「そうですね……動き以外はゼロからです」
「制作期間はどれくらいですか?」
「受験の前に作ったんで、三年くらいですね。人間の筆記の動作を上下、左右、前後の三つに分解して、それを独立した三枚のカムに記録、連動させて再現しているんです。カムの形状は手探りで、当初の想定通りにはいかず、作りながら考えて……六百回以上は試しました」
発条の回転運動を、様々な人形の動きに変換するための板状の部品をカムという。それを六百回も作り、試しながら、小さな人形の動きを調整し続けるなんて。この人の頭の中はどうなっているのだろう。
「一応は完成しましたが、正直満足のいく出来ではありませんでした。文字の完成度が久重の人形に比べてはるかに劣りますから。今作っている人形は、もっともっと人間らしい動きで、質の高いものにしたいです。誰かに見せた時に、大きな驚きが得られるようなものに」
佐野さんに、現在制作中の絡繰り人形の、実際の部品を見せてもらった。
木の板。細い棒。人形の顔や体を構成する、木製のパーツ。これらは木工の先生に習いながら作り方を習得したという。
だが、部品はそれだけではない。歯車。直径数センチのものからミリ単位のものまで、長短大小様々。そしてフレーム。カム。軸棒。ワイヤー。ネジ。ナット……。自動車の中身をぶちまけたような、大量の精巧な部品たち。
「これはまだ、ほんの一部ですが……」
「ずいぶんたくさんありますね。部品は全部でどれくらい、あるんですか」
「えっ、いくつでしょう……千は超えているとは思います」
「……それって、全部手作りですか?」
「そうです」
歯車は鉄板から、木のパーツは木から切りだして自分で作っているという。
「ど、どうやって作るんですか……」
「まずは歯車の本を買ってきて、勉強しました。正確な歯車の作り方がわかってからは、ひたすら作業ですね……方眼紙に図面を書いて設計するんですが、作りながら設計を変えたりもするので、そのたびに新しい部品も作ります」
方眼紙に歯が百個、直径三センチの歯車を「書く」だけでも気が遠くなるというのに、佐野さんは実際に「作る」のだ。何百個も。
「機械を使って作るんですよね」
「そうですね……部品によってやり方が違いますが、グラインダーとか……歯車を高速で回転させる機械とか、いろいろと使いますよ」
しきりに感心する僕の前で、佐野さんは淡々と説明する。
「でも、結局は手鋸と手鑿が一番正確です」
大きくて分厚い佐野さんの手は、マメだらけだった。
「機械ではなく?」
「そうですね。僕はいつも百分の一スケールのノギスを持ち歩いてます。そのせいか、つい何でもミリ寸法で会話しますね。一・五メートルであれば、千五百ミリって言っちゃうんです」
宇宙の果てから来た漆
「佐野さんは、どうして藝大を目指したんですか?」
「漆が好きだったからです」
佐野さんは即答した。
「……それは、絡繰り人形とは関係なく?」
「そうですね。漆のお椀とか、独特な魅力があって……小さい頃から好きだったんです。最初から工芸科の漆芸専攻に入りたくて、受験しました」
佐野さんと同じく漆芸専攻に在籍する大崎風実さんも、漆の魅力にとりつかれた一人だ。喫茶店で向かい合った大崎さんは、可愛らしくてお洒落な女子大生。ただ、その手だけがちょっと荒れている。
「漆は、あの質感がいいですよね……宇宙の果てから生まれてきたみたいな。私、母が茶道をやってまして。そこで漆の茶器を見て、好きになったんです。黒い深みの中に、瑞々しい緑のお茶が詰まってて……綺麗でした。でも実際に漆を扱ってみると、なかなか大変でした」
「どういった大変さがあるんですか?」
「工程がとても複雑なんですよね。漆を一度塗っただけじゃ、あのつやつやの質感は出ないんですよ。塗って、乾かして、また塗って……時には布や紙を載せて貼り固めたり、そこにまた漆を塗ったりして、何度も重ねていきます」
日本画専攻の膠についても、そんな話を聞いた気がするぞ。
「乾かすのにも条件がありまして。漆って、室温が二十から二十五度、湿度が六十五パーセントから八十パーセントでないと固まらないんですよ。条件が合うように密閉した木箱で、漆風呂っていうんですけど、その中で固めます。冬なら丸一日くらい、梅雨時なら四時間くらいかかります。その間は作業できないので、同時進行で複数の作品を進めるんです」
「けっこうかかりますね。どれくらい、その工程を繰り返すんでしょう?」
「二十工程くらいかな」
二十というと……。
塗って乾かして塗って乾かして塗って乾かして塗って乾かして塗って乾かして塗って乾かして塗って乾かして塗って乾かして塗って乾かして塗って乾かす。これは相当の手間だ。
「実際は塗ると乾かすだけじゃなく、磨いたり、炭で研いだり、貝を載せたり、いろいろあるんです。表面をどんな装飾、質感にするか、技法によって様々です」
「そういえば、螺鈿でしたっけ、キラキラの貝でお花なんかが描かれた漆器がありますね。たとえばあれはどんなふうにやるんですか?」
「えっとですね、簡単に説明しますと……」
テーブルの上で作業の手つきを再現しながら、説明してくれる。
「板の上にまず漆を塗ります。その上に貝を、これはシート状になったものが売られてるんですが、模様の形に切り出して載せます」
ふむふむ。しかし模様の形に切りだすだけでも、かなり根気のいる作業である。
「その上に、さらに重ねて漆を塗ります」
「塗ります」
「すると、貝のシートが漆に覆われてしまいますね」
「はい……」
「それを、ヤスリで研ぎ出すんです。模様となっている貝の上の漆だけ、慎重に削って取り除くんです」
「あの細かい模様を!」
「はい。研ぎ出し終わったら、もう一度上に漆を塗ります。そしてまた研ぎ出します。これを何回か繰り返すことで、貝の厚みが漆器にきちんと吸収されて、段差がない綺麗な模様になるわけです」
螺鈿細工とは、こんなにも手間がかかるものだったのか。お値段が張るわけである。
「かぶれは友達」
「そういえば、漆はかぶれるんでしたよね?」
力強く頷く大崎さん。
「はい、それはもう、かぶれます! 漆芸専攻では『かぶれは友達』です。敏感な人は、漆芸の部屋に入るだけでも体に出ちゃうくらいで。注意しても完全には防げないし、もう仕方ないですね。慣れです。漆が手についたら、油で洗って落とすんですよ。それから洗剤で洗って、次にハンドソープで洗って、ハンドクリームを塗る。そういう対策も覚えました。とにかくみんなかぶれてますから」
「漆芸専攻の人、一発でわかっちゃいますね」
「そうですねー……工芸科って年に一回バレーボール大会をやるんですよ。そこでも、漆芸専攻がトスしたボールで、他の専攻の人がかぶれちゃったりしますから。教室でも、あんまり近くに座んないでって言われたりとか。迫害されてます」
大崎さんは苦笑してから、続けた。
「あと、漆は高いです」
「あれは樹液ですよね?」
「ウルシの木から取った樹液です。日本で一般的な『殺し掻き法』という収穫方法では、十五年育てたウルシの木から、たった二百グラムの樹液しか取れません。それも、一度取ったらそれで木は死んでしまいます。生漆という一番シンプルな、木から取ったばかりのコーヒー牛乳みたいな色をした漆があるんですが……中国産の生漆が四百グラムで六千円くらい。日本産だと百グラムのチューブで一万二千円とかです」
「け、けっこうしますね。それも何度も塗るから、すぐなくなってしまいそう」
「はい。装飾の貝や、金も必要ですからね。これも高くて……」
大崎さんは頭を抱える。
「じゃあ、制作をするだけで随分お金がかかってしまうわけですか?」
「卒業制作の前に六十万くらいは貯金しとけ、って言われますからね。なので、頑張ってバイトしてます。あんまりお金がかかるから、取手キャンパスでウルシの木を栽培しようとした先輩もいるそうです。うまくいかなかったらしいですが」
漆はそんなに貴重品だったのか。近所のスーパーに百円の漆器が売っていたけれど、よく見たらウレタン塗装と書かれていた。本物の漆器なら安くても八千円はするそうだ。
「でも漆は面白い素材ですよ。私たち、とりあえず塗ってみます」
「とりあえずって?」
「とりあえず、そのへんのものに。紙コップに塗ったら、漆コップにならないかな、とか。先生が、みんなそういうところからやってみるよね、と言ってました。みんなやるみたいです」
「授業で技法を習いつつ、自分でいろいろ試してみるんですね」
「そうです。勝手に、自分で塗ってみます。まずはやってみないと。ちょっとしたアクセサリーを作るくらいだったら、そんなにハードルも高くないんですよ。東急ハンズで漆を買ってきて、百円ショップの筆でちょんちょんって塗るだけでも、立派な漆塗りですからね」
漆は応用のしがいがある素材だ、と大崎さんは言う。
「一人四役。塗料でも、絵の具でも、接着剤でも、造形素材でもありますから」
「造形素材にもなるんですか?」
造形素材とはつまり、粘土やゴムといった、材料そのもののことだ。
「はい、乾漆造形と言って、漆で木の粉を固めて櫛を作ったりできるんです。可能性は無限ですよ!」
ふーむ、本当に不思議な素材だ。
なんと一度固まった漆は、酸でもアルカリでも温度変化でも、ほとんど劣化しないという。そのため、縄文時代の漆製品がほぼそのままの姿で出土したりするそうだ。使っていた人がとっくの昔に死んでいても、何千年も残り続ける漆製品……ロマンである。
「やっぱり、宇宙の果てから生まれてきた物体ですよね」
大崎さんは、しみじみと言うのだった。
天才たるゆえん
絡繰り人形の佐野さんは、どんな漆器を作りたいのだろう。
「漆の技法で、表面を鉄錆そっくりに塗る方法があるんです。それを利用してみたいです。見た目は鋳物。なのに持つと非常に軽くて、蓋を開けて中を見ると、色とりどりの漆のつやがあるとか……びっくりしますよね」
絡繰り人形と同じく、佐野さんは「見た人の驚き」を大事にしているようだ。
だけど僕は、ちょっと不思議だった。漆芸をやりたくて藝大に入った佐野さんは、一方で千を超える部品を作ってまで絡繰り人形を組み立てている。どうしてそれが両立するのだろう。
「学校では漆をやって、バイト中に、バイトは予備校の講師なんですが、その空き時間に絡繰り人形の部品を作ってます。家でも、夜中まで作業してますね。睡眠時間は、だいたい三、四時間くらい……です」
「よく続けられますね。漆芸と絡繰り人形を、繋げようとは考えないんですか?」
「教授にも、漆を使って絡繰り人形を作ったら、と言われたことはありますが、今のところそのつもりはないです」
「別個のものなんですか?」
「まあ、無理に一緒にするものでもないと言いますか……どちらもやめずに続けていくとは思いますけど。いま作っている絡繰り人形は、卒業までに何とか完成させて、誰かに見てもらいたいですね。まあ、そんなに注目されることはないと思いますが……何か結果が出たら、嬉しい、そう思います」
何だか、肩に力が入っていない人だ。
ふと、音校の青柳さんを思い出した。二人とも独特のゆるさがある。絡繰り人形で世界に打って出るとか、口笛の魅力を世界に知らしめるとか、これ一本で食べていくとか……そういった勇ましい、積極的な言葉を彼らは使わない。考えもしていないようだ。
こんなに凄い人たちなのに、どうしてそうなんだろう?
佐野さんが何気なく口にした。
「僕、ものを作っている時間が、好きなんです」
赤坂の地下一階にある小さなライブハウス。
僕と妻は、青柳さんの「口笛ライブ」を聴きにやってきていた。ジンジャーエールを舐めながら待っていると、青柳さんがちょっと照れくさそうに笑いながら、手を振って現れる。拍手。スポットライトが当たるなか、マイクを持つ。
ピアノの伴奏が始まり、青柳さんが目を閉じて口をすぼめる。
高く透き通った音色がどこまでも広がっていき、唐突に素早いリズムに切り替わったかと思うと、また滑らかに伸びていく。まるで青柳さんは空中に浮かび、魔法の雲を口から吹き出しているかのよう。これが本当に口笛なんだろうか?
「こりゃすごさね……」
あまりの感動で妻が意味不明な関西弁を口にするくらい、素晴らしい演奏だった。だけど僕の心に残ったのは、誰よりも楽しそうに口笛を吹く青柳さんの表情である。見ているこっちが嬉しくなるくらい、とっても気持ちよさそうなのだ。
たぶん、そういうことなんだ……。
僕は、「ものを作っている時間が好き」と言った佐野さんを思い出していた。
誰かに認められるとか、誰かに勝つとか、そういう考えと離れたところに二人はいるようだ。
あくまで自然に、楽しんで最前線を走っていく。
天才とは、そういうものなのかもしれない。
7.大仏、ピアス、自由の女神
謎の“金三兄弟”
工芸科は謎の学科だ。
そもそも、彫刻科と工芸科は何が違うのかよくわからない。展示を見に行っても、どちらも動物の像を並べていたりするのだ。
「どう違うの?」
「…………」
妻は僕を正面から見つめたままフリーズする。
妻は工芸高校の出身で、現在は彫刻科に在籍している。どちらも経験しているのだから違いがわかるものと思ったが、そうでもないようだ。
「彫刻は美術品、工芸は実用品かな」
「でも、工芸の人も美術品を作るよね」
「うん……」
「実用品でも、装飾が凝ってれば美術品になるのかな。だとしても、どこからが美術だという境界線はないわけだし。作り手の意思次第ってこと? それとも見る側の受け取り方次第?」
「……ご飯食べる?」
妻は話を逸らす。
「もらう」
あれ。食器棚を見て僕は戸惑った。僕にはお気に入りの箸があって、いつもそれしか使わない。しかし、目の前にはその箸が二対あるのだ。
「僕の箸、増えてるんだけど……」
「あ。作った」
色も形も重さも手触りも、そっくりな箸が二膳。そういえば昨日、妻は顔を赤くしながらカッターと紙やすりで木の棒を熱心に削っていた。
なぜ作る。お気に入りがどちらなのかわからないじゃないか。
「へへ」
それにしてもこれは美術品なのだろうか。工芸品なのだろうか。
藝大の工芸科は基礎課程と専攻課程に分かれている。二年の夏までは基礎課程として全専攻をまたいだ授業が行われ、以降は一つを選んで専攻していくのだ。専攻の数は六つ。陶芸、染織、漆芸、鍛金、彫金、鋳金だ。
前半はまだイメージできるのだが、後半の“金三兄弟”は何だろう。読み方からしてわからないのである。それぞれ鍛金、彫金、鋳金と読むそうだ。
「あ、鋳金じゃないんだ……」
妻もわからないくらいだ。君は工芸高校にいたのだろうに。
これらは全て金工……金属加工の技術である。日本の金工技術は、基本的にはこの三つに分類されるそうである。僕は早速、一つずつ覗いてみることにした。
命取りになる機械しか置いていない
「鍛金の研究室を見ていただくとわかるんですけれど、ほとんど町工場なんですよね」
まるで山男のような風貌。工芸科鍛金専攻三年生の山田高央さんが、誇らしげに言った。
鍛金は簡単に言うなら、鍛冶屋だそうだ。金槌を持ち、金床があり、金属を叩いたり、切断したり、あるいは熱してくっつけたりして、望んだ形に変える。玉鋼を叩いて日本刀を作るのも鍛金のうちだ。
「一枚絞りと言って、一枚の銅板を金槌で叩いて、曲げて曲げて曲げて……器ですとか、そういった形を作る技法もやります。ただ、そういった技法だけでなく、うちでは機械加工もやらせてもらえる。旋盤とか、フライス盤とか。こないだも『スピニングの神様』と呼ばれる工場技術者の方が講師に来てくれて、直接習うことができました。あ、スピニングというのは成形加工のひとつの方法で、新幹線の先端とかを作る技術です。僕はもともと機械が好きなんで、この機械加工が面白いなと。受験する前から鍛金に行こうと思ってたんですよね」
旋盤もフライス盤も、工作機械の一つである。
「それを使って、どんな加工を行うんですか?」
「いろいろあって、一口には申し上げにくいのですが、例えば木目金という技法がありまして。これはですね、色合いの違う金属を組み合わせて木目のような模様を作る技法なんです」
「え。金属で、木目を……?」
「そうです。まず違う金属を重ねるんです。主に銅合金なんですけど、中に銀とか金を挟んだりして、パイみたいに。それをガス炉に入れて、八百度くらいまで温度を上げて、一日まるまる焼きます」
中に入れた金属が真っ赤に輝くという。
「そうして焼いたら、金属がアツアツのうちに出してきて、ひとまずプレス機で物凄い圧力をかけて、ある程度まで潰します。それが冷めないうちに、今度は鍛造機っていう機械のでっかいハンマーで、ガッツンガッツン叩いて潰します。これ、もっの凄い音がするんですけれど、もう、ガンガン叩いて潰します」
鍛造機は自動販売機よりも少し小さいくらいの大きさだが、動いている時の迫力は凄まじい。ハンマーが動くたびに衝撃が走り、鼓膜がびりびり震える。固定に失敗すれば材料が吹っ飛ぶそうだ。
「金属って叩いていくと、だんだん硬くなって動かなくなってきちゃうんですね。無理に叩き続けると、ひびが入って割れてしまう。なので、焼き鈍しと言って、バーナーで金属の色が変わるまでブワーッと炙るんです。そうすることでまた軟らかくなって、叩けるようになる。この鈍しと、鍛造機のガツンガツンを何回か繰り返します。最後の方では手で、金槌持って叩きますね。最初に十センチくらいの厚みだった金属の板が、一センチくらいになります」
「金属がそんなに、潰れるんですか……」
「はい、潰します。ここまですると、違う金属同士がくっつくんですね。これをグラインダーや鏨で彫ると、色の違う金属が繋がった縞模様が見えてきます。これをさらにローラーにかけて、薄い板にします。そうすると模様が木目のように見えてくるわけです。これが木目金。三年生の前期で習う技法です」
「…………」
絶句。
「日本独自の技法です。江戸時代に考案されたみたいですね」
飾り箱の蓋や、日本刀の鍔などに使われていたという。機械がない江戸時代だから当然、人力だけで叩いたのだろう。どれだけの労力だったことか。
「凄い情熱を感じますね。金属をそこまでして、加工したとは……」
「独特の技法は多いですよ。煮色着色という作業がありまして、作品を最後に薬品に漬けて表面処理をするんです。手順としては、例えば銅板から作ったお椀を煮色仕上げするとしましょう。まず、付着した手の脂なんかをとるためにお椀を重曹でよく磨いて、それから……大根おろしをかけます」
「大根おろし?」
「大根おろしです。なぜ大根おろしをかけるかは、具体的には先生方もわかってないそうですけど。そうすると、綺麗にできるんですよね。大根の中の何らかの成分が、還元剤の働きをしているんじゃないかと僕は思ってるんですが。とにかく大根おろしのついたお椀を、緑青とか明礬とか薬品の入った寸胴鍋で、半日くらい煮込む」
「何だか料理みたいですね」
「ちなみにその半日の間、ずっとこう、動かします。籠みたいなものの上にお椀を載せて、その籠をずっと上げ下げして。じゃぼじゃぼ。筋肉痛になるくらい」
「そうすると、色がつくわけですか?」
「はい。赤とオレンジの間みたいな色になります。元が銅なんで、最初は新品の十円玉の色なんですが。それが本当に綺麗な、独特な……均質な色に変わるんです。面白いですよ」
にこにこ顔の山田さん。それにしても大根おろしとは。最初にそれを見つけた人は、一体どれだけの数の材料を試したのだろうか。
「鍛金の作業場は、気を抜けない場所です。命取りになる機械しか置いてませんから」
エアープラズマ溶断機、大型高速カッター、ガスバーナー……。名前だけでも危なそうな機械が勢ぞろいしているという。
「機械の力で金属板が飛んで行ったら、そこにいる人、真っ二つになります。他にも旋盤に巻き込まれたらぐちゃぐちゃになるし、シャーリングも指とか飛んじゃうし、火も扱うし」
シャーリングマシンは、金属を切る巨大なハサミのような機械だ。
「緊張感がありますね」
「ズボンとかぼろぼろ、穴だらけですよ。グラインダーの火花で。あと、綿の服を着るようにしてます。化学繊維の服だと、火がついた時に一気に燃え広がっちゃいますからね。他にも金槌で自分を叩いてしまうこともありますし。金属の断面は鋭利ですから、切っちゃうことも。生傷は日常茶飯事です。ハンマーだこも」
「絆創膏を持ち歩いてる?」
「そういう人もいます。ま、僕は瞬間接着剤でピッと止めちゃいますけど」
実に豪快だ。
「金槌なんかは、たくさん種類を持ってるんですか?」
「金槌なら二十本くらい持ってますね」
「二十本も?」
「足りないくらいですよ。多い人は何百本も持ってますから」
「使い分けるだけでも難しそうですね。そんなにいろんな種類、お店にあるんですか?」
「あ、僕らは金槌を買うと言っても、頭の部分だけ買ってきて、自分で仕立て直して使うんです。面をベルトサンダーで綺麗に削って、紙やすりで磨いて、研磨して。木の柄も削って、くっつけるわけです」
「金槌も作るし、新幹線の先っぽも作るとなると、本当に何でもできるんですね……」
「鍛金は『大きいもの“も”できる』とよく言うんですけど、そこが魅力ですね。小さいものも、大きいものも、本当に幅が広いんです。好きにやっていいような空気もありまして。あんまり幅が広すぎて、放置されてる機械とかありますからね。誰も教えられる人がいなくて、置きっぱなし」
「工芸の中でも特に幅が広いんですか」
「そうですね。鍛金、正直、何でもできます! 他の研究室でできないものを、相談されることは多いです。うちの設備があれば何でも作れちゃうんですよ。こないだは漆芸の佐野君のために鉄板を切りましたね、シャーリングで」
「何でも屋、なんですね」
「よく彫金の学生も、うちの研究室に来てシャーリングで金属切ってますよ。まとめて大きな板を買って、細かく切って使うんです。その方が経済的なんで」
「技術もそうなんでしょうけれど、そういった設備のあるなしも大きいですね」
「そうなんですよね。だから大学にいるうちにできるだけ勉強しないと。大学でなら、機械も溶接もバーナーも使い放題ですから。一から個人で揃えるとなったら、こりゃきついですよ」
卒業したらどうやって作品を作ろうかなあ、と山田さんは首をひねった。何でもできるという鍛金の世界。あの自由の女神像も、鍛金の技術で作られているそうだ。
「ところで、工芸科も鞴祭をやると聞いたんですが」
山田さんは頷いた。
「ありますよ。各専攻でいろいろやってますね。鍛金の鞴祭は楽しいです。例のガス炉でピザと、マグロの頭を焼いて振る舞うんです」
さぞかし美味しく焼けるだろう。
「あと、鍛金は何でかわかんないんですが、毎年ゲストの神様が来るんですよ」
「ゲストの神様?」
「学生がやるんです。おととしは、町野先輩という方が全身を赤い絵の具で塗って。発泡スチロールで作った鼻をつけて。自分で溶接して作った鉄の下駄履いて、防塵マスクをかぶって、ヤツデの葉っぱを股間につけて。『本日はどこそこの山からマチノ坊さまがいらっしゃいました~』と」
「物凄いカオスですね……」
「実は、今回は僕がやらされまして。科のボス的な先輩に『今年お前な』と指名されるんですよ。先輩が鍛造で作った花と、スピニングで作ったコップを持って、裏でとってきた適当なツタを頭に載せて。上は裸で、先輩が日暮里の繊維街で買ってきた布を巻きました。『ギリシャからお越しの、酒と健康の神、ヤバッカス様です~』と……」
「ヤバッカス?」
「僕、山田じゃないですか。山田とバッカスかけて、ヤバッカスです」
山田さんが苦笑いしながら写真を見せてくれた。正面を向いて佇む山田さんは、思ったよりも威厳があり、神様っぽかった。
なお、ヤバッカス様がお召しになられた綿百パーセントの布は、その後細かく切って、機械の油汚れなどを拭くウェスとして無駄なく活用されたという。
貴金属の相場は毎日確認
鍛金の次は、彫金だ。
スケールが大きい鍛金とは対照的に、彫金は何かと小さく、細かい方向にいくのだという。
「彫金は細かい人が多いですね……、『ちょっとの傷も許せない』ような性格の人が」
どちらかといえばおおらかそうな印象の岩上満里奈さんは、工芸科彫金専攻の三年生。彫金のインタビュー、私なんかでいいんですか、と少し恥ずかしそうにしながら説明してくれる。
彫金は、主に装飾品や飾り金具を作る技術だそうだ。金属をねじって曲げ、磨いてピアスにしたり、鏨という鋼鉄でできた鉛筆型の器具で金属板に複雑な模様を彫りあげたりする。
「彫金はですね、金とか銀とか、場合によってはプラチナとか、貴金属を使うので材料にお金がかかるんですよね。だから、学生はみんな相場を毎日チェックしてます! 安い時に買いだめしておくんですよ」
一つ作品を作るのに、材料費だけで数万円かかってしまうそうだ。
「仕上げで銀をヤスリでこすると、銀の粉が出るじゃないですか。私たち、受け皿を置いてその粉を溜めるんですよ。業者に買い取ってもらえるんです。最初は捨てちゃってたんですけど、先輩に『お金捨ててるんだよ!』と言われて、本当にその通りだと思って」
僅かな粉でも無駄にはできない。文字通りの金銀財宝。
「彫金をやるようになってから、貴金属のありがたみを感じるようになりましたね。料理屋さんに行っても、食器の素材がわかるんです。このスプーン、本物の銀だ!とか。さすが高級店だって、テンション上がっちゃいます。本物は重みがあるんですよね」
例えばですけど、と言いながら自分の作品をいくつか見せてくれた岩上さん。その目は自信なげに下を向いている。
「まだ素人に毛が生えたようなレベルですから。恥ずかしいです」
「あ、指輪ですね」
大きな白い石がはめ込まれた、銀製の指輪。やや大きめで、僕の親指でもなんなく入る。
「ジュエリー作りの課題がありまして。宝石の専門家の方が講師に来られて、原石の削り方から学ぶんです。これは瑪瑙を使っているんですが、グラインダーという回転するヤスリみたいなもので、原石を削って磨いて丸くしていくんです」
「ヤットコなどで、原石を挟んで?」
「いえ、素手です」
「素手なんですか!」
「最初はもう、怖いですけど。だんだん慣れてきますね」
怖いなんてものじゃない。失敗すれば爪がなくなるという。危険と隣り合わせだ。
「こちらは……クマノミが泳いでますね」
金属製で楕円形のジュエリーケース。大きさは眼鏡ケースより少し大きいくらい。蓋の部分にクマノミとイソギンチャクが描かれている。
「これ、銀製ですか?」
「はい、銀です。まず問屋さんから笹吹き……純銀を買ってくるんです。こういうやつなんですけど」
見せてくれたそれは直径数ミリ程度の、銀色に輝く細かい粒。ケーキに乗っているアラザンにそっくりだ。昔は、水中の笹の葉の上に溶かした銀をほんの少しずつ垂らし、粒状に凝結させて作ったことから笹吹きと呼ぶ。
「これを溶かして型に入れて、ハイチュウみたいな形にします。それをローラーで伸ばして、板にして。板を丸めて円柱状にしたら叩いて、楕円の形にして、ケースにしていきます」
「このクマノミとイソギンチャクの模様は、どうやってつけるんでしょう」
「これは、切り嵌めという伝統技法で作りました。色合いの違う金属を切りだして、組み合わせるんです。赤い色が銅で、白いのが銀。黒いところは四分一。銀が四分の一で、残りが銅の合金です」
「微妙な配合の違いによって、色合いを表現するんですね」
「はい。それぞれの金属を模様の形に作って、パズルみたいに嵌めこむんです。丸い模様なら、板に丸い穴をあけて、そこに同じ形に切った銅の板を嵌めて、銀ロウで接着する。銀ロウというのは、ハンダ付けのようなもので。溶かした金属を接着剤にして、つなげるんですね」
「凄く細かい作業ですね」
イソギンチャクの模様、一本の幅は三ミリ程度だろうか。それくらい細かい部品を嵌めこみ、繋ぎ合わせるのだ。組み合わせた時に隙間ができないよう、切る鋸の厚みまで考えて設計するという。
「最後にヤスリで表面を削って、平面にして。最後に煮色で着色して、完成です」
溶かして。潰して。叩いて。嵌めこんで。
とてもそんな工程を経ているとは思えない、美しい楕円のカーブと、印刷のようにつるりとした表面だった。
「手先の器用さと、根気がいりますね。私、苦手です」
岩上さんは眉を八の字にした。
彫金の達人は日本刀に龍を描くという。胃に穴が空きそうだ。
熱気で睫毛が燃えそう
次は鋳金である。
「彫金はどちらかと言えば一人で机に向かって、地道にやる作業。鋳金は逆に、一人じゃできません。チームワークが必須です」
工芸科鋳金専攻の城山みなみさんは、大きな目をまばたきさせながら、そう言った。
鋳金は、型を使って金属を加工する技術である。例えば壺なら壺の鋳型を作り、そこに溶かした金属を注ぎ込む。冷えてから型を取り除くと、金属の壺のできあがりというわけだ。
「教室が砂場になってるんです。土間砂といいまして、川砂から作っているようです」
「床が全部、砂なんですか? どれくらい深いんですか」
「さあ、どれくらいでしょう。大きな作品もできるくらいなんで、相当深いですよ。底まで掘ったことがないんで、わかりません」
どれくらい深いかもわからない砂場。不思議な作業場だ。「たぶん鋳金が、金工の中では一番失敗が多いと思います」と城山さん。思い通りにいかないことがとても多いそうだ。
「まず原型を作ります。いろいろなやり方があって、これはその一つなんですが……粘土で作りたい形を作って、それをシリコンで置き換えてから、耐火材を混ぜた石膏で型をとります」
「型を作るだけで、粘土、シリコン、石膏……と使うんですか?」
「そうなんです。この型を作るのにとても手間がかかるんですよ。型そのものを電気窯やレンガ窯で何回も焼いて作ることもありますし。粘土、石膏、シリコン、ワックス……といくつもの素材を利用して作ることもあります。土で型を作る時は、様々な種類の土を何層にも重ねたりします。それから、鉄骨を入れて型を補強したりとか」
型の材質によって、複雑な手順があるのだ。
「型ができたら、シャベルで砂を掘って砂場の中に埋めます。型の上には穴があけてありまして。そこに、溶かした金属を入れます」
「金属は、そばで溶かしておくんですか」
「そうですね。型にどれくらい金属を入れるかを導き出す計算式があって、それに従った量のインゴットを買ってきて、温めながら叩いて割って……大きな壺の中で溶かします。一千度とかで。この溶かし方にも手順があるんですよ。ゴミが入っちゃいけないので、藁の灰で蓋をしたり。脱酸のためにリン銅というものを入れたり……」
お菓子を手作りするために、板チョコを割って溶かすのとは次元が違う。
「溶かした金属を流し込むのを吹きって言うんですけど、この作業が一人じゃできないんですよ。特に男性の協力がいりますね。重い壺を、何人かでせーの、で持ち上げて、よいしょって流し込むんです」
「真っ赤に溶けて、輝いている金属をですよね」
「はい。熱気で睫毛が燃えるかと思うくらいですよ……」
「凄くダイナミックな光景でしょうね」
「吹きは一人ではできないので、みんなでスケジュールを合わせてやります。そのためか、ちょっとイベント的なところもあって。吹きをやる日には、お神酒を供えて……作業が終わったらみんなでお酒を頂きます」
「なるほど、チームワークですね」
「他にも窯立てといって、型を焼くための窯を一から、煉瓦を組み立てて作ることもあります。これもみんなでやります。協力する機会は多いですね」
「窯まで自分たちで作るんですか!」
「鋳金の鞴祭では、自分たちで作った窯でピザを焼きますよ。美味しいです」
工芸科では、何かとピザを焼くようだ。
「これが、城山さんが作った作品ですか」
僕は城山さんのポートフォリオをめくる。そこには、細い棘が無数に生えた巻貝があった。
「はい。その巻貝の型が、これです」
「これは、また……凄いですね」
見せてくれた写真はもはやSFだった。巻貝の型なので、中心に巻貝らしき形はある。しかしそこに無数の色とりどりのパイプが繋がっているのだ。巻貝の棘一本に対し一本のパイプが繋がっていて、それらパイプは互いに合流しながら上へと流れて太いパイプになっていく。動物の血管を思わせる。
「そうか、金属がちゃんと隅まで流れるように、道を作るんですね」
「はい。湯道です。それから金属からはガスも出るんですよ。そのガスを抜くための道もつけないとなりません」
型自体が、美術作品として成立するんじゃないかと思うほど、複雑な形状だった。
「金属を入れたら……冷えるのを待ちます。半日か一日くらいで固まるので、そうしたら掘り出して、型を割ります。石膏だとハンマーで割り開けますね。土の型ならバリバリ剥がしていく感じで」
当たり前のように言う城山さんだが、ちょっと考えてみるとこれも驚きである。あれだけ苦労して作った型は、この時点でなくなってしまうのだ。
「それから仕上げです」
この仕上げもまた、手間がかかるのだという。
「ちゃんと、端っこに金属が行きわたってなかったり、穴が空いていたり。そういう失敗がだいたいあるんですよ。それから、作った道のところに不要な金属が入ってしまうことも多いし、はみ出してバリもできますから。いらないところを削って、穴を埋めて、足りないところは付け足して……最後に着色をして、ようやく完成、です」
ふう、と城山さんは息を吐く。
型で作ると聞くと、入れて冷やしてそれで終わり、のような気もしてしまう。だが実際には、複雑な作業の連続なのだ。
「ちなみにバリとか取り除いた部分は、とっておきます。また次回、溶かして使うんですよ」
大事な金属は、無駄にはしない。
「しかし、これは大変な作業ですね」
「そうですね、手間がかかります」
「大きな作品を作るとなると、かなり難しいんじゃありませんか?」
「難しいでしょうね。奈良の大仏は鋳金で作られたそうですが、どれだけの手間がかかったのかと思います」
見上げるほどの巨大な大仏を思い、僕も城山さんもため息をついた。
離れたくても、離れられない
藝大生たちの話を聞いて、よくわかった。金属という素材は、つくづく扱いにくい。硬くて重くて何かと手間がかかり、値段は高く、危険も隣り合わせ。何もそこまでしてモノを作らなくてもいいじゃないかと思えてくる。
工芸科のこの執念とも言うべきモノづくりへの想いは、どこから来るのだろう?
「それが、自分でもわからないんですよね」
鋳金専攻の城山さんは、不思議そうに首を傾げる。
「作業が押して、何日か泊まりが続くと、すっぴんですし。粉塵が凄いので、手拭いが必需品で、目だけ出るように顔に巻いて。いつも長袖に安全靴、軍手を二重につけて、ジーンズにモンペはいての作業です。たまには綺麗にネイルとかやりたいなーって思うこともあります」
「普通の女子大生が羨ましくなったり?」
「うーん。普通の学生になりたければなれたんですけど、でも私、結局藝大に来ちゃったんですよね。どういうわけか離れられないんです。美術は、好きかどうかはわからないんですけれど、腐れ縁的な存在ですね……」
腐れ縁。決して肯定的ではない言葉が出てきたことに、ぎょっとした。
彫金専攻の岩上さんも、似たようなことを言う。
「私、もともと藝大に行く気はありませんでした。高校が美術系だったんですけれど、なんというか美術ばっかりやってて、視野が狭いまま将来を決めていいのかなって思ったんですね。環境を変えたくなったんです。でも、他に行きたいところもなくて」
ぽつりぽつり、続ける。
「それで一年間フリーターしたんです。なんだか、美術が嫌いになってたところもあったので。美術と関係ないバイトをして過ごしてました。でも、暇な時に何するかっていうと……雑誌を読んでは、このレイアウト作ったりする人になりたいとか。ジュエリーを見ては、これを作る人になりたいとか……そんなことばかり考えてしまうんですよね。じゃあ、やっぱり美大行くかなって。どうせなら藝大を目指してみようって」
「結局、美術に戻ってきてしまったんですね」
「離れられないんです。何だか、引き戻されたみたいな。人間って、美術から逃れられないものなのかもしれません。正直、彫金も向いているとは思えなくて。夏休み頃は、いじけてたんです。みんなうますぎ、私向いてないって……。課題に追われてたりすると、作るのが嫌になりますよ。でも、課題とか何もなしに家にいても、やることなくて……結局、何か作りたくなるんです」
岩上さんが眉を八の字の形にする。
「これから自分がどうなっていくのか、不安になりますね。もう少し美術、やってみようって今は思ってますけれど……」
「僕も、藝大に入るまでは紆余曲折がありました」
鍛金専攻の山田さんも頷く。
「もともと、うちの両親が美術系の大学に行くことに反対だったんです。東大を目指せ、そういう方針で。ですが受験に何回も失敗してしまって。その間に妹の方が先に合格しちゃったりして、さすがにそろそろやばいぞ、となったところで親も藝大を目指すことを認めてくれたような次第で」
「そうだったんですか」
「でも藝大に入っていなくても、何かしらの形でモノづくりはしていたと思いますよ」
「モノづくりは、山田さんの中ではどんな位置づけなんですか?」
しばし考えてから口を開く山田さん。
「人生そのもの、ですかね」
「それがなくては生きていけないということですか?」
「いえ。他にやりたいこともないっていうか。変な言い方ですけど」
不思議なことに、三人とも燃えるような情熱を持ってモノづくりをしているわけでもないようだ。
なぜだかわからないけれど、この世界に戻ってきてしまう。何をしてもいいと言われても、結局モノを作ってしまう。そんな自分に、彼ら自身も戸惑っているようだった。
何だかふわふわした理由だな、と思っていた僕も、三人から同じ話を聞くと考えが変わってきた。
そういうものなのかもしれない。
やりたいからやるのではなく、まるで体に刻みこまれているように、例えば呼吸することを避けては通れないように、人はモノを作るのかもしれない。
鍛金の自由の女神像、彫金の日本刀の龍、鋳金の大仏……どれも、ちょっと凄すぎる。あれだけの技法を発展させるには、やりたい人がいた、くらいでは足りないのではないか。
つまり美術が面白いからではなく……美術から逃れられない人が常に存在したから、あそこまでの作品が生まれたのではないだろうか? そんな気がしてくる。
「そういえば、こないだ嬉しいことがあって」
取材の終わる間際に、岩上さんが控えめに笑った。
「私の、父方の祖母の、その父……ひいお祖父さんですね。その人が、彫金の彫り師だったんですよ。これ私、彫金に入ってから知ったんです」
「そうなんですか!」
「まあ……技術は受け継いでいないようなので、それがちょっと残念なんですけど……でも、嬉しかったです」
岩上さんに技術が受け継がれているかどうか、僕にはわからない。だけど美術の世界と体が繋がって離れないところは、確かに血として受け継がれているような気がした。
ひいお祖父さんはひ孫のことを、どこかで優しく見守っているのだろうか。