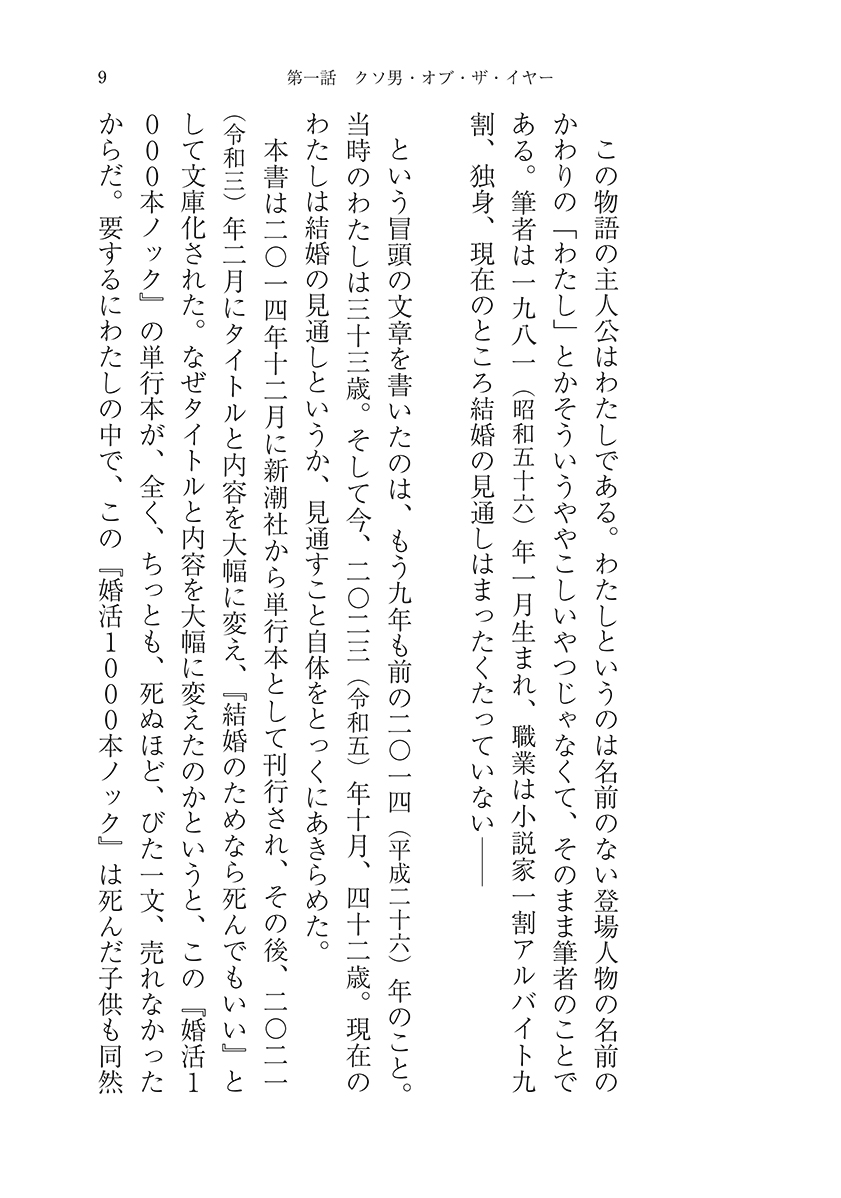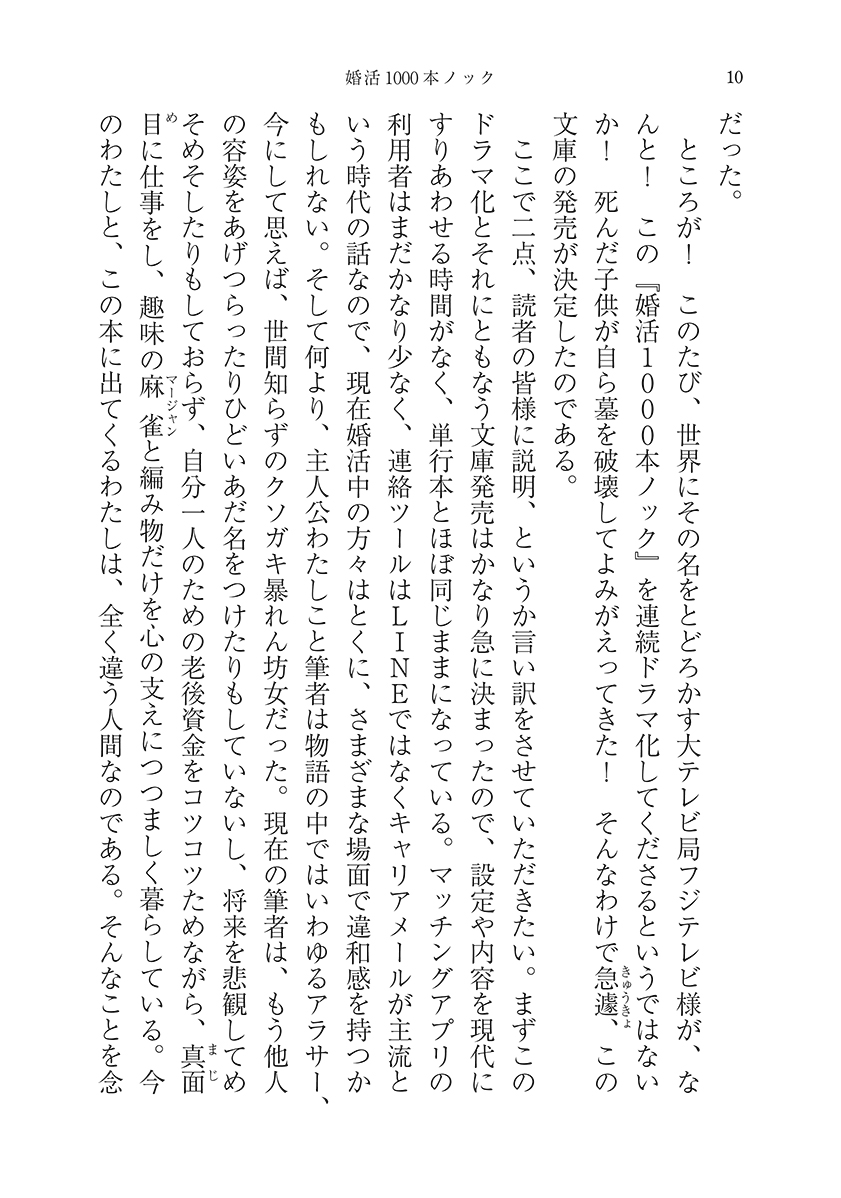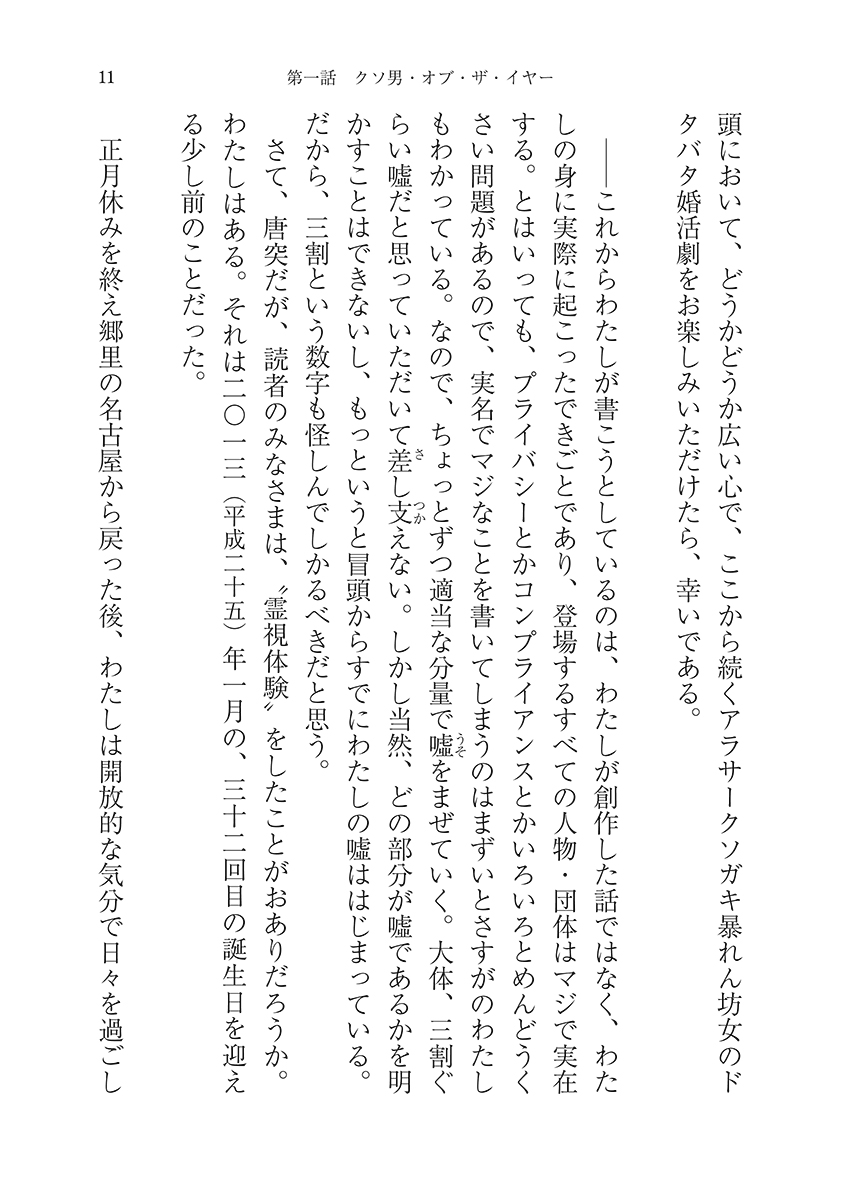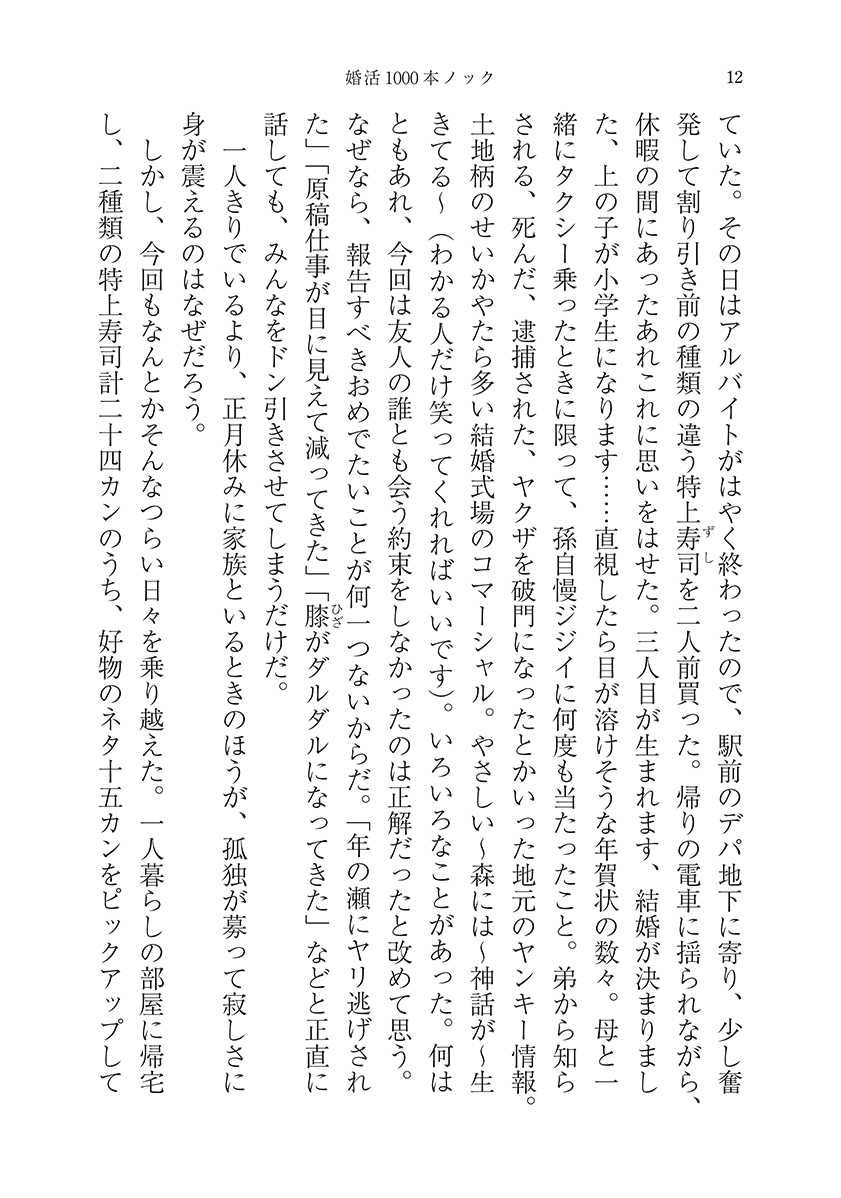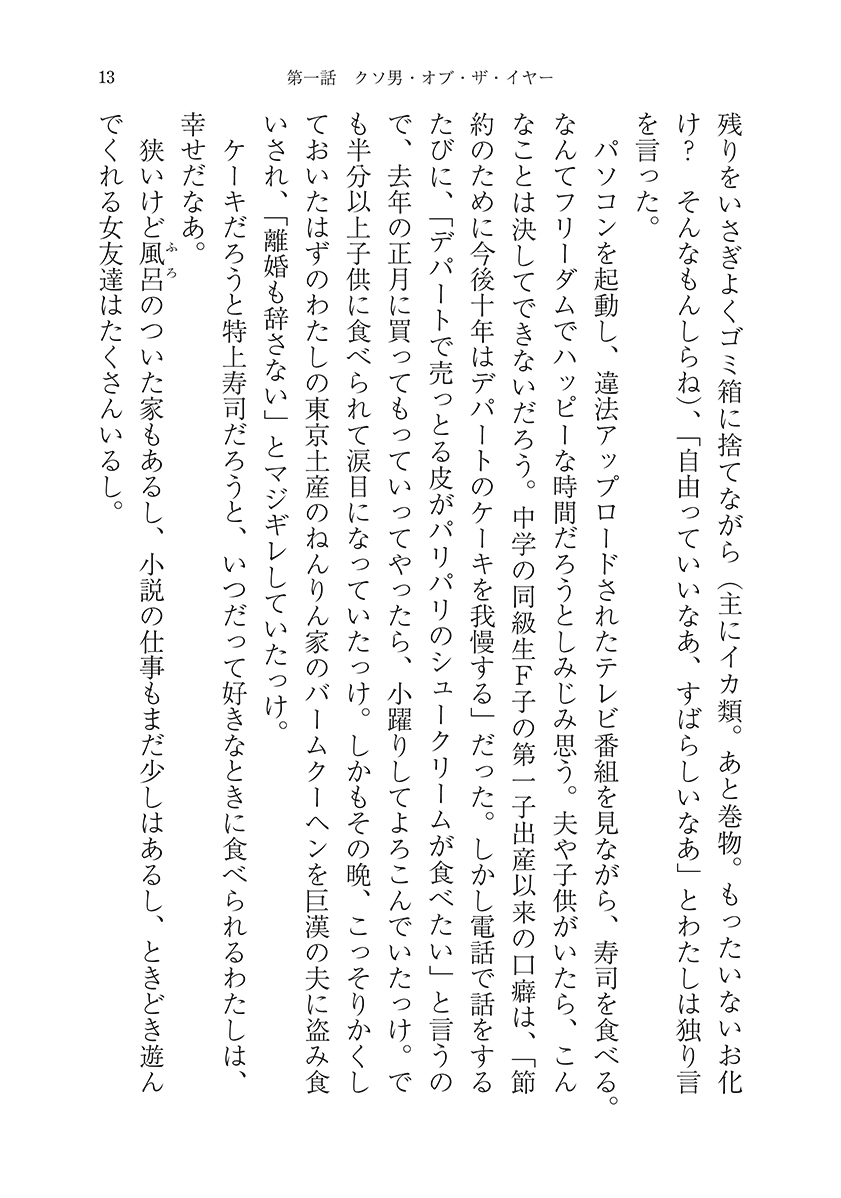第一話 クソ男・オブ・ザ・イヤー
この物語の主人公はわたしである。わたしというのは名前のない登場人物の名前のかわりの「わたし」とかそういうややこしいやつじゃなくて、そのまま筆者のことである。筆者は一九八一(昭和五十六)年一月生まれ、職業は小説家一割アルバイト九割、独身、現在のところ結婚の見通しはまったくたっていない――
という冒頭の文章を書いたのは、もう九年も前の二〇一四(平成二十六)年のこと。当時のわたしは三十三歳。そして今、二〇二三(令和五)年十月、四十二歳。現在のわたしは結婚の見通しというか、見通すこと自体をとっくにあきらめた。
本書は二〇一四年十二月に新潮社から単行本として刊行され、その後、二〇二一(令和三)年二月にタイトルと内容を大幅に変え、『結婚のためなら死んでもいい』として文庫化された。なぜタイトルと内容を大幅に変えたのかというと、この『婚活1000本ノック』の単行本が、全く、ちっとも、死ぬほど、びた一文、売れなかったからだ。要するにわたしの中で、この『婚活1000本ノック』は死んだ子供も同然だった。
ところが! このたび、世界にその名をとどろかす大テレビ局フジテレビ様が、なんと! この『婚活1000本ノック』を連続ドラマ化してくださるというではないか! 死んだ子供が自ら墓を破壊してよみがえってきた! そんなわけで
ここで二点、読者の皆様に説明、というか言い訳をさせていただきたい。まずこのドラマ化とそれにともなう文庫発売はかなり急に決まったので、設定や内容を現代にすりあわせる時間がなく、単行本とほぼ同じままになっている。マッチングアプリの利用者はまだかなり少なく、連絡ツールはLINEではなくキャリアメールが主流という時代の話なので、現在婚活中の方々はとくに、さまざまな場面で違和感を持つかもしれない。そして何より、主人公わたしこと筆者は物語の中ではいわゆるアラサー、今にして思えば、世間知らずのクソガキ暴れん坊女だった。現在の筆者は、もう他人の容姿をあげつらったりひどいあだ名をつけたりもしていないし、将来を悲観してめそめそしたりもしておらず、自分一人のための老後資金をコツコツためながら、
――これからわたしが書こうとしているのは、わたしが創作した話ではなく、わたしの身に実際に起こったできごとであり、登場するすべての人物・団体はマジで実在する。とはいっても、プライバシーとかコンプライアンスとかいろいろとめんどうくさい問題があるので、実名でマジなことを書いてしまうのはまずいとさすがのわたしもわかっている。なので、ちょっとずつ適当な分量で
さて、唐突だが、読者のみなさまは、“霊視体験"をしたことがおありだろうか。わたしはある。それは二〇一三(平成二十五)年一月の、三十二回目の誕生日を迎える少し前のことだった。
正月休みを終え郷里の名古屋から戻った後、わたしは開放的な気分で日々を過ごしていた。その日はアルバイトがはやく終わったので、駅前のデパ地下に寄り、少し奮発して割り引き前の種類の違う特上
一人きりでいるより、正月休みに家族といるときのほうが、孤独が募って寂しさに身が震えるのはなぜだろう。
しかし、今回もなんとかそんなつらい日々を乗り越えた。一人暮らしの部屋に帰宅し、二種類の特上寿司計二十四カンのうち、好物のネタ十五カンをピックアップして残りをいさぎよくゴミ箱に捨てながら(主にイカ類。あと巻物。もったいないお化け? そんなもんしらね)、「自由っていいなあ、すばらしいなあ」とわたしは独り言を言った。
パソコンを起動し、違法アップロードされたテレビ番組を見ながら、寿司を食べる。なんてフリーダムでハッピーな時間だろうとしみじみ思う。夫や子供がいたら、こんなことは決してできないだろう。中学の同級生F子の第一子出産以来の口癖は、「節約のために今後十年はデパートのケーキを我慢する」だった。しかし電話で話をするたびに、「デパートで売っとる皮がパリパリのシュークリームが食べたい」と言うので、去年の正月に買ってもっていってやったら、小躍りしてよろこんでいたっけ。でも半分以上子供に食べられて涙目になっていたっけ。しかもその晩、こっそりかくしておいたはずのわたしの東京土産のねんりん家のバームクーヘンを巨漢の夫に盗み食いされ、「離婚も辞さない」とマジギレしていたっけ。
ケーキだろうと特上寿司だろうと、いつだって好きなときに食べられるわたしは、幸せだなあ。
狭いけど
幸せだ。
あー幸せだ。
たまらなく幸せ。
幸せだあ。
……さっきから寿司の味がよくわからない。
最後にとっておいたうにの軍艦を二ついっぺんに口に放りこむ。まるで粘土を
たとえば今、この口の中のうにの軍艦が急激にモチ化して、のどにつまって死んだら、寿司を食べたことをわたしは後悔するだろうか。
……そーんなにしねえかなあ。
案外、こんなさえない人生もういっか、なんてかるーく死を受け入れるのかもなあ。
もうまもなくで三十二歳。いつまでたっても売れない作家。二十代の終わりに前の彼と別れて以来、彼氏いない歴数年。最近とにかく膝の皮がたるんでダルダル。この先も生きていていいことがあるのかどうか。
いや、ない。
本が売れて彼氏ができる。何年もかけて全くできなかったことが、この先突然できるようになるなんてとても思えない。
そうであれば、このままさえない人生をおくり続けるよりも、いっそ今死んで生まれ変わりに期待する方がずっと効率的ではないだろうか。死んで、ビヨンセの子供に生まれ変わりたい。ベッカムのところの五番目でもいい。アンジーとブラピ(筆者注・この当時は理想のカップルの代表例だった)のところは、なんか嫌だなあ。
今死んだとして、惜しいのは最後にセックスしたのがあの男であるという点ぐらいだった。そう考えるとかなり不愉快だ。晩節を
ピンポーンとインターホンが鳴った。
すでに夜の十時をすぎている。
こんな時間に荷物が配達されるはずはない。新聞とかNHKだろうか。とりあえず、室内のドアホンモニターを確認してみた。
建物入り口には誰の姿もなかった。
いたずらだろうか。
少しして、またピンポーンと鳴った。
さっきとは違うトーンの音だった。建物一階のオートロックドアのところではなく、部屋のインターホンが直接押されたのだ。
誰だ。
居留守を使うべきだ。それはわかっている。けれど、見えない何かに背中を押されるように、わたしは玄関へすり足で向かった。
おそるおそる、ドアスコープをのぞき込む。
ダウンジャケット姿のやせた男が立っていた。
とっさにわたしはロックをはずし、ドアを開けた。
男は無言でまっすぐわたしを見た。わたしも黙って彼を見返した。何にも言葉が出てこない。というか、なんと言ってやるのがベストなのかわからなかった。ぶち切れて追い返すべき? やっぱ追い返すべき? でもなんか、ちょっとよろこんでしまっている自分がいる。自尊心を傷つけられ、あんなに腹を立て、年の瀬の頃は一時間に二度の頻度で「正月に
こいつこそ、二〇一二年クソ男・オブ・ザ・イヤーの栄冠をわたしが与えた男。もうすぐ三十二歳になるわたしを、四つ下の分際であっさりヤリ逃げした男――。
「なんで何も言わへんの」
男はちょっとはにかみながら言った。
本当なら実名を
山田にされた仕打ちを一つ一つ思い返したら、わずかなよろこびは消え
「あのな、俺な、実は幽霊やねん」
「……は?」
「マジやねん。俺、死んでんねん」
わたしはまた、じっと山田の顔を見つめ返した。こいつは以前から突然何の脈絡もなく「俺な、実は視力四・〇やねん。サバンナでライオン発見できるで」とか「俺のひいひいひいじいちゃんは忍者やねん。
そんなことはどうでもいい。今夜はいったい何の目的で? まさかまたヤリ逃げしに? バカじゃないの? 死ねばいいのに。
「バカじゃないの? 死ねばいいのに」
「だから、もう死んでんねん。証拠見せたるから、部屋あげて」
「いや無理だし、はやく帰ってよ」
こちらがそう言い終わらないうちに、山田はするっと中に入ってきた。
数秒わたしは、その場に立ちつくした。なんだか、すごく変な感じがした。体がぶつかったはずなのに、どこにもふれていないような。自分の中を通り抜けたような。
山田は台所の前を通って部屋にはいると、パソコン前の
「パソコンで俺の名前、検索してみ」
サーチボックスに山田の本名の一文字目を入力する。去年のヤリ逃げ後、毎日のように山田の名前をググっていたせいで、予測変換ですぐにフルネームが出てきて
「なんか、今日は散らかってんなこの部屋」山田はつぶやいて、ふっと笑った。「この前きたときは、ちゃんと掃除してくれとったんやな」
当たり前だろクソ男。あの日はおまえのために原稿締め切りを一つブッチして、半日かけて大掃除したのだ。窓ふきなんて年末でもやらないのにぴっかぴかに磨いた。それなのにおまえは。それなのに。
「新聞記事、出てきたやろ?」
山田から視線をそらし、パソコン画面に向き直る。確かに、いくつかの事件記事がヒットしていた。適当に一つ選んでクリックする。わたしは記事を読みあげた。
「東京都渋谷区の路上で三日夜、同区の医師、山田クソ男さん(28)が胸を刺されて殺害された事件で……え、マジ?」
「マジやで」
他の記事も開いて見ていった。全部同じことが書いてあった。山田の本名は、姓はありふれているが、名前は当て字でかなり珍しい。同姓同名で同年齢の医師が同じ渋谷区に住んでいる偶然があるかどうか。絶対にないと断定するのは難しいが、ありそうだとも思えなかった。
そのとき、わたしはあることに気づいた。容疑者として逮捕された女の名前。
「ねえ、この女って」
「そう、あいつや」
山田はなぜかちょっと得意げな様子で、事件当夜のことを説明しはじめた。
一月三日の夜に実家のある大阪から都内に戻ってきた山田は、遊び仲間の男達と六本木のクラブに出かけた。そしていつものようにナンパで女をひっかけ、自宅に誘うことに成功。女とともにタクシーで向かうと、自宅マンション前の路上で、山田の自転車のタイヤに刃物でプスプスと穴を開けている女がいた。
G子だった。G子は山田と同じ大学の看護学部卒のナースで、一年生のときに三ヶ月だけ交際して別れた後も、ずっとつかず離れずの関係を続けていた。山田は気が向いたときにG子を自由に呼び出していた。が、G子からの連絡はほとんど無視している様子だった。
その夜、東京はかなり冷え込んでいた。しかし、G子は
「あいつ、さすが外科のナースやな。刺しどころ抜群でショック死ボンバーやったわ」
あまりに幼稚でバカバカしい表現にわたしは言葉を失った。こいつは本当に医師なのだろうか。
「なんや、その顔」
「マジで死んでんの? 幽霊なの?」
「そうや。殺害されたって新聞に書いてあるやん。それにほら、俺、少し浮いてるやろ」
山田の靴を履いたままの足下をのぞき込んだ。よーく見ると、確かに一センチぐらい浮いていた。
「マジだ」
「聞きたいことあったらなんでも聞いてくれてええで。幽霊としゃべる機会なんてめったにないやろ。小説のネタになるんちゃう」
わたしは腕を組み、しばし考える。「……死んだ日、クラブでナンパした女は、なんて言って家に誘ったの?」
「つまらんこと聞くなや」
「なんでも聞いていいって言ったじゃん」
「『俺が英語で書いた論文、読みにきてくれへん?』って言った」
開いた口がふさがらなかった。わたしのときと全く同じじゃないか。
「なんで女って、こんな言葉でホイホイ家についてくるんやろな」山田はどうでもよさそうに
「……なんで、五日まで家族でオーストラリアなんてG子さんに噓ついたの?」
「あいつ、いつ会えるいつ会えるってうるさいねん。年末年始の休み、二時間でも一時間でもいいから会いたいとか、何回も何っ回もメールしてきて。友達と遊ぶって正直に言っても、どうせ女と会うんでしょとかねちねち文句言うやん」
「だから噓ついたの?」
「うん」
「なんで正直に、予定が空いてないわけじゃないけど、君と会う気はないって言わないの」
「だから、面倒くさいやん」
「あんたからの連絡、ずっと待ってて苦しかったんじゃない? 彼女」
「待っててくれなんて頼んでへん」
「でも、また連絡するわ、とか思わせぶりなこと言ってたんでしょ、どうせ。そういうこと言うとき、待つ人の気持ちは考えないわけ?」
「待つのがイヤならやめればええやん」
ああクソ男。まさに「クソ男・オブ・ザ・イヤー・2012」にふさわしいクソ男ぶり。大して顔はよくない。性格は最悪。ぼそぼそと小声でしゃべるのでときどき何を言っているのかわからない。とりえは医師であることぐらい。こんな男がなぜやたらとモテるのか。G子はなぜこいつのために人生をフイにしてしまったのか。
そしてわたしはなぜ、こんなクソ男に一ヶ月近くもの間、執着し続けていたのだろうか。
「死ねばいいのに」
「もう死んでる」
「二回死ね、いや百回死ね」
「なんでそこまで言われなあかんねん。ていうか、もっと有意義なこと聞けや。俺はガチの幽霊やで」
「じゃあ……あ、そうだ。刺されたとき、痛みは感じた? 苦しんで死んだの?」わたしは
「いや、それがな」山田はちょっとだけうれしそうな表情になると、「めっ」とうめいてからしばらく息をとめ、
「……っちゃ痛かった。あいつ、
「ざまあ
「おい、笑いすぎや」
「あー、いい気味。ご愁傷さま」
「自分の家の前で死ぬまでのたうちまわったんやぞ。少しは気の毒やと思わへんの?」
「全く。で? なんなの? あんたが
「俺はおまえに謝罪する気などない」
「あっそ」
「だがしかし、いまのところ、お前の指摘する通り、俺は成仏できてへん」
「で?」
「成仏できへんのにはいろいろ原因があるらしいんやけど、はっきりしたことはよくわからへん。ただとにかく、
「らしいらしいばっかで、言ってることがよくわかんない。噂って何?」
「先輩の幽霊から聞いた噂や。あんな、俺もこうなってからしったんやけど、幽霊って生きてる人間の目には見えへんだけで、実はいたるところにうじゃうじゃおんねん。自分に俺が見えてるのは、俺がわざわざ見せてやってるからなんやけど、でもむやみやたらに人前に出ると成仏が遅れてしまうんやって。だから、本当はひっそりと隠れとかなあかんねん。なんでやろ? 霊界におる偉い人の怒りを
「ますます意味不明」
「まあ俺も、あの世の詳しいシステムはようわからん。とにかく俺は、なんとしても成仏したいねん。できれば一年以内に成仏したい。でないと、虫になってしまう。それでな、先輩から聞いたんやけど、成仏するための方法がいくつかあるらしいねん。その一つがな」
山田はそこで言葉を止め、ぐいっとこちらに顔を突き出した。
「死ぬ前に誰かとしたまま果たされずにいる約束を、果たしてやること……俺はそのためにここにきたんや」
「もったいぶった言い方してないで、はやく用件を言えよ、負け犬が」
チッと山田は舌打ちをする。「自分、前に温泉いきたいって言うてたやん。数年ぶりに彼氏ができたら、二人で温泉にいきたいって。温泉が大好きやのに相手がおらんから、毎年一人で温泉宿泊まってて、だけどそれが毎回猛烈にさみしいから、いつか彼氏と温泉いきたいって」
思わずわたしは目を閉じた。そうだ。わたしは山田と最初に食事デートしたとき、ついうっかりそんなことを話してしまった。それがすべての間違いの元だった。この男はぬけぬけと言ったのだ。「俺がその願いかなえたるわ。
その言葉を、告白の代わりだと受け取ってしまったわたしは、まんまとその後……。
「俺、結構珍しいねんで。ああいう、無駄に女を期待させること言うの。でもあのときは、なんでかしらんけど言うてしもた。先輩の幽霊から“最後の約束”って言葉を聞いて、すぐにあのときの話を思いだしてん。……南さんを温泉につれていくことやって」
「で? わたしにお化けと一緒に登別にいけって? イヤだけどね」
「いや違う。自分の望みは、彼氏と温泉にいくことやろ。俺は彼氏になられへん。幽霊やから。それに自分が望んでる彼氏はただの遊び相手やなくて、結婚を前提とした彼氏やろ? 年齢的に考えてもそうやし、ていうか結婚したいんやろ? そういう相手を見つけるためには今こそ
「……」
「しかも自分、婚活小説依頼されて書いてるって言うてたやん。あれ、進んでへんのやろ? 婚活して彼氏できて小説書いて本を出す。そして俺は成仏する。一石三鳥やん。最高や」
「やりません」
わたしはきっぱり宣言した。
「なんでや」
「いやいや、なんであんたのために婚活なんかしなきゃいけないわけ? 嫌だね。やりたくない。わたし、今そういう気分じゃないの。ていうか、婚活はここ一、二年の間にもう十分やったの。お見合いパーティもいったし、街コンもいったし、去年なんて合コン十五回もやった。でも全然彼氏ができない。いい人に出会えない。出会えたとしても、向こうは全然その気じゃない。この一年だけで何回振られたと思ってんの? 去年の終わりになってやっと、今度こそいけるかもって人に出会ったのに……ヤリ逃げされた」
三十二歳目前にしてヤリ逃げ。
しかも相手は年下の男。
こんな屈辱あるだろうか。
自尊心を粉々に打ち砕かれ、自分の女としての価値はゴミレベルにしか思えなくなり、何のために生きているのかわからなくなった。朝起きたらスマホのメール作成画面を開き、「死にたい死にたい死にたい……」と何行も打ちまくったあげく、自分のアドレスに送信するという
「あんな、うまくいかへんのは必ず原因があるはずやし、二人で協力したら何かつかめるかもしれへんやん」
「いいの、もう。今って四人に一人は生涯一度も結婚できないっていうじゃん。わたしってその一人なんだよ。その事実を受け入れることにした。そもそもさ、結婚したからって幸せになれるとは限らないんだよ。反対に、一人でいるからって不幸なわけでもない。そうでしょ? わたしにはわたしなりの幸せの形があるはず」
山田は何か言いかけて、口をつぐんだ。一重まぶたの鋭い印象のある目で、わたしをじっと見る。
「どうせ小説だって書いてもボツになるし。確かに、婚活小説やりましょうってS社の人に言われてるけどさ、もう何回も何っ回もボツになってるもん。わたしの本なんて出す気ないんだよ、あの会社」
「まあ、今日はひとまず帰るわ」山田は言った。「またくるわ」
「何度きても同じ。他の人との約束にかえなよ。G子さんのところにでもいけば」
「俺にはわかるねん。自分は近いうち、気がかわって俺と婚活することになると思うで」
山田はそう言うと、「じゃ」と右手をあげた。そして玄関ではなくベランダのほうへすたすた歩いていき、窓を開けてぴょんっと外に飛び出した。
あ、と思ったときには、もう姿が消えていた。
わたしは窓を閉め、ベッドに腰掛けた。急に猛烈な眠気が襲ってきた。フラつきながらもう一度立ち上がってパソコンを閉じ、照明を消してベッドに潜り込んだ。きっと今、わたしは夢を見ているのだと思う。朝起きたらいつも通りの日常が待っている。山田クソ男は死んでなんかいなくて、今もどこかでその晩限りの女を抱いている。
あっという間に眠りに落ちた。目が覚めたら昼過ぎだった。なんだか額のあたりが異様にかゆく、手で触れてみると、手のひら大のポストイットが
山田に話した通り、わたしは一昨年から昨年にかけ、あらゆる種類の婚活にいそしんだ。
S社から依頼された小説の取材目的でもあったが、結婚相手を探そうと本気で出会いを求めてもいた。遅くとも三十二歳になるまでには原稿を完成させて本を出し、なおかつそのあとがきで「実は本書の取材活動において、すてきなご縁がありまして……」と結婚を大々的に発表、いや自慢するのが
しかし実らない。
どうしても彼氏ができない。
向こうから言い寄られたときに限って、相手に全く好意を抱けない。その中には、いわゆる高スペックと呼ばれるような男性もいた。しかし何かがどうしても受け入れられず、二度目のデートをお断りしてしまうばかりだった。
勇気を出してこちらからデートに誘うことも、もちろんあった。二十代は完全受け身の動かざること山のごとし女だったことを考えれば、我ながら驚異的な進歩だ。しかしやはり実らない。高望みはしていないつもりだった。自分のスペックと相手のスペックを照らし合わせ、慎重に精査し、「この人ならイケるかな~」と判断できた場合に限ってこちらから動いていたつもりだった。一度はデートしてもらえてもその後が続かない。「また機会があればいきましょう」と社交辞令丸出しのメールが来てフェードアウト。
婚活をはじめて約一年半がたった昨年秋頃、合コンやお見合いパーティだけに出会いの場を求めることに、わたしは限界を感じるようになった。同じことを繰り返しても、出る結果も同じ。何か新しい風のようなものがほしかった。そんなとき、S社の担当編集者から「都内某所にある、必ずナンパされるスタンディング・バー」の存在を教えられた。場所柄、チャラチャラした若者は少なく、大手企業サラリーマンや士業などの身元が確かで高スペックな大人の男性が多く集まっているという。
何かピンとくるものがあった。わたしはさっそく友人J子(三十二歳・彼氏いない歴三十二年)を誘い、取材もかねてそのバーへいってみることにした。
そこで出会ったのが、山田クソ男だった。
実際に声をかけてきたのは山田ではなく、全く無関係のやたらと陽気な男だった。その男は一方的な自己紹介を済ませると、周りの男をひっつかまえてはわたしたちと無理やり握手をさせるということをやりはじめた。大抵の人はうれしそうに握手に応じたあと、品定めするような目でじろりとこちらの顔を確かめ、そして半笑いで去っていく。わたしもJ子も、その時点でプライドはもうがたがただった。S社の担当編集者から「客は男性のほうが多いらしいんで、よほどのブスでない限り絶対ナンパされるらしいっすよ」「年齢層はそれなりに高いみたいです。三十代前半だったら余裕でモテそうっすよ」などと聞かされていた。しかし、一時間近く店にいても、わたしたちは謎のご陽気男以外の誰からも声をかけられなかった。周りは二十代の若者ばかり。その上、ご陽気男によるこの仕打ち。今年一番不運な夜だと思った。
何人目かで、ご陽気男に引っ張られて山田が目の前に現れた。やけっぱちな気分だったわたしは、相手の顔も見ずに握手を拒否し、「もういいから! もういいから!」と二人を押しのけて帰ろうとした。
「なんで? 俺も握手したいと思ってずっと見てたのに」
わたしは振り返って、彼を見た。
正直、顔はネズミ男みたいでちょっとキモいと思った。
しかも服装はそろいのジャージの上下に、足下はサンダルとバカ丸出しの格好(あとで聞いたら、その日まで山田は盲腸で入院しており、退院と同時に友達に遊びに連れ出されていたらしい)。
けれど、この人を逃して帰ったら、一ヶ月は後悔し続ける、と直感的に思った。
山田はにっこり笑った。出っ歯がむき出てますますキモいと思った。
「で? 帰るん?」
「いや、帰らない」
わたしは言った。そして彼と握手をした。ほどなくして、彼が都内の病院に勤める整形外科医だとわかり、自分の直感は間違っていなかったと心の中で有頂天になった。
終電が近いことを告げると、彼はとくに引き留めようともせず、「じゃあ今度食事しよう」と連絡先を聞いてきた。翌日すぐに彼からメールが来て、一週間後、彼が予約してくれた豚しゃぶ屋で食事デートをすることになった。
出会ったスタンディング・バーは照明がかなり暗く、はっきりと顔が見えたわけではなかった。明るいところで会う彼は、記憶にあるよりさわやかで、みだしなみもきちんとしていて医者らしい清潔感もあった。「だらしのないネズミ男」という印象が、会って三秒で
食事中の彼は、常に淡々としている感じだった。これまでの経験上、デート相手の男性がこちらに気がある場合、会話にやたらめったら自分の自慢を混ぜ込んでくるか、こちらをチヤホヤしまくるかどちらかのパターンが多かった。チヤホヤの場合は要注意で、ただ単にセックスしたいだけだったりする。山田はそのどちらでもなかった。医者であることを鼻にかけることもなく、むしろあまり仕事の話はしたがらなかった。冷やし中華が好きだから将来は冷やし中華屋になりたいだの、冬場はオーストラリアで商売するつもりだの、背中の後ろで手を組めるほど体が柔らかいだの、どうでもいいことばかり話していた。そして、チヤホヤどころかわたしを褒めるようなことは一切口にしない。かといって、全く気がなさそうかというとそうでもなく、ときどきさりげなく「自分、モテるやろ」「あの晩、他に話したいと思う女なんておらへんかった」「若い女にもともと興味ないねん」などとこちらの心をくすぐるようなことを言ってくる。このさりげなさこそ、本気の
そして、そんな状態に追い打ちをかけるような、「俺が綾子ちゃんを温泉連れてったるわ」宣言。もう正式なお付き合いは決まったも同然だと、バカで間抜けなわたしは確信してしまった。英語で書いた論文の話は、何の脈絡もなく突然出てきたのだが(確か、お互い好きなお好み焼きの具材の話をしているときだったと思う。終電も近かったので焦っていたのかもしれない)、その唐突さなどもう全く気にならなかった。
店を出て、タクシーに乗り、彼の部屋にいった。そして、いたした。いたした後も、彼の態度は変わらなかった。淡々としていた。いや、少しは優しかったかもしれない。しかし、別れ
「久々にやらかしてしまった……」と初回のデートで関係を持ったことを、わたしはすぐに後悔した。相手に付き合う気は全くなく、一度限りの相手だったのだと素直に受け入れた。当然、こちらから彼と連絡をとろうとはしなかった。
ところが数日もしないうちに、彼から次の誘いがあった。今度はわたしの部屋に泊まりたいという。
もちろん即OKした。わたしのマンションの近所で食事をし、その後部屋に呼んだ。このために、締め切りをブッチしてまで大掃除を決行したことは前述の通りだ。その日の山田も、前回と同じく淡々としていた。が、部屋までの道すがら、唐突に味噌汁の味噌は何味噌か聞いてきたので、これは今後生活をともにすることを考えているのかもしれないとわたしは思った。部屋に着くと、エアコンのフィルターの清掃頻度について尋ねられた。ベランダの窓がぴかぴかであることを褒められたりもした。とにかくこの人はわたしとまじめに交際することを考えている。そうでなければ味噌汁のことなど気にするだろうか。いや、しない。そもそも、ヤリ逃げするつもりだったら二度は会わないはずだもの。二度会ったという時点でヤリ逃げではないもの。そう、自分に言い聞かせた。言い聞かせながら、いたした。言い聞かせている時点で、何か予感めいたものをすでに胸にいだいていたのかもしれない。
朝、彼が帰るとき、前回同様、次の約束はできなかった。その後、三日間連絡がなかった。四日目、思い切ってこちらから誘ってみた。
すると、二週間後に会おうと彼からすぐに返信があった。わたしは心底ほっとした。
ところが、その約束の前日になって、突然のキャンセル。別の日程を提案するでもなく、理由も明かさず、一方的な通告だった。さりげなく(いや、もしかすると全然さりげなくなかったかもしれないが)予定を伺うと、「忙しいからまた連絡する」という脈無し感満載のそっけない返事。
その後、彼からの連絡は一切なかった。
何度かさりげなく(いや今考えるとまったくさりげなくなんかなかった)様子伺いのメールをしてみたが、無視。
無視。
無視。
無視。
落ち込んだ。
あと少しだったのに、何がダメだったのか。自分の気づかないところで、とりかえしのつかないミスでもしてしまったのだろうか。むだ毛の
挙げだしたらキリがなかった。というか、考えても答えはでなかった。落ち込むわたしを、J子が再びあのスタンディング・バーへ連れ出してくれた。失恋の記憶は別の男で上書きするのが一番だ。
今度は前回とは違い、入店してすぐに声をかけられた。しかし、相手の顔にどことなく見覚えがあった。相手も同じく不思議そうにこちらを見ている。
「……アレ? 君、この間、クソ男に声かけられてなかった?」
そう言われて思い出した。山田に出会った日、彼のそばにいた男だ。確か、草野球サークルのチームメイトだと話していた。
「あの後どうしたの? 二人で会ったの?」
わたしは肯定も否定もせず、ただへらへらしていた。男は我が意を得たりとばかりにニヤついた。
「あーわかった。ヤられちゃったんでしょ、君も。ダメだよー、あんなヤリチン
ヤリチンに糞野郎までつけるとはひどい言いぐさだ。わたしは何も言わず、男の言葉の続きを待った。
「あいつってさ、特にイケメンでもないのに、やたらと女捕まえるのがうまくてはやいんだよな。だって、中二のときに初体験すませて以来、ずっと週に一度はセックスしてるって言うんだぜ? それが誇張でもなくマジでマジなんだからさー、すげえよ。今日は先週クラブでナンパした二十三歳の美容師とデートするって言ってたけど、今頃家に連れ込んでるのかもな。今度は何回目で飽きるのかな。はやいと二、三回でポイなんだけどね」
男は勝手にベラベラしゃべった。不思議とわたしは何も感じなかった。ただ、男の顔がひょっとこにそっくりだったので、面白い顔だなあと思いながらへらへらし続けていた。
冷えきった自分の部屋に帰ってきてはじめて、悲しみがこみ上げて涙が少しだけ出た。その後、いや、悲しいというより情けなかった。今頃、結婚している同級生たちは、夫婦で晩酌を楽しんだり、子供と川の字になって眠ったりしているんだろう。それにひきかえ、もうすぐ三十二歳になるのに、彼氏ができないどころか年下男にヤリ逃げされている自分。一体どこで何を間違えたのか。どうしてこんなに何もかもうまくいかないのだろうか。彼氏ができない。どうしてもできない。家に引きこもり続けた結果、今があるわけではない。この一、二年の間、出会いを求めて積極的に活動してきた。自分でもよく頑張ったと思う。でもできない。押してもできない。ひいてもできない。世の中にはとくにこれといった努力をしなくても、途切れることなく恋人を作ることができる人がいる。もしかするとそっちのほうが大多数なのかもしれない。つがいをつくって子をなす。生き物として当たり前の行動だからだ。恋人ができないことが人生最大の悩みって、何なのだろう。こんな人生もう嫌だ。
わたしの何がだめなのか。もうわけがわからない。
寂しい。
それから一ヶ月ほど、落ち込んだまま過ごした。自尊心はボロボロだった。一時は本気で死にたいとすら思った。死んでビヨンセの子供に生まれ変わりたかった。三十歳を過ぎてヤリ逃げされると、これほどまでに大きなダメージを受けてしまうのだということを学んだ。
しかしこうして時間をおいて振り返ってみると、山田のクズっぷりなど大したことなく、むしろ自分のバカさ加減のほうが常軌を逸しているようにも思えてくるが、それでも山田がクズであることには違いない。死んだのは自業自得。あいつが成仏できようとできまいと、心底どうでもよかった。協力するつもりは一切ない。そもそも、あいつに話した通り、今は合コンにもお見合いパーティにも本当に全くいきたくなかった。また傷ついたりがっかりしたりするぐらいなら、一人気ままな時間を過ごすほうがよっぽど有意義だ。このまま、一人きりで生きていく人生を受け入れる準備をはじめようと、わたしは本気で考えはじめていた。ひとまずは、彼氏だの結婚だのといったことから距離をとりたかった。
そのわたしの
二月は小説の仕事がほとんどなかったので、バイトの予定を入れまくっていた。ちなみにわたしの今のバイト先は探偵事務所で、わたしはもちろん探偵でなく、事務員として採用されている。実質はただの雑用係だった。詳しい仕事内容はこの小説の趣旨とは無関係なので差し控えるが、個人的に一番嫌いな作業は盗聴した音源のテープ起こし(起こしながらつい自分アレンジで面白いセリフに変えたくなってしまう)、一番好きな作業は男性用下着に特殊な液体をふりかけて精液の跡を浮かびあがらせること(理由はとくになし)。
二月の終わり、仲良しの同僚たちと焼き肉を食べにでかけた。メンバーは四十代のベテラン探偵I夫さん、三十代の探偵三年目のR助さん、四十代の経理担当Y子さん、そしてわたし。I夫さんはバツイチで独身だが、モデル並みの男前で常に恋人がいる。今は十歳年下の客室乗務員と
そのためこのメンツで集まると、わたしの婚活失敗話は酒の
しかし仕事柄、相手のプライバシーに踏み込むことに
「でもさあ、南ちゃんて、そんなブスってわけでもないのにねえ。いや、俺はむしろ美人なほうだと思うよ。なのに、なんで彼氏ができないんだろうねえ」
「
「そうかもな。美肌だし、全然三十代に見えないよ。二十九ぐらいに見える」
「髪切ってますます
そうやってチヤホヤとほめそやし、調子に乗せてしゃべらせようとしているのは明らかだった。普段ならホイホイつられていたかもしれないが、今日は付き合う気になれなかった。単に気分がのらなかった。
「でもさ、南さんって気を抜いているときは結構ヤバイよね。男から見てアレってどうなの?」
さっきから黙々と牛ホルモンを焼いていたY子さんが言った。
「どうなのって、何が?」とR助さん。
「いや、だから、南さんってさ、会社にスッピンでくるじゃん。二十代の頃はよかったけど、最近、日によってヤバイときがあるんだよね。あー、
酔っぱらいの話すこととはいえ、老けた、という言葉に胸がチクッとした。そうだよな。老けたよな。だからスタンディング・バーにいってもモテないし、年下男にまともに相手にされずヤリ逃げされるんだろうな。
「だって、ほら見て」Y子さんはいきなりわたしのこめかみを指でぎゅっと押してきた。
「ここにでっかいシミがあるの、わかる? 今は化粧と髪の毛でごまかしてるけどさ、すっぴんだと目立つのよコレが」
「え? どこ?」「どこだよ」男性二人が顔を突き出すと、Y子さんはわたしのこめかみを指で連打した。
「面倒くさがってないで、はやく皮膚科いってレーザーやってきなよ、みっともない」
みっともない。またグサッときた。それでも、場の空気を悪くしたくなかったわたしは、ヘラヘラしながら「だってレーザー、十万かかるっていうんだもーん」とおどけて言った。
「皮膚科といえば、俺、四十過ぎてるんだけど、
ジェントルマンのI夫さんが話題を変えてくれた。その後は誰もわたしの婚活話に触れようとしなかった。話題はI夫さんの髭脱毛から、探偵事務所の副所長のバレバレのヅラについて、さらにそこからR助さん宅で飼われはじめた猫の抜け毛事情に移り変わっていった。
「猫って、舌で
「へえ、そうなの?」
「いいな、わたしも猫飼いたいです」
「かわいいよー、俺も奥さんももうメロメロ」
「いやいや南ちゃん。一人暮らしの女の子が猫飼ったらもう終わりよ? 男なんて必要なくなっちゃうよ」
「いや、もうすでにそんな心境なんで、いっそ猫でも飼っちゃったほうが」
「つーか、そんなんで恥ずかしくないわけ? 南さん」
Y子さんの突然の大声に、一同は息をのんで黙った。
「え? どうなの? 女として恥ずかしくないのって聞いてるの。あのね、わたしは南さんより十歳以上年上で、しかも南さんのバカにする経産婦、中学生の子持ちだけど、ぶっちゃけ南さん、全然わたしと勝負になってないからね、女として。同じリングにも立ててないよ。ねえ、どうなの? 恥ずかしくないわけ?」
とっさに言葉が出なかった。わたしは今、侮辱されているのか?
「ちょっと、聞いてるの? わたしは真剣な話をしてるんだからね? あのね、いい
「……そりゃ、たまには、誰かに言い寄られたり……」
「言い寄られてるだけじゃん。でも全然うまくいかないじゃん。しかもどうせ単なる体目当てでしょ。ここ数年の間、一度でも男から真面目に『付き合ってください』って言われたことある? ないでしょ? はー、なっさけない」
「いやいや、Y子さん。そのうち南ちゃんにもいい出会いはあるよ。たまたま、今は一人だけどさ」
「ないない、そんなのそんなのないから、I夫さん。絶対ない。この人、もう三十すぎてるんだよ、もうろくな男と出会えないよ。そんな世の中甘くないって。女は一つ年をとるごとに価値が目減りしていくの。女の若さは男の年収だって言うじゃん。ていうか、なんでI夫さんはそう南さんを甘やかすの。ダメだって、きつく言ってやんなきゃ。美人だとかおだてるから勘違いするんだよ、この人は。一度、がっつり言ってやんなきゃって、わたしはずっと思ってたの。いい? 南さん。あのね、男がいない時点で、実際の見た目に関係なくその女はブス決定なの」
わたしの頰は完全に石化し、ぴくりとも動かなくなっていた。ぶつけられた言葉の数々がうまく消化できない。ただただ、動揺していた。動揺しつつ、Y子さんはわたしが以前、社内不倫している同僚のE美さんについて、「探偵のくせに職場で不倫ってどうなんだろう。あのはしゃぎっぷりは経産婦とは思えない」と話したことを、経産婦をバカにしたととらえて根に持っていたのだろうな、そしてわたしばっかりチヤホヤされてちょっとむかついたんだろうな、と頭の隅っこで冷静に考えたりした。表情を固まらせたままノーリアクションのわたしに、さすがのY子さんも気まずさを感じはじめたのか、「つーか、このハラミ、臭いっ」と怒りの矛先を肉にかえ、それ以上は何も言ってこなかった。
やがて、いつもより少し早いタイミングで「二軒目いこー」とY子さんが言い、我々は焼き肉屋を出た。なるべく一次会で帰るようにしているわたしは、極力普段と同じ態度で「お疲れさまでーす」と手をふり、皆に別れを告げた。
しかし背を向けた瞬間、涙がこみあげてきた。
三十過ぎの女が
いくら気の置けない同僚とはいえ、Y子さんは言いすぎだったと思う。男がいないというだけで、なぜあそこまで言われなければいけないのか。悪態を通り越して人格否定だ。悔しかった。でも何がどう悔しいのか自分でもよくわからなかった。わたしは彼女の言葉の、何に傷ついているのか。ブスと言われたこと? 三十過ぎたらろくな男と出会えないと言われたこと? それとも全部? もうよくわからない。よくわからないけれどとにかく悔しくて悲しかった。
駅に着いた。週末のせいか、ホームは混み合っていた。急行待ちの列に並ぶ。すぐ前のカップルのぎゅっとつないだ手と手を見て、再び涙がこみあげた。またこらえようと上を向いたら、ホームの上の
まだ、言葉がぐるぐる回っている。
やっぱりY子さんは言いすぎだ。何度考えても言いすぎだ。ブスなどと面と向かって言うなんて、ひどい。やっぱりブスが一番傷ついた。
ホームにアナウンスが流れる。遠くに大きな光が見えてくる。
けれど。
認めざるをえない指摘があったことも確かだ。
彼女の言う通り、今、わたしのことを好きだと言ってくれる男は身の回りに一人もいない。それは紛れもない事実だった。女として、誰からも愛されることなく一生を終える。一人きりで生きていくとはそういうことだ。本当に、わたしはそれでいいのだろうか。
自宅の最寄り駅に着くころには、涙も乾き、心の中で一つの決意が固まっていた。マンションの近くまできたところで自分の部屋を見上げると、防犯のために出かけるときはつけっぱなしにしていたはずの蛍光灯が、消えている。普段なら警戒して中に入るのをためらうところだが、わたしは迷わず玄関を抜け、
山田がいた。
わたしの仕事用の椅子に座り、火のともされたキャンドルを両手で持って、不気味な笑みを浮かべながらこちらを見ている。
「何してるの? なんでわたしのアロマキャンドルに勝手に火をつけてるの」
「なんか、幽霊っぽい感じで登場したかってん。どう?」
「幽霊っぽいって、あんたそもそもガチ幽霊なんでしょ」
「せやで。で、婚活する? するやろ?」
わたしは部屋の明かりをつけた。山田は幽霊のくせに、「まぶしっ」と目をほそめた。部屋中に
「これ、高いんだから、勝手につけないでよ」
「そんなことはええから。どうなん」
「する、婚活」
わたしがそう答えると、山田は勢いよく立ちあがった。
「これから一年がんばろうな。よろしくお願いします」
山田は折り畳み携帯のモノマネみたいなおおげさなお辞儀をした。びっくりして
やっぱり夢なんだろうか、と思いながら、手を洗うためにと洗面所へ向かった。鏡を見ると、額に手のひら大のポストイットが貼り付けてある。
そこには、クッソ汚い字で「片思い 思うだけでは 通じない」と書いてあった。
翌日の深夜、家で原稿仕事をしていたら、山田がベランダから侵入してきた。
婚活を本格的に再開する前に、合コンでのわたしの様子を観察して対策を練りたい、と山田は言った。
わたしはさっそく友人たちに連絡をとり、翌週に一つ、翌々週に二つの合コンの予定を組んだ。
一つ目の合コンの相手は、某大手飲料メーカーの研究員だった。人数は三対三。場所は銀座の和風居酒屋。飲み放題付きコースで一人五千円。日曜日だったので、全員私服だった。男性側幹事のG藤さんは三十五歳の京大卒、趣味は釣り。顔面が
T森さんだけでなく、ほかの二人も口数の少ないタイプで、イマイチ盛り上がりに欠けた。会計は完全な割り勘だった。十時前に一次会のみで解散になった。
翌週の一つ目の合コンは、わたしが幹事を担当した。相手はわたしの友人K
B場さんの提案で、二次会もやることになった。やる気がないなら帰ればいいのにF本さんもついてきて、「ねえ、君たち今から呼べる女友達いないの? 誰か呼んでよー」と駄々をこねていたが、当然のごとく無視されていた。
最後の合コンは二対二。幹事同士がカップルなので、合コンというよりは紹介といったほうがふさわしかった。相手は神奈川県庁職員のW辺さん三十八歳。髭が濃かった。筋金入りのハルキストだそうで、
「で、三度の合コン、計七人の男との出会いを経て、結果はどうやねん」
最後の合コンから三日たっていた。明け方五時過ぎ、わたしは湯たんぽを抱えて眠る寸前だった。山田はまたベランダから侵入してきた。
「昼過ぎにもう一回きて。眠い」
「あかん。これから婚活会議や。はよ起きろ」
仕方なくわたしはベッドを抜け、眠気覚ましのための紅茶を
「で、どうなん。成果は」
「別に。とくに無し」
「誰とも連絡とってへんの? 連絡、一人ぐらいはなんかきたやろ」
大手飲料メーカー勤務、バカみたいな腕時計をつけていたE川さんから、その日のうちに「今後もよろしくお願いします。よかったらまた食事にでもいきましょう」と社交辞令なのかそうでないのかはっきりしないメールがきた。それから、なぜかアベちゃんことF本さんからも、「二人で食事しよう」と誘いがあった。神奈川県庁のW辺さんからは、三日たった今日になって、「ありがとうございました。また小説の話がしたいです」と型通りのお礼メールがきた。
「返信したん?」
「してない」
「なんでや」
「だってさー。まずE川さんだけど、あの時計は何よ。三十近い男があんなおもちゃみたいな時計つけてるなんて信じられない。髪型といい服装といい、八〇年代からタイムスリップしてきたみたいだし。話が合うとは思えない。ていうか、どうせあんなメール、社交辞令だし。アベちゃんは若い女の子紹介してほしいだけでしょ。とにかく関わりたくない。W辺さんは、まあ幹事カップルに連絡しろってどやしつけられてメールくれたんだろうけど……ごめん、どの道、生理的に無理」
「ファッションなんてどうにでもなるやん。あのE川って
「……そうなの? 彼、わたしのこと気に入ってたのかな」
「俺は合コンの最中、ずっとそばにいて観察しとったんや。間違いない」
「……」
「それと、あのアベちゃんはちょっとひねくれ者なだけで、悪い奴とはちゃうと思うで。自分が小説書いてることに、一番食いついてたやん。知的な職業についてる人ってええなあって顔で見てたよ、自分のこと」
「え? マジ」
「うん。で、あのW辺はほっといてええわ。あれはな、多分ド変態やで」
「へえ」とわたしは感心した。なんとなく、山田のいうことに妙な説得力を感じてしまった。
「じゃあ七人の中で一番ダメなのは、W辺さん?」
「せやな……いや、ちゃうわ。自分の友達のK輔とかいう奴や。あいつはあかん。俺と同じ
「……あの子はお前みたいなヤリチン糞野郎じゃありません」
「ヤッてる女の数のことやなくて。多分、人を本気で好きになれんタイプちゃうかな。思わせぶりな態度はとるけど、いざとなると面倒くさなって逃げてまうねん。自分のことしか考えられへん奴。そういう男や」
胸がチクッと痛んだ。実はわたしは前々からK輔君のことをいいなと思っていて、これまで三回食事に誘ったのだが、「親が病気で忙しい」「入社説明会の時期で忙しい」「引越しを検討中で忙しい」と断られていた。それでも飲み会に誘うと、一も二もなくOKしてくれる。メールの返信もはやい。だから少なくとも、わたしのことを嫌ってはいないのだろうと、ずっとチャンスをうかがっていた。何度飲み会をやっても、彼はほかの女の子とは積極的にコンタクトをとろうとせず、お礼のメールも幹事のわたしにしか送ってこないことも、あきらめられない一因になっていた。
「プライドが高いから、自分からいくのはいやなんやろな。でも、めっちゃタイプの子が現れたら、ああいうのは行動はやいで、意外と」
「わたしのことは、どう思ってるんだろ」
「合コンやってくれる便利な女としか思ってへんわ」
うすうす気づいてはいた。が、はっきり断言されるとキツかった。
「まあ、でも、あれやな。やっぱ合コンで結婚相手見つけるのは、効率悪いんちゃう?」
「なんで?」
「全体的に男のモチベーションが低いわ。合コンに結婚相手を探しにきてる男なんてそうおらんで。ただ知らん女と酒飲む会やから、合コンは。どうしても彼女がほしいっていう必死感を感じたのは、その黄色の時計のE川君と、ド変態のW辺ぐらいやね。あとは、『いい子がいたら、自分から連絡してもええかな』って考えてるレベル。彼女持ちもおったんちゃうかな。ちなみにあのバーはもっとあかん。またヤリ逃げされるで」
「うーん」
「それに自分、K輔みたいな、女にそれほど困ってない感じのやつが好きやん。モテるやつっていうか。合コンやったらそんな男もくるけど、そんなもん競争率高いし、追いかけても時間を無駄にするだけやで」
「……なるほど」
「自分、結婚したいんやろ? 将来のことを考えてくれる男と付き合いたいんやろ? そんなら相談所入れば?」
「そんな金ない」
「なら、お見合いパーティみたいなんは? とにかく、合コンやナンパやなくって、もっと結婚に近そうな手段を選ぶべきちゃうの?」
「いや、実はわたし、一つ気になってるものがあるんだよね。お料理合コンっていうんだけど」
わたしはパソコンを開き、ブックマークしているお料理合コンのサイトを山田に見せてやった。お料理合コンとはその名の通り料理をしながら合コンをするのだが、人集めは運営側がやるので、合コンに呼んでくれる友達のいない人も参加できる。会員登録をしなければならないし、参加費は五千円前後とそこそこする上、キャンセルポリシーもわりと厳しい。やる気のないやつはそうそうこないだろう。
「ほうほう。ああ、ええんやない。結婚したそうな真面目な男が集まってそうやん。でも、お見合いパーティよりはなんか楽しそうやし。うん」
「そう?」
「うん。ただまあ、俺は絶対こんなんいかへんけどな。K輔みたいな黙ってても女がよってくるような男も、おらんと思うで。それでもええの?」
わたしは山田の顔をじっと見つめながら考えた。山田の言うことは一理あった。いや百理ある。これまで、わたしは山田やK輔のような、モテるタイプや女に不自由していなさそうな男ばかりを好きになる傾向があった。合コンにいくとその手の男が必ず一人はいる。だめだとわかっているのに、
そういう男が一人もいなさそうな場所に飛び込んで、ある中から決める。もう無駄な理想を追うのはやめよう。
「うん、やる。お料理合コン」
わたしはパソコンに向き直り、さっそくその場で会員登録をした。